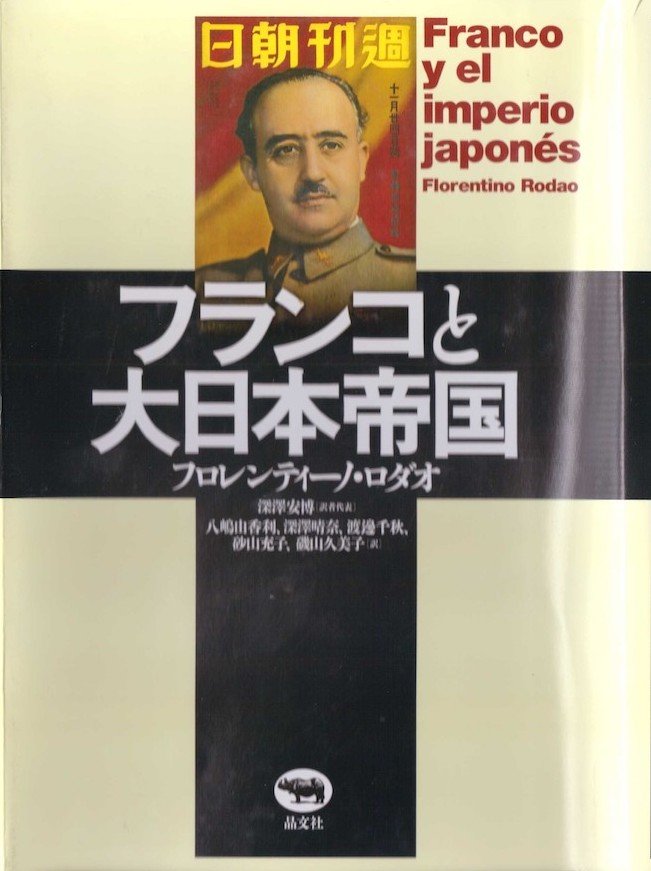Furanko to nippon teikokuフランコと大日本帝国-Tokio 晶文社- Shobunsha
Resumen
Introducción
Capítulos
フロレンティノ・ロダオ著『フランコと大日本帝国』
- 新秩序への期待
スペイン内戦の終結(1939年4月)は、拡大しつつある日西関係の転換点を期すものであった。両国の関係はとりわけ1937年7月の日中戦争勃発以後緊密になっていた。イベリア半島における戦闘終結に引き続き、スペインは日独伊防共協定に署名した。このことはこれらの国の友好がソビエト連邦に対する共通の敵意を基礎にしていることをよく表している。しかし、この協定は反共産主義のより一層の協力に向かわなかったのみならず、ソ連への新たな攻撃の序章ともならなかった。逆に、数多くの歴史の皮肉の一つとして、スペインの参入は、1936年に日独が最初に調印し、37年にイタリアが参加したこの協定の最後の光輪にすぎなかった。
内戦の終了と防共協定のスペインへの拡大(同様に満州国やハンガリーにも拡大された)は、枢軸諸国にとって誰が主要な敵であるべきかという問題の練り直しの時期と、偶然ではなく、一致した。この時期、枢軸国の主要な批判対象は徐々に変化し、西欧民主主義諸国が彼らの優先攻撃目標になっていたからである。それを最もよく表すのが、欧州での戦争勃発数日前に締結された独ソ不可侵条約である。イベリア半島で平和が回復された直後、こうした戦略の変化がアジアでも、異なる文脈においてではあるが、日本によってかいま見られた。最初に、天津疎開封鎖問題でイギリスの弱さとアジアにおける西欧の利権に対する攻撃で(日本が)成功する見込みが明らになった。そしてノモンハン事件――欧州での戦争勃発時にちょうど終わったのだが――の後、日本はその北方の古くからの敵と正面から対決することが困難であることを、はっきりと知ったのである。
欧州での戦争はもう始まっていた(数年後には悲劇的結末に至るであろう計算ミスの中で、独総統が前もっての計画を立ててから始まったのだが)。スターリンは一時的であるにせよ、枢軸国の戦争への衝動を他の方向へそらすことに成功した。国際政治の紛争をもっぱらイデオロギー戦争の帰結としてのみ考えてきた多くの人々が驚いたことには、これらの戦争では帝国の野望が勝ることになる。
欧州での戦争勃発は、生気を失いつつあった日西関係に新たな活を入れた。ドイツ勝利の明らかな見通しを前に、スペインと日本の両政府は、勝者の側に立つことに過度の満足を示した。全体主義諸国にとってその勝利は、彼らが感じる必要性と合致した(独)帝国の出現に加え、新しい世界の地政学地図を意味していた。そこではかれらが主導権を握ることになるであろう。反共主義で事前に結ばれていた国々は、もはやモスクワと戦うことにそれほど執着せず、むしろ自らの旗印の下にできるだけ多くの領土をかき集め、その結果、彼らには欠けている植民地というものを有する英仏帝国との国力の格差を是正しようとやっきになっていた。これらの野望はますます重要性を増してきた。すでに手がつけられたものもあれば、単なる願望に過ぎないものもあった。いくつかは文化的影響力の増大をめざしており、別のものは単に帝国の夢に新しい領土を付け加えるというに過ぎなかった。有名な話にあるように、乳の入ったどんぶり一つ売れないというのに、もう「新秩序」を模索する者がいた。
西欧諸国に対する最終的勝利が第一であった。彼らを打ち破りたいとする情熱から、スペインと日本はドイツ軍の勝利の航跡を同じように歓迎し、また欧州の戦争に直接参加せず、可能な支援は補完的なものにとどめるという点で似たような役割を担っていた。その上、お互いに帝国の願望の対象となる地は遠く隔たっていた。スペインは北アフリカへの目論見をはっきりさせていたし、日本は東アジアで英国の影響力と対峙しようとしていた。スペインがタンジールの町にまったく没頭している間、日本は自分たちの野望に抵触するどんな国に対しても自分たちのルールを押し付けようとしていた。問題が一つあった。日本は反植民地とその解放を訴えていたが、それは友好国である枢軸諸国と敵である英国とをほとんど区別していなかった。というのも、これら諸国は全てヨーロッパという一つの文化圏に属し、日本はアジアにおけるその地位強化を排除しようとねらっていたからである。
したがって、独・伊・西は英国支配に対する日本の戦いには同意していたものの、それ以外の目論見には控えめな態度で見守っていた。にもかかわらず、彼らは民主主義諸国に対する勝利を勝ち取ろうとするかたわら、日本を彼らと結びつける点に注意を向けようとした。そしてその先の問題には目をつぶる。欧州の独裁者たちは、不承不承ではあるが、東アジアの将来に関する決定を後回しにすることにしたのである。例えば、ミクロネシアにある古くからの独帝国植民地は第一次世界大戦後日本の占領下にあったが、議論に取り上げられることはなかった。結局のところ、輝かしい期待を伴う同盟であったが、同時に重要な矛盾も抱えてもいた。そしてこれは、後の将来に影を落とすことになる。
将来への野望は日西関係に主な内実を与えるものであった。東京都マドリードはその最終戦を勝ち抜かなければならないと考えていた。東京は満州や中国で、あるいは徐々にはっきりとした形を取ってきた南進政策やラ米諸国との関係促進において、スペインがどのように役立つかという思惑からこの国に着目していた。一方、マドリードは日本のアジアでの躍進が枢軸国の最終的勝利に寄与し、彼らもそこから利益を得るだろうと常に読んでいた。しかし、この時期はこうした野望の強さに何よりも特徴付けられ、一貫性のある理性的判断をないがしろにするほどであった。合衆国の経済力の強さに関する情報はないがしろにされ、英国の抵抗能力はすでに尽きたとされ、日本はいかなる方向へも有利な形で打って出る用意があり、枢軸国の勝利という夢が見られていた。その勝利の後、勝者は世界的規模での戦利品を分配するであろう。さらに悪いことには、当時多数の強気の弁がふるわれ、将来の危険がないがしろにされた。それは後に、当時敗者の一人と想定された国、合衆国をまえに高い代償を支払わされることになる。将来への期待が利害の相違を最小化し、利害を超えた支援の可能性を信じこませた。スペインがフィリピンで経験したように、そうしたものは決して起こらなかったのだが。
この見せかけの状態は長続きしない。1941年7月、にわかにこの蜃気楼は薄れ始めた。ドイツがソ連を突然攻撃したとき、日本は同じ行動に出なかったのだ。「新秩序」の支持者は、日本のその決定を理解することに苦しんだ。東京のそれまでのイメージが不完全なものであると判明したのである。独・伊・西は中長期的な日本の野望と自分たちのそれが異なっていることをはっきりと悟ったのである。しかも、さらに、枢軸国の勝利は決してやってこようとしないものであった。
- 古い同盟国にとっての新しい目標
1939年春の防共協定の弱小国への拡張は、皮肉なことにその死の宣告であった。ハンガリー、満州国、スペインの加入がもたらした表面的刷新にもかかわらず、協定の目標は記憶の引き出しの中に忘れ去られた。独・伊・日は新しい優先順位を持ち始め、1938年をとおして展開されたプロセスに従いながら、自分たちの敵意を民主主義諸国に向けるにいたった。1939年英仏は、自分たちが全体主義諸国の主要な敵であるという好ましからざる証拠を、以前はソ連が申し立てていたのだが、突きつけられることになった。この方向転換はさまざまな位相に影響を及ぼした。防共協定拡大の直後、5月22日、ローマとベルリン間の枢軸で、「鋼鉄同盟」が結ばれ、それに8月23日、意外な独ソ不可侵条約が続いた。それは一週間後のポーランド侵攻の嚆矢であった。そして最後に、パリ・ロンドンとベルリンの間で宣戦布告が発せられ、ここに第二次世界大戦が始まったのである。
ドイツはポーランド支配のためにソ連との協力を決意していた。そしてその後の民主主義諸国の反応は枢軸国間での優先順位を完全に覆してしまった。戦争への展開は驚きではあったが、説明がつかないものではない。なぜなら、ナチス党が政権について以来、日・独・ソ連間の三者協力は英米の優越に挑戦する唯一の方法として考えられていたからである。例えば、ナチの実力者カール・ハウショーフェルは1934年4月、この最終目標を見据えて、ナチス党と日本軍間の第一回目の秘密協議の場として自宅を提供していた。しかし、最も重要なことは、1939年のベルリンの新政策にローマが、そして2年と少しの後には東京も続いたということである。日本のそのゆっくりとした方向転換は、ためらいに満ちたものであったが、5つの時期に区分できる。それを知ることは、日本の外交政策の展開や、それゆえに日西間の接触の文脈だけでなく、絶頂期にある全体主義国家間の関係を理解する上で不可欠である。
ヨーロッパでの危機を利用しつつ、帝国の立場を強化する可能性を最初に日本に指し示したのが「天津租界封鎖問題」である。事件はこの中国の港湾都市で親日派リーダーが暗殺され、その容疑者を英国が日本当局に引き渡すのを拒否したことから始まった。あきらかに、法の裁きが情け容赦なく彼らに落とされるのを恐れてのことであった。英国の拒否によって、日本が、英国による容疑者引渡しまで、この治外法権居留地を封鎖するという事態を招いた。東京は、国際政治のかなり緊迫した時期に、英国とその同盟者である蒋介石の国民政府を屈服させた。英国は、ヨーロッパにおける敵がその弱さをついて攻撃してくるのを恐れ、封鎖を解除するための艦隊を送ろうとしなかった。その上、天津問題はヨロンドンではヨーロッパの方がアジアよりも優先されるということを明るみに出した。帝国の防衛は、帝国そのものの存続をはかることに最終的に道を譲ったのであった。日本はアジアにおいてますます大きな将来の自由を得ていった。
合衆国は日本のさらなる前進を食い止めることのできる唯一の国として残った。フランクリン・ルーズベルト大統領は、日本の大陸進出以後日増しに親中に傾いていく世論に支えられて、その役割を引き受けようとしていた。1939年6月26日、彼はそうした決意を示して、1911年から有効のワシントンと東京間の通商条約が今後6ヶ月で切れると通告した。この破棄の衝撃は日本にとって致命的である。なぜなら、合衆国で原料の大半を購入できないばかりか、中国大陸での戦争で日本は一層それらを必要とするようになったからである。日本は代わりの市場を見つける必死の努力をしたが、たいした成果はあげられなかった。他方、あらゆる手を尽くして石油のかなりを合衆国から購入し続けた。その結果、時間の経過とともに、攻撃能力を失う前に攻勢に出るという決定をしなければならないと感じるにいたった。天津での日本の勝利に続き、ワシントンは最終的に一つの手段をとった。それは、当時そう言われていたのだが、日本に自分は水が徐々になくなっていく水槽中の魚であると気づかせることであった。そうした認識は最後の瞬間パールハーバー攻撃を引き起こした。勝ち続けることで日本にはさらなる努力が一層必要とされた。
日本の政治的転換の第二はソ連との国境の安定化であった。今回は不快感のほうが先にきたけれど、東京は再びほろ苦い思いをした。独ソ不可侵条約は東京にとってあまりにも不愉快な驚きであり、平村騏一郎内閣の総辞職を引き起こした。彼は就任時にまさに防共協定の強化を目標の一つに掲げていたからである。独ソ不可侵条約で独総統は軍事的にも日本に打撃を与えた。なぜなら、これによりスターリンは、ちょうどノモンハンでの決戦時に、ヨーロッパ国境から注意をそらし、その分アジア国境に集中することができたからである。これは、1939年6月から8月の間、外モンゴル国境地帯で起きた日本軍とソ連軍の衝突事件である。衝突といってもその死者は1万7千人に上り、他の多くの戦いにひけをとるものではない。公式な宣戦布告と伝達手段がなかっただけで、ノモンハンはその規模と重要性からいって、戦闘というよりは戦争である。
西側国境が平静で、モスクワはジューコフ将軍指揮下、日本軍にほぼ40年間で最初の深刻な敗北を与えた。その結果は決定的であった。東京は援軍を送るという対応ができたかもしれないが、独のポーランド進行の報を聴き、自分たちの戦いをヨーロッパで生まれつつあるそれと混同しては為らないと気がつき、9月初旬に退却した。こうして戦いはすぐに終わり、和平が数週間で調印された。ノモンハンは、モスクワと東京間の関係にとってUターン禁止点であった。それ以来両政府ともその緊張の無益さについて熟考し、その敵意を別の方向に向けるほうが有利であると判断したからである。道理はあった。ソ連にとって国境の一つを軽減することは死活問題であったし、日本にも反共の戦いはむしろ不必要な妄想であると徐々にはっきりとしてきたからである。ノモンハンの一年前、同じような張鼓峰での国境紛争でやはり日本軍は敗れていたが、一方南での機会は輝かしかった。なぜなら戦いで常に勝利し、シベリアのステップと比べると戦利品と目されるものも一層興味深かったからである。実際にソ連軍の力を体験してみて、東京はドイツの道をたどり、その対決を同盟国とその帝国にしぼることにした。方向転換は世の支持を獲得するための仮定の一つではなくなった。
第3のステップは1940年7月の近衛文麿の政権復帰である。1939年初めの総辞職以来、いくつかの短命内閣(平沼騏一郎、安部信行、米内光政)が続いたが、支那事変以後確立した路線に代わる方向性も、当時の変わりやすい状況に必要や安定性も見出すことができなかった。近衛の復帰の主な帰結は次の3つである。外交関係における枢軸側への回帰、国内の権威主義の強化、新しい重要人物の入閣。
第一の帰結は、独伊の運命から日本の外交政策を切り離そうとする意図において、それまでの内閣が失敗したことであった。皇室も外交官やその他の主要行政に携わる人物たちも、日本がもし欧州の民主主義国との対決の道をとれば背負うだろう危険に気づいていた。それゆえ関係改善の可能性を模索してきたのである。しかし、他の選択肢の模索は失敗した。なぜなら、ドイツが仏・英・蘭を弱体させれば、それが間接的であろうと日本の利益に資することを忘れることができなかったからである。穏健派からの理にかなった主張や将来への警鐘は、日本軍の短期的利益とアジアにおける「新秩序」の模索を前に、ついに自らを優先させることができなかった。戦争の論理が支配的になった。地球のさまざまな地域から入るニュースからの影響が日増しに強まる世界で、第三帝国の勝利は誰の目にも明らかだった。そしてこの帝国と日本は目標および敵を共有していたのである。
東京は本来の同盟国のその「地位」を拒絶することはできなかった。一方、英国の重要性は仏・蘭・ベルギーが敗北して以降、過小評価されていた。さらに日本は、アジアにおけるヨーロッパ植民地へもの欲しそうなまなざしを向けていた。地域を支配したいという欲求の中、ベルリンが成立したての対独協力政権であるヴィシー政府との何らかの合意にもとづいて仏領コーチシナを占領するのではないかという見通しは日本を不安にさせていた。日本は日増しに親独になっていったが、しかしそこには限界もあった。
ドイツと同様の政治的展開をとげるために国内の改革に着手したことは近衛内閣成立の第二の帰結であった。第一次内閣の総辞職後、近衛は大政翼賛会を組織しながら「総力戦体制」という理念を具体化するために、新体制運動の総裁の地位についていた。これはナチス党やファシスト党とふつう比較される。共産主義者から急進派右翼まで、非常に多様な筋からの人間を一つの理念にまとめ上げ、大政翼賛会は近衛が首相に復帰するや否や、政府への支持を拡大するための主要な道具となっていった。これとともに、体制への異論を排除し、中国での戦争勝利のためにより強力な戦力の準備を可能にするような措置が段階的にとられていった。
近衛内閣の第三の帰結は、二人の急進的な人物の入閣である。一人は陸相・対満事務局総裁となった東条英機で、もう一人は外相に就任した松岡洋右である。東条は元統制派のメンバーで、満州派の創設者であり、中国における日本の拡大を熱烈に擁護していた。松岡は1933年満州事変を機に日本が国際連盟を脱退したときの外交団長で、満鉄(南満州鉄道)総裁を務めていた。彼はまた満州国建設の主要な擁護者の一人であった。満州は日本において、将来の自給自足、総力戦を可能にするだろう無尽蔵の資源の地として構想されていた。松岡も政党解体の動きに積極的にかかわったが、彼の主な貢献は欧米諸国を取り扱う際の彼の経験にあった。ワシントンは、アジア南東部にあるオランダや英国植民地が攻撃にあった場合は、自動的に戦争に突入すると警告していたが、松岡によれば、日本は何進をやめるべきではなかった。なぜなら、それは対等な立場の敵を相手にしているということを(アメリカ側に)最もよく分からせる方法であったからだ。
敵との正常な関係を回復するには、これらの国が日本の強固で決然とした態度に遭遇するしかなかった。いかなる戦術的な駆け引きがより適切であるか、交渉に際してのどのような宣伝に訴えるか(強硬であるというイメージを示すか)について日本人の間でも意見が分かれていた。松岡は外務省を刷新した。彼の強力な個性で自分の重要性を引き立たせ、新しい政策の旗頭になろうとしただけでなく、その実現のために、ドイツへの接近を遅らせようとしてきた外交官の多くを更迭した。その結果、枢軸との関係は、1936年の防共協定交渉時のようにもはや軍人ではなく、外務省主導のもとで行われたのである。新しい戦略的同盟は松岡が直接交渉し、人的・政治的コストは非常に大きかったものの、外務省が政治の舞台中央へ復帰したことを示すものであった。
三国同盟はかつて防共協定に署名した国々の結びつきを強化するにあたって第4の局面をなしている。1940年9月27日、日・独・伊によって調印されたこの協定は待望の勝利後の各自の勢力圏を確定した。防共協定とは異なり、その目的はソ連を締め付けることではなく、日増しに拡大する合衆国の干渉を押さえ、さらには原料輸出に対する規制強化の撤回さえも目論むことであった。三国同盟は技術的に言って、完全な軍事同盟ではなかった。同盟国は、もしメンバーの一国がその時まだ戦争に参加していない国から攻撃されれば、政治・経済・軍事的なあらゆる手段を持って互いに援助しあうことを約束していたが、その軍事的義務が直ちに発生するということはなかった。日本は紛争に参加するかどうかの決定を自主的に行うことが可能であった。むしろ、その性急な結論や条文の詳細における杜撰さから判断すると、この協定は「経済的見地からの」イメージを投げかけようとする広告的・宣伝的努力であるといえる。同盟国間の協力は、どちらかというと異なる形での言葉の範囲内にとどまっていた。というのも報道機関は抑制された調子を装い、1938年にローマが防共協定に参加した時のときのような大衆的な祝賀の表明はなかったからである。イタリアの政治的凋落への丁重さ、ファシストによるあふれんばかりの宣伝は過去のものであった。
ローマは確かに、それまで蓄えてきた巨大な政治的富を短期間で失っていた。ヒットラーとスターリンの合意の後の1939年、(イタリアが)日本にとって唯一真の友人であるという発言から、イタリアは第三帝国の影に1941年入ってしまった。理由は多くが政治的なものであった。敵を苦しめるために東京に依拠するという発想は天津危機以後その有効性を失った。なぜなら、アジアにおける危機を追い払う前にヨーロッパでの脅威に全力を注ぐという英国の決定が、その艦隊を二分させるために同時に二つの危機を作り出そうとするイタリアと日本の思惑を蹴散らしてしまったからである。イタリアとギリシャ間の戦争で東京は中立を宣言し、その目標の優先順位がまた一つ明らかになった。最近ヨーロッパで購入し、ギリシャ船籍の船で運ばれて来ることになっていたくず鉄の到着を日本は心配していたからである。日本政府は、船が無事に商品を引き渡し、次の目的地――連合国側の港であろうと――に向けて出港できるよう、あらゆる種類の保障を与えていた。しかし、中立の主な理由は明らかであった。イタリアの軍事的大敗を喫したことは、大国というイメージとゆがめられた現実との間のあまりにも大きな乖離を明らかにしたのであった。ローマは泥足の巨人で、1941年夏からイタリアの外交官たちは、からかいの対象とは行かなくても、無視されることが多くなった。
反響から米英との対決への日本のこの方向転換の最後の局面は、1941年4月の日ソ中立条約の締結であった。東京・モスクワ間の関係は、満州国とモンゴル間の国境合意に到達した1940年夏、はっきりと改善の兆しを見せていた。さらに、サハリン島での鉱山採掘許可や太平洋北部での漁業など、古くからの問題の合意に向けて交渉も再開された。その後、日本には三国同盟でソ連との均衡をはかる仲介役という奇妙な役割が回ってきた。ただ、スターリンは日本の友好的な思わせぶりを信用することはなかったが。そして最後に、松岡の重要なヨーロッパ訪問がくる。旅の途中立ち寄るモスクワで、松岡は日ソ両国の関係を「調整する」ためにソ連との交渉に入るという権限を付与されていた。ソ連指導者たちとの会談後、ローマ・ベルリンを訪れたが、そこでソ連への攻撃が近いことをまったく知らされずに、松岡は帰路再びモスクワを訪れ、1941年4月13日日ソ中立条約に調印し周囲を驚かせた。両国は今後5年間、一方が一つまたは二つ以上の第三国より軍事攻撃の対象となる場合には、他方は該紛争の期間中完全に中立を守ることを約束した。中国への支援を中止するようソ連を説得する必要性からこの条約を正当化しつつ、日本は南進への自由裁量をえて、北部国境の緊張から自らを解放することができたのである。
松岡はヒットラーに、彼のソ連侵攻時にようやく克服できることになる、あの世に聞こえた驚きを与えた。ドイツのソ連侵攻でもって力関係の地図は急激に書き換えられた。日本はロシアを徹底的に敗北させるという古い望みをまた持ち出さざるを得なかった。数週間で新しい不和が引き起こされた。日本は、モスクワが戦い続けていることを確認した後、南進を続ける方を選択する決定をしたのである。それで、こうした玉突きのような外交にもかかわらず、中立条約は第二次世界大戦を通じて最もよく維持された条約の一つとなったのである。スターリンはここから最も利を得た人物である。というのも日本が南進に固執したおかげで、ヒットラーとの戦い集中できたからである。12月にはパールハーバーで新しい衝撃が走る。世界の悲喜劇は終わりがないかのようであった。
- 膨らむ野望
国際社会は特別な瞬間にあった。変化は急激で、すべてがどう終わるかを予測できる者はいなかった。ドイツ軍が進攻を続けるにつれ、勝者と目される者の期待は膨らんで行き、常勝への喜びだけでなく、過去の欲求不満への償い要求があらわれて、自制を失っていった。大日本帝国の野望にも同じことが起こった。フランスとオランダの倒壊および英国の甚大な被害は、日本の目に「一生に一度の」好機と映り、そのおかげで日本は中国における最終的勝利だけでなく、無防備な南東アジアの植民地への支配も得ることができるであろう。そして手に入るものすべてを。三国同盟の交渉で松岡外相に渡された文案には、東京が手に入れようとした領土のリストがあったが、それらは日本の桁外れの野望を示している。それによると、旧ドイツ領ミクロネシア(すでに国際連盟の委任統治Cとして帝国の手にあったが)の承認だけでなく、インドシナ、仏領ポリネシア諸島、タイ、マレーシア、ビルマ、英領ボルネオ、蘭領東インド、オーストラリア、ニュージーランド、そしてインドに要求が及んでいる。その上この長いリストの終わりには、万が一の場合に備えて「等など」と書き加えられていた。どうなるか分からないこの変動の時代を前に、要求には限定を設けないほうがよいから。
しかし、この夢や展望の向こうには、中国においてさえ日本の野望がかなわないという現実があった。軍国主義者は、ヨーロッパの枢軸の勝利という状況と二つの具体的理由にしがみつき、最終的には勝利するという信念を失わなかった。理由の一つは、支援を立たれると中国の民族主義者たちは資源を使い切ってしまうだろうという可能性と、もう一つは王精衛の背信後の内部分裂である。「支那事変」後、中国は共産主義者、民族主義者、そして親日派という三勢力間の内戦に陥った。「仲違いさせ、勝利せよ」という政策はたぶん成果をあげて終わるであろう。仏領インドシナはこの時期日本が好んで活動するもう一つの舞台であった。日本は、中国国民党政府に対してそこに軍隊を派遣するため、フランス人将軍たち、そして地元当局と最初の合意に達した。日本は最初飛行場の建設と軍事施設の維持を求め、民族主義者への支援が南から行われるのを阻止しようとした。しかし、時の経過とともに更なる譲歩を引き出し、南から中国の敵を攻撃するためにインドシナ通過の権利を獲得した。日本の侵入はヨーロッパでのフランスの敗退と、アジア領域でのフランス当局の協力的行動によって容易になったと思われた。
英米の反応があった。インドシナでは米国が日本への鉄の輸出を禁止し、英国は「ビルマ街道」を再開した。それは重慶の国民党政府への唯一確実な供給ルートであった。日本の進攻は実施されたが、しかし決定的敗北を引き出すことなく、ますます重荷を抱えることになった。
ドイツ軍によって侵攻された宗主国オランダの植民地東インドは、もうすこし抵抗した。そこはインドシナより戦略的にずっと重要な目標であった。なぜなら日本は米国から拒絶された石油を得ることができるからだ。この目的のため複数の外交使節団がバタビア、現在のジャカルタへ送られた。しかし、オランダ人統治者たちは、かなりの量の供給を拒否した。その理由は、一つにはロンドン亡命政府に忠実であろうとしたためで、もうひとつは、日本の関税政策が中国への輸出に利するものであったため、日本には石油代金を支払うための強い外貨が残されていなかったからである。これは東京で外交交渉に努力してきた勢力にとっては打撃となった。オランダのこの拒絶が軍国主義者たちに有利に働いたからである。強引な侵攻が製油所や油井を破壊することになっても、ますます増大する燃料の必要性から、現在のインドネシアを軍事的に占領する以外の道は残っていなかった。そして、そこに到達するためには、途上にある領土を征服しなければならなかった。全アジアが日本の支配下に落ちる何らかの理由があったのだ。
ヨーロッパでも帝国の野望は今にも達成されそうだった。ナチス・ドイツは待ち望んだ民主主義帝国の最終的敗退から成果をもぎ取ろうと先頭に立っていた。ヒトラーの考えによれば、その野望の主たるものとはドイツ民族が権利として当然もつ居住地、つまりチェコスロバキアのように彼らが少数派である領域においてその生活圏を拡大することにあった。しかし、生活圏拡大という理念はロシア、あるいはスラブ民族によって占領されている領土を主に念頭においていた。1940年夏のフランス占領は、ヒトラーに考えを変えさせ、アフリカ領土ベルトまでを視野にいれたいわゆる中部アフリカ計画により重点をおくようになった。それは、ベルギー領コンゴ、仏領赤道アフリカ、そしてアフリカ南西部における旧ドイツ植民地、現在のナミビアをも多分含むカメルーンからアフリカ東海岸までの広大な地域である。さらに、モロッコの大西洋岸(アガディール、モガドル)やカナリア諸島における商業上の特恵や海軍基地なども含んでいる。確かにこの中部アフリカ計画がヒットラーにとってどのくらいの間優先事項となっていたのか、どの程度練り上げられたものだったのか、そしてどの程度考慮に値する実現可能なものであったのかは分からない。多分、長期計画として、また米国という未知の敵対者を阻止するために想定されたものであろう。とにかく、英国の敗北とその植民地の接収が必要不可欠の条件であった。
一方、スペインもあふれんばかりの帝国の野望を抱えていた。それは、アルフォンソ13世時代からの伝統的な権利回復というだけでなく、チャールズ・T・パウェルが言うように、「狭義のイデオロギー的符丁としてよりも一人の老練なアフリカニスタの願望に沿ったものであると理解するべきだ」。こうした野望を確信しているアフリカニスタの将軍であるフアン・ベイグベデル・アティエンサを外相に任命したこと、1940年にタンジールを占領したことは、スペイン政府の執着を示すものである。スペイン帝国の野望はフェルナンド・マリア・デ・カスティエーリャとホセ・マリア・デ・アレイルサによる「スペインの復権要求」という著名な本に明らかである。「イベリア半島内では、ジブラルタルの完全返還。
アフリカ大陸ではアルジェリア西部と、われわれのイフニ、リオ・デ・オロ領有に不可欠の緩衝地帯をスペインの主権下に組み込むこと。そうすればモロッコに関して、地中海から大西洋につながる道ができる。英仏がギニア湾でわれわれから奪った領域の返還。最後に、モロッコの保護領をセリフィアノ帝国範囲への完全拡大、もちろんタンジールも含んでいる」。
こうした野望は、今となっては現実性のないものと思えるのだが、マドリードにとって優先目標であった。しかし、ドイツや日本と違い、スペインの期待は敵の抵抗にあうだけでなく、同盟諸国自身の意志にも従属させられていた。ドイツは一番の不安定要因だった。なぜなら、ヒットラーは最低でも第一次世界大戦で失った旧ドイツ植民地の回復だけでなく、同時にアフリカに新しい勢力地図を作ろうとしていたからである。そこでドイツは領主であり、もし運がよければ分配可能な何らかの領土が残るかもしれない。第二の不安定要因は、新秩序のための戦いにおける「弟分たち」であった。ファシスト・イタリアもまた北アフリカにおける新しい植民地獲得に意欲的だった。しかし、スペインの期待はペタン老将軍の対独協力政権のそれと主に重なっていたのだ。スペインが欲する領土の多くがフランスの支配下にあっただけでなく、ヒットラー自身がもうすでに不安定となっている勢力均衡においてさらに付随的な変化を引き起こすよりは、それまでの状態を維持する方を好んだのである。さらに1940年、ペタンに忠実な駐屯軍がダカールで連合国の攻撃を撃退したことは、枢軸の国境が性急なスペイン人よりも猜疑心のつよいペタン政権下のフランス人によって守られていたほうがよいとドイツに判断させた。スペインは全体主義的な色彩に染まり、ヒットラーに対する賞賛を惜しまなかったが、その軍事力には疑問が残ったのである。さらに、連合国に対する枢軸の勝利と平和のあかつきに、各友好国の要求をいちいち聞き入れていたら秩序は全く定まらない。また、ベルリンが和平交渉で大英帝国の維持を持ち出すことも考えられた。もちろん枢軸の勝利の場合ではあるが。しかし、それに対する疑いもまだ晴れたわけではなかった。
スペインの帝国的野望は、確かにトランプの城のようにもろいものであった。切に望まれるロンドンの敗北だけではなく、ドイツの勝利が完全であるかどうか、平和の到来時にヒットラーがスペインの要望を承諾するだけの寛容さを示すか、分配をめぐりイタリアやフランスとの間で合意が成立するかどうかにかかっていた。これらはすべて、その土地に住む住民が自分たちの将来を決定することに関心があり、そのために戦いさえ辞さないということを忘れた上でのことである。その数年前までアブデルクリムが示したように。しかし、スペインの将来への願望は実在したのであり、マドリードが当時とった中・長期的決定にかなり影響した。こうした困難な目標にもかかわらず、帝国の野望はマドリード政府に強い息を吹き込み、スペインが日本に接近する強力な動機となった。同じ敵を持ち、両者とも利益を引き出しうる同時的戦いにおいての共力作用が期待された。それは宣伝戦を勝ち抜かねばならない必要があった。ここではそれを分析しよう。
- 反共主義から連合国に対する戦いへ
比類のない野望の変わりやすい状況を前に、宣伝も転換し新しい政治目標に適合されなければならなかった。相手のイメージを改善することが主たる動機であったから、宣伝で日西の友好がさらに一層促進された。イデオロギー的に近い国であったのみならず、反同盟国という同じブロックに属していたのである。当時フランコ体制を支持するスペイン人ならば、誰しも二重の意味で親日でなければならなかった。つまり、反共産主義者と反(帝国主義的)民主主義者として。日本についても同様のことが言える。モスクワといわゆるABCDに反対し、世界でより良い「ステータス」を渇望していたのだから。宣伝と投げかけたいイメージは、こうしたレンズを通して人は外界を認識するのだが、自分たちの理念を同じ方角に向けて推し進めるものでなければならなかった。なぜなら、スペイン人も日本人も同じ敵、同じ目的を共有していると感じていたから。日本におけるファランヘ党の代表、エドゥアルド・エレーラ・デ・ラ・ロサはこうした考えを持つ一人であった。彼は数年後日本の反西洋主義に遭遇したときも、「スペインの主要な敵」は英米であると「個人的に」考えていることを表明しつづけたのである。
こうした観点で相手国からのニュースは受け止められた。最も興味をもったのは、自分たちの賭けが成功していることを確認する内容のものであった。スペインの新聞が植民地帝国、特に英国によってアジアがなめている辛酸について好んで解説する一方、日本の新聞はスペインが枢軸寄りにいっそう関与することを示す出来事すべてに注意を払っていた。
相手国が第三者に対して与えるかもしれない打撃に関心を向けていた。1939年春から夏にかけての天津危機に関する「アリーバ!」紙の報道はその一例である。なぜならこの市が中国におけるヨーロッパの影響力の拠点であることを示そうとし、次のように結論付けていたからである。「今のところひびが入ったのはただ英国の権力だけである」。スペイン人は単にニュースを聞くだけでなく、彼ら自身の願望が最適な結論に至るために必要なデータをそこに見出そうとするかのごとくであった。ローマ・ベルリン枢軸成立後の1939年5月の報道、「合意は英国に対する断固たる返事であろう」もまたその一例である。「アリーバ!」紙は日本の支持を当然としていた。当時東京はその同盟関係から距離を置こうとしていたにもかかわらず。日本でも自分たちにより直接的影響のある出来事を追っていた。好まれたのはジブラルタルの陥落可能性である。東京「読売新聞」は、例えば、セラノ・スニェルのベルリン訪問を利用してあるニュースを掲載した。「スペインのジブラルタル攻撃の日は近い」というその結論は、自分たちの願望を維持するのに必要な材料を提供していた。願望が事実よりも勝っていた。
不協和音のニュースはしたがって、省略されたか人々の期待にうまく沿うように脚色されていた。例えば、スペイン人は枢軸に参加することに反対している、さらにドイツは「一時的な参加は歓迎されないだろうことをスペインに知らしめ」ているという横山公使の発言は無視された。脚色の一例として反共産主義の指導者である猪股のスペイン訪問をあげることができる。彼はスペインの同じような理念を持つグループによって招かれたのだが、インタヴューをついに受けなかった。というのも、彼に関するバルセロナの新聞記事は「ある部分は消され、他の部分は捻じ曲げられていた」からだ。どちらの国も、異なったやり方ではあるが、相手国の動向を利用して、自分たちの期待を裏書きしようとした。宣伝は隅に追いやられていた側面を回復し、以前は忘れ去られていた情報を利用し、あまり都合よくない状況をごまかすようになった。それが宣伝の本来の機能であるから。
1.2.1.新しいイメージ
宣伝はこの数年間、変わり行く必要性に合わせられた。取り巻く状況がその仕事をやりやすくした。一つには、しばしば願望が現実よりも優先されたからであり、またメッセージは繰り返されればされるほどその効果が増すからである。これは、ヒットラーからゲッペルスまでナチスの宣伝者たちがよく知っていることである。さらに、イタリアの例に倣って、軍事がこうしたイメージを支えた。この時期支配的であった相手国のイメージは、「第二世代」のものである。それ以前の準備段階の産物であり、軍事的側面を称揚するために特に適した状況の産物である。日本人に関するスペインの描き方の主な特徴は、近代と(スペインとの)歴史的結びつきという点である。しかし、微妙なニュアンスに欠けた最小限の基本的知識の産物といえる。こうしたものを一つ一つ別個に見ていこう。
当時、戦士の価値を称揚することはわりあいに普通であったが、各国で異なる側面を持っていた。スペインでは軍事的勝利への賞賛と武士道への言及が目立っていたのに対し、日本では武勇と騎士道精神が強調された。しかし、お互いの賞賛は表面的なものでしかなかった。アジアの軍人たちはここ50年間で長い勝利のリストを持っていたのに対し、スペイン軍はその時期、外国の支援で自分たちの兄弟に対する「民族的」勝利を除けば、敗北しか味わったことがなかった。。このように、双方の立場は釣り合いが取れていなかった。
スペインの軍人筋では中国における勝利が賞賛されていた。特に、対1904~1905年のロシア戦における日本の戦略が特に賞賛され、軍事学校では陸軍と海軍との間の完璧な連携であると教えられた。海軍提督カレロ・ブランコは、当時すでにフランシスコ・フランコ将軍の強力な助手であったが、日本の功績に対ししばしば賞賛を惜しまなかった。ある書簡では、20世紀初頭の日本の戦いを当時中国で行われていた戦いと比較し、「35年後、われわれは当時の基礎の確かさと、また一民族がどこに向かうべきかを知り、その目標に到達せんと欲する時、労働と粘り強さがもたらすすばらしい成果を確認できる」。サントーニャ出身のこの海兵は、一見したところ、日本の最終的勝利とその理由についていささかも疑いを抱いてはいなかった。
大名という封建領主への忠誠、その義務への没頭というサムライの古い倫理的おきては、スペインが日本を賞賛するときに使うもう一つのイメージであった。宣伝のイデオローグたちが必要としたそのままに、戦いにおける日本人兵士の道理や動機が改めて語られた。この理想的人物像が掻き立てた興味の最もよい例は、新渡戸稲造の『武士道 日本の魂』の出版であった。1899年に書かれたこの本は、膨張主義への道を邁進する日本において、伝統の再定義という明らかなプロセスの中、この規範を日本文化の最良で最も価値あるものと賞賛した。1908年にスペイン語に訳され、それ以来その叙事詩を思い出させる数多くの論考が現れた。それゆえ、この章で扱っている時代のイメージでもっとも顕著なのは、祖国に命をささげるサムライのステレオタイプの出現ではなく、こうした認識に対する公的な支持である。1941年の出版を日本が支援したこと―本の普及を「願っている」とはあるが、そう記されているわけではない―においても、またミリャン・アストゥライ将軍―彼は外人部隊の創設者であり、1936年の蜂起後、フランコの報道・宣伝の責任者でもあった―の序文においてもそう確認できる。序文で彼は次のように述べている。「トレドのアルカサルにある陸軍歩兵仕官候補生に対する道徳教育で、私は大いに『武士道』からインスピレーションを得たし(…)、外人部隊の信条、つまり戦闘と死、規律と同朋意識、友情、忍耐強さと頑丈さ、戦火に赴く覚悟といった部隊の精神について、私は『武士道』に依拠した」。この軍人は確かな記憶という点では優れていないし、『武士道』が彼の人生でそれほど決定的であったとも思われない。しかし、この一節は当時の決定的な時期に、彼が信じるに至ったもの、あるいは人に信じさせようとしたものについて語っている。
日本はまた、スペイン的なるものと軍事的なものとの結合についても範を示した。この意味で、フランコが日本から贈られた3つのものが顕著である。彼のために特別鋳造された日本刀。建武の中興のために戦死した14世紀の伝説的な武将である楠正成のブロンズ像。尊皇攘夷(天皇を敬い、外国人を排除する)運動の思想家であった吉田松陰の胸像。最初のものは祖国会(名古屋の愛国的青年団)が、二つ目は日独伊友好協会(日独伊防共協会)が、胸像は山口県下関市が、「偉大政治家、勇敢な軍人」であるとされたフランコに対する献辞とともに、愛国主義の力により自分を克服し、国際共産主義を打倒した国に対する日本愛国主義の記念として贈ったものである。
時代との関わり合いは明らかである。しかし、スペインの武士道に対するイメージに日本で対応するものは騎士道精神のそれであった。横山正行公使は『都』新聞にスペインでの滞在の印象を書いている。「スペインは戦いを愛する。スペインでは今日その騎士道精神が復活する傾向にあり、それゆえ日本の武士道に関心が高まっている」。さらに、1940年のスペイン経済ミッションをまえに、「月桂樹と、サムライの心と響きあう日本の桜とをむすびつける高貴なスペイン」に乾杯をした。それは、軍事的要素を介して互いの結びつきを構築し、宣伝における協力を強化しようとする共通の打算から生まれた騎士のイメージであった。この騎士のイメージは「武士は食わねど高楊枝」という日本の格言を思い出させる。その尊大さと過去の思い出が最大の資産なのである。
他の同盟国は、それぞれに弱いスペインという像を抱いていたが、日本はそこまで極端ではなかった。逆に、東京はスペインに対してもっと練り上げられた政策を持っていた。宣伝は相互関係の中でそれほど大きな比重を占めていなかったし、ラテンアメリカへの架け橋としてスペインを利用しようとする見方を決して見失わなかった。それは経済ミッションについて話すときに見てみよう。さらに、フランコ将軍の巧みな戦術に対する賞賛者はいたけれど、弱さと数多くの敗北という記憶が支配的であり続けた。この一世紀間にスペイン軍は合衆国からタガログ族まで実に雑多な敵の手で多くの敗北を重ねたのである。同様に、キューバやモロッコなどの半植民地反乱を迅速に解決できなかったことも思い出された。すでに松岡はスペインに関する有名な引用で、1898年の米西戦争の敗北やフィリピンでの混乱を極めた植民地支配の終わりについて述べているが、これらは東京にマドリッドが彼らと同等の高みにはいないと感じさせるものであった。
大戦開始時にスペインの宣伝がもっぱら取りあげた日本の二つのイメージがある。技術発展と歴史的結びつきというイメージである。科学技術の発展は日本への賞賛の基本的なもので、この国に関するニュースのかなりの割合を占めている。政治的利害関心が有利に働かなくなった後でさえ、「われわれは、地球の広大な領域に科学の光を投げかけようとする帝国を前にしている」といった類の賞賛は続いた。このスペインの関心には、単なる知的好奇心や友好国への賞賛という打算以上のものがあった。なぜなら、スペインは自給自足体制を確立するための解決として当時流行っていたアウタルキー理論に駆り立てられていたからである。友好国からできるだけ多くのことを学ぼうとしていた。そして日本は、スペインが自足経済の道をとろうとするならば、かならず必要となるその技術発展で支援してくれる主要国の一つであった。日本への経済使節団のメンバーが日本の産業とその技術発展を学ぶことに関心をもち、同時に最大限可能な情報を得ようと戦略を練っていたことは、日本についてのこうしたイメージが有効であったことを良く示している。発展に対するスペインの自己願望が、結果として伝統と近代性をあわせ持つという日本解釈を不必要に長引かせることになった。なぜなら、その近代性は直接スペインを利するかもしれなかったから。
同様に、日本との歴史的結びつきには、単なる歴史の知識以上のものを読み取れる。当時はスペイン人征服者たちの栄光を大いに楽しみ、アジア、太平洋の偉業が特に強調される風潮であったが、その一部を成している。その良い例がすでに述べた『スペインの権利復活』という本の中に見出せる。そこではコーチシナ戦争(1857-1862年)について一つ章が割かれている。著者であるカスティエリャとアレイルサは序章で、そのエピソードが世界を股に駆けたスペイン人の冒険の数々と豪胆さの例とし、しかし、それによってインドシナにおけるフランスの領有を窺う魂胆はないと述べている。とにかく、アジアに関する論がスペインの新国家の野望に関する本に含まれているということは興味がつきない。同様に、アメリカと太平洋におけるスペイン人の歴史に関する一連の記事が、当時のスペイン外交政策を理解する上で最も重要な雑誌『ムンド』に掲載されたのも同様である。1940年4月に登場したムンドは、同年10月から「太平洋におけるわれわれの支配の歴史」と呼ぶものに関する年代記を掲載した。この雑誌は1941年9月から週刊誌になり、かなりの期間続いた。例えばある記事は「太平洋は、16~18世紀の間、スペインの大きな湖であった。文明化という事業目的でそこを通ったのは、スペイン人とポルトガル人だけである。当時、フランス船も、イギリス船やオランダ船もその波を切って進むことはなかった。発見と征服以外に、スペインはもうひとつ別の画期的な事業をやってのけた。それは1540年、フランシスコ・ザビエルによる日本のキリスト教化である」。この覇権は16世紀に限られ、他のヨーロッパ諸国の船も、彼らは都合良く「海賊」とよばれたのだが、時折通ることがあったことを思い出す必要があろう。スペイン人宣教師や聖フランシスコ・ザビエル、キリスト教殉教者たちの所産としてのカトリック信仰への言及と同様に。要するに、この過去の関係を介して、現代の結びつきへの関心や、ついでに現在のアジアの政治に対するフランコ新政権の関わり合いを示そうとしたのである。
それにもかかわらず、太平洋での過去の偉業を思い起こそうとするこの試みの最終的な理由ははっきりしない。太平洋戦争が勃発した後、『ムンド』紙はこれらの記事が「極東からの憂うるべき知らせが時局に与える今日性に促されて」始まったと述べた。そして「その水域にわが国の国旗がもう50年近くも見られないが、何世紀にもわたる輝かしい歴史がもたらす精神的プレゼンスは続いている。それゆえ、この戦いの真只中、わが国の歴史の忘れがたい挿話を想起させるこうした記事を掲載し続けるのである(…)」と続けている。
過去を思い起こしながら将来への賭けもしている、と付け加えられるだろう。確かに、これら一連の記事は偶然や感傷の産物ではない。これらの記事が1942年に突然中断されたのが、セラノ・スニェスが外務省を去ったのと時を同じくしていることからも分かる。その後しばらく時を経て再び掲載が始まったが、頻度は減り、あきらかに
というだけの目的で行われた。帝国の夢は決してしぼみはしなかったが、最も強く想起されたのは1940と42年の間であった。スペイン当局の宣伝によって繰り返されたこの日本に関する3つのイメージは、世界大戦の勝者は枢軸国であるという認識を世論に高めようとするよう仕向けられていた。
1.2.2.行き過ぎ
これらのイメージをより詳細に観察すると、その親日は極端であることが分かる。当時の特異な政治状況からスペイン右翼がとりうる姿勢よりもはるかに好意的な立場を擁護するにいたった。これは例外的な事態であり、いくつかのイメージの中に具体的に現れている。最初、アジアにおける西洋の連帯との関係において、次に地理から日本をはずし、最後に類似性を大げさに論じる。これらがいくつかの政治決定を導いたからには、慎重に分析する必要がある。
第一に、中国で共産主義が広まったという認識がスペインの指導者の間で強まっただけでなく、その地域全体に広がった。アジアにおける共産主義の躍進は「パクス・コロニアル(植民地の平和)」がいったん死に瀕すると打ち破ることが不可能であると見られ始めた。週刊誌『ムンド』の報道記事ははっきりと次のように述べている。「アジアにおけるヨーロッパの影響は減退しつつある。モスクワを首都とするアジア合衆国をつくるというソビエトの古い夢は潰えた。イスラム教徒やインド人、中国人、彼らは別の世界を形作っているが、ヨーロッパの影響力が消えた日には、おそらくわれわれの敵となるであろう」。ドイツやイタリアによって示された道をたどる必要から、スペインは日本の進出をソビエトに代わる唯一の選択肢とみなすにいたった。西洋列強の凋落を喜ぶと同時に、それを回避できない傾向であるとみなしつつ、中国における治外法権と門戸開放システムの終わりは間近であると確信していた。東京だけがモスクワに対抗できる。それゆえマドリードはアジアにおける西洋の一国として享受してきた特権を遅かれ早かれ放棄せざるを得ないと考えたのである。こうした考えはホセ・マリア・コルデロ・トレスによる『スペインの普遍的使命の諸相』に見受けられる。この本は、その出版年が1942年と一つの周期の最後にあたるため、歴史学研究者からあまり取り上げられないが、日本に関する当時の見解を理解する上で基本的なものである。この本には「『白人の連帯』とよばれるものは、それほど遠くない過去にスペインを太平洋から追い出した国々が宣伝の武器として今まで使ってきた」という興味深い一節がある。世界大戦の他の局面でこれに賛同するフランコ主義者はほとんどいないだろうことを鑑みると、これはその時期特有のものである。政治的理由、しかしなによりも野望が、マドリードをしてヨーロッパ旧植民地に対抗する日本の支配の方をはっきりと望ませたのである。
こうした力学の結果、今日では第三世界への連帯とも受け取れるようなスローガンが叫ばれたのである。ファランヘ党機関紙「アリーバ」に1943年掲載された「枢軸諸国はインド人民が彼らの希望を達成するのに協力する」はその最も顕著なものの一つである。記事はベルリンと日本軍によって支援された独立派指導者チャンドラ・ボースを賞賛していた。しかし、当時の報道はイギリス支配を窮地に追い込める人物なら、マハトマ・ガンジーのように、だれでも賞賛したのである。奇妙な状況であった。特殊な政治状況の下、こうしたファランヘ党の賛辞は人目を引いた。なぜならガンジーやネルー、あるいはボースさえインドに権威主義体制を敷こうなどとは思わなかっただろうし、それ以上にスペインや独伊の全体主義者は植民地主義に対し倫理的慎みを少しも持ち合わせていなかったからである。ましてや植民地住民の政治的権利や福祉などに対する配慮などなおさらである。ヒトラー自身日本の政策を支持するこうした矛盾を認め、「基本的なことは勝つことである。その目的のためには悪魔と手を結ぶことも全く辞さない」と、自身の対インド政策では当座の目的を優先させた。日本の宣伝の内容は、長期的には逆効果であるとされながらも、確かに枢軸国によって取り上げられた。全体主義の帝国主義者たちは政治的必要から確信的反植民地主義者と共寝した。ただし、それぞれの行動範囲が重ならない時にかぎってであるが。
スペイン人の間での日本のイメージは、第二に、他の東洋の諸民族との差異化に至った。積極的な理由だけではなく消極的理由からも。内戦の間に生まれ、その後急進化していく過程の中で、日本はアジアという概念とますます同一化されていく悪に対抗する、積極的で反共産主義的な重石となった。
フランコ体制下のスペインで、こうした目的のために「オリエンタル」という用語を使用することは、内戦期に受け取った(モロッコからの)支援やスペインは枢軸国とアラブ諸国との架け橋であるという自負からも不都合であった。一方、「アフリカの」という言葉も温情主義(パターナリズム)を想起させ、すでに存在する植民地に対して都合が悪かった。結果として、「東方の野蛮」というありふれた用語を使い、将来の同盟国に対してはあまり中傷的でない表現を使い分けなければならなかった。アラブ諸国の場合にはそれほど困難ではなかった。なぜならモロッコ戦争で良い近東人と悪い近東人とを区別する必要がすでに生じていたからだ。ホセ・アントニオ・プリモ・デ・リベラ自身がアリカンテの監獄で「ゲルマン人とベルベル人」という題の文書を作成し、そこで、文明化されていない「ベルベル的な」スペインに対抗するアーリア的スペインについて言及している。またエルネスト・ヒメネス・カバジェロ、―彼はフェルミン・イスルディアガ神父と共にフランコ総統の主要な賛美者の一人であるが―、共産主義者について「またもや東方人である。紛れもない東方人がスペインへ戻ってきた」と書いていた。ファランヘ党の文案者たちは「モーロ人」と「アジア人」とを区別し、バルカンからはじまるヨーロッパへの「アジアの侵略」、そしてイベリア半島からはじまる「黒人とベルベル人」のそれに対する不安をほのめかしていた。こうして「オリエンタル」というイメージはあまりにも身近すぎまた幅広いものであったので、別の用語の使用がのぞましかった。
それゆえ「アジア的」という言葉がこの時期に最適のものとなった。それは経済的遅れ、従属、野蛮、異人種、共産主義、遊牧民、黄禍、未知の恐ろしい諸民族による西欧への実際的脅威などを意味していた。そうして、1939年、ドイツによるポーランド侵攻直後に起こったソ連・フィンランド戦争へのスペイン政府の公式発言において、この用語が使用された。「アジアの野蛮に対して戦ったスペインは、フィンランドの人々への深い親愛の情を示す」。1941年、ロペス・イボルという精神科医は西洋の問題に関するスペイン人の倫理的「パトス」について語り、「カトリック者としての尊厳をもって」生きるか、あるいはそうでなければ「アジアの共産主義者の一ジンギスカンの奴隷と成り果てるか」と述べた。
この有名な精神科医は、その後論調を変えなければならない場合に備えて、尻尾をつかまれないような話し方をしていた。次にどんな宣伝の転換がくるか誰も分からなかったのである。
日本は、そのアジアのイメージの対極になりつつあった。過去にモンゴルの侵入に対して戦ったからというより、政治状況、進歩や工業発展というイメージ、それ以前の時期に中国との関係上役立った認識上のバランスをとるという必要性などが、日本がアジアと同一視されることを妨げるのに役立った。日本は友人であり反共産主義であると受け取られていたから、「野蛮な」近隣諸国と同じ形容詞を当てはめることはできなかった。最も興味深いテキストの一つをヘスス・パボンが雑誌『頂点』に書いている。「共産主義は西洋の帝国主義に対する東洋の革命主義の勝利においてのみ可能であろう。それは世界がロシアのインドの、中国の支配に下ったとき発生するだろう」。日本は弁証法上の逸脱を意味し、その結果政治的・イデオロギー的一貫性の無さを後から正当化しなければならなかった。日本が反共主義で、しかも西洋から学んだおかげで進んだ国であるならば、それがアジアに位置することは地理上の過ちとして理解されなければならなかった。それは辻褄合わせのプロセスであり、歴史上それほど異常なことではなかった。ましてや独裁期においては。日本人自身が同じような自己認識をもっていたのである。
この時期の行き過ぎたイメージの第三は、類似性を追い求めようとすることである。外交の首脳たちも、他の多くの人同様に繰り返しそれを行った。例えば、マドリードの日本公使須磨ヤキチロウはイエズス会士モイセス・ドメンサインの『日本、その発展と文化、宗教』の序で「二つの民族の並外れた共通性」を強調した。東京におけるスペイン公使メンデス・ビゴもまた、日本におけるスペインのイメージは非常に好ましいと率直に語った。「知識人サークルの中には、まったく根拠が無いわけではない一つの見解がある。それは両国の間に性格上きわめて似ている点があり、それが互いの好奇心を刺激するのに明らかに役立っているということである」。類似点を探すということは確かによい手段であったし、手段である。なぜなら通常国民に好意的に受けとめられ、違いを言い立ててその補完性を見つけ出すより危険が少なく、より容易い知的行為である。しかし、両国間の関係にとって持つ意味を探るために、この類似性という見解をもう少し掘り下げてみよう。
当時の二つの文書がその理解を助けてくれる。最初は『アリーバ』に1941年4月に掲載された記事で、前述したエルネスト・ヒメネス・カバジェロが書いている。二つ目は『現代日本』に登場し、1940年5月、枢軸国との同盟に最も好意的であった『東京日日新聞』に再び掲載された一連の記事である。その執筆者は大学教授風間アキオと思われる。ヒメネス・カバジェロは初めに相互の親愛感や、数日前に調印された日ソ中立条約ゆえに明言はしなかったものの、共通の敵との戦いに共に立ち向かう日本に対する賞賛を惜しまなかった。それに続く一節の全文を以下掲載する。
しかし、スペインの日本に対する賞賛や親愛感は今に始まったものではなく、日本がもう一つのスペイン、あちら側のスペインであるとわれわれが気づいた時からのものである。つまり、日本は強大な西洋大陸(合衆国)と巨大な有色大陸(中国やインドのアジア)に対峙する国である。こちら側のスペインは英・仏(西洋)とアフリカ(オリエント)の間に位置している。スペインと日本は世界の二つの境界に位置する、二つの扉である。地球上で単一の運命を担っている。
日本を「有色大陸」から切り離し、日本のイメージを取っ付き易いものにしてから、ヒメネス・カバジェロは、スペインが「日本の発見者、布教者」であったことからその最初の「研究者、探求者」であったことまで、共通のアイデンティティーの理由を挙げる。その後中国人と日本人との違いに踏み込む。一方で、日本は中国人を理解するほど東洋的であるが、しかし、彼らを植民化するほどにアーリア精神をもっているとする。それはスペインが「ベルベル人やアメリカの原住民」に対すると同様である。宗教については、「中国」仏教は「自身の記憶」に欠け、「衆生への信仰」にあふれている。一方、日本は秩序を重んじ、祖先を敬い、「祖国のための死は名を残すことである」ということを知っている。日本人の「神身」―おそらく「神」のことを言っていると思われるが、彼は英雄と訳している―への崇拝はそこから来る。歴史を回顧しながら、ヒメネス・カバジェロはスペインと日本を比較もしている。彼はサムライの闘将を流し目の「シッドたち」ととらえ、(日本の)国の支配をめぐる古い戦いと「カスティーリャとカタルーニャ、カルリスタと自由主義者、ナショナリストとアカ」との戦いの間に類似性を見出すなど、多くの共通点を探した。文学の領域では、「俳諧」や短歌と自国のセラニーリャ〔15-16世紀にはやった恋愛歌〕、また「能」とロペやカルデロンなどの劇との間に類似性を見出そうとした。薩摩焼をタラベラの陶器のようにみなし、日本人が「自分たちの科学を西洋化した」ことを指摘するのも忘れなかった。ハラキリ(切腹)や「死万歳!」などを生み出し、生への執着に対する蔑みという共通点を示した「神秘的で兵士の諸民族」への賛歌で終わっている。結局のところ、このファランヘ主義者の論考は、帝国への期待を抱く当時のスペイン人がもっていた日本人のイメージの要約である。敬虔で、西洋化され、勇敢で、歴史上自分(スペイン)と似ており、文化的に発展し、文化間のかけ橋となる能力をそなえた日本である。
一方、風間アキオは、同じく歴史から、聖フランシスコ・ザビエルへの賞賛から始めているが、作品の準備にもっと時間をかけたことは明らかである。ザビエルがバスク人であることに着目して、次のように述べている。この民族が「外見や言語構造において」東洋人、特に日本人に似ているという点―そうではないと証明されているのだが―に基づくと、「彼がバスク人だったことで日本語がよりたやすく理解できたかもしれない」。また次のようにも主張している。聖人は16世紀の日本にいたとき、彼らを改宗させるよりも文化的手段で彼らを導きたいと考えていた。そしてロドリーゴ・デ・ビベロ・イ・ベラスコ―自分のガレオン船が日本に座礁した後、日本で生涯を終えたフィリピン総督―はおそらくルイス・フロイス―数世紀間この「日出る国」の最大の理解者と考えられているポルトガル人イエズス会士―と同じくらい日本語に通じていた。この二つもまたありきたりの解釈である。なぜなら、有名な漂流者が高度な日本語知識をもっていたとする証拠はなく、また日本ではザビエルをスペイン人兵士たちの先駆者として描くことの方が好まれるからである。政治的文脈によって論法は(ほとんど)自分の好き勝手にねじ曲げられた。
より同時代的テーマをとり扱うとき、風間は戦いと冒険に匹敵する精神に言及し、ピカソの作品と日本芸術とを比較し、二つの国の人へのもてなしや感受性という類似点を指摘した。また、明治を振り返り、門戸開放の初期にみられた外国への行き過ぎた賛美を批判することも忘れなかった。フラメンコにも着目し、それがヒターノに由来するものではなく逆であるとしている。そこにある直感的でかつ「品格と儀式を価値あるものとする心構え」を評価した。この二つはスペイン人の生活の基本的特徴である。東洋で最もスペインに近いのは日本であると断言する。
風間にも見知らぬ国を描写するときによく見られる女性への関心がみられる。彼はスペインペンの男性がイスラム教徒や他のヨーロッパ諸国との戦いで、そして異端審問によって男性が減少したという理由で、「スペインの女性が自国の男性よりも優位にあるという見解」に信憑性を与えている。それゆえ、日本女性もスペイン女性も洋の東西を問わず、他のすべての女性たちを凌駕していると結論付けるのである。彼は両国の儀式を比較し続け、セビリアのフェリア、メリメやビゼーのカルメンと日本の結婚式を関連づける。そして最後には、ヒメネス・カバジェロのように、サムライや「気高い貧しさ」についての非常に日本的な解釈に触れている。「イダルギア(郷士としての高潔さ)」や具体的な人物への言及はなかったものの、この「気高い貧しさ」はスペイン精神にもあると述べている。風間は勇敢で日本化されたスペインを描き出し、それは歴史や文化の発展において日本との類似点を示している。
ヒメネス・カバジェロや風間の論調は時代の風潮を映し出し、当時の政治状況に利するこれらの相似点を高らかに掲げるため、資料をねじまげ差異を無視する強い傾向をもつ。さらに、この二人を比較してみるならば、互いのイメージに違いのあることが分かる。スペインの著者は帝国としての目標を獲得するための一つのモデルとして日本を見ているのに対し、日本人の方はスペインのエキゾチックで民俗的な側面を取り上げようとしているからだ。一方は他方を男性的な国として、その逆は女性的なものとしてみている。二つの民族とも互いの相手国にとって好都合であるが、スペイン人は日本について理想的イメージを作り出す必要があったのに対し、日本人にはそれがなかった。この点では、一方(日本)の帝国の目論見にとって他方(スペイン)はそれほど好都合ではなかったといえよう。
日本との具体的な関係はそれほどないにもかかわらず、宣伝によってこの国は新生スペインの友好国の中で最も傑出した一国となった。その結果、日本について理想的なイメージが出来上がった。この国との有効の重要性が持ち上げられた例としては、イタリアやドイツの「バンザイ」の後に「日本万歳」が聞かれ、ヒットラーやムッソリーニの後に天皇がくるといった具合である。ミリャン・アストゥライもまた年頭の挨拶で「現在の偉大なる指導者がそびえ立つ民族が覚醒しないかぎり」救済の道はないと説き、ムッソリーニ、ヒットラー、ヒロヒト、オリベイラ・サラザールという順番でその名を上げ、最後に自国の総統でしめくくった。
日本のその理想的イメージは短期間で終わった。それは1937年から膨らみ始め、1940年夏のフランス降伏で強まったが、ソ連へのドイツ侵攻を日本が支援しなかった1941年の中ごろにはしぼみ始めた。それはヒメネス・カバジェロの論考が出版されて数ヵ月後のことであった。日本を夢見る期間は短く、その反響も限られていた。この国に関する情報は非常に乏しく、間接的情報源にしか頼れないという欠点をもっていた。さらに、日本に関する部分的な賞賛はあったが、全般的に魅了されることはなかった。所詮、日本はヨーロッパではなかったからである。例えば、スペインに対する日本人世論の動向はマドリードでの優先事項ではなかったようである。外務省文書の中で「第二次世界大戦に対するスペインの政策の日本世論における反響」に関する電報が他の公使館のものに比べ非常に乏しいことからも分かる。
それにもかかわらず、日本の理想化はスペイン左翼のソ連に対するそれと同じである。ソ連邦における社会主義を革新的で積極的なもの、「人類の偉大なる希望」とみなす完全に理想化された認識は様々なイデオロギーを持つ人々を引きつけた。例えば、アントニオ・マチャードは決して共産主義に傾倒したわけではないが、ソ連やスターリンに対してさえ彼の作品『フアン・デ・マイレーナ』の中で賞賛している。明らかに軍国主義日本と社会主義ロシアのイメージはかなり異なっている。前者は膨張するために生まれ、後者はむしろ防衛という面をもっと持っていた。 一方は伝統の、他方は革命のイメージ。一方はすぐに消え、他方はより長い時間もちこたえ、そしてフランコ独裁さえを生き延びた。日本への認識は左翼の間でのソビエト社会主義国のそれほど強烈でも強固でもなく、むしろ偏っていた。それにもかかわらず、類似点もあった。双方とも接触の欠如から、また幻影を信じるというまさにその必要性から生まれ、主に宣伝によって支配されたヴィジョンに基づいていた。ソビエト化されたロシアもサムライ日本も、スペイン内戦の各陣営の夢想によってもたらされた価値を体現するものであった。それらは固有の現実というよりは各自の野心と願望の産物である。人はそうしたイメージを抱きはしたものの、それに触れることにより価値が損なわれることをおそれた。スペインと日本の両民族が相手に対して持っていた認識は温度差もあったが、確かに肯定的であった。
こうした刷新された肯定的認識が両国の関係にどの程度まで貢献したかを知ることは実際のところむつかしい。両国が相手国について持っていた理解を進めたことは確かである。そのために時節をより利用したのは日本であった。スペインでは相互理解への期待は当時出版された本や新聞紙上の域を出るものではなかったようである。日本に関する専門家集団がいたわけでもないし、知識を流布する手段もなかった。スペインにおける唯一の日本に関する活動主体は宣教師たちであったが、映画を上映し、展示会を開催する程度であった。当時すでに日本のスペインに対する片思い状態であった。日本のスペイン理解はスペインの日本に対する理解よりもはるかに大きかった。
日本のスペイン研究者たちはスペイン人よりも、より広い立場から政治的便宜を享受することができた。またスペインの代表者たちのコメントも引き出すことができた。例えば、メンデス・デ・ビゴは、風間アキオの論文について言及した後、商業を活発化することへの関心がスペイン文化やスペイン語への関心をも喚起していると述べている。ファランヘ代表のエレーラ・デ・ラ・ロサも、当時のスペインが日本でかなり知られており、「特に行政面についてはおそらく他のどの国よりも、われわれの所業が注意深く研究されている」と語った。どちらも名前を挙げていないが、軍国主義日本におけるスペインの主たる宣伝者である藤沢親男について言及している。九州帝国大学の教授で、日本人の人種的純粋性を説く最も急進的で多作な流布者の一人であった。そのために、彼は日本が「母なる地」として先史時代に崇められ、神武天皇がダビデ王から由来し、一方バビロニアやエジプト、中国は「子孫の地」と考えられていたことをおそらく示すであろう考古学的、言語学的情報をさがしていた。彼は大政翼賛会の研究部長を務めるなど幾つかの要職に就き、メンデス・デ・ビゴやエレーラらスペイン人には報知新聞の局長として紹介されていた。この新聞は1942年強制的な合併により読売・報知新聞となったが、1923年ビセンテ・ブラスコ・イバニェスを東京に招き公演を開催した。しかし、熱心な藤沢がそのようなポストについていたかどうかは確認できなかった。
藤沢はスペインに大変関心があった。1940年にはイタリアを経由してイベリア半島に旅行する計画をもっていたが、彼がやって来たという証拠はない。スペイン語でかかれたパンフレット「日本の世界政策の精神的基盤」にみられるように、広範な宣伝活動を行っていたことは確かである。
日本のスペイン研究者たちはスペイン人よりも、より広い立場から政治的便宜を享受することができた。またスペインの代表者たちのコメントも引き出すことができた。例えば、メンデス・デ・ビゴは、風間アキオの論文について言及した後、商業を活発化することへの関心がスペイン文化やスペイン語への関心をも喚起していると述べている。ファランヘ代表のエレーラ・デ・ラ・ロサも、当時のスペインが日本でかなり知られており、「特に行政面についてはおそらく他のどの国よりも、われわれの所業が注意深く研究されている」と語った。どちらも名前を挙げていないが、軍国主義日本におけるスペインの主たる宣伝者である藤沢親男について言及している。九州帝国大学の教授で、日本人の人種的純粋性を説く最も急進的で多作な流布者の一人であった。そのために、彼は日本が「母なる地」として先史時代に崇められ、神武天皇がダビデ王から由来し、一方バビロニアやエジプト、中国は「子孫の地」と考えられていたことをおそらく示すだろう考古学的、言語学的情報をさがしていた。彼は大政翼賛会の研究部長を務めるなど幾つかの要職に就き、メンデス・デ・ビゴやエレーラらスペイン人には報知新聞の局長として紹介されていた。この新聞は1942年強制的な合併により読売・報知新聞となったが、1923年ビセンテ・ブラスコ・イバニェスを東京に招き公演を開催した。しかし、熱心な藤沢がそのようなポストについていたかどうかは確認できなかった。
藤沢はスペインに大変関心があった。1940年にはイタリアを経由してイベリア半島に旅行する計画をもっていたが、彼がやって来たという証拠はない。スペイン語で書かれたパンフレット「日本の世界政策の精神的基盤」にみられるように、広範な宣伝活動を行っていたことは確かである。この教授は日本の「国家」が歴史を通じて日本帝国という一つの家族の核が拡大されたものであることをスペイン語圏の人々に説明し、神道を「太陽の創造的でダイナミックな宗教」と定義しようと骨折った。また、徳川時代の儒教学者サカエトウジュの「春の来ない冬がないのと同じように、平和の来ない戦争はない(冬を経ない春がないのと同じように、戦争を経ない平和というものはありえない)」という言葉を引用しながら、中国での作戦行動を同じく周期的な必要性に基づくものであると分析した。彼は政治状況に通じていたため、こうした文章を翻訳し出版するための助成をおそらく得ていたと思われる。
藤沢は日本語でフランコのスペインの政治構造に関する論文をいくつか出版した。「申請スペインのイデオロギー」や「再生したスペインのイデオロギー的基盤」でファランヘをナチズムになぞらえ、それを共通の目標(「第三帝国」あるいは「一つの、偉大な、自由なスペイン」)に達するために、優れた者と劣った者との間の秩序(die Rangordnungあるいはヒエラルキー)を維持しつつ、一致団結した協働運動であると定義した。藤沢はまた、「人種の全体主義的理念。日本とスペインの基本的形態の類似性。フランコ将軍の政治原則」と題した作品で、スペインと日本との間にも類似点があるという考えを強調した。出版の時期や彼が訴えかけようとしていた読者層、著者の他の作品などを考慮すると、藤沢はヒットラーがヴォルテールや大フリードリヒの作品を通して儒教に影響を受けていたといったようなスペイン人にとって理解に苦しむ断定をしていたと思われるが、その文書を特定できなかった。別の日本人教授岡田隆がフランコについて述べた見解は、彼の経歴や情報収集に重点を置いているが、それとてもフランコの無謀さ(フランコはいつも白馬に乗り、イスラム教徒の銃弾に挑みながら戦線を移動していたとされている)や帝国の野望といった先入観から免れていない。帝国の野望について岡田はカルロス5世(原文のまま)やフェリーぺ2世を想起した後に「明らかにフランコは将来のスペインに過去の栄光を投射し、そこへの復帰を考えている」と断定した。イメージは、現実よりも、その当時優先されたものであった。
この時期日本におけるスペイン研究者の活動は活発であった。例えば1941年6月、慶応大学で「スペイン祭」が開かれ、学生の一群によるスペイン作曲家の作品や「カラ・アル・ソル(太陽に顔を向けて)」のギター演奏が行われた。彼らはおそらく日本への経済ミッションの一団を歓迎して歌を歌った人たちと同じであろう。慶応におけるこの行事は日本にいるスペイン・ファランヘ党(つまりエレーラ・デ・ラ・ロサ)や日西協会によって組織された。学生たちの参加は日本人の大学教授の積極的支援を示唆している。なぜなら、共和国スペインの元通商担当アルバレス・タラドゥリスはまだ大学における自分のポストさえ回復していないし、ホセ・ムニョス・ペニャベルはフランコの公使館に登録しないという余裕を示していたからである。
最後に、この時期の通商関係の強化は微々たるものであった。こうした肯定的なイメージによって通商関係は好転するはずであったが、実際にはゼロから出発しなければならなかったし、外国為替など多くの問題を抱えた当時の複雑な状況下での製品交換は肯定的イメージをもつこととは次元が異なっていたからである。さらに、スペイン経済はアウタルキー政策をめざしていたし、日本の経済はもっぱら戦時努力に集中し、絹や香水などスペインへの輸出を占めていた奢侈品は、東京にとっての税収源としても、最も困難な時期にあった。当然ではあるが、両国のイメージは通商関係を促進しなかった。だが、政治という領域ではより大きな反響をえた。
- 日本と内戦後の外交関係
内戦が終わり、スペインの外交面における目標はドイツ・イタリアとの近い関係に応じて変化していた。しかし、日西関係にも影響を与えた二つの一般的目標を上げることができる。一つは戦争で中断されていた世界における外交の建て直しという急務であった。最後にフランコ政権を承認した国もあったが、彼の軍事的勝利にもかかわらずそれを拒否し続ける国々も依然としてあったのである。他方、枢軸国の団結の強化によって日西関係が活性化され、ヨーロッパにおける戦いにおいて両国の役割の補完性がより一層認識された。
ラテンアメリカのように、内戦の最後の時期に創設され、あるいはすでに機能してさえいた非公式代表者に基づいて、政府が外交関係を正常化できた地域があった。日本を除くアジアではそうしたことは起こらなかった。例えば中国ではイタリアの兵站支援を維持し続ける必要があった。展開の遅れの理由は資金の不足である。しかし、それまでのアルプスを越えた協力の機能の仕方に対してスペインペン人、イタリア人が満足していたことも影響していた。ローマにとっては自分の威信を引き立たせていたし、サラマンカにとっては政治的関心よりもインフラ支援の方がより大切であったからである。そうして、内戦後の中国におけるスペインの代表は、紛争に関する情報を頼りにするときや、日本支配下にある領域で領事館の治外法権を維持するにも、さらにスペイン人の利益を擁護するときにさえ、引き続きイタリアに依存していた。ホルナダの後任フアン・ベイグベデル外務大臣自身、そうしたイタリアの覇権を快く思っていなかったが、就任直後「日本軍占領下にある中国の全領域で」スペイン人の保護をローマに依頼するよう指示していた。
戦場においてイタリアの宣伝気球がしぼんでしまうと、イタリアのこうした影響力はドイツに対するイタリアの地盤沈下を食い止めた。スペインの海外におけるプレゼンスはこれにしたがって1940年夏再編された。しかし、アジアではその変化は部分的なものにとどまった。ローマがマドリードの仲介者としての役割を維持し続けようと努力し、その一方ベルリンはイタリアの影響力に取って代わったり、スペインを通してその国際的威信を高める心積もりもなかったからである。これにより、中国大陸ではスペインの対外関係に対する独・伊の影響力は均衡した。内戦以来のローマの介入はこうしてその力が薄れたときでさえ、成果を上げ続けたのである。当時の日西間の接触はそのとき以降、全体のレベルでは均衡が崩れていたにもかかわらず、イタリアとドイツから同じように影響をうけた。
第3章 東アジアにおける協力
日本がスペインと会談する際、主にアメリカ大陸を念頭においていたとすると、スペイン側は、すでに日本軍の支配下にあった点においても、近いうちに支配下におかれるだろうとされていたことからも、主として東アジアに目をつけていた。本章ではこれらについて扱う。まず満州国について触れ、それから中国中央部に重点を置きながら、タイとフィリピンについて叙述していく。
1.遠い満州
前章は、スペインと満州国の「反コミンテルン協定」への加盟から始まる。推察のとおり、この調印による二国間の歩み寄りはほとんどみられなかった。というのも、両国の関係は未だに膠着状態にあり、より積極的な新たな協力への意思表明や、それを実行に移す困難さの狭間にあったためである。
関東軍の支配下にあった満州国政府は、1939年4月、スペインに常設代表部を置いた。外務省公文書保管所にある記録文書によると、この機関は、定期的な宣伝冊子を発行していたというものの、その実体ははっきりしないままであった。この非常に限られた活動によっても、両国の関係性の不十分さが露呈されている。そこでの重大な事柄は、メンデス・デ・ビーゴ大使の来訪とスペイン経済使節団の訪問に表れるように、政治的というよりは外交議定書の性格を帯びていた。大使の訪問は、国交樹立2年後にあたる1939年11月であったが、大きな影響を及ぼすことはなかった。それに加えて、長春(当時の名は新京)で解決が試みられていた2つの重大な問題が不成功に終わることになった。スペイン側の約束であった常設外交代表部設立の不履行と、バーター貿易に基づいた通商協定建議の破棄である。唯一実現可能な結果となったのが、訪問の次行程マニラにてであり、メンデス・デ・ビーゴはその地で、公使館のための資産保険加入手続きを取った。
セラーノ・スニェルの外務省就任半年後にあたる1941年春、スペイン政府は、「世界『新秩序』の勝利を意味するかの国々との最大限に充実した関係の実現をかけた願い」をもって、即座に新京政府に向けて外交官を赴かせなければならない、という決定を下した。しかしその意に反して、それが誘導剤となることもなかった。公使館を設立するのは、誰がそこへ赴くのが適当かという問題とともに、依然として困難であった。このような状況下で、3人(マリアーノ・アモエード、トラータ伯爵、フェルナンド・バルデス・イバルゲン)が指名されたのだが、彼らが就任に至るようなことはなく、北京の外交官ホセ・ゴンサーレス・デ・グレゴリオ・イ・アリーバスにすがるほかはなかった。彼は当局の命令に反してスペインに戻ることを拒んでいたこともあり、太平洋戦争開始後の1942年1月、言うまでもなく信任状を受け、提出した。だか、当局の示唆にもかかわらず、彼が常時満州に駐在することはなかった。その理由は、公使館を設立しようと考えていた館について、彼がメンデス・デ・ビーゴに宛てた私信からうかがうことができよう。「・・・7度から10度にしかならない気温の部屋で暮らすのは快適ではありません。最初に来た時だけはもっと暖房が効いていたのですが、あそこにいる時、私はいつも風呂場とベッドの間を行き来しています。そして、束の間その2ヶ所以外に居なければならない時は、2・3枚のオーバーを羽織っています」。この手紙は、ついに当局に届くことはなかったのだが、ある意味で、スペインとの関係のために送り込まれていたあるアメリカ人の次のコメントを確証している。ひとつの通商協定もなければ、スペイン人居留地も全くない、大使1人さえもいない、と記した後、スペインのねらいを次のようなもっとも平凡なかたちで解釈している。「枢軸国を前によい位置にとどまること、それだけだ」。新聞記事に活用できることを別にして、拘束力のないまま、満州国とスペインの関係はほとんど機能していなかった。
2.汪兆銘政権
中国のそのほかの地方の状況は、しかしながら、はるかに複雑であった。また、本章でとりあげる数年間の中国との関係は、この本で分析している10年間のなかで、そして20世紀全般に渡ってさえも、スペイン外交にとって最も入り組んだものであったと言えよう。1939年夏、スペインは中国において公的な立場を正常化しようと図った。そのためには、正式な関係を樹立し、内戦が理由で撤回されていた請求権を回復するべきであった。その大望は、特に微妙な時機に実現したのである。それはちょうど、日本占領下の中国で中央政府が動き出すのと同じ時期であった。故に、スペインの内戦は終結していたが、中国では、交戦状態が続いていたばかりではなく、未だ主流二派のどちらにも決定的勝利がもたらされることがないまま、対立関係にあった。両勢力とも、最終的勝利がそれぞれの側に傾くだろうと確信して、そのために重要な動機を探っていた。そしてそれらの期待のあいだで、国交正常化と以前の立場を回復しようとするスペインの意図が、その対立に影響を及ぼしたのである。イベリア半島側から眺めると、それは実現可能な望みであった。しかし、中国からすると、それ程ではなかった。その上、これらの誤解の真っ只中で、スペインの意向は二国間の意義を優に凌ぎ、これから見てゆくように、国際レベルでだけではなく中国の内政にまで関わるに至ったのである。
スペイン内戦終結後、利権を守ろうというスペインの望みは、あらゆる種類の困難にぶつかった。第一に、司法権について、現地の法や裁判から外国人を保護する治外法権を回復しようとした。総計18ヶ国が、19世紀以来その特権を得ていた。しかし、それは中国ナショナリズムによって次第に異を唱えられつつあった。スペインは、最終条約以来かろうじてその大権を確保しており、それは1928年12月27日から一定の期日なしにその期限切れを承認したときまでであった。また、ソ連など、この特権を決定的に失っていた国々もあった。しかしながら、中国が理由なくそれを回復させることに同意するだろうとは思われなかった。第二に、政治的難局であった。なぜならば、中国で誰が勝利するだろうかを判断するのは困難だったからである。その上、スペイン政府は、中国の諸派からだけではなく、日本・イタリア・フランス・イギリスからも非常に多種多様な圧力を受けていた。その極めて重大な時期に、法的回復と外交正常化の追求を両立することはできなかった。最後に、本来的な難題もあった。スペインは、直接の対話者の不足・目的の具体性の欠如というさらなる問題を抱えており、結局のところ、スペイン・中国間の関係そのものの重要性が薄れていたのである。そしてその関係は、外部の他の要因に左右されていた。
その展開をみてゆくとこのことが特にはっきりする。それは、スペインの新政府の優柔不断さ、動き出す際の難しさ、そしてとりわけアジアで独立した活動を成し遂げることの不可能さを明らかにし、最終的に、スペイン政府がなぜイタリアを後ろ盾にしたがっていたのかを確認することになる。
これらの諸要因をその展開段階に分けて検討していこう。まず、中国の複雑な主権の概説から始め、次に、初めてのスペイン人外交官の就任及び1940年のスペイン経済使節団訪問、最後に、1941年7月のスペイン政府による汪兆銘政府の承認についてみてゆこう。
2.1. 中国における権力と合法性
当時中国における政権分裂は極限に達していた。軍閥が割拠していた1920・30年代の中国の無政府状態に、日本軍による最も人口の多い豊かな地域の占領という新たな問題が加わった。その複雑さは、スペイン内戦に言及された「4つの中国と2つのスペイン」というホセ・E・ボラオの発言に要約されている。後に、これが中国の複雑な現状を単純化した見方であることがわかるだろう。
中国内には、1911年の清朝滅亡以来、中央政府が存在していなかったが、王朝時代にすでに政府の分裂は始まっていた。列強の侵略開始後、政府は取引時期に外国勢力を広東の在外商館に留め、それ以外の時期の商取引を澳門に限ることによって問題を回避しようとした。商業の後押しとともに、この枠組みは「開港場」と呼ばれる地をつくり出しながら拡張した。そこでは外国人の居留権・所有権・商業活動権が認められ、外国人が管理する中国の海事税関事務所があった。さらに、他2種類の定住地が40程現出した。勢力範囲の設定のみになった場合もあったが、地区又は地帯と訳された「租界」とかなりの数に上る利権の獲得によって、その地での中国に対する外国勢力の権限はさらに明白になった。1つめは、外国人によって管理された中国領であった。それらは、諸政府機関と独自のサービス施設の備わっていた中国の諸都市とは通常切り離されていた。諸租借地については、それらは「正当な」居留地であるとし、領土は租借され、統治権は租借国の領事にあった。また、その「租界」との本質的な違いは、中国人又は多国籍者の立ち入り・居住・所有権が否認されうることである。1937年の日中戦争勃発以来、主な外国人定住地は南京・厦門に隣接する鼓浪屿島及び役人と外交官に制限された北京の外交地区であった。一方、最も重要な租借地は天津・漢口・厦門及び広州に隣接した沙面島であった。その上、澳門・香港・台湾は外国統治領のままであった。半独立状態のチベットもネパール人商人との間の治外法権を維持しており、はるか遠方の新疆は中国政府に傾くこともあれば、ロシア側である場合もあった。
上海は特殊な状況にあった。上海は、揚子江の河口に位置し中国貿易の半分を抱える経済の中心地であったため、列強の中国侵略にとって大変な重要性があった。この時代を通じて、国の抱える無数の問題や火災・洪水・日本人に押し付けられた諸規制・1937年の市の商業地域の体系的な破壊という上海特有の数多くの問題にもかかわらず、商業・金融の首都であり続けた。上海は3つの統治機構に分けられていた。中国中央部の秩序回復のために親日派中国人一派の裁量に委ねられて組織された大上海と、上海に居住するおよそ6万人の外国人によって支配された2つの居留地であった。それらは、制限選挙によって選出された市評議会と治外法権のある外国諸国の領事らの後見人によって統治された共同租借地と、南部で面積の半分を占めるフランス租借地であった。
したがって、上海は、大上海を支配していたとはいえ宣戦布告の危機を冒すことを恐れて他地域と同様の態度を取れなかった日本軍に包囲されていた。その法的枠組みの複雑さと、中国における紛争は公式には戦争ではなく事件であるとされていた事実によって、そこでいかなる企業が取引することも阻止されなかった。外交の場でもそれと同様のことが起こっていた。上海には、重慶で国民政府に信任された者も南京で親日派のもとにあった者も、かなりの数の中国人代表者が居住していた。スペインの外交状況であれ、その領事ら個人のケースであれ、そこで皆が複雑な外交情勢を明確にできないという難局に直面し続けていた。そこでは多くの場合、領事と外交官の職務が一緒になっていた。「我々は皆なし得るように共生しております」とあるスペイン人代表者はその状況について述べた。外国との錯綜した関係によって、スペインは結局のところかなり前途多難な状況にあった。
日中戦争による情勢によって、それがさらに困難なものになった。およそ1世紀に渡って、中国では、イデオロギーの相違や領地が引き金になったものにしろ、単なる権力争いであるにせよ、戦争状態が続いていた。しかし、1939年に争いの場にあった勢力は、大まかに3つのグループにまとめられる。共産党、国民党、そして日本軍とその側近であった。まず共産党は、内陸部の農村地帯を支配しており、現在の延安を拠点としていた。しかしその当時、共産党は中国全体を統治することを望んでいたのではなく、国民党と共に日本軍の侵略に抗する統一戦線を結成しようと努めていた。
次に、国民的英雄孫文が設立した国民党は、軍の相次ぐ敗北のために困難な状況にあった。南京と武漢という主要二都市から撤退し、四川奥地の豊かな地重慶に臨時政府を移さざるをえなかった。中国内陸中央部と南部の省における勢力が弱まったため、国民党は結局中国中央政府となることを一時諦めた。しかしながら、相変わらず権力のある元軍閥勢力からのある程度の忠誠が常に変わりやすいが得られるというような種々の有利な条件は維持していた(最も難局にあった時に連合国の援助を受けた南部の省雲南の龍雲、陜西省の阎锡山、山西の李宗仁と白崇禧)。国民党はまた、イデオロギーの同一化というよりは状況に応じた必要の産物ではあったが、フランス・イギリス・アメリカ合衆国の援助を受けていた(アメリカ合衆国では『タイム』誌や『フォーチュン』誌のようなHenry Luceの雑誌グループによる強力な後援があった)。国民党と民主主義との関係は、他の理由でそれ程密なものではなかった。というのは、国民政府軍は1938年初めまでドイツの訓練と支援を受けており、党首である蒋介石は全体主義イデオロギーにかなりの影響を受けていたのである。彼は、ドイツとイタリアの例を見ながら、国の復興を成し遂げるために、中国には意気軒昂たる指導者が必要であると考えていた。
中央政府の形成を望んでいた第三の党は日本軍派であった。彼らは、日本軍の進撃によって国の最も人口の多く豊かな地域を占領していた。それ故に、蒋介石をドンキホーテになぞらえ揶揄していた。しかしながら彼らの中国の概念は、地方の概念よりも小規模であった。それはまた変わりやすく、占領地域の漸次掃討に取り組んでいた。台湾のようにすでに大日本帝国によって併合されていた地域又は満州国のように「事実上」全く分離された地域もあった。紛争の拡大に伴って、日本軍はますますこの方法を取るようになった。こうして、中国の北部にモンゴル皇太子を長としたいわゆる内モンゴル連合自治政府が創設された。同様に、王克敏を主席とした中華民国臨時政府というもう一つの傀儡政権は、河北・山西・山東省を支配し、1940年3月以降、中華民国政府と呼ばれるようになった。中国南部には、上海と南京に梁鴻志を長とするいわゆる維新政府が置かれた。それは1938年に中華民国のために、北京の政府と共に連合評議会を組織していた。
1939年以降、日本軍はこの極端な分裂が自らの利害に好都合ではないかと疑い始める。それは中央政府の設置を目論んでいたためであり、彼らはそれが最終目的やこれらの傀儡政権の有効性を上げるために有利であると考えていた。ある日本政府報告書がこの見地を表している。「臨時政府も維新政府も中国人の熱烈な政治的支援を確立していない。これらの政府に関与している者達の思想は共通していない。両政府ともに権限と欲が欠如している。国民政府への脅威となる代わりに、我々の内政に争いの種を蒔いた。」中国国民党の人物が希望を抱くのに手を貸し、国民党の中心的指導者のひとりである汪兆銘を離党させたことは、日本側の策略の急激な変化であった。
汪には国民党を離れる理由があった。国の英雄孫文から彼の後継者として推薦されており有力な党首候補であったのだが、その後蒋が軍権を駆使したクーデターによってその選択肢に片をつけた。1937年の盧溝橋事件後、汪は中央指導部と次第に距離を置くようになり、1938年末に重慶を後にしてハノイに到着した。その国民党の支配権の及ばない地で、彼は当時の日本の近衛文麿内閣による主要3提議、善隣・防共・経済提携を根拠に、将来の和平のために日本の支配を受け入れるようかつての同志に呼びかけた。蒋はそれを受諾せず、彼を反逆者であると非難した上、1939年春、彼の暗殺を命じた。そのため汪は日本領へ避難せねばならなかった。この後、日本政府は汪が中華民国国民政府と呼んでいた、そしてその他の者は中央中国政府又は維新政府と命名したものを樹立することを約束し、彼は中国大陸へ戻っていった。確かに汪の人気は蒋に匹敵するものであり、国のかなりの地方における支配権とともに、国民党の代わりになりえた唯一の親日政府であった。この時日本軍が全てを誤ったようには思われない。しがたって、南京に到着し政権の意図をもって新政府組織を発足した後、汪の重要な懸念のうちのひとつは国内外両方で合法であると認められることであった。そのために他諸国の承認を得ようとし始めたのである。その中でフランコのいるスペインによる承認はそれ程難しくなさそうなものの1つであったのであろう。
- 関係の回復
フランコ政権の側でも、中国の一政府を承認したがっていた。両国は中国での公式な関係を回復させようとしていた。「ここで起きていることを誰も把握していなかった。それは我々が戦争に勝ったばかりの時期であった」ので、後に回想されるところによると、解決策は、現場の状況を調査するべく、具体的な指示のないまま外交官1人を上海に送り込むことであった。中国での目的は、対立以前の「地位」回復のための摸索以外の何ものでもなく、ペドロ・デ・イグアル・イ・マルティネス・ダバンをスペイン代表長として指名しようとした際、その地で何が起こっているのか、また何を成し遂げようとしているのかさえも十分に理解されていないままであった。認可を協議するようにと要請する電報からは、マドリードの新政府が、イグアルは(スペインの)共和国(派)とつながりのあった(中国)国民党に認知されなかったということのみならず、その代表の指名手続きがあったということさえ知らなかったということがうかがえる。例えば彼らは日本軍下の上海で任命されることになっていた。つまり、そこでの日本軍の権力が非公式なものにすぎず、北部や南京の親日政府が東京から認知されていないということさえ知らなかったのである。
しかしながら、公式な関係よりもはるかに多くのスペイン国内の問題が、中国で進んでいた。一方では、単なる情報不足によって重大なミスが犯されてしまうといった関心の薄さ。また一方では、1937年4月3日、中国法務省第177判決によって解消されて以来、治外法権とスペイン人への領事裁判権の欠如。そして結局それが単に機能しているということである。中国に送り込まれた外交官の数の割には、内戦勃発以来、イベリア半島のいずれの政府も、中国の情報を絶えず確実に得ることはできなかった。その期間フランコ派を支持し、その下で働いていた唯一の外交官エドゥアルド・バスケス・フェレールは、上海駐在の領事であった。彼は給料を受け取ってはいたが、サラマンカとほとんど連絡を取っていなかったため、何の役目も果たさなかった。他の外交官らは、国民党派に転向する際、外交官としての経歴に関する裁判所に一時的に拘束され、対立の間ほとんどずっとフランコ派の新国家に認知されようとした。その中の一人、上海の副領事であったホセ・ララコエチェーアは、彼に対する訴訟事件に直接抗弁するためにスペインに戻った。しかし北京に配属されていたフスト・がリード・シスネ―ロスとリカルド・ムニス・ベルドゥーゴの二人は中国に妙な状況の下留まった。彼らは、機能していない北京公使館の建物に居住していたが、彼らを咎める者は誰もなく、それどころかその間の給料が支払われていた。それは、上辺は数年後になされた付属地の一部売却による金であるとされていた。最後に、到着したばかりのペドロ・デ・イグアルの人格については、戦後、「最も無責任で甚だしく軽薄な」人物の一人であると記述され、彼もやはりこれらの難題を一時的に解決する助けにはほとんどならなかった。
イグアルはスペイン内戦の勝者代表の長として中国に赴いたのだが、その職務を遂行するにはかなりの難局にあった。彼の同僚の外交官らは任命の有効性を疑い、彼が語ったところによると(おそらく誇張しながら)、ジャーナリストの間では、彼を無視するようにという風潮さえ広がっていた。フランコ政権は国民党政権に承認されておらず、各市当局も外交官らに通常の特権を認めていなかった。それは伝言文に対する政府の無知と税関での支障を意味したものであり、それゆえ通信文は香港で検閲されてもいた。一方で、代表になろうとしていた800人近いスペイン人居留地の構成員らは、治外法権終了のため、微妙な状況にあった。宣教師らは国家によって離散させられたため、さらに悪い状況にあった。中国での戦争でますます身の安全が確保されなくなり、ヨーロッパで紛争が勃発すると、事態はさらに悪化した。1939年9月1日以降、米国人とそのスペイン人自身(ヴァチカンの調査によると全2,834人の修道士のうち269人)のみが比較的正常な状態にとどまっていた。さらに、スペイン人居留地内では、主にファランヘ党員(上海でも天津でも特にバスク人のペロタ選手ら)と共和党員の関係が、過去の固有の敵意も加わって、かなり悪化していた。
しかし、スペイン人にとって本質的な問題は、1936年10月から治外法権がなく、正式に中国当局の司法権に移っていることによる他のヨーロッパ諸国に関しての不利益であった。つまり内戦による一時中止後に常態を取り戻そうとすることは(次の)3つの大変重要な問題の故に、妨げられていると見受けられていた:情報不足、侵略国日本と友好関係にあるフランコ新体制への潜在的な敵意、植民地の孤立無援。
(スペイン)内戦終結及びイグアルの到着によって、そのスペインの立場の正常化への多少の障害は克服された。少しは古くからの2人の知人、中国駐在イギリス大使アーチボルド・クラーク・カー卿とイタリアの領事ネイロン司令官のおかげで、スペイン領事は領事として受け入れられ、フランス租借地の市評議会は、領事認可状の規則つまり事前の公的承認はなかったが、結局その外向性を認めた。イタリアもまた他の問題を解決するのに協力した。どのようにイグアル(公使ならびに総領事、つまり領事と外交官の職務を兼任)が任命されるべきかを報告し、またスペイン人居留地の財産保護を引き受けた。それはまず、ベルギーの管理下に100人程の構成員がいた天津市において、後に日本軍の支配下にない中国領土について行われた。
しかしながら、治外法権を取り戻すことはさらに複雑であった。中国当局はスペイン国民である犯罪人らを相変わらず領事館に引き渡してはいたが、それは恩典付与にほかならなかった。また、居留地には十分な法的安全性がなく、保護されていない観があった。したがって、イグアルの主な目的はこの特権の回復であった。彼の第一歩はマドリードにその必要性を強調することであった。
勿論それはささいな課題ではなかった。イグアルによると「最も重要な(原典下線)取引を上海でしているスペイン人修道士ら」とされるアウグスティノ会修道士の代表団は、チャイナ・レアルティ・カンパニーに70万中国ドルとその利子の支払いという有罪判決を受けていた。イグアルはまず、イギリスの友人カーを介して、中国国民党員らと直接の接触を取り付けようとした。彼はマドリードに対して、治外法権の取り戻し、また国民がその権利を持つことによって領事館に登録しに行くことがないようにと切望するならば、重慶と正式な関係を結ぶことが必要であると弁明した。それを成し遂げる決意をし、イグアルはまた、それが困難であり双方の探りを克服するには支持を得ることが必要であろうということを意識しながら、マドリードが国民党と関係を確立するようにしてくれないかと打診した。その関係を再開するには、否定できないあまりにも深い溝が存在した。それは親日派の怒りの原因にも、又、たとえわずかであれ、スペインが枢軸国勢力側に確実に接近する際の一つのマイナス要因ともなっただろう。このように、イグアルの目的は重要であったのだが、その全般的な意味合いはより大きいものになりえた。
マドリードは、国民党に接近するかもしれないというその政治的意味を見逃さなかった。その要望を拒否せず、公使館の建物を維持するほか機能していなかった北京へ一人の書記官を任命し、また、天津のイタリア領事に対して、その地に居住しているスペイン人の保護を率先して要請することを引き受けるにとどめた。重慶との友好関係樹立というイグアルの提案は公式の指針とは程遠いものであった。そのためホルダーナ大臣はその職を更迭される少し前に、その道を歩み続けるな、たとえ確固たる道が整えられていなくとも、とイグアルに訴えた:「全般的な、最も重要な理由が(治外法権回復のようなもの)に優先されるべきであり、我々と親密な関係にある国々との状況を困難にするような発意は慎むべきである」。一方では、初期、スペインで中国の状況が何も知られていなかった頃にイグアルに出されたいくつかの指示が思い出される:「(・・・)目の前に現れる困難を回避していかなければならない。何の約束も求めず、諸友好国の代表らの援助に頼りながら(・・・)例えば、イタリアのような」。日本に派遣されたのちの経済使節団副団長ホセ・ロハスの覚書にも「現在の情勢において大変微妙な原理的方向」に対する何らかの解決策が、事実望ましいと記されていた。いっそうの混迷が支配的であったが、蒋を認知するという概要はそれ程都合のよいものではないということがわかった。反対方向つまり親日派へ歩み寄ろうとするのは、あまりにも無謀であったが。フランコ体制外交は王か蒋かを選ぶこと以上の二者択一を迫られていた。その決断はむしろ、日本との友好関係か、蒋がもたらすとされる利権、すなわち治外法権を取るか、にあった。しかも、全体の利益か、中国との関係という部分的な利益か、そのどちらがより重要性を持つかということを反映させるべきであった。
駆け引きの時期があり、その間、イグアルは独力で行動しようとした。領事は、その「諸友好国の支援」によって望ましくない状況を辿らされていることをすぐに悟った。例えばイタリア人らは、大上海の親日派市長を訪問するようにと彼に圧力をかけ、それは後にプロパガンダに使われた。彼はこれを不愉快に思い、マドリードに意見を求めることなしに、いくつかの声明を記者団に発表した。そこでは、スペイン人の利益を保護するという願望のみからその訪問をしたのであると告げ、彼の自主性を守った。また一方では、ドイツやイタリアに対するスペインの謝意は、反コミンテルン協定にある以上にこれらの国々との結びつきを意味するものではない、と付け加えた。イタリア領事は、これらの言い回しを好むはずはなかったうえ、イグアルが中国においてイタリアの政策に追随するスペイン政府の意向を拒否するためにイギリス人カーに宛てたある興味深い書簡を気に入るだろうはずもなかった。そのイタリア人がこの手紙を読んだはずはない、というのも、イグアルはそれをマドリードの上司らにさえ送っていないからである。しかしながらそれは、中国人間の対応の変化をもたらす際に重要な効果があった。彼らは、カーにイグアルとともに国民党の本拠地である重慶を訪問するように提案させたのである。それが、中国のフランコ・スペインに対するより柔軟な姿勢の前触れであった。マドリードは相変わらず日本の侵略を支持していたにもかかわらず、この国民党は、初めて、交渉を開始する意向があるという証拠を示した。イグアルはすでに目標の半分を成し遂げていた。国民党の目下の変化は、彼の成功であると理解されるであろう。
すべてがそのようではなかった。というのも、全体の状況の様々な変化もまた1939年秋を通じてスペインに対する柔軟性にとって決定的であったからである。国民党の存続が最も厳しかった時期のひとつであり、蒋は外交成功の可能性を取り逃がさざるをえなかった。汪兆銘はその頃、南京に居を定めて、北京・上海・中国北部の親日派三政府の戦士らに、見かけ上統合された国民政府をつくることをなんとか説得し遂げていた。その努力には、中国国民の大多数を統治しうる内閣成立を指揮できる可能性があった。蒋政権に対峙するに妥当な有力な位置についた際には、勢力均衡の変化が想定されたであろう。それは、在中国イタリア大使が述べたように、スペインと似かよった状況をつくり出すことでもあった。汪の新政府は変化に対する多大な期待を生み出し、そのために、国民党のかつての同志らの間には相互に恐れをもたらした。彼らの戦いの持続にとって、ヨーロッパでの戦争勃発は、ますます厳しさを増す状況に思われた。イギリスとフランスはドイツとの泥沼にはまり込んでおり、ヒトラー・スターリン間で交わされた不可侵条約は、ソ連にアジアにおいて徐々に中立的な立場を取らせることとなった。ノモンハンでの停戦後には日本との協定の実現の可能性が大いにありえたからである。
これらの新しいニュースは、ヨーロッパでの戦争勃発と平行して、多くの者の予測を見直させることとなった。1939年秋、重慶の蒋介石政府が近く消滅するところにあると予想していた領事館イグアル当人もそのうちのひとりであった。結果として、一触即発に違いないと言われていた来るべき出来事を待つという案に達した。数ヶ月のうちに事態はすっかり逆転していた。今や国民党の方がスペインとの関係確立のための新体制を立てたいとしており、一方フランコ側は日本の勝利を仮定して、その利益に浴しようとうかがっていたため、国民党への関心を失っていた。この新たな状況下で、外務省が下した決断は「急速な消滅に向かっている政府を率先して承認することを全面的に控えること」であり、ロンドンでもすでに国民党と接触していたアルバ公爵に対しては、「日本に関して我々が偽った立場に身を置きながら望まざる重慶の承認をさせられずに済むように」慎み深く行動するようにと勧告した。今や汪兆銘の時代であり、それゆえにその敵方は、枢軸国寄りのある国、しかしそれ以前に国民党に接近したいという態度を見せていた国、つまりスペインとの関係を改善することに特別な関心を示していた。
2.3. 親日政権に対する好意的見通し
1939年から1940年にかけての冬、蒋はかなりの苦境にあった。その頃、汪のような信望のある人物による中国国民政府の前途には、国民党の他の将軍らや将校たちを引き入れ、この党の政府を政治的に阻害させてしまう可能性があった。国民党の唯一の国際的戦略は、その運命を西洋民主主義のそれと結びつけることであった。
フランコ政権が重大な決断を下さなければならなかったのはこの時期であった。なぜならば、中国の二政府のどちらに傾くにしろ、それが中国内の争いに国際的合法性を与え、重要なかたちで影響を与える可能性があったためである。結果的に、両政府ともに、マドリードがそれぞれの政府に傾くようにと努めた。中国国民党政府の場合、スペインの武器と水銀を買うという奇妙な申し出によって強い興味を示していた。それは政権の中心に直接届けられた。一方、汪政権は、日本人らを介してその関心を示したのだが、彼らは、承認されるようにと、スペイン人らに最も聞き入れられるにたる論拠、つまり「イタリアはもうそれをする意図がある」、をその手段に使った。その上、その意見書をそのままパリとローマの公使館を通して、または直接マドリードへ、と様々なルートで送った。しかし、それはサンティアゴ・メンデス・デ・ビーゴのいた東京の公使館を通じてではなかったので、他のたいていの場合と同様、彼はこのことを報道で知ったのである。
1940年初め、前年の二者択一はスペイン人の関心をすっかり薄れさせていた。国民党政府は「まもなく消滅す運命にある」と海外局はイグアル当人の報告書に従って指摘していた。それが完全な決め手となった。その新情報でスペインは大いに満足したに違いなかった。マドリードは蒋の失脚に全面的に賭けることに決め、ロンドンのアルバ公爵に、すでに控えるように促してあった交渉の中断を命じた。アジアにおいてイタリアの後ろについていくことによって成果が生まれつつあり、日本の勝利に賭けるという決断に対して、外務省では一見したところ異論はなかった。汪はスペインに気に入られただけではなく、将来国の統治者になりそうであると思われていた。野心と期待とが一致しようとしていた。そういう訳で、マドリードは、蒋と一度も関係を保ったことがないという事実によって埋め合わされることを願いつつ、イタリアと同様に、国民党との関係確立を拒否し、汪と係わりを持つのを待つことに決めた。このように、スペインの(在イタリア)外交官ペドロ・ガルシア・コンデは2月14日、在イタリア日本大使天羽英二にそれを知らせることとなった。マドリードはローマと同じ道をたどっていた。
イタリアがすでに有していた治外法権を所望していたため、スペインの姿勢は微妙に違っていた。そのため、一度外務省が汪の承認を決定してしまうと、いかに交渉していくのかという内部論争が起こった。それはスペインができうる決断のわずかな領域であったが、それを利用しようとしていたのである。外務省は様々な選択肢を考慮した。イタリアの承認を待つか、ドイツがおそらくするように延期するか、それとも日本に対する友好の意の証しとして単独で先手を取るか。この議論のなかで、メンデス・デ・ビーゴはある交渉を提議した。それと同じプロセスが1937年のサラマンカ承認の後にあったことを思い出し、日本の進軍に関する新情報を告げ知らせた。しかし、汪が「政権樹立のための基本的な助けになろう権威と名声の方策」を当てにしていない、ということにも触れている。同様に、元総理の阿部信行が二国間の安定した関係を定める条約交渉のために汪のもとに特派大使として任命されたことも報告している。間違いなく、メンデス・デ・ビーゴはこれによって汪承認の決断を遅らせることを望んでいた。なぜならば、阿部と汪政権の交渉が開始されたのはその何ヶ月か後、7月であったからである。それは直の情報を持つ者の強みであった。マドリードではそれを知るすべがなく、メンデス・デ・ビーゴは決定延期をすることができた。
外務省は、ローマと同様ベルリンにいる外交官に対しても、スペインが再び中国での治外法権を認められるにはどのくらいの保障がありうるのかということを尋ねていたが、その一方、東京のメンデス・デ・ビーゴに対しては、「スペイン政府が汪の承認をイタリアと共に、あるいは単独で、決断する時が来る時のために」この交渉の可能性について相談していた。メンデス・デ・ビーゴは、新たな時間稼ぎに努め、汪政権の新任代理人が東京に到着するのを待つことを勧めた。なぜならば、彼の意見はその時点の外務省において支配的ではなかったからである。早急な利益の追求と治外法権の回復に目を眩ませないことが望まれていた。このため、サンタ・クルスは1940年3月30日に予定されていた政権樹立以降いつでも汪を承認できる準備をした。イタリアの後でも先でも、日本がそれを要請したらすぐに、ドイツがすることを特に心配することなく、例えば中国の承認を難しくするだろうとイタリア大使が述べていた、どの旗がこの政権により適切であろうかという中国国内の関心事を無視して。イタリアの後援は、最終的には、ある種の政治的自主性を容認していた。
しかしながら、そのマドリードが独立した立場にあるという可能性は最終的に実現に至らなかった。3月の後半、汪新政権がまさに宣言されようとしていたとき、日本は以前の政策を転換し、その国際的承認に関心を向けなくなった。「汪計画」は脆かった。おそらく国民党要人のうちの一人の兄弟で、氏名詐称者ということがわかったSung Tzuliangを介してにせよ、いわゆる「キリ計画」[1]によってにせよ、日本とは何の和平会談も結実させることができなかった。一方で、政権のメンバーのうち数人が国民党出身者であったとはいえ、汪は肝心な分裂も、約束された雲南又は四川での蒋に対する蜂起も成し遂げていなかった。その上、汪による熱心な中央集権化は、他の主要な指導者であり協力者でもある臨時政府の王克敏と維新政府の梁鴻志の間に、強い猜疑心をかきたてていた。又、日本がほとんど植民地化を強要しているという交渉を嗅ぎ取られ、自らの党から数人の中心的人物が国民党陣営へ逃げ出した。重慶の国民党政権は、離党により弱体化していたが、時が経るにつれて、代わりをたてられる可能性は低くなっていた。さらに、分裂の軍事的効果は全く無効であった。
不安定であったとはいえ、蒋は、日本軍が汪に傾倒するのを遅らせ国民党との交渉を維持するためかのように、十分持ちこたえていた。東京は国民党を引き寄せ、元の反共協定を取り戻すという望みを残しておくほうを選んだ。それゆえに、全てを汪に注ぎ込まないことを決断した。その一方で、阿部信行の任務は、自国軍に強要された制約に真っ向からぶつかっていた。特に、いかなる方法をとっても、戦況不利になりうる情勢を許さないということであった。つまり、阿部は汪と条約交渉する権限を与えられていたが、彼の第一の要請であった日本軍撤退を認めることができなかったのである。それは一方で、日本側の将校らが前もって秘密裏に受諾していたことであった。日本は、他の場合と同様、合意されていたことを翻し、中国はその揺れ動きがいつ終わりになるのかを知らなかった。
当の東京では、米国の不承認表明の姿勢に対立させて、イタリアと同様スペインも汪承認の意向を非公式に伝えていると報道していたのだが、マドリードは汪を介して日本への支持を表明する機会がなかった。その一方で、国民政府は外交術で「汪計画」を失敗させようとなおいっそうの努力を重ねた。したがって、ひとたび汪承認の意向が知られると、国民党はスペイン外務省に対してますます強い姿勢で圧力をかけるようになった。それは二ヶ所で別々に行われた。パリでは、偶発的な汪政権承認に異議を申し立て、上海では、イグアルにフランコ政権承認とスペインの治外法権を約束した。当然、マドリードが汪承認の可能性を考えないという唯一の条件の下にであった。
イグアルは、これを前に、1940年4月、再び意見を変えた。ケ・ドルセーのフランス人同僚領事アンリコスムに送られ、そこからスペイン大使館へ、そしてマドリードへ宛てられた電報のおかげで、彼は、日本の中国における「殺人・誘拐・略奪」方式と汪政権の「操り人形組織」を見極めた。東京のスペイン公使館を通じて送られた別の電文はより控えめで、蒋政権に「厚い信望、長命、そして万国からの支持」があると述べ、「事実がその手堅さを明らかにし、新政府の権能が他国に認知される」までは汪承認を思いとどまらせるにとどめてあった。言い換えれば、「決してするな」ということである。というのも、その敵方を「長命」とみなしていたのである。領事は、ついに、スペイン国民軍と国民党の関係を結び始めるという長年の夢が果たされるとみて、中国におけるスペインの利益にとってかなり重要な問題であろうと考えられていたそれらの条件の受け入れを強い調子で支持し始めた。この、たった三ヶ月間で、目に見える兆候もない板挟みに関する彼の考えの新たな転換の理由を正確に知るのは難しい。しかし、中国国民政府の立場を支持するイグアルの情熱は、さらなるなんらかの動機がありえたということを示唆している。「汪計画」がさんざん苦労をなめるだろうことは確実であったが、国民党もまだかなり厳しい時期にあり続けた。特に、1940年のちょうどその夏、主要な供給路であった通称「ビルマ街道」が封鎖されたことによる。
国民党を支持するということは、イグアルにとって政治的に無謀な提議であった。1939年、ロハスが示した「事実の解明」と「主義の方向づけ」との一致を切り離すという望まれざる知られを送っていた。その上、イタリアと逆をいくことを提案していた。そのため、多分、同僚の(イタリア)領事ネイロネに気づかれることを懸念して、スペイン領事イグアルは、その電報を東京から送るほうをとった。上辺の理由は、公使館により安全な暗号があるということであったが(彼は宣教師の手を介して電文を送った)、サンティアゴ・メンデス・デ・ビーゴがちょうど枢軸国勢に接近しようとしているもう一人の外交官であったということを見逃すべきではない。イグアルは日本による暗号解読の可能性よりも、中国におけるイタリアの干渉のほうを危惧していた。
イグアルの提議を打った電報はサンタ・クルス宮を当惑させ、南京における汪の将来の成功が疑われる最初のきっかけとなったが、決定は変えられなかった。周りの状況から察知すると、国民党はまもなく消滅に向かっていると確言していた東京から、別のもっと期待に沿った情報を気にかけるほうが好まれていた。蒋との関係によって、スペインがより実際的な状況に位置するだろうということは受け入れられたが、マドリードは依然として汪のほうに傾いていた。外務報告書の告げるところによると、「日本の政府で起こるだろう反発は(・・・)スペインに対してかなり大きなものとなるだろうということは疑いの余地がなく、従って、中国におけるスペインの利益にあまり有利ではない」という理由からであった。この論拠は興味深い。この地域に居続けようとすることで、中国におけるスペインの利益は日本との政治的関係に従わされていた。計画の第一部がもう古いものだと分かったかと思うと、第二部は新しかった、というように、この時期の中国における接触と存在は、完全に日本政府との関係をめぐって展開していた。
イグアルは支持を得ることに熱を入れ、新たな情報の探求に挑みかかった。外務省は、「他の列強、特に日本自体の南京政府承認に関する実状と、日本にそれとなく中国における我々の権利保持はスペインがぜひとも明らかにしておきたい問題であるということを分からせることは可能であろうか」探りを入れることを望んでいた。汪にとって有利であるような返答が期待されていたが、マドリードはある重大な事実を意味する新たな疑念を提起していた。それは、イタリアの権勢に追随していくことに対する今少しのほのめかしであった。マドリードが再び、汪に対する態度と国民党との関係とについて質問するやいなや、彼らはすぐにこのことに気がついた。イタリア人らは、不快の念で、新たな情報を送り、ローマのスペイン大使ともマドリードのベイグベデル大臣とも、直接にスペイン人らと面談することで、反撃した。ローマはスペインの従属を保持するのに努め、しかも、ペドロ・デ・イグアルを直接糾弾した。そのためには二つの論拠が使われた。中国における同僚らとの連絡不足(つまり、ネイロネに報告しないこと)と、さらに悪いことは、「イギリスの下僕」となること。「前述の重慶政府の[スペインの承認手続き]の遅れが始まるのは、あのイギリス大使[クラーク・カー]に吹き込まれたのであろうと判断する理由がある」。イグアルと、一節前で重慶の使者に非難されたカーとの接触の意味合いは明らかであった。スペインの利益保護者としてのイタリアの役割に対する明白な挑戦がすでに答えを出していた。
外務省は、イタリアの圧力に屈した。ベイグベデルはイタリア大使フランチェスコ・レキオへの交替を否認し、その後、イグアルに「重慶政府の誘いに応じることや、支持を受けるまでに関係を回復すること」のないようにと命令した。領事は、良い機会を逃してしまい、「スペインの利益保護に関する私の見解と一年近くになる私の苦労は、貴当局の承認に値しない」と嘆き、失望した。預言者故郷に容れられず、であった。どうにか一部分を彼の立場に同意するようにしたが、彼には上官らからの支持が足りなかった。むしろ、イタリアに代わってフランスとイギリスを仲立ちに利用し続ける彼らの、ますますあからさまな非難を浴びた。治外法権を無視して、対中国政策では全般的利益が優先されていた。
フランコ政権スペインの初期、断固たる枢軸国寄り政策のなかで、イグアルは、自分の中国に関する知識をもって外務省に働きかけることができるだろうと考え、行動していた。しかし、それは意に添った協定の情報を送っている間、または、彼が来た当初のように、はっきりと状況認識がされていない際のみ有効であった。領事は、しかしながら、自分の相対的成功の基盤である粘り強さを失わずに、重慶の申し出に応じるのは都合がよいと力説し続け、経済使節団の中国訪問中に、彼らに対してマドリードの公式な政策に立ち向かう新たな根拠を示した。イグアルは、実に行動的な外交官であった。経済使節団の中国訪問を前にして、再びこのことを証明した。
2.4. 中国での経済使節団
カストロ・ヒローナ率いる使節団は、アジア大陸の日本軍統治領における旅程を続けるように勧められ、その結果、朝鮮、満州、その後日本の傀儡政権である中国政府へ赴いた。それは、日本によってすら承認されていなかったときに南京の汪兆銘傀儡政権を訪問した初の公式使節団となった。したがって、この旅は重要な政治的内容を帯びるにおよんだ。
ペドロ・デ・イグアルはその意味するところに気づき、その訪問を避けようとできる限りのことをした。その行程を知らされてはいなかったが、南京へ向かうということを知るとすぐに、ハルビンで派遣団と会しようと、飛行機で満州に向かった。この親日国家の主要都市で、彼は派遣団のメンバーにその政治的意味の危険性を説明した。というのも、彼らが、汪の中国政府へ旅する権限を承認するように、とマドリードに要請したからである。外務省はすぐに肯定の返事をし、その結果として、彼らは行程をそのまま前に進ませることに決めた。ただし、イグアルの言い分を受け入れ、訪問は三日間に短縮され、四人のメンバーのみが参加するということになった。駐上海領事は、中国人が時を経てもなお覚えているだろう間違いを防ぐことができなかった。スペインは、ラテンアメリカとの関係においてだけではなく、彼らの勝利を認知させるためにも、親日派に利用されていた。
派遣団は1940年8月2日から4日にかけて南京を訪れた。滞在中の中心的な行事は国民政府主席、汪のレセプションであり、それが初めての国際的な後援だったため、彼はかなりの歓待をした。彼はこの好機に乗じて、この訪問がある種の正常な関係樹立に向かっての第一歩であるとの期待を表明し、アルベルト・カストロ・ヒローナは、将来的な承認に関するなんらかの口約束をもって応えなければならなかった。なぜならば、スペインの記録文書に直接の関係書類はないが、中国が後にそれを根強く記憶していたのである。このアフリカニスタの将軍は、スペインが中国に対して行った非常に重要な政治的御土産に対して日本の傀儡政権の中国人らが示した至福感を取り払うはずであった。スペインの訪問は、東京の当の後援者らも回避し続けていた待望の初の外交的承認を予示していたからである。在上海アメリカ合州国大使館のある関係者の指摘するところによると、「それは、間違いなく『国民政府』がその『公式承認』をすでに先取りしていたという意味であった。(汪は)それに関して一見したところ桁外れの望みを抱いている」。汪はスペインから、国民党を非合法としようとする資格を認められた。孫中山の真の後継者であると自己宣言しており(皆がそうしていた。含共産党員)、自らの政府の「合憲性」と重慶の支配的な「独裁」を対比し、和平へ向けて蒋がほとんど尽力していないことを批判した。さらに、西側の政権に承認されていたのである。マドリードの決断にはかなりの重要性があった。
目に見えた見返りなしに、スペインによるこの政治的御土産の動機を理解するのは難しい。経済使節団の訪問をカストロ・ヒローナのある種の至らなさのせいにするのは、とくに副団長のホセ・ロハスがすでにスペインへ発ってしまっており、彼のアジアへの関心が最少でしかなかったことを考慮すると、簡単である。彼に関するとある逸話によって、いかに旅の準備が不十分であったかを理解することができる。彼が、肖像画に描かれている男性が誰であるかを質問したとき、周りの者は、それが中国の国民的英雄の師、孫中山であることを、かなりの驚きをもって彼に教えた。カストロ・ヒローナは、その名を一度も聞いたことがない、と気後れすることもなく述べたのであった。イグアルは後に彼について「スペイン軍のなかの最も間抜けな将校のうちのひとり」と言い切ったが、領事が不満を感じるのはもっともであった。なぜなら、訪問の私的な様相を保つという約束に背いただけではなく、ほとんど考えなしに承認の可能性について喋ったのである。しかしながら、その訪問の決定的な動機は、数々の失策は別にして、そのメンバーらにあったのではなく、電報で直ちに南京訪問を認許したサンタクルス宮にあった。
結局、将軍はマドリードにあった雰囲気にのまれていた。派遣団出発の際に渡された訓令にははっきりと「蒋介石は我々にとって何の役にもたたない」とあった。それは汪支持の見解の表れであり、フランコ総統もまた見たところそれに賛同していた。またその考えは、後に須磨大使を前に語った第三インターナショナル解散に関するいくつかの思案と一致していた。フランコは1943年5月、ロシア人にとって「インターナショナル」という語が使用されるのは大変都合が悪くなってきている、また、日本の動きが非常に効果的になって、反共軍の支持を勝ち取り続けている、との声明を出した。続いて、妙な結論を引き出している。「ロシアによるコミンテルンの解散は、単にこの混乱を抑えて重慶政府崩壊を防ぐための一案であると言ったら間違っているだろうか」。総統は明らかにこの変数を、多かれ少なかれ共産主義を、東アジアで起こっていたことを理解するための唯一の決定子として考えに入れていた。
南京訪問の委任に関して、マドリードの誰がどのようにそれを決定したのかを知るのは困難である。早急に答えを出すと、交渉または政治的利害の追求について考えなくなってしまう。
[1] Sung Tzu-liang was the younger brother of T. V. Soong and Madame Chiang Kai-shek. Kiri kosaku[*] (Kiri Operation), and the Japanese high command showed a great deal of interest in it. Both sides agreed to a preliminary conference in Hong Kong in early March, which held up the inauguration of Wang Ching-wei’s government. Taiheiyo senso e no michi , IV, 230; Chou Fou-hai jih-chi , p. 52.] One legendary Chinese wartime intelligence operation was Chongqing’s secret negotiations with Japan in Hong Kong and Macau from March to September 1940. The Chinese principal negotiator was supposed to be Chaing Kai-shek’s brother-in-law Song Ziliang, with Chiang’s official letters of authorization. Tokyo code-named this peace route as «Kiri Kosaku» (Tung Operation). The negotiations went so far that the Japanese side even prepared a direct meeting with Chiang. The Chinese side demanded that Japan renounce the support for Wang Jingwei and his puppet Nanjing regime before a direct meeting with Chiang could be held. Tokyo wanted a Wang-Chiang joint government in Nanjing instead. Wang Jingwei and his followers did as much as possible to sabotage the negotiations. The supposed Song Ziliang turned out be an agent of Chinese military intelligence under Chiang’s trusted intelligence master Dai Li. n early December, 1939, Lieutenant Colonel Suzuki Takuji, a Japanese Army attache in Hong Kong, had gotten in touch with a man who claimed to be Sung Tzu-liang through the introduction of a Hong Kong University professor. Sung Tzu-liang was the younger brother of T. V. Soong and Madame Chiang Kai-shek. Peace exploration through this channel was code-named Kiri kosaku[*] (Kiri Operation), and the Japanese high command showed a great deal of interest in it. Both sides agreed to a preliminary conference in Hong Kong in early March, which held up the inauguration of Wang Ching-wei’s government.[21 [21] Taiheiyo senso e no michi , IV, 230; Chou Fou-hai jih-chi , p. 52.]
第4章 日本の勝利
1941年12月7日から8日にかけて、ワシントン-東京間に戦争が勃発したことにより、止まるところを知らないぎすぎすした衝突の中で、新しい時期がその到来を告げた。世界大戦が始まったのだ。数ヶ月前にソビエト連邦が加わったこともあって、様々な闘争が、決定的にひとつの戦いになった。しかしその戦いは、ラテンアメリカやサハラ以南のアフリカには、その政府は結果的には戦いに組み込まれることとなったとはいえ、かろうじて特権を残したのであろう。5大陸は2つの陣営で対立するようになった。
合衆国と日本との紛争は驚くに値しないことだった。これはずっと以前から布告されていた戦争だった。合衆国との和平交渉が失敗すると、東条英機新内閣が組閣された。この内閣は、アジアに対する西洋の支配に対抗はしたが武力への道に踏み出す準備がなかった東条の前任者、近衛文麿には能力がなかったので、根底に軍事目的を掲げてつくられたものである。1941年10月に東条が国家を統率するようになってからの新常識では、日本はできるかぎりはやく戦争に突入しなければならないというものであった。もはや交渉の余地はなかった。石油その他一次産品を奪われ、日本はそれに反応する力がゆっくりとなくなっていくに感じたのだった。その後、日露戦争時と同様に、日本は真珠湾奇襲攻撃によって戦闘を開始した。この攻撃によって、最初の数日間に、軍事的成功のロザリオの祈りに合わせて、日本軍はベーリング海峡からインド亜大陸という、非常に離れた境界まで支配領域を広げることになった。表面的なだけの勝利によって広い地帯に膨張したのはいいが、それはのちには罠となっていったのである。
当時のスペインはファランヘ党と保守派との間の権力抗争による政治的騒乱の最中にあった。その騒乱にあって、各陣営の勝利の可能性をどうみるか、は重要な論点であったし、太平洋戦争の勃発は、決定的な衝突としていうよりはむしろ将来何が起こるかを暗示する複雑な出来事として見られた。真珠湾攻撃には直接的に重要だったわけではない。というのも日米開戦はすでに時間の問題だと捉えられていたし、各グループの予想を確かめるものとして、そのニュースは使われたからである。解釈を変えるにはもっとたくさんのデータが必要だっただろう。
真珠湾攻撃後も、以前ソ連への攻撃で起きたように双方のつながりの一般的な文脈は変わらなかった。スペイン人は抗議デモには出なかったし、日米どちらの側にもつかなかった。友好関係は継続したが、その性質は根本的に変わった、というのも、一方の国は戦闘に突入し、もう一方はそうではなかったからである。ヨーロッパの戦闘に直接関与せずに両国が枢軸国の戦いを支持した以前の平衡感覚は消滅した。相互扶助もスペインと日本の自然発生的な結びつきも終わりを告げた。チアーノ伯爵の有名な日記の中に、ハワイでの戦争の勃発に端を発した、その最後の例がでている。イタリアの大臣はドイツの友人リッペントロップから電話を受け、アメリカへの宣戦布告へ加わるよう求められた、と書いている。そして日記は決して回答を受け取ることのなかった質問の一行で終わっていた:「では、スペインはどうだろうか?」結果として二国間の関係は以前とは異なる利益によるものとなった。日本はスペインの戦力をあてにし、スペインはフィリピンにおける自らの権益を擁護することを模索した。幻想は明白な現実に道を譲ったのだった。
民主主義大国と戦争に入った結果、日本とスペインの関係はいままで以上に重要性を持つことになった。日本は中立国にまかせる2つの主要な活動をスペイン人に頼った、つまりアメリカ大陸での臣民の利益を守ることと、合衆国に関する秘密情報を集めることである。スペインは、そこで初めて旧植民地のフィリピンが戦争の被害を受けているのに気づいた。フィリピンには多数の市民が暮らしているばかりではなく、経済的・文化的にも強い絆があったのである。
真珠湾攻撃はスペインにおける日本像に重大な意味の変化をもたらした。既に分析したように、1941年の夏には理想化されたイメージに終止符がうたれ、新しい現実が決定的に優先され、期待はまったくなくなった。日本は夢みた地や将来の計画において重要な存在ではなくなった。この頃にはスペインの将来の帝国としての自己見解が消滅したからである。またそのスペインの理想像は、フィリピンに対する懸念、またフィリピンでスペインが継承したものに対する懸念によって、すっかり飲み込まれてしまった。日本とスペイン両国の関係は将来性よりも現状を、理想よりも現実を見据えるものとなった。フランコのスペインでは、日本関連のニュースのもつ機能は根本的に変化した。普通通りに聞かれてはいたが、対外的野望を膨らませるのではなく、国内議論の糧となったのである。ファランヘ党員と軍部との間に起こった苦い権力闘争において、日本は論点を提示し、それぞれが都合のよいように使うようになった。将来の可能性より現実のほうが重かったようだ。
よって、本章からはスペイン人がもつ2つの日本像を明確に区別することができる。一方は、楽観主義者の持つ日本像であり、枢軸国の最終的勝利への通例の貢献に集中したもので、このアジアの帝国に疑念からくる恩恵を与えつづけていた。もう一方は嫉妬深い者たちの日本像であり、アジアにおける日本の侵攻が悪い結果をもたらすことを選び、そのときまでは動揺を導く以外のなにものでもなかった「新秩序」のための争いに賭ける前に植民地時代へと戻ることを夢見ていた。スペインの政治的分裂はこのような日本についての視点に集約されていて、ファランヘ党員は最も頑固な日本の擁護者であった。
太平洋戦争は両国の関係にもうひとつ最終的な影響をもたらした。接触は再び第一義に外務省を通じて行われるようになったし、大臣のパーソナリティがその行方を左右する鍵となった。日本をたたえるために定められた新しい枠は、太平洋における争いの発生によって、またそのグローバル化された軍事対立に日本が介入したことにより、相互の関係が覆っていた将来の計画の多くを消滅させた。決定は直接的な結果を導いた。もっとも明確な結果は外務大臣ラモン・セラノ・スニェルの失脚である、なぜならば彼の辞任は外務省におけるファランヘ党勢力の後退を意味するばかりではなく、日本の戦争力にたいするスペインの援助の終焉を意味していたからである。スペイン外務省内を担っていた人物は、とても重要であった、なぜならば日本に関する決定は間伐を入れない反響を呼び始めたからである。日本は、フランコ体制の外交関係においてますます迷惑な「熱いじゃがいも」であったのだが、このとき以降、内政にも影響を及ぼすようになった。
1真珠湾の輝き
1941年12月7日、日本はそれまで4年半の間引きずってきた戦争で質的な鍵となる一歩を踏み出した。公式に宣戦布告したのである。そうして中国での事件から、力ある敵に対する対峙へと戦いを拡大した。この敵は、以前は公に衝突することは避けたいと思っていたはずの、日本軍が勝利のないまま駐屯する中国よりももっと勝つことが困難であると悟っている相手であった。この戦いには、日米戦争、太平洋戦争、大東亜戦争など、さまざまな名前がつけられた。これらの名称は史学史上最も用いられているもので、最もすばらしい偉業をあらわすと同時に、すべての国が忘却したい未完の事業の意味合いも含まれている。誰に対して負けたか(どこが敗北しなかったか)、攻撃者は誰であったか、(つまり自己愛の戦いの正義とはなにか)もしくはあまり発展していない国々に文明をもたらすという使命を帯びた戦いであったか(こうして攻撃の重みを軽減している)などを意味している。本書では、第二の、太平洋戦争という用語を使おうと思う、というのも日本の連合国への対峙が、スペインと日本の接触に重要な意味をもたらしたからである。しかしその一方で大東亜戦争という名称の利便性も忘れてはならない。大東亜戦争という語は、日本が野心を抱いた大東亜、そして戦いが展開した場の地理的範囲と、戦争の起源としての大陸における日本の帝国主義的野心をも明示している。大東亜の用語があまり使われなくなったのは、北米の占領下でこのことばが使用禁止にされたことによるのだ。
これ以前の状況を思い出しておくのがよいであろう。つまりアメリカ合衆国や他の西洋列強との戦争は1937年の盧構橋の小競り合いにさかのぼるだけではなく、1931年の日本軍の目覚しい勝利から続く満州事変にさかのぼるのである。また1904-05年の日露戦争にも発端はある、なぜならその折にも日本は、これは東洋における平和のための戦争であって、他に方法はないのだ、という、同じような言い訳を使ったのだから。20世紀はじめの力学、また1930年代初頭の軍の勝利による力学では、日本が決定的な敗北に至るまで降伏させるのは無理だった。これに関しては満州への人々の広い好感や1931-1932年の時期に日本に存在した関東軍の知名度と、最終的降伏の前に予測された苦しみ・死・飢えとを関連づける必要がある。片方がなければもう片方もありえなかったろう。日本における15年間の「暗い谷間」は、苦悩によって後に贖われることになる喜びのうちに始まった。それを忘れてはならない、なぜならば、よく知られていることだが、戦争を始めるのは、戦争を終わらせるのよりずっと簡単であるからだ。
多数の日本人が、続く戦闘の行方・進展具合を心配した。日本の軍国主義に対する反対運動があったのは、後世の発見でもなんでもない。列車が目的地についたなら、光の当たった風景がどこにあるのか知るのはやさしく、それは歴史家たちの研究にもよく現れている。しかし太平洋戦争が勃発すると、勝利を意味する叫び声である万歳や人々の間での喜びのデモンストレーションは、長期間にわたっては、日本人が物不足の中で生き、勝利の平和への約束で栄養をとりながら、食料を奪われていたことを隠しえなかった。
ナショナリストの熱弁は、戦争の行方に関して増加しつつある内部分裂を部分的にだけ隠した。おそらく日本の文化は突発的な変化や自らの行方を全体的に他の人びとにゆだねることに反発するものであり、軍人も代表的文民も誰一人として、たとえ大政翼賛会や、戦闘が要求する国力増強のために作られた隣組のような組織をもってしても、社会に絶対的な権威を押し付けることはできなかった。東条は独裁を行わなかったし、彼の人物像は、戦争を有効に遂行するのにほとんど役に立たなかった。彼の取り巻きグループも、自分たちのリーダーの意義ある援軍にはなれなかったし、東条も将来的に対外戦争へと向ける熱情もしくはナショナリスト的な熱望を呼び起こすことはできなかった。その理由は明らかである。大政翼賛会はどの指導者にとっても行動の支えにはならなかったし、ムッソリーニやヒトラーと比較できるような人格への崇拝もなく、首相東条は軍の同僚に首位にはあってもそれ以上の権威はない人間と考えられていたのだった。海軍は東条の命令に服従せず公然と無視し、東条は陸軍参謀本部に対しても具体的なイニシアチブを強いることができず、また戦争の全体的進展の後には、参謀本部独自の戦略を捨てさせることもできなかった。人間として、日本の「独裁者」には他のヨーロッパの指導者のようなカリスマ性はなかった;退役軍人のリーダー石原莞爾は1941年のはじめに、東条は逮捕され、処刑されるべきだったろうに、と述べた。また海軍司令長武田しんいちはガダルカナルの戦いの後に面と向かって彼をばか者呼ばわりしたほどであった。批判を前にして、首相はほとんどなにもしようとしなかった(できなかった)。例えば石原を封じ込めようと、たとえば、1942年の終わりに、石原と話すことで懐柔し自分の政府のために使おうとした。しかし何も得られず、昔日の満州における膨張主義の信奉者は、指導者としての東条に関する自分の否定的な意見をばら撒き続けた。東条は自分には権力が不足していることをよくわかっていたし、その不足を正当化するために、自分は単に上層部の意向を実践する者であるのだ、と明言した。一億人について一つの声で話したスローガンは、ともかく対外的には有効であった。しかしそれは表の部分、つまり外部に見せていたものだったのだ。
裏の部分、国内的な部分は、西洋ではあまり知られていなかった。軍部の権力は、膨張主義者中野正剛の埋葬に集まった2万人をはじめとする、右派から自由主義的見解を持つ新聞まで、市民社会の間接的批判に耐えなくてはならなかった。マスメディアは知的で批判的な公民を維持しようと尽力し、時には首相を揶揄する記事も掲載した。ある種の自由を手に入れるためには、海軍と陸軍の間の論争はよい隠れ蓑であった。自由をえるための必要な組織はまだなかったにしろ、そこには日本軍国主義への対抗があった。その上、それは指導的階級にのみ限定されたものではなく、というのもそのメンバーに罰を与えることは複雑なことだったからだが、1942年5月に軍人によって召集された帝国議会選挙で証明されたとおり、残りの国民にも広がっていた。この選挙では、軍部の勝利が広く開花したことで軍部による推薦者の一覧表が存在してはいたが、一方で日本の歴史のなかでもっとも多くの立候補者が出た選挙であった。そればかりではなく、無党派が投票数の3分の1の得票をあつめ、466人の議員のうちの85人を占めた。日本人の多くは軍部の勝利に酔っていたに違いないが、一方で最も熱狂的に望んでいたのは、その勝利が決定的であることと、そして戦争がこれきり終わるようにということであった。また、イギリスとアメリカが「黄色い火」の元に敗北したときですら、日本政府への不信は人々の間に広くひろまった。
真珠湾の奇襲攻撃で日本軍が表向き勝利した後、ドイツとイタリアは共に、12月11日にアメリカ合衆国に宣戦布告した。それは、ローマが独自に危険を冒してやろうとした宣戦布告の宣伝効果を盗むためにドイツがとった興味深い道筋であった。多くの人々は予告されたアメリカ艦艇の破壊は勝利への道をはっきり示すものだと考えたが、ヒトラーは世論に対し、自分のとった方法を正当化して、遅かれ早かれドイツはアメリカに宣戦布告しなければならなかっただろうといい、また真珠湾は勝利を約する重要な保障であると述べた。ドイツ・イタリアは、この攻撃で数年の間連合軍は動けなくなると考えた。そしてその間は、全体主義国家の軍には勝利の圧力に耐えることはできないであろう、と考えたのだった。ある意味、その考えは理にかなっていた。日本は太平洋において空軍・海軍の優位を確立しており、そのおかげで、その戦力は、大きな抵抗なくアジア南東部全体において油のしみのように広がっていった。しかしそれは数ヶ月間だけのことだった。
目に見える形で勝ち続けた枢軸国諸国は、相互協力体制に関する合意を取り付けることに躍起となっていたが、それは決して実行されることはなかった。アメリカが太平洋と大西洋のどちらで強く攻撃にでるかわからないので、アメリカに最も攻撃を受けたところの補償を約した、たとえば、結局一度も概略すらも明示されなかったが、艦船を送るなどしがそれであった。しかしもっとも興味深い合意は1942年1月18日にとりかわされた世界分割に関するものであった。これは約4世紀半以前トルデシリャスでスペイン人とポルトガル人が取り交わしたものとそっくりであった。地球というケーキに関して、日本は、ほぼインド川河口に至る垂直線まで行動範囲とし、またドイツはそこから先が領土になるはずであった。しかしながら、その考えを実行に移す機会はなかった。3国の協力への合意は、日本がドイツの援助なしで戦うのを恐れたことと、初期段階の高揚状態による意向の宣言に過ぎなかった。だから戦争の進行状況ではこの合意は決して重要性をもたなかった、たとえば共同軍の指揮や片方の軍が別の軍の指揮に従うといった問題についても話題にされなかった。軍事的・経済的な調整はほとんどなかった。そのようであったから、どのようにケーキを食べるのかについて分け方を議論している間に、時機を逸してしまった。
スペイン政府は真珠湾攻撃を知ったからといって宣戦布告を行ったわけではないが、イタリアやドイツと比較しうる反応を示した。セラノ・スニェルは合衆国大使アレクサンダー・W.ウェデルと日本国大臣須磨彌吉郎の訪問を受け、東京には勝利を祝う祝電を送り、マドリードの日本領事館にも祝いの書翰を送るよう、係に指示を出した。公的出版物でも同様のことを行った。たとえば、日本の印象に繰り返し現れる一連の期待を示しつつ、影響力ある週刊誌『世界(Mundo)』は当時よく使われていたはなやかなことばづかいで歓喜を表現した。「現在の世界戦争はスペインが望む新秩序を導く手段となるであろう。その信念と希望とのおかげで、全世界で今起こっている大変な試練を、私たちは男らしくも乗り越えることができるのだ。」日本への親近感はその特権を取り戻したように見えた。スペインの公的立場は枢軸国寄りの非交戦国であった。しかしこれは、ヨーロッパで戦争が勃発した時提案されたもの、つまり共に争いをやめさせようとする計画とはかけ離れていた。外交は既に存在意義を失っていた。
表向き、日本の理想像は新しい推進力を得たのだった。須磨大臣は日本の記者団に、背中が痛いほどのあまりに多くの祝いを受け、またフランコ将軍自身から新年の夕食会で聞いたと語った。「私にとっては日本の有効で特筆すべき戦略が英米に突然大きな戦争への恐怖をもたらしたのは、すばらしい出来事であった。これで彼らも、日本精神の何たるかを少しは知るであろう。」しかしそのような祝いや背中の痛みは幻想が消えるのにかかった時間だけ、続いただけであった。
スペイン人の日本主義者の感情には、ばら色の部分ばかりがあったのではない。真珠湾攻撃以降、日本の味方をすることは以前のようにたやすくはなくなった、というのもデータが賭けていたし、また国内の大きな対抗勢力も呼び起こしたからである。この戦争でスペイン政府が直面した最初の問題は、情報が、つまり日本人に好意的な情報が入ってこなかったことだった。入ってくるものは、最低限の信憑性しかなかった、というのも日本がドイツの情報部に渡した情報であっても、多くの場合は、日本国内向けの宣伝文と大差なかったからである。そうしてスペインには日本側の新しい一次情報が不足したのだった。それは在東京スペイン使節を通じても変わらなかった。その裏付けとしては、真珠湾以前の最新の直接情報が8月・9月・10月の日付になっていることに明らかだ。データの不十分さは新たに物議をかもし出したわけではないが、中国における利権よりももっと大きな利権をめぐる作戦区域への影響が及ぶと、それは悪化した。その上で人びとはそれほど有利ではないデータを探した、というのも日本軍勝利の情報には具体性が欠けていたが、枢軸国側の敗北はますます確認しうるものになってきたからである。ヒトラーは約半年間約束してきたにもかかわらず、ソビエト連邦へ決定的な打撃を与えられずにいたし、またヒトラーの敵ともなった冬将軍もあり、加えてアフリカにおけるイタリア軍の敗北と同様などが、大戦の行方を予想させるきっかけを与えた。剣は高々と掲げられてはいたが、しかしアメリカの参戦によって枢軸国の最終的な勝利に対する疑いが強まった。あまりのデータ不足のため、セラノ・スニェルは英・葡・日本そしてバチカン大使に対してスペインの立場を説明する会見をも、情報を最大限に収集するために利用した。太平洋戦争について議論する際には、多くの他の人々同様スペイン人の間でも推測が優位を占めた。このことは、決定的なものとして知らされた勝利にもかかわらず、日本の参戦について人々が無関心だったことを説明する手助けになりうる。
体制内では保守派が枢軸国の勝利について主な疑念を表明した。アメリカ合衆国からもたらされる数多くの情報から考えると、日本側のあまりに断片的なデータや日本の最終的勝利はゆるぎないものだとする公的見解は簡単には信頼できなかった。しかしそれにはもっと別の理由もあったのだ、というのも新たな局面にあって、公式見解の相違はありうることだったのだ。保守派は公然とファランヘ党員の新たな歓喜と矛盾する情報を得ようとした。もはやイギリスが抵抗しうると主張するからといって、また連合軍が最終的には勝利を収めると信じるからといって、で非国民呼ばわりされることはなかったからである。太平洋戦争では、ヨーロッパ戦とは異なって、データ分析はさほどの政治的含みをもたなかった。日本に対してアメリカ合衆国を支持することは。ドイツに対する友好を示すスペインでは政治的には正しくないことになりえたが、それはどちらかといえば理解しえる、許容範囲の態度であった。というのも歴史・地理的理由からも経済的重要性の点からいっても、合衆国への軽蔑の度合いはイギリスの場合よりも少なかったからである。また日本という選択肢は絶対的な好感をもっては見られていなかったということもあった。
開戦を前にしたメンデス・デ・ビゴの反応は興味深い。開戦前夜にアメリカ人の友人ジョセフ・グルーと夕食を共にしていたが、ラジオで日本の陸・海軍がハワイ・フィリピン・グアムでの戦闘を開始したというニュースを聞くや否や、二つの建物の近さを利用してアメリカ大使館へ出向き、もっとニュースをくれるようにとグルーに頼んだ。そのときグルーに会うことはできなかった、というのもグルーには日本の東郷茂徳外相との会談予定があったからである。その会談では、開戦ではなく日本と合衆国の交渉決裂が伝えられたのだった。だからグルーが大使館へ午前9時ころ戻った時に真珠湾攻撃を知らせたのはメンデス・ビゴだった。グルーはすぐに東郷へ電話をかけ、事実確認をしたが、東郷はグルーにまったく知らないと言い、そして彼に公式に伝達がいったのは、1時間たってからのことだったのだ。この逸話から、日本外務省とその高官がカヤのそとに置かれ、軍人たちは彼らに何週間にもわたって敗北のニュースを隠しえたことがわかるし、またスペイン人が日本に個人的・政治的に接近するには障害があり、難しいこともわかる。スペイン大使は日本人よりもアメリカに尋ねようとした。メンデス・デ・ビゴは実際、すでに同年の5月にグルーとの友好関係についてあえて知らせていた。セラノ・スニェルやファランヘ党員の怒りはもうどうでもよくなっていたのである。あまりに失望していたので、アメリカ寄りの自分の感情を書き残すことに頓着しなかった。彼のケースは、日本が熱烈な膨張主義をとるという点ではフランコ体制との一致があるとわかっていても、日本に対する疑念を抱いていた重要なオピニオン・グループの代表例に思える。太平洋戦争勃発によって疑念は噴出し、保守派はファランヘ党員やスペイン外務省のものとは大きく異なる見解を公に表明したのだった。
オーストラリア・オランダの分遣隊によるポルトガル領チモールの「予防的」占領に起因して開戦後たった10日でそのように確認された。彼らはオランダ主権の島のもう半分を防御し、ポルトガルの領土を保護する必要性を申し立てた。日本はポルトガルという中立国の支配下にある地帯を占領するつもりはなかったし、マカオにおけるポルトガルの主権を常に尊重していた。しかし占領は、ポルトガルと日本の友好関係に波風をたてるために主としてイギリスが企んだことであった。事実、ポルトガル首相兼外務大臣のアントニオ・デ・オリベイラ・サラサールは、占領に激怒して抗議しただけではなく、イギリス側の弁明を拒否した。
スペインではイギリスの占領に対する返答は日本の拡大に対する態度しだいでもあった。『アリーバ (¡Arriba!)』はイギリスの策略を強く批判し、占領の最終的目的を予測し、ポルトガルの中立を冒すものだと批判しながら、イギリスの弁明をろこつなものと評した。しかし『ABC』はそのような立場をはずれ、ポルトガルの置かれた難しい立場を指摘するだけにとどまらず、オーストラリアから発せられた予防的占領は法的に正当化できるとまで述べた。この新聞は、その上、非常に冷たくポルトガルの中立に対するイギリスの挑戦を見て取っていた、なぜならば、植民地占領は余計なものと認めながらも、イギリスとポルトガルが結んだ相互協定で、日本に対する軍事基地としてのこの島の使用をさけることができると思い起こさせたからである。『ABC』はスペインにおけるイギリス外務省のスポークスマンの役割を果たした。それによってイギリスの水面下での目的について説明する『アリーバ』の役割と釣り合いが保たれた。まったくのところ、オーストラリア軍隊の到着は2ヵ月後に日本軍による占領を引き起こしたが、その占領は中国のマカオで行ったように、部分的にでも島を占領しないほうがいいと考えていたはずの日本の元々の意思に反していた。そうしてイギリス(もしくはアメリカ、というのもポルトガル領チモール占領することをほのめかしたのは、合衆国海軍大将トーマス・C.ハートであったから)は最終的には日本とポルトガルの間に根気強い後ろ盾を作ることに成功した。なぜならチモールのケースは、紛争の間中、この二国間、そして世論における緊張を生み出したからである。議論は役立った。そしてスペインでは好みの傾向が定められた。しかしチモールはあとでやってくる一飲みの前のたった一口にすぎなかった。
1.1.フィリピン、戦争突入
フィリピンの情勢はスペインに直接影響を与え、また考えてみれば明らかだが、フィリピンでの日本軍の侵攻はチモールでよりももっと強い懸念をおこさせた。この群島においては、すでに見たように、スペインは日本とアメリカ合衆国とのライバル意識がスペインにとって利益をもたらすようになると踏んでいた。一部の者は、日本の影響力の方が一時的で、必要悪のように見えたので、アメリカに対する日本の覇権のほうが好ましいと思っていることを表明していた。
しかしながら日本の膨張に関係しているフィリピンの将来への見通しは、理想の日本という幻想が終わると同時にソ連への攻撃と共に既に終わりを告げていた。時を同じくして東アジアでの絶対的な支配権をますます希求する帝国の現実が道を開いた。友人だろうが敵だろうが、東アジアには白人の自由になる場は隙間すらもない、とされた。真珠湾攻撃が始まったとき、ロドルフォ・レジェスが書いた雑誌『世界』に書いた「スペイン性」についてのページでは、以前ののどかなイメージに対してこの笛行く矛盾は、1941年12月7日時点で現れていた。この論文は日本の掌中にあるフィリピンの未来に関して既に示されたコメントに対して、抜本的な転換を提言し、フィリピンではスペインの影響力はアメリカ合衆国の植民地化でも共存しうると断言するに至った。数年間で初めて、最も公式である出版物で全体的に、前章で述べた通りフィリピンを占領する可能性を捨てるだけではなく、日本に対して明らかにアメリカに味方する文章が読めた。「しかし再征服のユーモアも可能性に見合わない尊大さもなく、スペインは現在フィリピン群島に存在する決定的影響力と社会的なものにおいて共存することができる…。装置はある、だからその装置は政治的・国際的な全能の介入者の疑念を起こさせないように注意深く扱われなければならない。これによって私たちの懸念や機転は、フィリピンを保護するものとなり、精神の内にそれこそがスペイン性のやろうとするものの全てだ、とした」スペイン的であることに対する日本の態度を前に、悲観主義が数ヶ月前の楽観主義に取って代わった。こうしてスペインの唯一の目的ははっきりと、文化面に特化されることとなった。
敵対が始まると、レジェスの論考が明らかな例であるが、フィリピンの将来についてのスペインの公式の立場づくりに、具体的に変化が見られた。スペインはフィリピンの将来について発言するようになり、またその独立を擁護するにいたった。「我々スペイン人の最も強い要望は、地理的な宿命を超越した、独立し文明化されキリスト教的であるフィリピンという生命の維持である。」スペインは、日本がオランダやイギリスの植民地でいわゆる「マレー民族」を支配するのは理解できたが、文明化されキリスト教的でスペインの胸中に形成されたフィリピンの民族を占領するのは受け入れなかった。様々な党派はこの立場を受け入れたが、それぞれ、異なる状況を付け加えそれを協調したがった。あるグループでは枢軸国側の勝利が重要だったし、また別のグループには侵略がのびてスペインが喪失するのはなにか、が最重要データだった。ある者にたちは事実を操り、またある者たちは将来起こりそうなことに賭けつづける以外に選択肢はなかった。
確かに、当時フィリピン占領に関しては、積極的な期待はほとんどなかった。ファランヘ党員も保守派もそれは同じだった、というのもスペインの旧植民地が、望まなかったにもかかわらず日本とアメリカが対立する戦闘地になってしまったことについて、悲しみを顕にするのが大勢を占めたからである。『世界』は戦闘開始後数週間でスペインの抱える矛盾について述べた:「地理的運命がフィリピンを太平洋の支配権をかけた戦いの中に巻き込んだ。アメリカ合衆国はフィリピンを防波堤にしたがっているし、日本は南海へ出る橋渡しとしてフィリピンを必要としている。スペイン性の最も遠い子孫は、運命で最も重い十字架を背負っている。」ファランヘ党員も保守派もすべて、フィリピンにおける将来の出来事を恐れていた。しかし願望は積極的であったが期待より恐れが支配的であった。
しかし理解しうる不安を越えて、そのスペイン性の状態がむしろ保守派とファランヘ党員との間で既によく知られた議論中の新たな言い訳に使われたところでは、フィリピンに関するニュースは政治的なテストであった。皆が太平洋戦争に、既存の自らの政治的立場を擁護する論点を探した。そして、ある人々はアメリカ合衆国からもたらされた最も懸念すべきニュースを流すのをやめなかったし、また他の人々は被害を最小限にして伝えた。例えば『アリーバ』は、在マニラスペイン領事の電報を掲載し、全てのスペイン人は良好な状態にあり、大多数がマニラに踏みとどまる方がいいといっている。反対に、日刊紙『ABC』は在ニューヨークのEfe通信の担当を通じてもたらされた合衆国発のニュースを広めることを選んだ。そのニュースはパナイ島のイロイロで死亡したスペイン人修道女に言及していた。フィリピンに多くの家族的つながりもあるスペイン人読者に、保守的フランコ主義者は心配を静めるよりも論点に勝つことを選んだ。平和と平穏について語りたがる者もおり、問題点を強調したがる者もいた。
こういったニュースにみられるように、逸脱は大きかった。スペイン外務省は、『アリーバ』の見解に組みして仲介役を務めようとしたが、理由はあまり明確ではない。おそらく、民間人の間で苦しみや破壊が起こるのを避け仲介を試みるようにというマニラのカスターニョ領事による提案や、東京の領事館によってそうなったのであり、確かにセラノ・スニェルの政治的必要性にもっと近づけた形で世論を賛同へとしむけようとしたのであった。結果として東京からの電報の翻訳を受け取った後、外務省はこのような文章を発表した:「フィリピンに親族がいる、もしくは権益をもつスペイン人を安心させるため、またスペイン人修道女がフィリピン群島への爆撃の犠牲となったという昨日のニュースの続報がある。他の情報源によれば、この修道女は怪我をしたのみであると付け加えなくてはならない。」外務省はこのニュースを日本寄りの解釈を広めるために利用し、次のように認めた。:「この折に、日本政府は日本の飛行部隊によるフィリピンへの爆撃ででた民間人の犠牲者は非常に少ないと明示しているし、日本の飛行部隊は最も厳密に軍事的目標のみを探す模索することを宣言している。ただし50を超える宗教団体の建造物も、様々な文化センターや商業施設などもあるのだから、スペインの植民地において、偶然にも一人のけが人がでたことは嘆かわしいことだ。」フィリピンに関するニュースに見える公式の交渉は、しかしながら、セラノ・スニェルがこれこそが自分の意思なのだと須磨外相にいったような「民衆感情を導く」ことにはあまり役にたたなかった。というのも『アリーバ』は人々を沈静化させようと新しい見出しを出したが(「フィリピンでの空爆のスペイン人女性唯一の犠牲者は負傷したのみである」)、ABCはこの件について以下のように情報を流すに留めた:「外務省のメッセージ」フィリピンに家族のいる市民は自分たちの苦しさを軽減するのには最適な情報を信じる選択の自由がある。しかし外務省は日本への好意を示すという、危険な一歩を踏み出してしまった。
なぜなら、この外務省覚書で、体制派閥間の意見の相違が国際的様相を呈したからである。一方では、スペイン外相が日本外相に伝えた民衆感情についてのコメントを通じて、また特にこの公式声明はアメリカ大使館がフィリピンのニュースにかかわることを誘発したからだ。大使アレクサンダー・ウェデルは、スペイン外務省を日本外務省のスポークスマンとし、激しく攻撃した。そして日本寄りの覚書に公式回答をせずに放置はできないと述べた。「間違った印象」を与えないために、よって、公的に、以前の、敵の覚書と同じ宣伝を自分の書いたもので行うべきと説いた。
3ページに及ぶ回答について様々な案が出されたこと、そして「閣下の言葉遣いや意図が回答を大目に見てくださるだろう」と肯定的に答えたことが示すように、セラノは合衆国の覚書の厳しさに動揺したに違いなかった。もちろん、彼は日本政府の仲介役となることを否定したし、それは、たとえ嘘でないとしても、悪意ある非難だとした、というのは、北米のラジオからの相対する情報についての論点のいくつかを、別の日本の文書から提供されたものととったからであった。しかし最も重要なのはなぜセラノ・スニェルが自分の親日感情が透けて見えるようにしたか、である。そして個人の期待をこめて、暗号でメッセージを伝えることのできない、当時のデル・カスターニョ領事の状況に対比した、なぜならば将来的に受け取ることを期待していたマニラからの自由に書かれた報告書に言及していたからである。
このような回答からは、スペインが日本側の最良の期待を守り続けていたことがわかる。ある絶賛すべき政治的協調は、前章でみたように、すでにドイツ軍のソ連侵攻によって消えうせた日本の理想像の回復に結びついた。なぜなら報道関係の覚書を書いたのは日本だとするアメリカの非難は正しくはないが、日本はセラノ・スニェルやファランヘにそれ以上、何か頼むことはできなかった。須磨自身、スペイン人の日本に対する「よき感情」について言及し、そのことを認めて、イタリアやドイツにあった親日感情よりももっと強いと述べた。しかしそれはつかの間のことで、他のあまり有望ともいえないニュースによって、輝きはすぐにうすれた。
2 反米的な「日本主義」
セラノ・スニェルは日本寄りの非常に冒険的な歩みをとった。彼の賭けはさほどの危険がなかった時だった、経済的現実は期待の上にますますのしかかっており、アメリカは、ハワイで艦隊を沈められてはいたが、スペインで有効なプレッシャーをかけるという点では日本よりももっと説得力ある手段を持っていたからである。例えば、同じ12月以来石油供給が停止したことによって、スペインは対峙政策を続けるか、もしくは石油送付を再開してもらうために必要な処置をとるかを、明確に決めなければならなくなった。そうして、スペインは頭を下げてアメリカの要求をのまねばならなかった。それはスペイン人にとって実現しうる唯一の選択肢であった。そして交渉の間、時間はワシントンに有利に働き、スペインは、スペインが枢軸国側に石油を売ることを避けるという名目のもとに、石油割り当てに関する全面的コントロールを受けるという侮辱的条件をのまねばならなかった。スペインの困難な経済状況を打開しようとするならば、別の道はなかった。政治的差異を優先する傾向にあったセラノの立場は、政府内での信頼を失った。その状況は、フランコが商工大臣デメトリオ・カルセリェールに「我々の外務大臣は経済問題に関しては何もわかろうとしないのだな」と述べたコメントに現れている。「娘婿」は石油の行方がかかっている時には、物議をかもし出す評価を維持することはできなかった。そして論争をとめるようにしなければならなかった。政府にとって、食糧援助の可能性のほうが、何の利益ももたらさないままの政治的対立よりも日を追って重要になった。
よって、アメリカの断固とした答えに対し、セラノ・スニェルは報道機関に再び公式声明を寄せることも、日本の奪取に先立ってマニラからの電報をそれ以上広めることもしなかった。というのも、論争とは関係のないフィリピン首都の領事自身が、報道機関の覚書に反論し、日本の爆撃による教会破壊のニュースを確認したからだ。セラノが総領事デル・カスターニョにだした命令は、結果として、より大きな破壊が起こらないように、日本に位置の情報を与えるべしというだけにとどまった。しかし外務大臣の沈黙に対し、アメリカ大使館は強気に出て、日本の空爆についての情報を広め続け、全ての外交の代表へその評価に関して写しを送り続けた。論争はセラノの敗北に終わっていた、というのもこの論争ではあまりに打ちのめされていたので、この問題を引き起こした張本人である日本人にそのことを語ろうともしなかった。日本がもうさほど「かわいがられた娘婿」でもないセラノ・スニェルを辱めるのはこれが初めてではない。彼の「日本主義」はまったくのところ根拠に乏しいものだった;分裂し、費用のかかる戦争に立ち向かうことのできない国としての北アメリカ像は、正しくないことが明らかになってきていた、というのも一方で、日本人はアメリカ人に団結の動機を与えていたからである。そのうえ、そのアメリカという「全権的介入者」は、ロベルト・レジェスが『世界』で評価したことによれば、たとえ多くのファランヘ党員がアメリカを憎もうと、そうやって憎まれるほうが日本人のように猜疑心と軽蔑をもたれるよりもまだましだとわかっていた。
輸出の独占権を持っていた者に必要な善により、アメリカの圧力はスペインの外交関係においてますます明らかになっていった。スペインと枢軸国との協調のなかの最もきしみを招いている困難を減らすため、アメリカはいくつかの譲歩を得ることができた。例えば、フェリペ・ヒメネス・サンドバルが率いたファランヘ対外部の活動を廃止するというガイドラインがそうである。アメリカはセラノ・スニェルの想像よりずっと力があり、日本が間接的な役割を果たした2つの新事実によって、明白な形でそれが強調された:イベリア・ブロックとリオ会議である。
いわゆるイベリア・ブロックは、ポルトガルの独裁者アントニオ・デ・オリベイラ・サラサールとスペインの独裁者フランシスコ・フランコとのある会談を機に、1942年2月に開始された。その目的とは、単に2中立国間の結びつきを緊密にしようとしたのだった。二国のうち一国はイギリスよりの世論をもち、もう一国には枢軸国よりの世論があった。しかし召集は連合国の戦略へならったものであった、というのもイベリア・ブロックは、少しでもスペインをその代父であるドイツから切り離す試みだったからである。つまりヒトラーを孤立させ、イタリアが戦争への参加を段階的に縮小できるように中立国グループを作ろうとする取引であった。結局この試みは成功しなかった。なぜならある意味時期尚早であったし、またスペインとポルトガルの関係は1943年まで深まることはなかったからだ。
しかし他方、イベリア・ブロックはスペインにチモールをめぐるポルトガルと日本の緊張関係をもたらしたため、日本との関係には害が及んだ。イギリス軍が占領していたポルトガル領チモールを日本が征服したことで、緊張は最高潮に達した。2月19日、チモールでの日本軍の侵攻開始と共に、ポルトガルと日本の間の緊張関係は高まり、スペインにも影響した。ポルトガルは、極東に関連したスペイン世論に影響を及ぼしていった。チモールのことがあるので、ポルトガルは日本に宣戦布告はしなかった。しかしスペインの盟友である二国、ポルトガルと軍国日本との間の緊張関係がセラノ・スニェルの政治的立場を害したのは想像するに難くない。第三国の間で軋轢を引き起こそうとするイギリスの戦略は相互に機能していた。しかしリスボンから送られたポルトガル兵が島の防御のために間に合って到着していれば、それはもっと有効であったはずである。ポルトガルは敗北を自らは体験しなかった。ジョアン・ベロ号・ゴンサルベス・サルコス号は、日本軍の攻撃を受けて、インドに引き返さねばならなかったのだ。
1942年1月15日から29日にかけてリオデジャネイロで開かれた第3回アメリカ諸国間協議会で、セラノの政策はまたひとつ重要な打撃を受けた。この会議は、1940年にハバナで承認された相互援助に関する大陸間合意の結果として開催されたのであるが、大陸外の国がアメリカ大陸に攻撃を仕掛けた場合に自動的に召集されるようになっていた。真珠湾攻撃の後、戦争によって広がった反日本熱のなかで、共通政策について議論するために大陸の21カ国が一同に会したのであった。アメリカは大陸が一致して枢軸国側と国交断絶をするよう熱望したが、「権威主義体制の賛同者、スペイン寄りで、まったくの反アメリカ主義者である」と考えられていた外務大臣エンリケ・ルイス・ギニャスが率いたアルゼンチンが反対したため、アメリカの要望は通らなかった。このアルゼンチン人は会議における不協音であった。もういくつかの国はすでに枢軸国に戦線布告を行うかまた枢軸国との国交を断絶しているときに、一致して共通の方針を受け入れることを考慮するのは矛盾であると文句をいった。その上、太平洋の真ん中にあるアメリカ合衆国の「アジア的」領有地への攻撃は、アメリカ大陸に対する攻撃にはあたらない、とおこがましくも断言した。
アルゼンチンは孤立していたわけではない。そしてボリビア、ペルー、ウルグアイ、チリと中立のためのブロックを作ろうとした。しかしそれに従ったのは海岸線における日本軍の攻撃に対する世論に脅えていたチリだけであった。会議はアメリカの経済的影響と参加国の大半がもっていた反日本感情、そして枢軸国との国交断絶を逃れられないものとする宣言に署名することにアルゼンチンとチリが嫌悪感を示したこととの間で進められていった。最終的に、アメリカ共和諸国は「アメリカ大陸のある一国に日本が攻撃をしかけ、続いてドイツとイタリアがその国に宣戦布告したのであるから、日本・ドイツ・イタリアとの外交関係断絶を勧告する」という文書が承認された。単なる忠告でしか一致した意見をしめすことはできなかった、なぜならばチリとアルゼンチンには、ウルグアイ・ペルー・ボリビア・パラグアイ・ブラジル・エクアドルなどの国々が枢軸国に対する反動の鎖を解き放った時に、中立を維持することが許されたからである。これらの国々は1月末以前に枢軸国との外交関係を断絶した。北アメリカの経済的圧力は南アメリカに関する政治的論点以上の重みがあった。チリとアルゼンチンの中立さえも相対的なものであった。非交戦国とされたアメリカ合衆国とは、貿易が承認される一方で、イギリスを含めて、他の国々との貿易は禁止されたのだった。
リオデジャネイロはサムナー・ウェルスとルイス・ギニャスにとって相対的成功を作り上げた。なぜ相対的かというと、国務次官にとっては一般的な支持を得たからであるが、しかし一致した国交断絶は得られなかったからである。また連合国にとってのもうひとつ恵みとなったのは、戦艦を大陸の港から出航させ始めたことだった。ルイス・ギニャスには会議がアメリカ寄りにならないようにすることはできたが、自分の立場の違いは鮮明になった。彼は強情だと非難はされたが、一時的な形ではあっても、純粋に祖国の名誉を守ろうとしたことで、熱狂的な賞賛を与えられた。リオ・サミットで負けたのはスペイン外交だった。ラテンアメリカ諸国の中立を維持しようとするスペインの試みは完全に失敗し、それを通じてアメリカが擁護した「汎アメリカ主義」の前に「汎スペイン主義」は大陸から消滅した。ラテンアメリカにおけるスペインの関係と影響力はこれまでにないほどの低い点に落ち込み、世界大戦中悪化の一途を辿った。
このアメリカの勝利は、大陸全体に共通の敵の存在を見出させたハワイでの攻撃のおかげで得られたものだったので、フランコ政権はこの失敗の一因は日本人にあることを忘れないにちがいなかった。ロドルフォ・レイェスは『世界』において、アルゼンチン大統領と非常に似た形で理由づけを行っている:「その攻撃は存在した。それは真実である。しかしアジアでの話しであるし、北アメリカの旗に覆われた場であって、アメリカ大陸の上で行われたのではないのだ。」スペインは真珠湾における日本の罪を部分的に認めた。その上、自分たちの間違いを隠すために、必要以上に日本を拒否したことも想像しうる。そのことに対して、日本人の隊長、セラノ・スニェルは、将来的な可能性を数え挙げることでしか答えることができなかったのだろう。変化するために。
その上、ラテンアメリカにおけるスペインと日本の協力はリオ会議以後空転した。日本はそれに気付き、アメリカ大陸への跳躍台としてスペインを使おうという考えは、意義を失った。対立の初期には、例えば連合国側が放送したものの効果をなくそうとラテンアメリカ向けの日本の宣伝のため、在フィリピンのスペイン・ポルトガルの公務員にインタビューをして、スペイン語のラジオ放送を流そうという計画があったが、二度と話題が出ることはなかった。部分的にはラテンアメリカの国々の多くが既に日本との外交関係を絶っていたこともあり、ラテンアメリカでの宣伝協力には意味がなくなっていたのは明白であった。
戦争以後、スペインにおける日本像には大きな変化が生まれていた。この時期には、二つの異なる視点を鮮明に区別することができた。保守派の視点はますます反対者に対抗する新しい主張を見出し、ファランヘ党員の視点では出せる主張がどんどん少なくなっていった。そのうえ、もっと注意して見れば、「日本主義者」の日本像はますます苦い味を秘めていき、日本の軍事的勝利に対するスペインの賞賛は、以前の賞賛とは異なるものとなっていた。ファランヘの新聞を読んでいくと、明らかに、アメリカ合衆国を打ち負したいと望むがために、日本が勝つように願っていたのがわかる。またマニラ陥落の数日後に出た『アリーバ』の論説では、アメリカへの際立った批判はもちろん、日本を手放しで賞賛するのを気にかけているのは興味深いことだ。太平洋戦争勃発で、日本の軍事的成功に対する繰り返しの絶賛にもかかわらず、人びとは新聞では抑えきれない親日の熱狂を話すことができず、何人かの書き手が確認したように、フランコやセラノ・スニェルの視点を反映することもなかった。反対に、ファランヘ党員の中での感情が薄れ始める以前に、反アメリカ合衆国感情が日本主義を超えた。
フィリピンでの出来事で、日本に対する以前からの期待は決定的になくなり、単なる幻想で以外のなにものでもなかったことがわかった。その年のはじめ、フランコは須磨へコメントで、日本軍侵攻に関してはフィリピンにおけるスペイン的なものの将来が刺激されていると述べた。「あなたたち日本人が、文化的にも歴史的にも、フィリピンがスペイン的であるのを、全体を考慮にいれるつもりであることはわかっている。」メンデス・デ・ビゴは、東京から恐怖を煽り立てる役割を果たした。日本の言論がフィリピンにおけるカトリック教会の権力に対する批判や1898年以降「没落したスペインの王権」に対する批判を広めたという情報を流し、「日本がフィリピンの民をアメリカ合衆国やスペインという過去の体制の圧制から解放したのだ」とも付け加えた。スペインに対する激しさはなかった;情報に基づくどの記事をとっても、見出しではそのような批判を際立たせることなく、また人びとは特別の敵意について語ることもできなかった。ある意味メンデス・デ・ビゴがもはや英字新聞以外の新聞を読むことができなかったからである。しかし、この議論に関して、スペインは、王党派外交官がその重要性を認めるほどの疑い深さで、フィリピンではスペインの利益は日本の利益と相反するのだと感じ取った。その当時につくられた日本像はセラノ・スニェルの野望にはあまりに不利であって、またセラノ・スニェルは、在マニラ外交官でファランヘ党員のデル・カスターニョの最も類似した情報にも、あまり支持を見出すことはできなかった。なぜなら、まずはほとんど1ヵ月半の間なんのメッセージも送れず、その後真珠湾攻撃後アメリカ人のもとで厳しい制約を受けながら、やっとのことで送ったのである。電報は、数値を使わずに、また英語で送られねばならなかった。デル・カスターニョの状況における唯一の相違点は、その中継は東京から行われたということだ。最もはっきりした形で、ますます日本人が敵と見方を区別する努力を怠っていることが分かってきた。「反スペイン・反イギリスの怒りで炎がついた」とメンデス・デ・ビゴが書いたように。昔のような、日本の友好的な慈愛への期待は冷水のシャワーを浴びたのだった。フィリピンでは、すくなくとも、見せかけのものであったことが判明した。
結果として、セラノ・スニェルは、新しい過ちを自らが冒すのを許すことができなかった。日本公使館はセラノにマニラにおけるスペイン居住地の将来的安寧についての別の文書を渡した、というのは、外務省の覚書として広められるようにと考えてのことであったが(「フィリピンでのスペイン居住地が変わりなくあるという意味で、マニラにおけるスペイン総領事からの電報として公にすることができる」)、セラノは回答しなかった。日本の覚書も日本占領下のマニラからのデル・カスターニョによる最初の電報も公開しなかった。「日本による非人間的行為を支え、擁護している」というアメリカの非難が彼を押し止め、セラノ・スニェルは日本人に対して、デル・カスターニョに謎のメッセージを伝えてくれるようにと頼むにとどめた:そのメッセージとは、「キューバにおけるスペイン市民はよい状況にある。」というものだった。戦闘的なファランヘ主義は、ますます日本寄りの立場を強調するばかりであった、というのも日本に対する以前の理想的賞賛は余りに「考えの甘い」幻想に基づいていたとわかったからである。マニラは、結局、日本軍の圧倒的勝利によるファランヘ党員の喜びを覚まさせた。
3.戦争の世界化を前にするスペイン
初めのニュースがもたらした驚きや、愛する土地の侵略に対する懸念の段階を超えて、スペイン政府は、短い間で、非常に離れたテリトリーで起こった出来事ではあっても、新しい紛争がスペインにもたらす直接的な結果に気付いた。国境まで届いていたヨーロッパの戦争についての反響ほど重要ではないにしろ、太平洋戦争はスペインに国内的にも国外的にも影響を与えた。二重の反響があった。
3.1太平洋戦争と外交的文脈
1941年秋は世界戦争の結果の明暗をわけた。この時期に戦後の二大列強が、戦後の戦略的問題提起に多くの影響を与えるだろう1941年のショックから、介入し始めたからだ。その折、当然のことながら将来何が起こるのかまったくわかっていなかった、しかし全ての国々の政治的井戸端は、アメリカ合衆国とソビエト連邦という戦争に新しく参加した勢力の軍事力を測るのに一生懸命であった。鍵となる質問は、2度の奇襲攻撃で決定的に動けなくなったか、またそうでないとすれば、初期の敗北から立ち直るのにいったいどれくらいの時間がかかるか、ということであった。枢軸国の敵が最終的に散々な結果で終わると見た人々には事欠かなかったが、しかしヒトラー自身、1941年9月19日に初めて個人的にドイツの最終的勝利に疑念を抱いたのは意味深長である。ドイツ側についたスペインでは他の国で起こったのと同様に、その件についての論争が起こった。違いはスペインに届いた情報にあった。日本の攻撃の重要性に関するその議論の中で最も目立ったのは、しかしながら、特別の利害関係があった2つの様相についてであった。つまり、戦闘の主要展開地としての海の利用と、ソ連に対する攻撃の可能性についてである。
太平洋戦争は大部分海上での戦いであり、それはスペイン軍の戦略にとって2つの理由から基本的なことであった。まず、第二次大戦にスペインが参戦するのか、それとも独自の領土独立の保全を目指すのかということは必然的に海と関連していた。特にイベリア半島から非常に離れたところにあるカナリア諸島や、またバレアレス諸島という、外国が野望を抱くには余りに魅惑的な島々を保有するスペインとすれば、海はスペインがとる行動にとって明らかな現場であった。太平洋における様々な島々の位置測定とその距離関係がもつ利益は、その証拠だった。例えば雑誌『世界』に至っては、戦争が始まるとすぐに、太平洋の地図を出したほどだ。第二には、日本の軍艦は当時世界の主要な艦船の一つとして有名であり、報道機関やエリート官僚の繰り返しの注目を集めていたからである。前マニラ領事だった上海領事のアルバロ・デ・マルドナドは、まだ敵意が芽生えずにいた頃、はっきりと、日本の例に学ぶ可能性を示唆して、こう述べた。「我々にとって、日本のケースは利用し学ぶべきよい教訓である。ただ、スペイン人が海上ルートに再び目をむければ、世界有数の列強の中にスペインを位置づけることは可能であろう。」
スペインの視線は、シンガポールに向けられていた、なぜならそこはイギリス帝国の重要拠点であり、陥落しえない要塞として有名であったし、またジブラルタルのケースとのよく似ていたからである。このことで総統は須磨と話したたった数度の機会の中で、こう宣言するに至った:「私はシンガポールもすぐに陥落すると確信している。その時には太平洋における戦争は終わると考える」と。シンガポールは陥落した、しかし、マレー半島から植民地を攻撃した日本の大勝利にもかかわらず、戦争は終わらなかった。スペインはこの戦略から何かを学ぶことができたはずだが、その頃は、そういった作業はますますされなくなっており、日本が次に決定打を与える場所はどこかを考えるのに賭ける方を好んだ。新聞はその未来の攻撃の場をインド亜大陸と予想した。これはあたっていた、というのも4月初頭に、真珠湾攻撃を行った南雲艦隊は、セイロンにおけるイギリスの東方艦隊を攻撃したからである。しかしイギリス艦隊を倒すには至らなかった、なぜならばアメリカ情報部からの情報で、イギリス海軍は、ソメルビル大将の指揮下にあって、日本の攻撃をかわしたからである。戦争の終結は再び空に浮いた。その上、スペインは日本の戦略から学ぶところはほとんどなかった。以前はスペイン人から、またカリブ海からフィリピン、そして赤道アフリカの距離をおさめたスペイン帝国海軍の歴史的な困難から学んでいたのは日本人だったにちがいない。なぜなら南雲についていえば、そのセイロンへの長い旅を終えた後、それ以上は艦船を完全な形で用いることはできなかったからであった。艦船の多くは帰還後には修理のためドックに入る必要があった。それがミッドウェー海戦での敗北理由のひとつである、なぜならばこの開戦を見てみると、日本の大将たちは新しい挑発に備えるよりも、走行距離をのばすことにより多くの時間を費やしていたからである。このような形では、日本の優位は消え去った。一方で、アメリカは、初年は望んだ作戦の半分しか実行できなかったが、燃料と北アメリカ海軍の輸送の問題は終わりを告げていった。兵站学が局面を変えていった。
スペインが二番目に重要としていた日本に関する利益は日本像がスペイン政府に対して維持していた主要な善のうちのひとつに関係していた:反共産主義である。スペインは、日本は1941年調印の中立条約はあっても、ドイツの例に続くであろう、そしてソ連を攻撃するであろう、と見ていた。日本はそうはしなかったが、可能性はなくなったわけではなかった;日本は権威ある広東軍を満州に駐留させ続けていたので、望みさえすれば、いつでもシベリアを攻撃することはできたであろう。この利益はまた、将来の可能性にも立脚していた、しかしそのことはスペインにおける日本像がもっていた肯定的な主要要素のひとつであった。最も熱狂的なファランヘ党員だけでなく、一般にソビエトの敗北を熱心に願っていた人々の間にもあった日本像だった。そういう人々の中には、東京のスペイン使節、メンデス・デ・ビゴがいた。1942年2月に彼は日本陸軍の最新の勝利に言及した後、期待を示し、「次のロシア攻撃でウラジオストックを攻撃して、日本がドイツを援助するであろうというのは一般的な意見になっている。」と述べた。
フランコ自身もこの可能性に非常に興味を覚えていたので、戦争が始まると、須磨を招集し様々な機会に攻撃を示唆した。1942年1月には、例えば、ソビエトがもたらす余りに重い問題についてコメントし、こう付け加えた:「人々は、スペインか日本が状況を救わねばならないといっているし、さもないと遅きに帰すことになるだろう」。またしばらくして、次の秋には、かなり回りくどいかたちで、日本にソビエト攻撃をしかけさせようとして、「日本のアメリカ合衆国およびイギリス連邦に対する戦略、またソビエトとの中立条約において、日本の極東での立場は、複雑ではあるが、並外れたものである。その積極的な助力なしでは、戦争はもっと長く続くのではないかと思う」と言った。スペインを巻き込むことなく、フランコは須磨に多くの人々が共有している意見を述べた。それはつまりそのような裏切りの攻撃がソビエト連邦を決定的に打ち負かす唯一の可能性だと見ている、という意見であった。
3.2. 真珠湾に対する内政
日本とアメリカ合衆国が戦争状態に入ったことで、内政の文脈でも影響があった。フランキスモの様々な派閥の間で内部の緊張状態がおこっていたのは既にみた通りである:軍人と古くからいる保守派は中立寄りだったので、ファッショ化した若者が大部分を占めドイツやイタリアが打ち立てる新秩序を模索することを賞賛するファランヘ党員とは対立していた。そしてファランヘ党のリーダーとして、セラノ・スニェルがいたのである。1941年12月には、セラノに対する軍人の攻撃は勢いを失った。軍人はフランコに外交上のどのような約束事でも受け入れる前には自分たちに相談するべきだとしてはいたが、セラノの更迭を頼むことはやめた。この資料は、日本の攻撃と時を同じくして、国内の議論に国際的事件が影響したことを示すものであろう。
しかし、穏やかな状況は長くは続かず、1942年1月から2月の間に、セラノは国内での論争に勝つため、日本の勝利の恩恵を利用しようと試みた。ファランヘ党と保守派との間の論争は再び活性化した。ファランヘ党は自分たちに有利な論点を見つけるのに真珠湾のきらめきと日本軍の勝利に拠り所を求め、力を蓄えつつあった保守派はファランヘの主張を拒否した。この対立の中で最も興味深いのは、ファランヘ党の日本人へのバックアップに関する第二の解釈である、つまりこの解釈でフランコ体制内部の論争の様々なニュアンスをよく理解できるようになるし、またファランヘ党対軍人という一般化ではない、もっと進んだ解釈が可能になる。時折、最終勝利についての分析よりも具体的な様相に集中した討論での3つの要素について分析することにしよう。
「日本主義者」の主張は、はじめに、反ドイツというキーワードに読み取ることができる。枢軸国側でのドイツのヘゲモニーはますます強圧的になっていたので、ドイツの侍祭たちは最も完全な形で、失われた平衡を取り戻すため力を合わせることのできる別の勢力の存在を望むようになった。そうして、イタリア・ファシスト党員やスペインのファランヘ党員のように、ナチのほとんど完全な支配にますます消極的になっていたものにとっては、枢軸国の「第三国」の成功は好意的に受け入れられた。チアーノは日記で、「ドイツに対するはらいせのために日本の功績を強調する」者の心のうちに秘められた喜びを記している。チアーノ自身は親ドイツ派だったが、ムッソリーニ自身はナチスの耐え難い支配をからかうのが好きな人の一人であり、チアーノは彼についてこう認めた:「いつもムッソリーニは親日派だ、そして一方でドイツ人をますます嫌うようになっている」。
スペインでも同じような感情には事欠かなかった。セラノ・スニェルの場合でも、ドイツ人との、特に盟友リッペントロップとの関係が悪かったことはよく知られている。だからドイツ人への悪くなるばかりの印象と釣り合いをとろうとして、日本人に魅力を見出そうとしても何の不思議もなかった。須磨は、セラノが外相ではなくなって、真珠湾攻撃以降に自分の日本への賞賛が明らかになったことを認めたときのことをこう回想した:「その時、ドイツはあまりに強すぎた、そしてセラノ・スニェルはヨーロッパの全ての国をドイツの力を中和させる立場に置きたかったし、もしくはドイツと対等の力関係を持つ国を通じてドイツを操るために、何かを動かし始めたかったのであろう。」日本は将来的にドイツと対等の力を持つ唯一の国であり、それが日本との友好関係を築こうとする重要な理由の1つであった。セラノの「日本主義」は、ただ反米的であるのみではなく、ドイツに対する留保の一面もあったのだった。
第二に、カトリック教会は、日本関連のニュースを介して保守派に対するファランヘ党の主張の巻き添えをくっていた。ファランヘ党は、日本が占領地域で宗教に気を遣っているという日本側から喧伝された努力をたてに、教会ヒエラルキーとより特権的な関係を築き、論争に勝とうとした。教会ヒエラルキーは常にファランヘの「国家主義的レトリック」に対して不信を抱き、ファランヘは教会がファランヘに国家装置の支配に関するフリーハンドを与えてくれるように望んだので、ファランヘ党とカトリック教会との関係は曖昧であった。ナチスと同様ファシストも、教会と擦り寄っていった。宗教がファシストの命に従わない選択肢的な力を意味することに関しては、彼らは正常であった。ドイツ人が宗教を支配する一方で、南欧人は、常に、教会ヒエラルキー、でなければ少なくとも民衆の宗教性を考慮しなくてはならなかった。ファランヘ党が野望を抱こうとも、伝統的なモデルに対する選択肢となるようなモデルを構築することはできなかった;エミリオ・ジェンティーレが言うように、「ファシズムが全体主義国家とはどのようなものかを語るごとに、カトリック教会によって表象されるモデル以外はありえないとわかる」のだった。
ファランヘ党員は新しい対立に巻き込まれるという贅沢に身を許すわけにはいかなかった。だから、日本の宣伝はセラノ・スニェルにとっては教会との関係を改善するのに役立った。そうして、フィリピンと残りのアジア地域でカトリック教を支えるために、日本との仲介役をかってでて、ファランヘ党は世界のキリスト教化に賛同するものとしての自らの役割を強調した。またそれは脇からではあったが、非現実的な選択肢ではなかった。日本の新権力は占領国の民衆を引きよせようとして宗教的観点に注意をはらい、宣伝にそれを入れようとした。これは1930年代にまで遡る努力であり、その頃日本は、宗教を通じて人びとの共感を得ようとして、メスキータを建築し旅行を企画するなど、東南アジアにおけるイスラム教の擁護者としての姿を自ら創造しようとしたのであった。カトリック教会に関して言うと、1939年にはキリシタン文化研究会が作られ、スペイン語圏の新聞は、日本の領土の認知も含めて、これらの表向き良好な関係に注目した。
宣伝は功を奏した。太平洋戦争が勃発すると、日本陸軍は民衆の宗教的感情を支持すると決め(自分たちの支配が乱されない限りではあるが)、タイで仏教が支持されたのと同様に、フィリピンではカトリック教が尊重された。日本は、結果として、島々に多数のカトリック宣教師(日本人の)を連れて行くことになり、1943年3月に代表を通じて教皇庁と相互派遣の合意をかわした。そうして「平和のため、また共産主義の撲滅のために」日本の宣伝で、教皇ピウス12世が日本を支持していると引き合いにだすことになった。ファランヘ党はその宣伝が気に入って、真実のものとして受け止め、特にバチカンと東京との間の公式な関係の構築を強調した。占領されたイスラム教の国々への架け橋として、つねに枢軸国側におけるスペインの積極的役割を探してきたファランヘにとっては、この状況は自分たちの野望に都合がよいものだった。その上、日本のキリスト教化の初めての試みの記憶を、現代の文脈で使った。例えば『世界』は、こう確信するに至った:「日本の教会はスペイン教会の子どもである。世界を前に我々が他の肩書きを持たないときでも、世界は我々から十分卓越した地位を得るであろう。」それまでの年月における争いや不和はすっかりなりをひそめた、というのも歩くべき新しい道があったからである。
こうして、戦争勃発後、初めのうちは、日本への祝辞が増えた。保守派で在東京のメンデス・デ・ビゴも、ファランヘ党で在マニラのデル・カスターニョも、前者は日本人司教、田口のマニラ訪問がもたらした好意的な様相に言及し、後者はフロリダブランカ市におけるアウグスティヌス会士への卓越した待遇について述べ、日本の宗教に対する態度を賞賛した。またその上、マニラのサン・フアン・レトラン小学校長であったドミニコ会士フアン・ラブラドールは、秘密裏に書いた『戦争日記』で、日本人の宗教政策をよきものと評価した:「日本人は征服した人々の宗教を尊重するであろうという確証を持っている。日本は征服地の民族と日本民族との間にある精神的な類似性を強調している。大まかに言って、その約束は守られたといえる。」しかしファランヘ党は、スペインの人々にあまり適切でないと判断した情報は与えなかった。日本では、スペイン人の面倒をみる責任者の地位は、帝国臣民が占めるようになり、四国教区代表モデスト・ペレスは例えば、大阪司教によって任命されたハビエルE.田中に任を引き継ぐよう、辞任を強いられた。光るものが必ずしも金であるわけではなかったが、ファランヘ党は太平洋から来たこれらの主張に非常に満足していた。自らの利益のために、スペインでの権力闘争に使うことができたからである。
セラノ・スニェルの戦いは、第3に、個人的なものでもあった。おそらく彼は「ホセ・アントニオの思想」に従ったよりよい世界を目指していたのであり、そのためにはカトリック的感情を称え、協調組合主義国家を創造しなくてはならなかった。しかしこのファランヘ党員はまた、かれの権力の及ぶ範囲を広げるというあまりイデオロギー的ではない目的のためにも戦った。だからこそ、彼は、日本との協力を通じて、自分の個人的な立場を強化しようとしたと考えることができる。なぜならば、スペインが枢軸国の手から飛び立たてるようにするだけでなく、ファランヘ党員としてまた権力闘争を行う者として利があったので、大日本帝国の主張を探したのだ。それは、後から出てくることだが、だからこそスパイ網を使い、また日本国民の利益を代表することを通じて、ドイツを警戒し、日本には非常に広い協調を見せたことからもわかる。セラノは日本の盟友になろうとしたばかりではなく、自分の目的のために、日本に欠くことのできない仲介者となろうとした。
このような協調がラテンアメリカに集中している事実は、戦争の当初は、外相はアメリカ大陸と日本的アジアとの間で仲介役としての役割を求めることができたということを意味している。セラノ・スニェルは、ドイツとイタリアが日本とともに政治的な枠組みを作るときになって懐疑的な姿勢を示したのとは反対で、日本ともラテンアメリカ諸国とも政治的に協力する裁量があることを自慢にしていた。ヨーロッパの枢軸国構成員は、日本がもう既に「配分された」地域である東アジアのむこうで、その政治的触手を伸ばす可能性があることを嫉妬深く見ていた。しかしセラノ・スニェルはそのことに関して心配しなかったし、というのもほかの個人的なそしてまたファランヘにとっての集団的利益を考えることができたからである。しかし、彼がもった期待は、そう長くは続かなかった、というのもリオ会議での失敗の後、ラテンアメリカの国々に日本が影響を及ぼす可能性は非常に低くなり、同様に日本がセラノにあてた信頼も大きく損なわれたからである。しかしそのときはすでに日本の勝利を願う力は動き始めていた。
4.勝利を助ける
太平洋戦争は派閥間の論争にある主張を勝たせるか負かす時にだけスペインに影響を及ぼしただけではなかった。アジアの争いで一般化した政治的・軍事的事件は、日本像を塗りかえ、スペイン国内勢力の相互協力における変化をおこすだけではすまなくなっていた。なぜならばスペインも、スパイ活動・日本人の権益を代表すること・商業活動・フィリピンにおけるスペイン居留地、という4つの要素を通して太平洋における戦争に参加したからである。
スペインは、日本に、たとえば敵の秘密情報や領土内で不足している一次産品を得ること、戦闘にある国々における日本人移民の居留地を保護すること、少数派の植民地の力をかりて日本に支配されている民衆の間から支持をえること、など、戦争に勝つために必要な援助で、多くの場合日本が自ら行うことは不可能であったことを提供してくれる最適の国のうちのひとつであった。スペインが公式にとった中立という立場は、ドイツもイタリアも果たせない役割をスペインが行っているという再評価もたらした。またナチスやファシストは情報を日本と共有する準備はあったが、日本が必要としていた情報はもっていなかった。政治運動の自由もなかったし、外交使節は皆友好関係にある国にしか置いていなかったからである。よって、日本にとってスペインとの関係がもたらす利便性は重要なものだった、なぜならばスペイン領では枢軸国側の国民は連合国側の国民と混ざっていたし、外交使節は全ての重要な国におかれ(ソビエト連邦を除く)、新聞は世界中に特派員を送り相対的にみて質が良く、また決定的なのは、国民には移動の自由があったということからである。
そのうえ、日本とスペインは友好関係にあった。両国とも戦争で支持する派についての疑念は抱いていなかったし、その最終勝利に巻き込まれていた。真珠湾攻撃の後のまばゆい最初の時期に目がくらんで、日本は、スペインがその戦闘力の柵から日本を援助したがっていると見ていた。またそうやって、あるものは真摯な形で、またあるものは日本が勝つほうが政治的にみて望ましいという理由で、またあるものは日本勝利の可能性にしがみつく必要があったために、他のものは日本の金を望んで、日本を援助することで、スペインが自らの利益を得ようとしていることにも気付いていた。
4.1. スパイ活動
日本は、他の国々と同様、生き残りのためには必要で時には恥ずべきことともなる目的を達成するために、いわゆる諜報部を用いた。諜報とは3つの主要な概念を含んだことばである:まず、機密情報や公開された情報などのデータ分析とその解釈。次に情報を集めることに関連する活動、たとえば情報収集やメッセージ隠蔽、メッセージに他のものたちがアクセスできないようにすること、データやその意味を取り違えさせることなど。そして最後に、その仕事を遂行する組織は、通常隠密行動をとる諜報部員をつかう、ということである。
全ての国に諜報部があった。たとえばドイツのドイツ情報部(Abwehr),イギリスのイギリス情報局保安部(MI-5)や イギリス情報局秘密情報部(MI6)、共和国陣営側スペインにおける軍事研究サービス(SIM),フランコ陣営側スペインにおけるスペイン北東情報サービス(SINFE),軍警察情報サービス(SIPM)などがそうだし、またイタリアの軍情報サービス(SIM)やアメリカ合衆国の戦略事務局(OSS)やアメリカ連邦捜査局 (FBI)がそうである。それぞれが独自の行政事務所をもっており、少なくとも理論的に言えば、その活動領域は相互補完的なものである。例えばアメリカ合衆国にはFBIがあるが、これは1924年以来エドガーJ.フーバーによって指導されていた国内での国家への脅迫を調査する組織であるが、1942年4月にはOSSが組織され、国外からの国家への脅迫を受け持つこととなった。OSSを指導したのはウィリアム・J.ドノバンつまりワイルド・ビルで、戦争が終結すると中央情報局(CIA)へ移った。
日本も例外ではなかった。第一次大戦以前のドイツを模範に諜報部を作ったが、その主要な性質として、典型的な日本のお役所仕事の問題点のひとつが浮き彫りになっていた:命令系統の不統一である。海軍にも陸軍にも諜報部は存在した、しかしその本体と同様にそれぞれが別個に機能していた。確かにそれぞれの本体ごとに、参謀本部は行動のための諜報部を別個にもってはいたが、防御のための開かれた諜報活動や秘密裏の行動をまとめる構造は存在しなかった。その上、主にジャーナリストによって構成され、半分公的な諜報部員として接触と代弁を行う外務省の特殊部門も存在したし、軍の対抗諜報部もあったがこれは軍警察つまり憲兵隊と呼ばれる本体の責任のもとに機能していた。このような不統一は、諜報部員の訓練にも現れ、陸軍があの有名な陸軍中野学校を開いても、海軍は決してそれを必要なものとはしなかった。しかし海外では、そのようなすり合わせの欠如が顕著になった。各部署が秘密諜報部員を雇う予算を別個に持っていたので、たとえ探している書類は同じでも、3つの諜報部が世界中にそれぞれ代表を送って別々に機能していた。その上、関東軍も、これはもはや第4の諜報部といえるだろうが、スペインのように満州国を承認した国々の満州国公使館を通じて独自の情報網をもっていた。
諜報活動が必要になると、日本はイタリアやドイツの協力を仰ぎ、これらの国は日本に情報・機器・技術のみならず、ヨーロッパにおいてアンテナを立てることができる安全な場を提供した。しかし、敵国における情報収集に関しては、イタリアもドイツも役に立たなかった、というのもそこでは彼らも自由には行き来ができなかったからである。そのようなこともあり、イベリア半島は最も適切な基地であった。第一次大戦時のベルギーと同様に、第二次大戦中は、その国境の近さと残りの国々とのコミュニケーションが相対的に始められたおかげで、イベリア半島はスパイのメッカとなった。結果として、任命された諜報部員の数が多いことに反映されているが、交戦国の全政府がイベリア半島にスパイ活動の力を注ぎこんだ;時には、分野に精通した大使たち、日本では須磨彌吉郎やそのナンバー2の三浦文夫、イギリスはサミュエル・ホーやバーナード・マレイ、またアメリカ合衆国ではカールトン・ヘイスなどは、諜報部員だった。これはスペインの重要性の究極の理由を示している:スパイがよりたくさんのスパイを呼び寄せたのだった。
その上、日本はイベリア半島で諜報部を組織したが、それはスペインとポルトガルの機能を相互互換させるためだけではなく、枢軸国の国々でもその中心的諜報組織と相互互換させるためだった。海軍の場合は、双方の組織はイタリアの影響下に置かれたが、その責任者は島田海軍大臣の娘婿であるみつのぶ大佐であった。これらはドイツ情報部によって備えられたラジオの連絡通信機構で結ばれていた。またドイツ情報部は連れて行くのに日本人の諜報部員に訓練を行った。スペインとポルトガルの日本公使館は直通電話で結ばれ、マドリードでは三浦が、リスボンでは表向きは通常は須磨によって任命され諜報部と連絡をとる役職であるのだが、財務委員としての上野武雄が、外交スパイ組織のヘッドとして、その電話を使うことができた。財マドリード公使館はラジオを通じてイギリスとアメリカ合衆国の放送を聞くことが任務だった。同様に、内戦に参戦した後スペイン国籍を得たトルコ人のファランヘ党員が率いている在イスタンブール大使館を通じて、スペインはインドでのスパイ網を開発するのに専心した。インドにはそれ以前には情報網はなく、インド洋の動向を押さえるにはボンベイを押さえなければならなかったからだろう。海軍もアルヘシラスへスパイを送り、ジブラルタル海峡をどのような艦船が通過するのか知ろうとした。またカナリア諸島へ一人の日本人を送りこもうとした。
リスボンはアメリカ合衆国の意図を知るのに格好の場であった、なぜならばロンドンやアメリカ大陸東海岸からやってくる艦船のとまる主要中立港だったからである。そのためこの国の諜報部員は主に連合国側から直接やってくる船員を通じて、印刷物の情報を集めることを主な任務としていた。そういった情報の中には、技術的性格の強い雑誌など、入手困難な出版物が含まれていた。ポルトガルは南アフリカとインドに戦略的植民地を保有していたので、諜報部員はリスボンで輸送船団に関する情報を得ようとしたし、また一方バルカン半島への強い影響力を持っていた。敵国の経済状態を知る必要性はますます高まる一方でポルトガル自体とそこでの情報収集グループの重要度は高まった。しかし、ポルトガルは、よりよい自己発展を遂げる前に、限界に苦しんだ。ポルトガルの新聞社は「文化的にあまりに低いレベルである」外国には特派員を置かなかったので、ポルトガルの情報は質が貧困であった;また、チモール占領によって生まれた緊張関係はポルトガルの役人との公式連絡の障害となり、日本は、結局影響力のある役人と人的関係の基礎を作ることができなかった。これはスペインで起こったのとはまったく逆のことだった。
おそらくこれが主な相違点だった。ポルトガルで日本人は全ての重要な仕事を行う任務を引き受けたが、スペインではその上にスパイ活動のために地域的メンバーを巻き込んだ。これらの母語話者は政治的便宜のおかげで、ある種の責任を負うことになった。
4.1.1.日本の諜報部とスペイン人
日本はスペインが提示した手段を活かそうと計画したが折りには、ドイツの仲介と役人とをあてにすることができたし、またスペイン人にも日本人を助けるのに協力のする準備があった。その中心人物の一人として、高い地位から日本人を援助した者がいた:ラモン・セラノ・スニェルである。
政治的・個人的利益の組み合わせが、外務大臣が他の枢軸国リーダーが及ばなかった域でまで日本との協力を受けいれた理由のようだ。一方で彼は枢軸国の勝利のため完全に巻き添えになっていたので、以前にドイツやイタリアが行ったように、情報部を通じて日本の戦力を支えるのは普通のことだった。その上、当時使用されていた用語でいえば北米の金権政治に対する戦いは、確かに、最も差し迫ったものではなかったにせよ、ファランヘ党の目的に含まれていた。日本を援助するのは同じ敵を前に協力することを意味した。他方、セラノ・スニェルにとっては、もう他に残された守るべき政治的選択肢はなかったのだ。フランコは自分で常に政治的かけひきから一定の距離を保ち、異なった選択肢を持ち続けるすべを知っていたが、「娘婿」は政治的範囲の末端に隔離された、そこではただ枢軸国の勝利にのみ彼の政治的生命を保つ可能性がのこっていた。しかしセラノはそこでもすべての解決策を手に入れたわけではなかった。既に見たように彼とドイツとの関係は親密というには程遠かったのだ。
そのような政治的・個人的重圧のため、セラノは自身を日本人のために役立たせようとしただけではなく、自分の指導下にある外務省の機能や影響力を使い、組織としてのファランヘ党の機能をも使おうとした。しかしその緊急の必要性と開かれた裁量からは、日本への援助は、個人的な動機と保守派との内部抗争に生かすため決定されたのがわかる;セラノは軍との対峙のために権力を有する必要があった。スペインで日本人にとっての不可欠な存在となることは、スパイ活動同様、セラノの目的の手助けをした。それでも、その政治闘争では、日本の仲介を通じて得られる情報はごく基本的なものであったろう。単に敵対者にとって有害なニュースを知るというだけではなく、日本の勝利に関してもっとよく知ることで、真珠湾攻撃後に、太平洋の戦場に関する情報を得ようと各大使を調べて以降セラノが求めていた主張に有利な論点を与えたにちがいない。1940年代においては、知ることは力であったのだ。
太平洋戦争勃発後、最初のセラノの決断は、シンプルなものであった:大使館の情報を渡すことである。結果として、外務省執務室の長であり国外の出版物に出るニュースの検閲官ヒメネス・デ・サンドバルに命じ、ワシントン・ロンドン・リオデジャネイロ・ブエノスアイレスから受け取った外交公文書を日本の公使館へ送るように命じた。よってこのようにして東京に送られた情報を「スニェル諜報」という。須磨外相は、そのような協力姿勢を前に一歩進めて、在ロンドンや在ワシントンのスペイン大使館づきの外交官が秘密裏に情報を得ることができるかどうかと尋ねた。既に派遣済みの外交官が秘密裏に協力するのは困難かもしれないので、セラノに、スパイ網をつくるために日本を手助けしてくれるかと尋ねた。セラノは表向き疑念なく応じた。その結果として、公使館がセラノと電信で連絡をとる時には彼個人の番号をつかうように、また郵送での報告は、郵便小包として彼自身に当てた私信として送るように、また関係者が短波の送受信に起こりうる問題を無視すること、そして最後に参加する要人にはスペインのパスポートが送られること、が決められた。
セラノの指示を守るべく、セラノが全信頼を置いた2人の人物、ヒメネス・デ・サンドバルとアンヘル・アルカサル・デ・ベラスコがいた。ヒメネス・デ・サンドバルはスパイ活動において日本と協力する作業にはあまり長い時間は関わらなかった、というのも1942年3月には、不可解な事件がきっかけとなって辞任しているからである。外務省文書館に残っている、外務省執務室の長だった間もほとんど空のファイルは、ある時期にはそれが書類であふれていたことを示している。アルカサル・デ・ベラスコは、セラノの旧友であり心酔者で、最近「自主的賞賛」本を出版したのであるが、『ファランヘ党におけるセラノ・スニェル』という書籍にあるホアン・マリア・トマスの言葉を借りれば、セラノこそホセ・アントニオの本当の後継者であるといっていた人物である。
アルカサル・デ・ベラスコには急進的ファランヘ主義における長い政治的履歴があり、諜報活動の分野でも新参者ではなかった。フランコに権力を与えるに至った1937年のサラマンカ事件では、ファランヘ党の急進派リーダーだったマヌエル・エンディーリャ支持者のうちの一人で、よってその反乱後に死刑を宣告された12名のうちの一人でもあった。アルカサル・デ・ベラスコはまず減刑された後、受刑中のパンプロナの監獄で共和国軍側投獄者の大量逃亡を失敗させた褒美として、刑を免れた人物である。監獄から出ると、アルカサルはマヤルデ伯に見出されてドイツ情報部で訓練を受けた後、諜報活動に入った。ドイツ情報部とは、1935年からヴィルヘルム・カナリスが率いる軍諜報機関であり、そのマドリード事務局は戦争組織だった。回想録でアルカサル・デ・ベラスコはアストゥリアス革命にまで自分のスパイ活動を遡っているが、彼の最初の具体的活動は1940年のことであった。そのときにはカール・エリッヒ・クーレンタールとフリッツ・カナップの教導を受けた後、当時ナチズムの信奉者で、ドイツ勝利の暁にはイギリスの王位候補者となるウィンザー公をポルトガルで暗殺しようとした試みを撹乱させる手助けをした。
その後、1941年2月には、アンヘル・アルカサル・デ・ベラスコは彼の諜報部員としてのキャリアの中で最も重要な成功のうちのひとつを収めた。イギリス大使館がロンドンでの記者団補佐官として彼の任命を支持したのだ。イギリス大使ホールはその回想録で、スペインにおけるイギリスの情報部チーフ、バーナード・マレイはアルカサルの任命を支持することで最も重い過ちを犯したと述べている。アルカサルの名前こそ出してはいないが、マレイはこうしてイギリスに、フランコに対する根本的選択肢をもつ利点について考えさせた。アルカサルの成功は、明らかに、彼の敵対者が犯した過ちと結びついていた。ロンドンに到着するとアルカサルは、ドイツのためにスパイ活動をしてくれる人物を探した。その間、イギリス外務省の役人は、マドリードのホールの勧めにしたがって、その奇妙な確信を評価するのに精を出した。「私たちは注意深くスペインの帝国主義と立ち向かわねばならない」というのが、アルカサルと知り合いになった後のイギリス外務省での最初のコメントのうちの1つであった。しかしすぐに恐怖から全員一致で拒否の態度をとるようになり、彼のことを「最もたちの悪い蛇」と評するようにさえなった。その結果、イギリス外務省では、ホールに自分の過ちを気づかせるだけでなく、1941年4月に国内の対抗諜報部であるMI-5に、アルカサルの活動に目を配るように情報を流した。
このように、アルカサル・デ・ベラスコは、主要目的の達成を難しくさせる数々の無分別な行動をとった。彼に求められた報道関係の活動は、フランス語でも英語でも、話すことも読むこともできないので、ほとんど行われないままだった。同国人からも油断のならないやつと不評だった。しかしながら、アルカサルはこの任務で相対的に成功し、スパイ網をつくり、機能させるのに協力した。このスパイ網は、想像するに、イギリスの政治状況とドイツによる爆撃の被害についてベルリンに情報を流すためのものであった。しかし戦後のアメリカの報告書によればスパイ網は日本のために作られ、その情報は、追加の支払いがあるときにだけ、外交用郵便でドイツ諜報部へ送られた。スペインへ2度出向いた後に、アルカサルは太平洋戦争が始まる少し前におそらく最後の失敗を犯した。なぜならば、自分がワシントンでの外交官ポストに送りこまれると予告したからである。結果として、イギリスは、同盟国にそのことを知らせ、おそらくこの情報のおかげで、アルカサルのビザは下りなかった。アルカサルはロンドンからアメリカへわたる代わりに、ラ・マンチャ海峡を渡るはめになり、マドリードでその旅を終えた。1942年1月にロンドンでの役職を解かれたとき、彼はマドリードにいた。アルカサルは、職業上の隠語を使っていうなら、もうだめであった。アルカサルにプロ意識が欠けていたことがわかったのでそうなったのだといえる。しかしそうであっても、マドリードに場所を移して、まだアメリカにとっての危険は続いていた。セラノ・スニェルは信頼のおける人物に事欠いていたのであった。
マドリードへ戻った後、アルカサルは日本人のために働き始めた。戦後の報告書によると、日本人に協力話を持ちかけたのは1942年1月のことで、日本人はその情報に支払いをすることを受け入れた。諜報活動システムへこのようにすばやく入り込んだのは、主に3つの理由によった:前年の8月から、既にアルカサルと三浦文雄は知り合いだった。三浦は、スパイ網の実践的仕事にたずさわり、アルカサルに金を支払ったに違いない;東京は情報を得る必要に迫られていたし、セラノがアルカサルを推薦したからであった。セラノは日本にとって非常に便利な情報網の活用を申し出た:日本は必要機材と経費とを受け持つ一方、スペインはその他のことを担当するというものであった。そうしてアルカサルは初めて、1月2日にミゲル・アンヘル通りとガルシア・デ・パレデス通りの角にあった公使館へ極秘報告書を提出するために出向き、須磨とレストラン、ラ・バラッカで昼食をとった後、8日には既に暫定的に受け入れられていた。その日、公使館は東京へアルカサルがこれはフランコとセラノが読んだだけであるといって手渡した、21人からなるスパイ網のもたらしたイギリスに関する報告書を送った。その情報は独自の「トウ(東)」という見出しがついていた。
日本人は当然、諜報部員を急いで見つけようとしていた。特に、アメリカでの日本独自のスパイ網が解体され、ドイツの諜報部が弱い中では、日本は必死に情報を収集する必要があった。よって、後で見るが、他の国々がスペインの提案を上回るものを出すのは不可能だった。スペインはラテンアメリカ地域で力をもっていたし、また情報を得るのに日本の利益を代表していく友好的政策に基づき、橋渡し役を務められたからである。日本にはほとんど選択肢はなかった。だから、直ぐにアルカサル・デ・ベラスコがもたらした情報を受け入れなくてはならず、その情報には、表意文字つまり漢字を使って、あまり慎重とはいえない「東」という名を当てたのだった。
既に始動していた諜報網を通じて示されたその経験と、おそらく相互的なものではあっても、彼に情報を提供していたであろう、ドイツとのつながりによって、アルカサルは、セラノが推薦した最も適切なエージェントと見なされた。三浦と須磨は、この確信犯的ファランヘ党員が提案しえた可能性を見極めるのにそう長くはかからなかった。1941年1月8日、最初のメッセージを送り、報告書から情報を拾い集める以上の計画を実践することの是非について問い合わせた。彼らの考えにあったのはイギリスにある情報網からの情報を使うことであった、そしてまた、アメリカで探し求めたようなスパイ機関をスペインで組織することであった。そのためにセラノは、スペイン外務省が経費の一部を支払うとして協力を申し出たし、その一方で盟友のアルカサルがマドリードに残れることが条件でもあった。それは理想的計画のようだった。それは必要性を完全に満たし、日本はすぐに諜報活動を改善するための作戦費用として、多額の金銭を渡すことを承認した。
このようにして、日本は、スペインにおける諜報活動の土台を広げながら、どうすればその情報網をもっと拡大できるかを考えた。だから、アルカサルが渡した情報には、音は似ているが意味はもっと無症候性の、東方を意味する別の漢字があてられた。この命名は成功だった、というのもほかのスパイがもたらした情報は基本方位に基づいていたからである:北(ポルトガル方面からもたらされる情報)、南(在マドリードイタリア大使によるもの)、西(コンスタンチノープルの領事から送られてくるもの)、そしてある情報が尽きて、新しい資料を名づける折も、同じ名称を使い続けていた。このような名称が終わっても、名前の地理的関連付けは続き、ポルトガル大使からの機密報告は、例えば、富士として知られていた。一方、スペイン大使の連絡を含む「スニェル諜報部」は、音節的なアルファベットのひとつであるカタカナ「ス」で短縮表記された。これらの全情報の中で、際立って最も重要で複雑な仕事は、アメリカにおける諜報網を軌道に乗せることだったにちがいない。それは東機関と呼ばれるようになった。アルカサルが準備した情報とそれとは全体的に混同され、東機関と呼ばれるようになった。FBIは東機関を「スペ―日」と呼んだが、それは、東機関の活動を熟知していたことを示す。このことに関しては、次の節で見ていくことにする。
4.1.2. アメリカ合衆国における諜報網
東機関は、他の手段では情報を得ることができない日本の利益を追求したことから生まれた。日本はアメリカと対立しており、一度日本人の共同体が西海岸から強制的に追い払われ、強制収用所に住むことを強いられると、日本が手にする情報は以前の情報網が壊された後、最小のレベルに落ち込んでいた。日本はその主たる敵国に関するできる限り多くの情報を必要としていた。その証明としては、マドリード公使館が最初にそれを提案した折の東京からの回答があげられる。情報の穴を埋めるのは重要な問題であった、その諜報機関が得なくてはならない目標から考えると、イギリスを含めて他のヨーロッパ諸国について日本が求めた情報よりずっと具体的な目標を定めなくてはならなかった。軍備に関しては、日本の高位の軍人たちはハワイで被害を受けた戦艦の修理状況や戦艦や潜水艦造船の建造に関する統計を知りたがり、また戦前は南太平洋に依拠していた戦略物資の輸入問題をどのように解決しているのか、またその生産能力を測りたがった。アメリカの軍事力に関しては、戦艦の動向や、太平洋への軍輸送の状況を知りたがるいっぽうで、また戦闘での前線の復旧状態も気に懸かけていた。スペインやアフリカに攻撃があった場合、その防衛力はどのくらい影響をうけるかと尋ねてもいた。宣伝活動の分野では、日本はルーズベルト大統領を失脚させる可能性を知りたがり、アメリカが抱える人種問題やインフレについての情報を得ようとし、例えばオーストラリアや南アメリカなどのケースに言及して、アメリカとその他地域との関係についてもっとデータを集めるように求めた。最後に、軍の領域に入る質問には、宣伝目標もあった:軍隊がどのような民族で構成されているかを知りたがった。
想像するに、目的を限定して、諜報網を動かし始めるのが、アメリカ大陸で越えるのが最も難しい障害であった。この様相について、データをそろえるのが一番大変だった。そのためアルカサルは、一度も言及されたことのないある人物の協力を仰がねばならなかった。彼は、いつも、メキシコから一緒に入国したロヘリオというスパイの存在だけは話したが、彼についてはそれ以上知らされることはなかった。アルカサルがアメリカ大陸へ渡っていたことはその上、否定はされていないが、証明されてもいない。アルカサルが自分で認めるように、おそらく潜水艦で海を渡ったのであろうが、セラノの希望はアルカサルがマドリードに留まることであったし、また継続的にスペインにいたことや英語での自己表現が得意ではなかったことは、アルカサルのアメリカ滞在に疑念をもたらす。とにかく、アルカサルはアメリカ合衆国に在住する主な接触者をもつこと必要としていたのだ。
ファランヘ党はイデオロギー的動機によって、またワシントンのスペイン大使館は下部構造の必要性から、諜報網を軌道に乗せるため最初は援助をおこなった。アメリカでの諜報網づくりでアルカサルが初めに接触したのが誰であったかはわからない。しかしそれをセラノ・スニェルが明確に承認していたことを考えれば、国外ファランヘ党と関係していた可能性はかなり高い。エドゥアルド・ゴンサレス・カリェハによれば、ファランヘ党には、「地下活動の核」があり、1938年にアレハンドロ・ビリャヌエバによる旅をもとに創設されてから、ニューヨーク・サンフランシスコ・ホウストン・フィラデルフィア・バルチモア、そしてその他の港湾都市に広がっていた。このグループからは2人の名前がでている。ニューヨークとワシントンにおけるファランヘ党の長として、ホセ・デ・ペリグナットはメキシコからスパイが入国するのを助けたようである。またホセ・マルティネス大尉は、ファランヘ党のサンフランシスコでの活動的なスパイであった。
在アメリカのスペインの外交団の中に、アルカサルはスパイ網に関して、送られてくる外交文書や秘密文書を受け取り、諜報部員の動きを手助けする彼を助けてくれる人物を求めていた。それは必要な連鎖の一環ではあったが、候補がいろいろいたため、再び疑念が起こった。派遣されていた外交官のうち2名は日本に住んだこともあり、おそらく個人的つながりももっていた:王党派の古くからのメンバーである、フアン・フランシスコ・デ・カルデナス大使自身、そして内戦勃発時に東京に在住していたエリオ・フアン・ゴメス・デ・モリナ参事官である。彼らの外に、アメリカは特に2人の人物について疑っていた。その一人、大使館の農業参事官で、以前に宣伝参事官を務めたミゲル・デ・エチェガライは、国外のファランヘ党の活動メンバーといわれていたが、大戦が始まる少し前にサンフランシスコへホセ・マルティネスに会いに行っていた。また大使館づきのマヌエル・デ・ラ・シエラ空軍大佐は、ワシントン側からの提案で、1942年6月に予備役となった。
半島から送られたスパイたちについては、後に述べることにしよう。しかし、ここで知っておくべきなのは、スパイのうちの幾人かは戦争開始以前にアメリカ合衆国へむけて出発していたであろうということだ。アメリカの対抗スパイ活動は1942年1月に3人のスパイが既にニューヨーク・ワシントン・サンフランシスコに身を置いていると考えたが、おそらくセラノ・スニェル自身が、同月送り込んだ3人からまだ重要な知らせは受け取っていないと認めたことに基づいてのことである。
スペインが立てた計画は、その上、野心的なものだった。セラノ・スニェルは日本の諜報活動に便宜を図って、外務省を使う許可をだそうとしており、情報獲得に従事するよう、新しく4名を外交官パスポートでアメリカに送り込む計画を立てた。4人のうちの1人はサンフランシスコの領事館に、1人はニューヨークのスペイン情報図書館へ、一人はセネガルのダカールへ、また最後の1人はマッカーサー元帥の将来の総司令部が置かれるオーストラリアへ行かねばならなかった。この貪欲な構図はルイス・カルボ事件が引き金となって失敗した。事件がこう呼ばれるのは、ロンドンにおけるアルカサルの後継者、出版物担当官であったルイス・カルボの外交用郵便を使った秘密活動がイギリスの諜報部に見つかったことによる。これはセラノ・スニェルの行った枢軸国のための秘密活動にとっては重大な失策となった、というのも、情報自体はさほど機密性の高いものではなかったのだが、出版物担当官の逮捕とその後の証言によってその活動が明らかになってしまったからである。にもかかわらずセラノは、秘密の暗号と公使館の下部組織の使用を許可し続けたが、機密性を高める必要性を避けることはできなかった。また、他の国々がスペインの外交官として任命する経験のない人物全てにあからさまな不信を抱くのを妨げることもできなかった。アメリカはその諜報局を通じてそれに気付いていただけでなく、アメリカ合衆国に送り込むスパイを獲得する場になっているとしてスペインにおける日本公使館を非難する記事を新聞に載せて、スペインに圧力をかけた。以前は公然の秘密であったものが、世論の標的となった。1942年2月から日本人が強制収容所に移されたことによって、計画は困難になった。予定された日本寄りの外交官を派遣する考えは失敗した。
それは重大な失策であった、その後4人の将来の「外交官」はやらずにすんだサービスに対する贈り物を受け取ったのち、解雇された。アルカサルは、実際、当時弱い鎖につながれていた、しかし最終的には、ドイツ人がスポンサーとなったイギリスにある諜報網からの報告書を受け取り続けるために残留した。東機関のアメリカ合衆国での展開は、様々な面でルイス・カルボ事件の影響を受けていた:外交団に新しい人物を入れることが不可能になった、作戦開始の遅延、財政面でのセラノの約束不履行、などである。日本は約束していたのより多く金を支払わねばならなかった。その上、セラノの立場は、日本との協力という彼がとったあまりに異常な裁量によってますます弱くなっていった。いわゆる「セラノ諜報部」が1942年1月20日まで、つまり明らかにセラノの親日政策は危機にあってその反対派によってつぶされるまでしか続かなかったことでもわかる。しかしアメリカ合衆国での諜報網は存続した。日本はその諜報網を必要としていたのだ、必死に。
もっとも重大な技術的・組織的な問題は、アメリカ大陸とマドリードの間でメッセージをどうやって伝えるかということであった。例えば各スパイのもつ手段と情報のタイプをうまく適合させ、危険を分散させるためにも、補完として使われたはずの様々な方法についてのいろいろな報告がある。アルカサル・デ・ベラスコは後年、メッセージは普通メキシコへ送られ、そこから短波でカリブ海に停泊しているスペイン船に送信された後、マドリードへ送られていたと認めた。そのような説明からは、スパイ活動が洗練された非常に高いレベルであったことがわかるし、また三浦義秋の活動に支えられていたにちがいないこともわかる(マドリードにあてがわれた外交官との関係はなかった)。三浦は表向き、1941年夏に準備のためにメキシコへ派遣され、イギリスの諜報網が表向き機能していたことで、情報を送るのには持ち運び可能な打電器が使われた。しかしこの方法は、よくいったところでアメリカからイベリア半島へ送られた情報が通るひとつの道でしかなかった。その理由としては、アルカサルは往来についてなんの言及もしていないことが挙げられる。
そういった進んだ説明を拒否することはできないにせよ、例えば、少なくとも補助的に使うよう外務省が手を回してくれたものやイギリスでのスパイ活動のモデルに沿って、スペイン人スパイは秘密情報を流すのにもっとありふれた方法を用いた、と考えたほうがよいようだ。確かにアルカサルはいつもそのことを話すのを避けてきたが、ルイス・カルボ事件後の失望したスパイたちとの計画は、例えば、公使館に設置された打電器で連絡がとられたので、スパイ自身で暗号の開発や人物の選択に力を尽くさなければならなかった。アメリカの対抗諜報活動は、情報がワシントンのスペイン大使館から電信のオフィスを通じて送られたことや、また船舶についての情報はニューヨークの領事館から送られたことをつきとめた。一方FBIは、スペイン大使館がブエノスアイレスへケーブルを通じて情報を送り、その情報はマドリードそしてベルリンへと伝わったであろうことを明らかにした。このブエノスアイレスの果たした役割から、チリやアルゼンチンなど南米の中立国も枢軸国の情報収集に重要な機能を果たしたことがわかる。そしてその役割は戦争が進み、それらの国々が中立を捨てた後も大きくなっていった。しかし、確かにアルカサルは認めてはいるが、これが彼を通じて行われたものだと証明するものはない。また、ジャーナリストに関していえば、もっと簡単で使いやすい手段を使った。たとえば、疑いを招かないような住所に送られた手紙に使われた目に見えないインクの使用や、三ヶ月ごとに変えられた新聞に送られたメッセージの中の暗号の使用などがそれにあたる。
情報を受け取るには、このような方法がより簡単だった。そしてスペインにおける情報網機能のためにアルカサルがやとった人の給与からは、彼らが最もよく用いられたことを推察できる。そうして、情報網の機能を補助するために、アルカサルを助けたのは、彼の妻のほかに、フランシスコ・アギレラ(もしくはエスコバル)という運転手を務めた人物や、アルカサル・デ・サン・フアン生まれの印刷工であり、安全を期して消えるインクを使って書かれたアメリカ合衆国からのメッセージ(主にワシントン周辺の消印のもの)のあて先になったアルトゥロ・カステリャノスなどだった。
マドリードに着くと、情報は様々な機関に配布された、しかし、そのテーマによっては配布先の数は変わったかもしれない。はじめのうち、アルカサルは、日本にメッセージのコピーを渡すとともに、セラノ・スニェルにも手渡しでコピーを渡していたようだ。しかし須磨は1942年6月に、何度も東からの報告書についてセラノにコメントしたがセラノは何も知らなかったと通告した。須磨は、スペイン側からアルカサルは時によっては報告書を渡さなかった、というのも手渡ししなくてはならなかったので、外務大臣の日程のせいでそれができなかった、との説明を受けた。しかし、そのような理解は全面的に正しいわけではない、特に、実際あったようだが、アルカサルはいくつかの情報を勝手に捏造していたからである。セラノは、時に日本人を欺くことを楽しみ、「日本人たちの目が利かない度合いは大きい。」とコメントもしているが、盟友アルカサルの捏造ではなく、真実の情報にだけ興味があったにちがいない。
その上誰がどのような範囲で東機関の情報を受け取ったかを知るのは困難である。そうしてはならないという指示があったにもかかわらず、ドイツや日本が支払った情報は別の人間の手に渡っていた。アルカサルの情報の大部分は、ドイツ大使には送られなかったものの、ドイツ情報部のドイツ特殊事項事務局に送られた。同様にして、日本はイギリスの情報を受け取っていた。双方とも当然、これはアルカサルの特別の厚意によるものだと考えていた。第三国への情報のリークは、政治的というより個人的な意味での、諜報網の長自身の決定によった。だから、最終的な様相、諜報網を機能させる鍵を握るのは、スポンサーによるものである。
日本は、日本軍の示した数値が正しいとすれば、戦費の約1%を諜報活動に使った。その上、増加する予算の中でその重要性を維持し、戦争が最終的な段階に入っても、諜報活動費を増やした。唯一存在する資料によれば、陸軍の諜報活動は、全体と比較してその費用割合は相対的に安定していたが、1941年の0,36%と1942年の0,26%という数値の間を維持し、0,48%になった戦争の最後の年を除いて、平均0,33%であった。しかし全体的な数値は、1941年と1942年の4200万円-4600万円から、1億2500万円-4億円へと、最後の2年で10倍に膨れ上がった。資金が予算に組み込まれた後には、日本からスペインへ、その一部を、疑いを招かないようにアメリカ合衆国で換金してから、確実な方法で送金するのはもっと複雑なことだった。開戦以前から、各省庁はこのような目的に使うために、ヨーロッパの銀行口座に充分な資金を蓄えてあった。スペインの場合は、須磨大使は国庫とドイツ帝国銀行から金を引き出した;大石むねつぐ海軍担当官は、ドイツ帝国銀行とリスボン・アソレス銀行の口座から引き出し、桜井敬三陸軍担当官は、チューリヒの連邦銀行から引き出した。
銀行の支店は必要な資金の一部を供給しえたに過ぎなかった。諜報活動の支払いには他の方法を使うことが肝心であった。最もよく使われた方法は、後の売却のことも考えて、真珠を送ることであった。紙幣の価値がどうなるか予見できず、公正とはいえない方法で多くの財産が築かれる中では、真珠は持ち運びも難しいことはなかったし、またヨーロッパでは非常に高い値をつけるものだった。重大な失敗が2つあったのがわかっている。
初めのものは、特に面倒だった。太平洋戦争中に東京からマドリードへ送られた唯一の外交郵便袋に入れて、1万円の価値のあるミキモト真珠がリスボンにいる安藤という名の公務員に当てて送られた。本件は、ミキモトへは送付を隠されており、スペイン人には公式事項であるとされて、トップシークレットとして扱われたのだが、この悪い目論見は失敗した。真珠はあて先の住所には着かず、バーミューダ島で差し押さえられたのだった。もっとも不名誉だったのは、ある新聞がドイツへの輸送中に捕らえられた日本の真珠に関する売却を載せた後に、それはワシントンのスペイン大使館へ引き渡されたのだった。それは、日本人に自分たちの手段を自由に使うままにさせておくことが、どんな問題を生むのかを立証することになった。別の真珠の送付としては、1942年9月に横浜から出された封鎖潜入船でのものだった。ラコティス(Rhakotis)号は、ボルドー近く、ビスカヤ湾で発見されたが、敵の手に落ちる前に沈められることを好んだ。とにかく、戦争末期には、公使館とその外交官が余剰金をもっていた事実からもわかるように、きちんと到着した送金もあった。
スパイ活動のためにどれくらいの金額がどのようにしてアメリカへ送金されたかはよく知られていない。ワシントンはスペイン人の銀行口座の金銭取引にあやしい動きがないかどうか、毎月ごとにその明細を調べ、また時にはフアン・ゴメス・デ・モリナに質問したように、あやしい動きがあったときにも、チェックしていた。日本は宣戦布告がされた時に、ワシントンの大使館の金庫に保管してあった約50万ドルを使おうとした、というのもスペインは、アメリカにおける日本人の権益を代表する役割を担っていたので、暗証番号さえわかれば、スペイン人が金庫を開けることは可能だったのだ。それは複雑な問題だった、なぜならば資金はスパイ活動もそうであるが、日本人の権益を代表するためにも必要となりうるものであったからである。法規則に従って、日本政府にそれをどのように使うべきかたずね、後に報告すべきであることになってはいた。そうして東京からマドリードに暗証番号は送られたのだが、金庫は決して開けられるには至らなかった。須磨は初めのうち、誰か公務員が旅行するのを待つつもりだった、なぜならば外交文書袋も自分たちの電信も信じられなかったからだ、だから資金の使用を遅らせたのだった。
日本側がそのことを質問しても、須磨は、誰もまだ旅しておらず、よって金庫を開ける確実な機会がないとコメントした。しかしこれは真実ではなかった、なぜなら須磨自身がマドリードでカルデナス大使と会談していたのだ。だから、スペインがミキモト真珠をいきなり渡された一件がもとで、そのことに協力するのを止めたがっていた、というのがありそうなことだ。この資金については本書では後ほど、再び言及することにする。
スペインでの日本のスパイ活動費用総額を知るのは難しいが、公使館の当初の予算は50万ドルとなっていた。この額では不十分であったので外務省は1943年に陸・海軍に費用を捻出するための援助を求めた。しかし、海軍だけがそれを認めた。この他、残りの情報は部分的なものであるが、ここで指摘しておくのが望ましいのだ、というのも、いつでもこのスペインと日本の関係における様相を知るのは困難であるが、この情報は、スパイ機能に関する決定的なデータを示唆するものだからだ。例えば、アルカサルが1942年8月に日本円にして約40万円を請求したことがわかっている、それは諜報網のためのものであり(公的レートでいうと120万ペセタである;うち10万円はミキモト真珠の売却で埋め合わされたのであろう)、また月300ドル(レートで約3600ペセタ)をアメリカにいる諜報部員に渡そうとするものだった。一方当時、イギリスにいる諜報部員はドイツから月800ペセタ、その地域のヘッドには2000ペセタを受けとっていた。また、タンジールにおける海軍のスパイ網の月額費用は約3000ペセタだった。このことから、アメリカの情報網は最小限マドリードにあった全体資金の半分を使い、また日本から支払いを受けていたスパイはドイツから支払いを受けていた者よりも多く稼いでいたことがわかる。しかし、枢軸国だけが諜報活動に資金を費やしていたわけではなかった;連合国側も同様で、またそれはもっと「知的な」形態で行われた。なぜならば、対抗諜報活動のおかげで、敵の財源を自分たちに有利になるように使用したからである。
4.1.3.アメリカ合衆国対抗諜報活動
対抗諜報活動とは、安全保障・対抗スパイ活動という手段を使い、敵の情報を錯綜させることを意味する。つまり、外国のスパイをとらえるか無力化して、彼らが秘密情報を得てそれを伝達するのを妨害する秘密行動のことである。諜報活動の4つの要素としては、データ回収・分析・隠蔽行動・対抗スパイ活動があるが、この節では対抗スパイ活動を扱う。しかしその様相は、「知識」という名が示すのと同じように、非常に広い意味を含んでいる;他国によって引き起こされる知識情報に対する被害に従って様々なレベルの情報を分類することから、情報を収集するために敵のスパイの仕事の熟達度を妨害するように安全保障の方策をとることまでを示す。これらの方策は、反対に、情報へのアクセスが妨げられる時には受身のものとなるし、また敵の諜報活動がどのように機能しているかを調べ、その活動を頓挫させ、それが最終的に自らの利益となるようにしむけようとする、という時には積極的なものとなる。いわゆる「対抗諜報活動」、つまり敵のスパイ活動を知ろうとすることは、非常に多くの活動を意味する。たとえば常に監視を行ったり、敵を説得して転向させ、あわよくば敵の諜報活動の中で働く二重スパイにすること、つまり敵国の諜報活動をするふりをしながら、実際は表向きスパイ活動をしている国側のコントロール下にあるスパイをつくること、などである。
戦争のこの段階だと、連合国は敗北が続いた初めの頃とは比較にならないほど大規模な勝利を遂げていた。そうして、大戦中に敵国組織の活動を監視する中での最も大きな成功は、イギリス人が「ダブル・クロス・システム」で獲得したものであり、これによってイギリスは領土内におけるドイツの諜報システムをコントロールすることができたのだった。帰国の旅にでたあるドイツ人スパイを逮捕した後、イギリスは非常に広範なスパイ網を構築するにいたった、そしてそのスパイたちは、ナチス高官を欺くのみならず、新しいスパイを開拓し、ドイツ諜報部の責任者やその方法についての情報を収集し、また敵国ドイツの将来の試みを明らかに読み取ることのできる暗号や秘密の数値を得た。
アルカサルの活動はこのイギリスの優位に影響を受けていた。彼の活動で、イギリス滞在中、なぜ逮捕されなかったかわかるというものだ。アルカサルが使っていたスパイがもたらす情報はなんらかの方法でイギリスによってコントロールされていたにちがいない。1941年12月、マドリードへ戻ってすぐ、彼は日記を盗まれた後に、それは嘘で、主にドイツから資金を引き出すのに用いられていたことが分かる。時間はかかったが、キム・フィルビイが書いていることによれば、「1・2週間の困難な仕事」であった。また、イギリスはアルカサルがスペインへ戻るまで、「アルビオンの不実」における彼の活動の虚偽を知らなかったとすれば、このデータは、戦後アメリカ人が語っているように、アルカサルが最初から日本人のために働いていたことを物語っているであろうし、もしくはこの「ダブル・クロス・システム」の成功は言われるほど完全なものではなかった、ということでもあろう。なんにせよ、アルカサルの日記は、ルイス・カルボ事件を引き起こしたとき、イギリスが安全な道をいくのを助けた。つまり、それはコントロールしていなかったドイツ向きの通信方法のひとつ、スペインの外交文書専用袋という方法を阻む、入念に準備された決定であったようである。この袋を介して、スペイン補佐官アルカサルは、指示の他、ドイツ中央銀行によって鋳造されたにせものだと確定できない貨幣を受け取っていたのだった。
連合国側の組織化された対抗諜報活動の成功はまた、アメリカ合衆国で情報を得ようとするスペインの目論見を害するものだった。アメリカにはアルカサル・デ・ベラスコという人物がもつ危険性についてのニュースが伝わっていたからである。アメリカ人は、警戒して、このスペインのファランヘ党員に外交官ビザを発給しなかったのみならず、彼に対するスパイ活動をも準備した。1942年2月、FBIはアルカサル・デ・ベラスコに関する情報を国務省に要求し、その後、1942年3月10日に開かれたFBI高官の会議で、スペイン人たちに対して最大級の警戒を行うとした。その処置には、外交文書専用袋で送られるスペインの公的書翰を定期的にコントロールすることも含まれていた。この方法は、確かに法律上の越権行為ではあるが、他の中立国にも適用された。アメリカの領土内でできる限り多くのスペインのスパイを捕える目的で、全ての方法で、つまり通常のやり方から最も進んだ方法・卓越した技術までを用いて、彼らスパイの努力を妨害する方策が求められた。
連合国側対抗諜報活動はスパイ活動の中で最も有効な武器をあてにできた:それはメッセージの傍受である。二重スパイや問題を起こして逃げたものとは反対に、中央情報部と海外支部の間で送られた内部極秘メッセージの解読は、(だまされないように)敵の意図をよく知るための最も信頼の置ける証拠のひとつである。
事実、そのメッセージが電信を通じた伝達、書面による伝達、また特にラジオ放送でのメッセージ、など、様々な形態をとっていても、メッセージの傍受は、第二次世界大戦における運命をわける様相であった。それは何も新しいことではなかった。全ての諜報部や海外代表団は、暗号で書かれたメッセージや進んだ技術を取り入れた機器を使うことで、敵が相互に伝達している命令や情報を知ることができないように、常にセキュリティに気を使わねばならなかった。アメリカの参戦は、実際のところ、ドイツへのメッセージを解読したことがもととなった。ラジオ放送のメッセージは誰でも聞けるので、その解読を防ぐには暗号を使うしかなかった。よって、文字の順序を変えたり、テキストにある文字を他の文字・数値・シンボル等に置き換えたり、この二つを組み合わせて使う、などした。だから、最も決定的な技術競争のひとつは、その他の人々が、メッセージが周波に送られた数値のリストと整合的なテキストを取り出すことができないようにし、敵の公式声明に対して、自分たちの利益になるように同じ事ができるシステムを開発するというものだった。他の多くのケースにみられるように、この戦争の見込みと戦闘自体もが、以前は想像するだけだったレベルまで到達する技術の革新を後押しした。メッセージの解読は、後衛が実践する、最も重要で必要な仕事のひとつであった。皆がそれを熱望し、何かを得て、またあるときには最も大切な秘密を発見しているように感じた。
これは連合国が枢軸国に再び勝った面であった。イギリスもアメリカも敵国の通信を解読することができた、しかし他の国々では、そこまでは技術は進んでいなかった。この明らかな敗北の理由はたくさんある、しかし、具体的な知能や人的開発能力よりも、お互いの科学的進歩に対する態度を深めることに関して、ヨーロッパの現場に目を留めるのがよい。戦争開始の数年から、枢軸国と連合国とでは、新しい技術がもたらすものに対する見解があまりにかけ離れていたことを証明することができる。空爆でドイツは敵の目標物を破壊するためにより伝統的な手段を使ったが、イギリスは、例えば、「作戦研究」に時間を割いた、例えばどうすればバッテリーをまとめることができるか、もっとよい結果をだすには銃弾を撃つ頻度をどうすればいいか、飛行機をカムフラージュするために最もいい色はどれか、危険地帯を通るときには運搬車の大きさはどれくらいがちょうどよいか、などについてである。一方が主に量的な進歩に勝因を求め、(爆弾投下の場合は、過剰なまでに)もう一方はもっと長いスパンで考え、戦闘でついやされたお金をできるかぎりうまく使うことを追求した。
長い面でみて、違いは運命をわけるものとなった。それは戦争の戦術と一致していた。枢軸国は直ぐに勝利することを望んでいた。それだからこそドイツもイタリアも、長期間にわたる計画を立てても役に立たないと判断し、戦争の状況がもう後戻りできないところに来るまで自分たちの間違いに気づかなかった。しかしこの過ちは説明可能であるが、技術発展に関する主要な問題点は、ヒトラーやムソリーニにあれほどまでに絶対的な形で決定プロセスが集中していることだった。総統の意見は不可欠なものだった、例えば、ドイツが原爆を製造しなかったのは、そのような種類の武器に対するヒトラーの個人的な不信が乗り越えられるまで、ナチス・ドイツは必要な処置をとらなかったからだ。この技術競争(そして他にもたくさんあるが)でヒトラーを敗北に追いやったのは、彼の反ユダヤへの狂信だけではなく、独裁システム全体における決定過程のもつ困難もあった。信奉者が、意見を変える必要があると自分たちのリーダーを説得する方法を考えているあいだに、第三帝国は貴重な利点を喪失し、もう決してそれを回復することはできなかった。民主主義システムの場合には、決定過程は一般的にもっと時間がかかるものだが、しかしその決定はたった一人の人間の気まぐれや決定によっていたのではなかった。例えば、宣伝の大衆への使用をウィンストン・チャーチルは拒否したが、それはこの武器を実践に移していくためのひとつの障害に過ぎなかった。
太平洋でも似たようなことは起こった、ただし決定権はそこまで一極集中していなかったが。北米の対抗諜報活動における質的向上、G-2は、重要であったし、またそれは量的にも反映されていた;日本の公使館と東京の間にかわされたメッセージの大部分、また主に海軍のものであるが軍の通信のほとんどは、解読された。外交文書に関しては、アメリカ人が日本人への情報を解読する量が非常に多かったので、1942年4月以降は、毎日、「マジック・サマリー」 (後には「マジック・ディプロマティック・サマリー」となった)という報告書がだされ、それには電報のなかから最も興味深い部分を選択して、データの重要性と信憑性について比較が掲載された。であるから、連合国側の主要な武器とは日本の機密通信を解読することであった。翻訳には議論の余地がある;小松敬一郎は太平洋戦争の原因に関する興味深い博士論文で、戦争に関する誤った理解の方向性のなかで支配的だったバイヤスのせいで翻訳にまちがいが生まれたとしたが、また一方で作家逢坂剛は、戦争の時期とマジック・サマリーに言及するに当たって、翻訳を「ほとんど完璧だ」と評した。なんにせよ、このサマリーは戦争の進展にとっての鍵となる重要なものであった。
アメリカが戦争に勝利するためにとても重要な武器を手にしたことを公に認めた後、最初の反応は、真珠湾攻撃は避けられたのではないか、と自問することであった。この論争の効き目をよく知っているアメリカ合衆国政府は、マジック・サマリーへのアクセスを許可すると同時に、『真珠湾攻撃の背景』と題して、1944年の集大成を出版した。この何巻にもわたる資料集は、攻撃が奇襲であったという見解を述べるために、日本人から傍受したメッセージを載せた。その本の中では、攻撃されると以前からわかっていたとは述べられていない。しかし解読された電話での会話を文字化しているところからすれば、前もって攻撃を知っていたことが明らかではないだろうか。その会話は、野村海軍大将とともに日本代表団を率いていた来栖大使と、外務省の東方アジア部門局長であった山本との間で1941年11月27日に交わされていた。そのなかで、山本は来栖大使に、たとえ何の結果を出していなくとも、交渉を続けるよう求めている。その上、戦争は起こるであろうと、二度繰り返していっている。「誕生はあるでしょう」という文言であるが、これを諜報部は「危機は切迫している。」と解読した。よって、アメリカは危機がせまっていることはわかっていた、まだ疑いがあったとしても、その後12月3日には別のメッセージを解読し、日本が公使館の文書を全て焼却処分にするよう命令をだしたとわかったのだから。皆が戦争を回避する方法はないとわかっていた。雑誌『世界』の国粋主義者たちでも、12月7日の論説で次のような質問を投げかけた。「太平洋で戦争が?」その答えは、インクが乾くか乾かないかのうちにはっきりしたのだった。
海兵隊員で引退したジャーナリストのロバート・スティネットの研究は、日本が攻撃してくるとわかっていたということのみならず、それは真珠湾で行われるというのも前もってわかっていたと暴露している。意識的にハワイ艦隊の司令官たち、ハズバンド・E.・キメル総司令官とウォルター・ショート中将には攻撃に関する情報が隠されたのだ。それは日本の戦闘行為を妨げないようにするための処置だった。その上、南雲艦隊は、何度も樺太からハワイへ向かう間ラジオで連絡をとっていたので、そのメッセージの内容がわからなくとも、北アメリカ艦隊にどんどん近づいていたのはわかったはずである。付加的な一連の出来事は、奇襲攻撃は避けられたことを示している。太平洋戦争は真珠湾攻撃の数時間前に、コータ・バル、現在のマレーシアで、始まっていたのだとすれば。回避できたのだ、なぜならば、決定的な瞬間における北米の航空母艦の敗走は、予想された事件を前にして、危険は分散されていたと考えさせるに足るものだからである。おそらく、奇襲攻撃のあとの日本の膨張への抵抗は、ダグラス・マッカーサー将軍の頑固さによってフィリピンで維持された兵士を例外として、なぜあれほど手薄であったのか、と考えてみるのがいいだろう。数ヶ月間で日本は支配領土を増やしたが、それとともに能力が増したのではなく、身体がコントロールできないほど大きくなる一方で、両足は泥でできたままだった。日本軍の勝利自体が、日本軍をこれまでにないほど弱いものにしたのだった。
結局、喧伝された「悪夢の日」は、それほどのものではなかったようである。なぜならばアメリカ合衆国はさほど愚かではなかったからだ。宣戦布告を渡すのが遅れたいい加減な公務員については別として、当時70%の戦争は公式の布告なしに始まっていたという逸話がある。むしろ日本人攻撃者が後で述べるように、真珠湾攻撃は指導者側が不可避とした戦争に立ち向かうよう国民を仕向けることになったので、アメリカ政府にとっては最良の贈り物であった。その時までは中立派の国民感情が支配的だったが、ドイツ寄りの国民感情こそが、いわゆるラジオ司祭と呼ばれるより権威主義的な政府のために働くルーズベルトに批判的な人々が、4000万人をも秩序ある聴衆にまとめる能力があるように仕向けたのだった。公からの推進力、たとえば、「ヨーク軍曹」(第一次世界大戦を舞台とし、ゲーリー・クーパーが主演、平和主義者が結果として20人の敵であるドイツ人を殺し、100人以上を捕らえた英雄になった)のような映画や、戦争の進展そのものが、アメリカの人々にヨーロッパでの戦闘に参戦する必要性を感じさせるのに貢献した。しかし決定的だったのは、真珠湾攻撃を裏切りであり下劣なものと考える国民感情であり、それ以降日本人はアメリカで使われていた最悪の形容詞が使われる対象となった:狂信的な、残虐な攻撃者、除去されるのがふさわしい「非人間的動物」などである。宣戦布告を渡すのが遅れたからといって、大きな軍事的結果にはつながらなかったようである。なぜなら日本は意表をつき続け、例えば形式がととのっていないととがめられないような奇襲攻撃をかけて、フィリピンにおけるアメリカ合衆国の航空母艦を破壊した。真珠湾以降は、世論が日本との戦争が長引くことを耐えられないだろうと思われたし、またアメリカ合衆国の技術・兵站学・作戦面からみた戦略への心理的様相も加えられた。不名誉は中央部・南部のアメリカ人の多くを扇動した。結果、当時作られた不名誉なイメージは重要な成果を挙げた。それは何世代にもわたって継続し、戦争50年の折には、販売部数の非常に多い雑誌が見出しとして、ルーズベルトが下院に戦争宣言を提案するおりにつかったフレーズを用いたほどである。合衆国の人々、またアメリカから情報を受けていた多くの人々の心には未だに日本は邪悪だという感がある。
戦闘開始という主要ではないテーマがもちうる影響をはるかにしのいで、対抗諜報活動は、たとえば日本が戦争を遂行する上でのアキレス腱だった東インドからの石油の輸送を妨害する等の決定的な作戦に貢献した。合衆国陸軍参謀総長ジョージ・マーシャルの1944年の書翰は対抗諜報活動の重要性を指摘している。その書翰は、戦争の行方に対抗諜報活動がもたらす利点を使って、ルーズベルトの再選を妨げようと計画したときに、共和党の大統領候補に送られたものである。
「珊瑚礁海戦は解読されたメッセージに基づいて行われ、よって我々の側のわずかな戦艦は、当時適切な位置にいた。その上、我々は限りある我々の戦力を進行してくる敵海軍と向き合うためにミッドウェーに集中させていた、別の形であればおそらく300マイルは離れたところにいたにちがいないのであるが。我々の潜水艦活動に苦しむ敵側の情報が刻一刻と送られてくるのだが、我々には敵の輸送船の出発日やルートが分かっており、我が軍の潜水艦に適切な場所で待つよう指示することができたおかげで、敵は撃沈されたのだった。」
アメリカ人には大きな利点があった、既に一部見てきたので、想像できると思うが、マーシャル将軍の確信の力で、その利点を守ることに力を注いでいた。マジック報の配布は20部という限定されたものだった、そして敵がその存在に気づくことがないように、取り扱いは厳密であった。解読されたメッセージは読後すぐに諜報部へ戻されたに違いなかった。誰にもメッセージの保存は許されなかったし、続けては読むこともできなかったのだ。書面や電話でその存在を明かすことも禁止されていたし、非常に具体的な場合にだけ、海外の公使館へコピーがおくられた。もちろん厳命により、その複製は禁止だったし、建物の外に持ち出すことも許されなかった。
その上、アメリカは、日本だけではなく、他の国々も友好国を通じて価値の高い情報を得ることができるのだとわかっていた。スペインやスイス、スウェーデン、ポルトガルなどは戦争の間、書翰を開封されるという辱めに甘んじなければならなかった。最近になって、32もの国の極秘書翰が傍受されていたのがわかった。連合国側は、枢軸国はメキシコなどの友好国の秘密システムに関する情報を解読する力を持っているとわかっていた。よって、ワシントンや他の場所で、それらの国の代表のメッセージを知らねばならないと感じていた。
日本は対抗諜報活動において独自の進歩を遂げた。例えば、外務省の諜報活動は真珠湾攻撃以前にアメリカの極秘書類のうちのあるものを手に入れたし、海軍はメッセージのやりとりを分析するだけで、重要な資料を手に入れた。陸軍のコードは1943年夏までは解読されていなかったが、小和田通信隊は戦争末期には中国の電信のみならずアメリカの電信も全て解読していた。しかしこういった達成は、敵によって矮小化されてしまった。というのも、時期的にみれば、第一次世界大戦から1922年までに既にアメリカは敵の通信を解読していた。その後、アメリカは技術競争にも勝った。日本人自体もそのことを1931年に知り、結果として、日本の外務省は1934年にレッドマシーンという呼び名の進んだ技術を取り入れた暗号機を使うことにした。しかしそれでも不十分であった。アメリカ合衆国人は翌年に機械が使用されるようになると直ぐ、メッセージを解読しはじめたからである。1938年には日本は市場に出回っている中でも最新の器械を使うことにし、ドイツのエニグマ機を取り入れた。ちょうど世界にその器械が少しずつ出回り始めた頃のことだった。しかしエニグマ機からのメッセージを解読するのもさほど難しくはなかった。なぜならば、一方では機械はすこし遅れたものになっており、またドイツが後に使った機種ほど複雑なものではなかったからである。また公使館のうちには、新しい機械の性能を試すために、古い機械とそっくりのメッセージを送っていたところもあったからだ。それは暗号解読部隊にとっては天からの贈り物であった。アメリカにとっては、連合国のあいだでパープルと呼ばれていたポーランドの暗号開発者コヴァルスキーが1939年につくった新しい暗号システムを知ることのほうが大変な作業であった。しかし最終的に20ヶ月後には解読できたし、その暗号を生んだ機械を再生産することもできるようになった。
日本は自分たちの極秘通信に他の国々が興味をもっていることを明らかに自覚していた。しかし日本が解読を避ける努力は敵国が行った努力には及ばなかった。だから、暗号(秘密裏にごくあたりまえの文章を変えるための適合のリストがある)、記号(何千もの単語や、フレーズ、数値がごくあたりまえの文章に埋め込まれていた)等をしばしば変更しても、解読は敵にとっては簡単に解決できる問題であった。暗号の大部分は、イギリス、アメリカ、ソビエト、ドイツ、イタリアの少なくとも5カ国で読まれた。また前述のポーランド人の暗号機には盲目の信頼が置かれたが、日本人には財源がなかったので、わずかな年月で、新しい通信システムを軌道に乗せ、いつまでその価値があるかわからない新しい器械を買うのは無理であった。
ゆえに、アルカサル・デ・ベラスコにとっては、アメリカ合衆国でのスパイ活動網の整備が任せられたが、それは考えていたのよりもずっと大変な仕事となったのだった。既にしっかり歩んでいて力のある諜報活動に対してのみならず、日本が自分に支払いを続けるように、かなり信憑性の高いメッセージを産むことに立ち向かわなければならなかったし、その上外交ルートを通じて送った暗号の文章や、特に日本人に渡された情報が、時にその届け先よりも早く、アメリカに知られるようになったであろう。アルカサルだけが職業意識の不足の例ではないし、彼の上司も似たり寄ったりだった、なぜならば日本が敵国の耳から自分たちのメッセージを守ろうとする努力は、非常に部分的なものであったからである。
ホルナダ外相の時代におけるアメリカ情報網の情報と情報網の発展は、次の章で扱うことにする。なぜならば、セラノ・スニェルがスパイ網をつくろうとして尽力した分の結果のほとんどが、皮肉にも彼が外相ではなくなってから、実を結んだからである。セラノは諜報網を開始し、ホルナダは諜報網を我慢して受け入れると同時に、その利害関係の重みをもいやいやながら受け入れた。では続けてみていこう。
4.2. 利益を代表する
日本が緊急に必要としていたことのうちのひとつに、ひとたび戦争に突入した暁には敵国に在住する日本市民を守らねばならない、ということがあった。これは新奇な問題ではなかった。現代の重要な争いを繰り返しながら、政府指導者はこういった種類の懸念が広がらないように「人道的な処理」を標準化するため、一連の国際的規則を設けた。1929年には、第一次大戦時の経験に基づいて、ジュネーブで第二次世界大戦前の最後の国際的合意が形成された。そこでもたらされた刷新は、スペインと日本の関係に影響を与えることになった。例えば、傷痍兵・傷病兵を助ける義務や戦争捕虜の権利、中立国規約などが確立された。この中立国の規約についていえば、これは戦闘下にある敵の領土に在住する臣民の利益を中立国を通じて守るための試みであり、中立国は捕虜の状況を観察し、人間的な扱いを受けさせる要求をするのが仕事であった。
日本はある中立国によるそれらのサービスを緊急に要した。真珠湾攻撃の後、アメリカ合衆国とイギリスの他にも、日本は多くの国々から外交関係断絶と宣戦布告を受けた。特にアメリカ大陸においては、ほとんど全ての国々が日本に宣戦布告をするか(コスタリカやドミニカ共和国のように、直ぐにそれを行った国もあったほどである)、キューバやベネズエラ・ブラジル・メキシコのように、外交関係を断絶した。日本はポルトガル・スペイン・スイス・スウェーデンという4つの中立国に日本の利益を保護するように依頼した。4カ国のうちでもスペインは、ポルトガルが担当したメキシコとグアテマラという例外を除いて、南北アメリカ大陸の大部分を担当しなければならなかった。そうしてアメリカ合衆国・カナダ・コロンビア・キューバ・エクアドル・サンサルバドール・ベネズエラ居住の日本人は直ぐにスペインの法規のもとに置かれたし、少し時間が経ったあとは、ウルグアイ・ボリビア・ブラジル・ペルーでもそうなった。
最終的には、日本が日本人の権益を代表してくれるよう依頼したこれら4つの中立国のうちで、スペインが最も大きな責任を担う国となった。それは担当国の数にだけよるのではなく、これらの国々にペルーやブラジルなどのように日本の居留民がたくさんいる最重要国が含まれていたからでもあり、また政治的に最も重要な国である、「我々の利益が大きい国、だから私たちが非常に深い懸念を抱いている国」アメリカ合衆国の代表を担当したことにもよる。
スペインは非常に重要な任務のために日本によって選ばれた。その理由は、技術的・政治的性質の動機が混ざっており、また政治的動機のほうが重かった。技術的な理由としては、スペインがラテンアメリカにもっていた外交網の広さが挙げられる。この外交網は、ラテンアメリカで移民の大部分が農村地域に居住していた日本にとって、都合のよいものであった。その上、以前に既に似たような経験があったのだ、つまりスペインは第一次大戦中ドイツにおける日本の利益を代表したことがあったし、その上、ヨーロッパでの戦争開始以降、ドイツ・イタリアの利益を擁護する国として行動していた。しかしまた政治的動機もあった。日本はスペイン人職員が日本の利益を最も代表しうると判断したのだ、なぜならば敵側では、アメリカ大使グルーが、スペインに、日本におけるアメリカの利益を代表するよう依頼していたからである:メンデス・デ・ビゴはマドリードで上司が行ったことにもかかわらず、よく知られた連合国ひいきであった。
それだけが理由ではない。セラノ・スニェル外相時代の外交文書の中にある日本に関する資料であたることのできるわずかな数の電報のうちの一通によると、また別の意図があったのがわかる。このテーマに関してワシントンに送られた最初のメッセージは、日本がスペインへ少なくとも合衆国に関することに関して、仕事を依頼したことを語り、諜報によって情報を得るための手段として日本の利益代表権を使うことを考えて、その役割を引き受けると決定された、というものである:
「日本政府の依頼により、スペインはこの国における日本の利益を代表することを受け入れる。政府にその旨伝達願いたい、また日本の領事館に関する役割を果たすようわが国の領事たちに命じるべし。スペイン領事館ではなく日本領事館のある都市に至急情報を流すべし。関連する地帯をスペインの領事館の法治下に入れるよう[不明語]。日本政府は特に大使館と、ニューヨーク・サンフランシスコ・シカゴ・ロスアンジェルス・ポートランド・シアトル・ニューオリンズ・ボストンにある領事館での全体的保護を求めている。至急、新しい機能を果たすのに必要な人員と資金を送られたし。また関係する居住地に、「同年兵」としてのアメリカ政府に対して問題をもたず、信頼の置けるスペイン人、しかも国家にとって高い利益のあるこの任務遂行に協力しうる人物がいるかどうか、知らせていただきたい。」
4.2.1. 人道主義と批判
理由はどうあれ、スペイン人は直ぐに多数の任務を請け負わねばならなかった。アメリカ合衆国での主な仕事は日本市民の大量収容に関するものだった。第一世代から第三世代までの6万人以上の移民が、家とはかけ離れた東海岸にある、いわゆる強制収容所に送られたのだった。直接行動主義によって目立っていた3000人ほどのドイツ人やイタリア人とは逆に、日本人には政治思想によって差別するような努力は払われなかった。東京に情報を送るかもしれないという恐れがあったので、日本人は皆強制収容所送りとなった。アメリカ大陸のほかの場所でも、厳格さに差はあったものの、類似した方法がとられた。時折はアメリカ合衆国への送還もありえたし、手紙の検閲や銀行預金の封鎖も行われた。古くからの移民とその子孫にとっては大変な時期であった、しかし南アメリカにおける主要な日本人共同体であるブラジルの共同体には、約50万人の日本人がいたが、大きな問題もなく、彼らのうちのわずかな人々しか迷惑を被ることはなかった。
スペイン人職員の予定表は、日本人の置かれた状況を確認し、家族が同じところにいられるような請願をおこない、日本人移民と東京との間の通信の経路となるよう行動するために行われた、強制収容所への訪問・拘留・4~6週間ごとの巡回、などで埋まっていた。
結果として仕事が増えたので、外務省はこの仕事のために日本人を雇用しただけではなく、1942年1月29日に中央保護事務局を発足させた。翌月、この事務局のやることが明らかになった:合衆国におけるスペイン人外交官は既に西海岸にある強制収容所全てを訪問し終えていた。例えば、FBIがもっている収容者のリストと赤十字のリストとの間の相違や拘留の性質に関して注意を喚起し、学生の逮捕について議論した。そういったスペインの要求を、アメリカはある意味苦々しく思ってみていたが、日本の互恵主義への恐れからスペイン人に不利な報告書を出すのは得策ではなかいと知っていた。日本は、スイスの外交官に日本列島での活動を許可したが、技術的に正しい論拠にしたがって、上海という例外を除き日本が征服した地域へ出国するのを許さなかった。故に交流者の大部分は、たとえ一時的でも、金銭的にも、自分の国からの援助を受けることもできず、日本の示す条件に苦しんだ。唯一可能だった援助の方策は、戦争の間に、スイスとスペインの組織がアメリカ合衆国と日本の間の民間人を交換することだった。一度目は1942年6月、二度目は1943年9月に行われた。
しかし、スペインの仕事は、職員との契約よりもっと先をいっており、非常に複雑なものになってきた。複雑だ、というひとつには、拘留されていない「反日本主義的」波動に影響を受けた人々を助けることがあった。ブラックリストに載った日本企業は、銀行預金を凍結され、大量の従業員解雇を行い、山賊的な活動によって商売もめちゃくちゃになっていたので、それまで割合によい経済状況のもとにあった居留地を貧困に陥れることになった。必要に駆られ、スペインは日本・アメリカ合衆国政府に対して、急激に貧困に苦しむようになった日本人を金銭面で助けるように要求した。初めのうち、日本は、ジュネーブ条約がホスト国に対してそういった援助を供給することを義務化しているのに気づきながら、援助を拒否した。しかし最終的には誰も金を貸すわけもなく、日本が自ら受け入れるしかなかった。
問題は他にももっとあった、たとえば両国が外交官にかける圧力がそうである。日本政府は、例えば、「スペイン経路」で流されたメッセージは人道主義以上のもので、臣民の間で戦いの気力と宣伝効果が生まれるようにしたいと願った。以降マドリードは、どんな種類のメッセージでもそれを送るのにどんどん疑い深くなり、須磨は上司に「メッセージの取扱いにもっと慎重になっていただきたい、というのもスペイン政府を窮地に陥れたくはないからだ」と依頼した。スペインにとっては、労力のかかる協力関係であり、交換船の例以外は、宣伝の恩恵はほとんどなかった。
4.3. 相互貿易への支持
日本はスペインとの商業協力も求めていたが、様々な種類の官僚的で政治的な問題が発生し、戦争開始から数ヶ月間で、遠慮がちな試みは失敗に終わった。
既に述べた東京寄りの宣伝ニュースよりもっと進んだ形で、閣議によって主要な対策として知らされ、誤って呼ばれた「通商条約」の更新としては、行政側は、太平洋戦争勃発以前の条約更新を妨げた問題がわかっていたので、相互貿易を促進するのにほとんど動こうとしなかった。
戦争がはじまると、企業は2国間の商業貿易を促進することで生まれる利益を引き継いだ。三菱などは、例えば、スペインを通じて南米の特産品を購入するために調査を行った、と同時に、ビルマでの生産量で必要分はまかなえたにもかかわらず、イタリアで、コルクと交換で鉛を手に入れる可能性を模索した。
スペインの場合では、フィリピン・ゼネラル・タバコ社が様々な方法で、「フィリピンを中継点とするスペイン―日本間の通商を確立する可能性の擁護のために」、スペイン外務省を巻き込んで圧力をかけた。同社の経営陣はセラノ・スニェル外相を訪問しただけではなく、マニラが陥落してすぐ、フィリピンへスペイン船を送る可能性について質問するために、外務省内の高官(副局長、パン・デ・ソラルセ、そして通商部長)が須磨外相に会いに行くよう仕向けた。ソフィンドゥス社が加わっていただろう計画は複雑なものだった。日本、アメリカ合衆国、イギリスに打診するだけでなく、双方へ商品を動かすことが計画されていたのだろう。表向き、スペインは日本所有のコルクを購入し、銅を売り、食料を運ぶことになっていた。しかしそれだけではなく、フィリピン産タバコを輸入しようとしていたことは見て取れる。それにはイギリスが輸入に関する商品に対して許可を与える、つまり航行許可書をだす必要があった。そのうえ、戦闘状態にあるため、アルゼンチンを通っていく長い航路を考慮しなくてはならなかった。
日本はそれを拒否せず、須磨外相ですら、戦争が勃発した時に三井物産が買い取る寸前であった物資に利益を見て取るだろうとふんで、それを支持さえした。しかし実施するのが困難だというのも、十分に分かっていた。日本は、船の使用目的や、またスペインとアルゼンチンとの間の交渉の進み具合を心配していた。ともかく、スペインは真剣にフィリピンを接舷点とするスペイン―日本間の貿易の可能性を考慮した。そうすれば、外国の商社を通さずに日本と直接通商を行えるとも考えていた。
スペイン職員は、おそらく、これらの交渉にいつも以上に力を割いた、なぜならばゼネラル・タバコ社はスペインにとってもフィリピンにとっても重要であったからである。戦争が進むにつれて、フィリピンでビジネスを展開するのが難しくなり、セラノ・スニェルは可能な限りの方策をつかって、問題を解決するように命令を出した。しかしほとんどできることはなかった。この会社の本部が最初に考えたのは、できるだけ早くフィリピンで始めることであったが、マニラ占領による一時的交渉停止の後、意見交換を始めるのは、どんどん困難になっていった。メンデス・デ・ビゴと話をしたフィリピン在住のスペイン人が東京を訪問したことは、重要な警告だった。この人物はメンデス・デ・ビゴに、はじめて仲介者なしで、会社の損失が大きいこと、タバコ貿易の落ち込み、スペインの居留地にとってひどくなるばかりの苦悩などについて報告した。このニュースがマドリードへ届くと、外務省自体、この先行き不透明な商業計画を軌道に乗せようとして画策し、そして結果として、アルゼンチン船にまで考慮に入れた。後で触れるが、以前のスペインの所有物は、群島に在住している人々も含んで、日本との関係における鍵の役割を果たし続けた。
4.4フィリピンにおけるスペイン人
フィリピンにおけるスペイン人コミュニティは、第二次世界大戦によって影響を受けた外国のコミュニティのうちで最も重要なものであった。その困難は、スペインに非常に関係深いところで続いていたのだった。これについては既に日本によるマニラ占領に関する部分で考察した。はじめは日本人の来訪を悪くはとらなかった。しかし一度戦争行為がおこると、どんな代償を払っても法と秩序を維持することが最重要課題となった。それについて、サン・フアン・レトラン学校長であったドミニコ会士ラブラドール神父はこう述べた:「こんなにひどい略奪をとめてくれるよう、日本人の到来を切望するものは多い。もう誰も安心していられないほどなのだ。マニラは征服された都市の様相を呈し、その都市民自身による略奪にさらされていた。」保守的な感情が支配的であった中で、特にこの文書は、スペイン人が平和を求めたことを示している。
しかしそうはいっても、日本の攻撃はスペイン人の財産に被害を与えた。イントラムロス修道院・サン・フアン・レトラン修道院・サンタ・カタリナ修道院やコンコルディア小学校は爆撃されたし、またしっかりした建築でないもののうち、例えばサン・フェルナンドにあるタバコ社の倉庫は火災によって失われたし、また何隻かの船は日本人が使えないようにするため破壊された。またスペイン人は太平洋戦争勃発と共に、強い緊張を強いられた、無政府状態における商店の略奪や、セブでの例のように、もっと政治的動機で、第五列として非難された3人のファランヘ党員が逮捕されたことなどが起こった。その上、マニラにおけるファランヘ党は、ドイツ人やイタリア人受けたような扱いの的とならないように支所を閉鎖し、武器をとってスペイン・カジノや総領事館を守った。総領事館はレコレトスの修道院に移されたが、そこではアメリカ親派による攻撃が恐れられた。しかし、日本がやってくる前にはトラブルは相対的に少なく、これら初期の攻撃においては死者が出たというニュースはなかった。テレタイプで示されたリョイロの修道女死亡すらもなかった。これらの問題が起きた後、占領が相対的に早くすんだのを喜ばしい事として、領事デル・カスターニョ自身は、それまでの恐怖をこう表現した:「日本人がマニラを占領するのに3週間以上かかっていたとしたら、我々の仲間のうちの誰かが注目の的となったことであろう、もしくは少なくとも、実際に苦しんだ以上の苦しみを感じたことであろう。」そうして最初の試験ではある程度無傷で状況を乗り越えたのだった。
新しい占領者の定住、という第二の問題は、そうして望まれた社会秩序の復帰やスペインと日本が一般的に政治地図の中で保っていたよい関係があったとしても、ある程度まで時間のかかるものだった。日本が選択肢となるような経済計画を何も立てていなかったとしたら、上部階級の覇権への脅迫は、少なくとも経済面においては宙ぶらりんのままだった。しかし、そうはいかなかった。占領が始まると、兵士の人々への扱いは思っていたものとまったく異なっていた。挨拶のときに兵士の前で頭を下げないなど、どんな小さなミスでも罵声が飛びかった。その上、日本はフィリピンがまるで西洋の影響から抜け出したがっているかのように主張した。その影響には、「ハリウッドの40年」だけではなく、「修道院のもとでの3世紀」も含まれていた;日本の目的は、公式の宣伝が示したこととは異なり、カトリック教会の長年にわたる影響力を取り除くことであった。
フィリピンにおけるスペイン人コミュニティの対外的な関係は、特にひどいことになった。日本は通信に関して特に厳しい処置をとった。手紙や電報は日本語か英語で書かなくてはならず、また暗号を使ってはならなかった。その上、2月から公式にマニラにある外国領事館を廃止することにした。領事館は、口頭の許可を得て、実際は以前通りに機能していたし、同国民の不満を察知するためにも、居留民の保護と指導の機能を事実上実践した。疑いが、スペイン人植民者同様、フィリピン社会に生きる人びと全てにとって支配的な感情となった。
スペイン領事、ホセ・デル・カスターニョは、公的な法規のないまま、フィリピンに残った。外部とのメッセージのやり取りに暗号を使うこともできず、廃止された外務省の記章と解決しなければならない問題を山のように抱えながらも、である。フィリピンを出国する機会もあったが、マニラへの在留を望み、それとともにある非常にふさわしい決定をした、なぜならば彼が残留したおかげで領事館が機能し続けたからである。不確かな時代に、スペイン人たちは(他の国の市民と同じように)兵士の下す横暴に対して、保護を求めるようになった。「これまで領事館に足を踏み入れたことがない同国人が何年分もの書類を申し込みにやってきた。既にはるか昔の出来事となった婚姻の登録にきたり、2・3人ものこどもたちを同時に登録しにきたりした。正規の書類を持っていた者は、徴用された家や車、商売道具や商品を要求しにやってきたし、怒鳴りつけらたり不当な扱いを受けたことに対して抗議しにやってきた。」領事館は、半公式のものであったにせよ、今までにないくらい妥当な意味をもつものとなった。
そのうえ、領事館の機能はコミュニティの中で拡大した。なぜならば情報を流すこと、もしくは地方の県に加えてまだ日本軍が占領していない地域で起こったことに関するうわさを確かめることが必要だったからである。こうして、ニュースへのニーズが高まるにつれて、スペインのラジオ放送から捕えた情報を載せたビラが編集された。それにあたる人員や資金の必要性は高まり、時代の特異性を考慮して、スペイン外務省は人員数増加をごまかして物品費として記し、マニラでの資金の引き渡しに談合を行い、スペインへあるまとまった金額を送金したい人々を利用した:外務省が彼らの銀行口座にある金額を入金し、一方で彼らは領事にその金を給与として金を支払う、というものである。こういった危急を要する事態を前に、できるだけのことをしたのであった。
4.4.1. ファランヘ党員と占領
フィリピンでのファランヘ党はデル・カスターニョによって表現にしたがえば、ほっと一息つく感じで、日本の占領を受け止めた:公然と枢軸国の一員であっても報復を受ける心配はなくなったからだ。しかしながら、日本はスペインの政治的同盟者ではあったが、アメリカを負かしたいということ以外は二国の間に共有するものはなかったので、日本人への疑念は決してなくなりはしなかった。ファランヘ党は長い間望んできたアメリカの敗北に居合わせた、なぜならばフィリピンからアメリカ人は放逐されたままだったからである。しかしそれを味わう時間はあまりなかった。というのも勝利は、日本人と同じぐらい信頼できない他の者たちの手中にあったからである。そうしてファランヘ党員は新しい時代が始まったとき、矛盾した感覚を抱くようになった。占領者が到着したときには、希望が支配的感情だったが、直ぐに、現実は前に夢見ていた喜びとはかけ離れたものであることがわかった。スペインの影響に対する日本の批判、コミュニケーションの不可能さ、敗北したアメリカに対して示した同じようなある種のさげすみ、そして厳格な統制はこの現実をもっともよく現す特徴のうちのいくつかであった。現実は以前に期待されていたものとはかけ離れていたのだ。日本軍が支配したほかの地域でドイツ・ナチス党員やイタリア・ファシスト党員に起きたのと同じように、わずかの間で、日本人とファランヘ党員との間に共存者に対するあてこすりが目立つようになった。その上、日本の占領が始まって、ファランヘ党員のフィリピンでの目標は根本的に変化した。なぜならば、他の者が権力をもったからだけではなく、ファランヘ党にとっての意義深い見通しがなかったからであった。想像したのとは反対に、スペインは直ぐに、日本人が指揮する立場にある限り、将来のフィリピンにおいてスペインが担うのは、単なる観客以外の何者でもないと理解したのだった。
ファランヘ党の活動は、結果として、スペイン人居留地に集中した。一方、党は主に娯楽・文化的協会として機能した。講演会を開き、ミサをおこなう一方で、慈善事業をうけもつ社会扶助は日に1度から週1度へ食糧分配の頻度を下げ、そのうえその食糧には味がついておらず、しかもその分配は資金不足のため急いで行われた。ファランヘ支部では人々は社会変革を計画するよりもピンポンにかまけて時を過ごし、ファランヘ党の名は新聞にも出ず、デル・カスターニョガ指摘するように、当局と重要な関係を結ぶことはなかった。「党を訪れる日本人はおらず、我々の活動があまりにも慎み深いままだったので、ファランヘの名前はあの時代、どんな新聞にも載らなかった。」前の時代と比べたときの唯一の変化は、日本で経済調査団が移動上映を行ったホセ・アントニオの埋葬に関する映画を上映できたことだった。
しかしデル・カスターニョは自らが内戦勃発以来参加してきた共同体のなかで起きた権力闘争を忘れてはいなかった。ファランヘ党の目標は社会の他の人々にはもう通じなかったし、スペイン人共同体の状況は変わってしまっていた。デル・カスターニョは、ある種の権力と散り散りになった人々の同意を自分が優位に立つためにうまく利用することができた。共和派は、例えば、共和国の家を閉鎖し以前は『スペインの民主主義』という名称だった『民主主義』というすばらしい雑誌の発行を停止した。一方保守派は、アンドレス・ソリアノの亡命によって指導者を失い、フィリピンのエリート層の人々と同じように、新しい統治者に対してより柔軟な立場をとることにした。
デル・カスターニョは自分のグループの優位を確立するための方法を模索した。スペイン・カジノやサンティアゴ病院などの伝統的組織の指導評議会を関係者で埋め、また日本による占領に基づき領事館で新しく雇った人々も同じように集めた。例えば、機関紙『くびき』の前編集長であり、アンドレス・ソリアノに最も対立していたリーダーのうちの一人であったフランシスコ・フェレールは、兄と一緒に、『マニラ・グラフィカ』という街の外国新聞のなかでも最良のキヨスクうちのひとつを所有していた人物であり、スペインからの反対にもかかわらず、領事館代表書記官となった。自分の仲間が困難な時期をできる限りうまく生き延びられるようにして、デル・カスターニョは過去の問題に対して復讐しようとした。そうして、軍部がスペイン左翼の人々の名を尋ねた時、領事はスペインの体制に反対する共和派の影響力を決定的に一掃するために、その時期を利用することを決めた。このように、外国の警察をスペイン国内の事がらに引き込んだのだった。このことは、在東京の上司、サンティアゴ・メンデス・デ・ビゴに宛てた手紙の中に現れている:
「日本軍の占領後まもなく、憲兵隊長が私に在住スペイン人の中の赤色分子の名を明かすよう求めてきた。我々の戦争時のみならず日本軍入場までの間、活動的であり国益に反する行動が目立っていた赤色分子の数は、12名は越えないかと思われる。その大部分は憲兵隊が「ビリャモール・ホール」と呼ぶ建物を巣窟としており、他の国籍をもつ政治的理由で望ましくない分子もそこにいた。数週間後には大多数が自由の身となりましたが、うち1グループ、より重要な任務があった人々は、フエルテ・サンティアゴの軍刑務所へ移送された。その者たちの中には、赤色陣営での行動が目立っていたベニト・パボン・イ・スアレス・デ・ウルビナや、以前マニラの共和国の家の書記だったホセ・マリア・カンポスなどがいた。」
デル・カスターニョは日本当局に13名を告発した:フィリピン人5名(ミゲル・プハルテ父子、トマス・デル・リオ父子、レスティトゥト・インチャウスティ)、アメリカ人1名(リカルド・アッリアンディアガ)、そしてスペイン人4名(作家であり詩人、共和国軍人バルセロの未亡人であるレオノール・ゴンサレス、ペンネームをラミロ・アルダベとしていたラファエル・アントン、そして既に述べたカンポスとパボンである。)、その上他に、マニラにいなかったので逮捕を免れた3人がいる。彼らが受けた罪状は軽いものであった。ベニト・パボンとラファエル・アントンは他の者たちよりも長く投獄されていたが、1942年秋には釈放された。デル・カスターニョは彼らを投獄したままにしておいて欲しいと願ったが、日本は彼らの健康が弱っていることを釈放の口実にした。彼らのうちの誰かが日本軍によって処刑されたかどうかは不明であるし、またデル・カスターニョがフィリピン人やアメリカ人を密告していたかどうかも不明である。少なくとも、領事としてはそれなりに彼らのうち何人かが法律上の義務を怠っていることはわかっていたに違いないだろうが、デル・カスターニョは常にスペイン人に言及していた。
その上、デル・カスターニョがパボンとアントンの逮捕に関する唯一の責任者というわけでもなかった、というのも、スペイン側が合意していたからである。外務省から逮捕の情報を受けて、「日本側が共通の権利に反する犯罪者であるベニト・パボンとラファエル・アントンの引渡しの機会が来るまできちんと逮捕拘留しておくことを交渉するのがデル・カスターニョの危急の任務となった。」これは、まだ決済しなければならない内戦のツケがあったことを示している。距離を越えて、戦後スペインの反対勢力を罰しようとする望みがはっきりとフィリピンまで伝わってきた。1940年以降、マルドナド領事がマヌエル・ケソン政府に対して雑誌『民主主義』の編集長ピオ・ブルン・クエバスの国外追放を求めたのは、このような態度のひとつの顕れであるといえよう。フィリピンの事件への干渉は、距離のせいではなく、群島における支障のせいで決定的に制限されていた。なぜならばファランヘ党員には、同盟国が権力を奪取したときに、ドイツ人が到着したときのフランスで起こったのと同じように、過去の傷に対して賠償してもらいたいという気持ちがいっぱいだったからである。
デル・カスターニョは戦争が終わると別の明らかに協調主義者的な行動によって告発された(スペインへ送るため、まず東京に送ったメッセージがこれを裏付けている):コレヒドール島の奪取を助けたこと、そこでのアメリカの抵抗が終わったことを、在フィリピン大日本帝国陸軍司令官に対して祝ったせいである。手紙の文面はこうである:「マニラにおけるスペイン居留地の名において、ミンダナオとコレヒドールにおける最近の決定的な勝利を心よりお喜び申し上げます。この国が今後偉大なる日本国の保護と指導の下に末永い平和の恩恵に与ることができますように。(…)まだこれからである復興という大変な仕事のために、フィリピンにおけるスペイン人コミュニティは再び日本軍部に対して熱心な協力を申し出たい。」スペイン領事は日本人との近しい関係を、自分とまたその側近グループとスペイン居留地の現状を改善するための都合の良いてことしてみていたのだった。
どの点までデル・カスターニョが他の彼の同僚たちの考えを代表していたかを知るのは難しい。日本軍占領後の初期において彼が示した明確な協調主義的行動からは、果たしてコミュニティの他の人々もそうだったのかという疑問が浮かぶ。家族・地域・個人的な文脈の方がある外国籍に所属することよりもはるかに、普通具体的な時間の中に留保された感情に影響を及ぼした。フィリピン社会では、そのようなスペイン的アイデンティティは同じ資料がなくても多くの人々と共有されていたからである。そのような強制的多様性の中で、日本の膨張に極度に反対するスペイン人の例にはことかかなかった。彼らは、第二段階はラテンアメリカに向けられると確信していた。しかし、フィリピン社会の他の人びとのコミュニティ像を分析すると、新しい日本の権力とよい関係を築こうとするものが優勢だった。
戦争中この像は主に民衆層で強かった。フィリピン民衆はスペイン人を日本軍部の権威に最も似通った外国人グループとしてみていた。しかしながらフィリピン人エリートの間では同じことは起こらなかった。このエリートたちも、自分たちの利益を守り自分たちを追い払おうとする新しい社会階級の登場をさけようとして、新しい権力に協力していたにちがいなかった(必ずしもそんなに親切ではなかったとしても)。もっとふかくこのスペイン市民と新しい軍部との間の推定的な協力を研究する必要がある。スペイン人の間には経済的には日本軍へ物資食料品を調達すれば、経済的に利益を上げられるだろうという意識があった。しかしまた他に、カマリネス地方やヴィサヤス地方におけるゲリラ運動によって処刑されたものもしくは暗殺された者の意識は別だった。動機は多くの場合個人的なものであり、また制御できなくなった暴力の多々あるケースにイデオロギー的な言い訳を見つけようとするのはいきすぎだと思われる。しかし領事デル・カスターニョ自身、1943年には、スペイン外務省に秘密裏に送られた報告書でフィリピン社会にあったスペイン人の協調主義の感覚に基づく政治的問題を記した。彼の論点は、ネグロス島ではゲリラによって殺害されたスペイン人はいなかったという事実に依拠していた。その島では居留者は主に、ファシズムよりはナショナリズムに近い立場がとり、経済的に良好な地位にあったバスク系の農場主によって構成されていた。スペイン内戦中、彼らはバスク・ナショナリスト党を支持し、太平洋戦争中は彼らの幾人かはゲリラと共に戦いもしたのだった。そうして、フィリピンの優秀な砂糖生産地域においては、地域のニュースは新聞の祝辞よりももっと重要だった。スペイン人に対する憎悪はなかった。
ディヴィッド・J.スタインバーグの名著にあるように、その当時は、フィリピン人が協力を拒絶するのは、アメリカへの感謝の借りがあったからだ(Utang na loob)とはまだ理解されていなかった。デル・カスターニョがとった態度は、日本との協力は第三者への感謝や友情から、というよりはむしろ、自分の利益のために決定されたのだと考えさせる。特に占領初期、人々が日本の支配が長く続くと考えられていた頃はそうだった。その意味で、デル・カスターニョが自分たちにとってはあまり関係ない戦争にとらえられた他の多くの居留者と大きく違っていたとは考えにくい。それぞれが家庭・社会・地域・国の文脈によって、できるかぎりうまく苦境を乗り越えようとした。誰もその不安定な時代が何をもたらすのか、よくわかっていなかった。生活の糧を求め、金を稼ぎ、生き延びることは、将来に何をしてくれるか分からない国への忠誠よりももっと決定的な動機であったにちがいない。「アイ・シャル・リターン」という非常にこった形で、ダグラス・マッカーサーが戻ってくると宣言したことはわかっていたが、彼の政府が実際にどのような決定をしたかはわかっていなかったし、このフレーズは、一時期はからかいの対象ですらあったのだ。ある者は、大衆受けする将軍のフレーズを、自分が便所から戻るのを知らせるために使った。
スタインバーグの解釈はなぜフィリピン人の行動の理由を知るためというよりはむしろ、北アメリカ人の竿尺を知るのに興味深いものである。最も重要なのは日本との戦いの中でフィリピン人がアメリカ人の味方であったか、敵であったか、である。それには、フィリピンの新聞ページからファランヘ党は消滅したとはいっても、アメリカ合衆国では時間とともにますます現れるようになったということに気づけばよい。それを理解するためには、『ニューヨーク・タイムス』の記事が興味深い。記事ではグラナダでのピラール・プリモ・デ・リベーラによるフィリピン・ファランヘ党への特別叙勲や、アントニオ・トバールが「真珠湾攻撃はアメリカ合衆国の名声を激しく攻撃している」と認めた宣言や、メキシコにおけるファランヘ党スパイと思われる人物からの報告書などを掲載した。その日刊紙はフィリピンでのこのグループについて付け加えた:「ファランヘは商業・文化活動に影響力を持ち、その社会扶助は大きな事業をなし、すばらしい影響力を獲得している。」そして特に挑発的文章で記事を閉めた。「フィリピン人はアメリカ的なくびき捨てる機会を尊重している」と。アメリカはファランヘ党員が日本びいきであるというよりはむしろ、反アメリカ的だというのをよくわかっていた。長期的に見て、それは彼らの中心的問題であった。アメリカとあれほどの対立を引き起こした「日本主義」の体現者であるセラノ・スニェルのケースを、イベリア半島に戻りながら見ていくことにしよう。
5.不信
推量できた全ての問題点にもかかわらず、セラノ・スニェルが政治的に生き残るには、日本を援助し、その勝利を信じる以外に選択肢はなかった。どんどん権力を失っていくファランヘ党に追いやられて、セラノの可能性は他の人々と結束をかためることにではなく、唯一自分を支持し続けてくれた外国の盟友が勝利する可能性にかかっていた。似たようなことはマニラにいるデル・カスターニョ領事にも起こった;デル・カスターニョはアメリカへの敵意から日本を選び、日本人がやってくると、望んだとしてももう後戻りはできなかった。ファランヘ党は日本に賭け、もう後退することはできなかった。任期中セラノは戦争初期に日本に与えた協力関係を続ける以外にできることはなかった:その協力の内容はといえば、スパイ活動もしくはラテンアメリカにおける日本臣民の利益を代表すること、また日本への熱狂的な支持と友情を示すことなどであった。直ぐに、ファランヘ党は日本に頼っている状態を認めざるを得なかった。
そのような日本との仲介者役の地位はすぐに不快なもので満ちた。1941年12月、セラノ・スニェルは、フランコ自身からコメントを受け取ると、須磨にスペイン人の「不安」を和らげ、雰囲気を静めるために何かしてほしいと頼んだ。しかし一方でこういう認識も示している:「時間の危急さからみて、これらの事柄のうちのいくつかは大目に見なくてはならない。」須磨は東京に「セラノの対日本外交は対抗的になり危険な状態にある」と知らせた。またもっと具体的に「裕福な階級が常にフィリピンとの関係において最大のコネである一方、部下がある種の消極的な反抗を行いつつあるのがその証拠だ。同様にビジネスの世界でも、外務大臣の無能さに対して声が上がっている。」と述べた。結果として、須磨自身はデル・カスターニョ領事がマドリードと直接連絡をとれるように、またフィリピンにおけるスペイン人のビジネスが尊重されるよう気を配ることを勧めたが、東京はほとんどこれに関知しなかった。外務省は軍国主義下の日本ではほとんど権力をもたなかったし、おそらくこれらの問題を軍に知らせる以外には何もできなかった。軍は、スペインが政治的盟友であることは常に認めながらも、白人種に対抗する一般的宣伝を変えるつもりはなかったし、フィリピンでのスペインの植民地化に対する批判を変えるつもりもなかった。また外務省自体も火急にセラノを助ける必要があるとは思わなかった。というのも、双方の公使館レベルから大使館への地位の向上のように、ある外務省サイドの決定を行うのにも時間がかかった。マドリードの準備が終わっても、東京は待つほうを選んだ。
マニラ占領後、メンデス・デ・ビゴのスペインへの攻撃にかんする情報で、1942年1月にはセラノ・スニェルの思いやりは尽きた。須磨にフィリピン問題に関して困難な状況にあることをと述べただけではなく、彼と食事を共にした折を生かして、非公式にではあるがフィリピンにおけるスペイン植民地の状況について、に対する日本の言論の攻撃について、尋ねるまでになった。それは彼の活動の幅がスペインの旧植民地の重要性によって減った最も明白な証拠だった。この論点を使って須磨は日本が彼に答えるようにした。東郷大臣は日本の態度を正当化した。電報の問題に関しては、それは時期の複雑さからくる問題であり、また東京と違う場所を通じて出せないことによるのだと認めた。その上、領事デル・カスターニョに「当然」平和な時期と同じことはできないだろうが、「いろいろ大目にみて見逃しながら」スペイン人の利益に気を配ることを保証した。このような処置はデル・カスターニョにだけに特別なものなので、他の国に対しては秘密を守って黙っているようにと付け加えた。それは非常にありがたい答えというわけではなかった。須磨は無頓着とスペインとの友好関係と協力とがかかっていることに気づいた。だから東郷に送った電報では、不快感を示した:「こんな形で友好国との我々の関係の機会を浪費し、古傷を再び開くのに言い訳はない。近い将来、そのような反スペインの新聞記事の出版においてより確固たるものとして見られるように、適切な処置をお取りいただきたい。」こうしてよき時代は終わりを告げた。
日本と他の枢軸国との関係と比較すれば、状況はいたって普通のものだった。問題が発生するのに、旧植民地が日本の掌中にある必要はなかった。戦時下で増えゆく神経質な状況が盟友との関係をも不和にした。例えばムッソリーニは、日本が世界を支配することを望んでいる、なぜならば天皇はこの世における唯一の神であり、ドウーチェもヒトラーもこの現実の前にはひれ伏すのだとした白鳥敏郎大使の宣言に憤慨した。チアーノは、もっと落ち着いていたが、「本当に言語同断だ」と、向こう見ずな白鳥のこのフレーズを批判した。日本人は独自路線をとっていた。このようなとっぴな転化に、セラノは日本勝利のジェットストリームが自分に恩恵を与えるだろうという期待がはずれたのがわかった。それは失望だった。彼は最も微妙な時期にアメリカと不必要な論争に陥り、マニラ占領は、彼の期待以上に反対勢力の恐怖を確認し、真珠湾攻撃の地震は、リオデジャネイロ会議において証明されたように、彼のラテンアメリカへの努力が無に帰したことを示していた。セラノは日本の勝利のジェットストリームから恩恵を被るだろうと考えていたのだったが、しかしその勝利は時間が経つにつれてますます害をあたえるような悪臭を放った。結果として、日本との関係は、一般的な性質のものに伝染するようになった。そうして、初めて、1942年春に外務省と日本大使館との間である種の緊張が見られた。日本の前進の全てが、その弱体化の証明だった。
日本の勝利に告ぐ勝利の100日が経つと、進軍は止まり、敵は始めに予想されていたのよりもっと早いスピードで、その地方における戦闘能力の建て直しを始めた。連合軍はヨーロッパ戦線優位を決定したが、アジアは長い間隅においやられていたのではなかった。日本の進軍に対する抵抗への望みは増えており、1942年春・夏にアメリカ合衆国から太平洋へ送られた補給は、例えば、追加兵の数を含めて、最初の6ヶ月に、ヨーロッパに送られたものの2倍になっていた。
武装と増援の撤退とともに、日本軍の最も弱い側面を思い出させるような連合軍側の反日本宣伝が増えた。スペインはアジアにおける反西洋の戦い、長期間の損失の中で、ヨーロッパ的文化のための闘争を想定するのに影響を及ぼした。連合軍は日本の戦争に関するニュースに矛盾したデータを回すだけではなく、例えば、兵隊に打たれうるかもしれない罰のもとで、全ての白人は家の外へ出ないようにという命令について情報を流した。その上、当然のことながら、逮捕されるだろう白人に対する単なる第一歩である、と付け加えた。セラノ・スニェル自身はイギリス国営BBC放送によって行われた「心理戦」の成功、そしてそのスペインにおける「すさまじい影響力」を認めた。日本は敵のあまりに否定的な宣伝を回避しようとした、しかしそれに対抗できる手段がなかったと同時に、多くの公的メディアがそういった種類の反日本的ニュースを好意的に受け入れたことで、あまりできることはなかった。
1942年春には既に述べたように、セラノ・スニェルの外務省での右腕、フェリペ・ヒメネス・デ・サンドバルの更迭という、重要な出来事が起こった。ヒメネス・デ・サンドバルは、セラノのもとにあった外務省事務局の長で、外国の新聞に対する検閲を行っていた。その当時からスペインにおける日本人に関する公的な情報は明らかに保守主義的フィルターを通していたのがわかる。最高の攻撃力をもち、その当時までは勝利がずっと続いていたにもかかわらず、ファランヘ党の新聞は日本の勝利に関して絶対的な信憑性をもっていなかった。戦闘で日本が勝利しているばかりではないという最初の情報は、珊瑚礁の戦い(1942年5月6から8日にかけてのニューギニアとオーストラリアの海岸線での戦い)でのもので、実際日本に対する最初の批判を導いた。この戦いは日本の勝利を表したが(日本の戦艦一隻もはじめて沈んだが、北米の空母一隻を沈め、もう一隻を戦闘外に追いやった)、スペインは始めて、当然同盟国との連絡では自分たちの全体的な勝利を話す枢軸国側と連合国側の情報の信頼性を比べたのだった。日刊紙『アリーバ』では、その後「珊瑚礁海と周辺海域ミッドウェー島での二つの混乱した戦闘」に関するコメントが発表されるに至った。日本の海路進出の行き詰まりは、まだ最高地点に届いていなかった頃に既に感じられており、日本像に重要な変化をもたらすのとなった。:期待は以前のように輝いてみえるものではなくなった。日本はまだ敗北してはいなかったが、敗北はいつか起こるものとして見えていた。
しかしスペインはまだ日本の敗北を望んではいなかった。その理由の大部分は、「悪の帝国」に対するドイツ(そして青い師団)の決定的な勝利のため、シベリアのステップで奇襲攻撃が行われるようにという期待がまだあったからである。スペイン人はロシア戦線に対して日本が動かないことに対してますます不安になり、フランコ主義者が両国の友好にどのような様相が重要と考えているかを示して日本に行動を起こすよう圧力をかけるため、可能な限りのことを行った。結果、マドリードはシベリアにおける日本の攻撃を求める、明らかな提案の場となった。既に述べたように、フランコだけがそれを行ったのではなかった。イタリアやドイツの大使は、それぞれが「ほとんど同時に」、「戦争の終結を早めるために」須磨に中国やインドではなくソ連を攻撃することを提案し、新聞までもが、そのことについてますます直接的に掲載するようになった。(「日本はおそらくウラジオストックが体現する危険を遠ざけようとするだろう」)。1942年8月には、マドリードでは、まず日本が攻撃しなければ、自分で結果に対する償いをすることになると示されるに至った。「ソ連と日本の間の武装闘争の可能性。ウラジオストックは極東における危険地域である。日本に脅威を与えるばかりでなく、満州や韓国に対しても脅威を与える。アングロサクソン人は将来的な援助をソビエトと議論するにあたって、この切り札を使っている。」戦争の予想外の終わり方を前にストレスがあり、日本の落ちこみはますます明らかになっていった。
その他の二つの出来事で、双方の国は大きく友好関係を損なうことになった。この出来事は、双方の信頼の減少や、以前はお互い拒否していた別の国に関する情報を聞いたり信じたりする用意ができていたことに影響を与えたにちがいあない。まずひとつ目は、ヒメネス・デ・サンドバルの申し出であった。それは彼がまだセラノの外交事務の長であったときのことで、アントニオ・アウノス教授をバルセロナにおける日本の名誉総領事として任命する件に関するものであった。須磨は当時代表部を開く計画はないとして、それを断ったが、それは真実の言い訳ではなかった、というのも、戦争の末期には、バルセロナには2人の職員がいたからである。これで、総領事館は非公式な形で機能していたか、もしくは連合軍による接収場所から逃げた外交官が後にバルセロナで配置されたか、ということになろう。サンドバル自身知っていたに違いないし、個人的にあれほど外交情報の不法譲渡を行い、好意的なニュースをながすことによって、継続して日本の側に味方していたのにもかかわらず、見返りが余りに少ないことにひどく落ち込んでいたにちがいなかった。
第二の事件はかなりスペインの信頼性を損ねたし、金さえ手に入れられればどのような形でもよいのだという「金儲け主義」のスペイン像を作ることになった。日本の外交官が数名、リスボンから日本へ戻る途中で、フエンテス・デ・オルーニョのスペイン税関を通ろうとしたとき、交換銀行において、職員が全部で3400ペセタを日本人から取り上げた。日本人は外務省を通じて金銭の返却を求めたため、この事件は長い間決着がつかなかった。金を取り戻すことはできなかった、というのも税関職員はそんなことはしていないと否定し、支払い証明を要求したからであり、上司は誰一人として税関職員に返却要求を強く求めることができなかったからである。その徴用はスペイン行政の建物で影響を及ぼしたが、金は決して取り戻されなかった。関係者が外交官であったこともあり、事件はスペインがどうみられているか、またスペイン人と協力するのはどうかを考えるのに、否定的に影響した。職員は「金儲け主義」の数人であり、とにかくなによりも金を探していた。だから外交袋に入れられて送られたミキモト真珠が到着せず、キューバへむかうスペイン外交官にそれを調査するように求めて、袋が既にバーミューダ諸島で開封されていたという報告を受けたときも、それを鵜呑みにしたわけではなかった。この二つのエピソードは小さなことだった。しかし、相互の信用という決断の過程が変動していくのに影響した。人びとは二国間の率直な関係の欠如を思い出し、相互不信に落ち込んだ。重要度は低かったが、戦闘のニュースよりももっと長い期間影響力があったため、その反響は耐えられないほどになった。
その上、直ぐにファランヘ党が鼻にかけていた成功のひとつは宣伝されていたほど正しいものではなかったことが判明した;日本政府とカトリック教会の推定的に素晴らしいとされた関係は、さほどのものではなかったのだ。メンデス・デ・ビゴは東京から、マドリードへ3月末に「全宣教師が受けている不当で厳格な扱い」について情報を流した。この様相について異なる情報を受け取るに当たって、セラノ・スニェルの裁量が強い注意を喚起している。翌日、スペイン外務省はメンデス・デ・ビゴに「電報でより詳しく」日本における宣教師の置かれた状況について述べるようにと依頼した。結果として、外務省は無礼な行為の長いリストを受け取った。イエズス会のアルーペ神父、グアム司教のオラノ猊下、そしてサイパン島とロタ島の二人のスペイン人宣教師は、大使が具体化するに至らなかったケースのほかに、「この国の政治的に盲目な疑い」によって、「去る12月にスパイ容疑により異端審問よろしく逮捕された」のだった。おそらく意図的に、情報は誇張されていた。例えば、将来イエズス会総長となるペドロ・アルーペ神父は、1940年にスペインへ戻ったモイセス・ドメンサインの後任として山口の教区司祭となっていたが、1942年1月11日に自由の身になっていたので、この情報がマドリードに着いた頃には既に解放されて2ヶ月ほどが経っていた。またグアムの旧スペイン居留地のミゲル・アンヘル・デ・オラノ司教もまた、野蛮な扱いを受けたわけではなかった。日本軍が占領した月に、二人のネイティブ修道士が教会の面倒を見るという条件で、信者から彼を離すために、秘書とともに島を出ることを強いられたのであった。しかし、ひとたび目的が達成されると、司教はひどい辱めを受けることはなかったし、また日本に到着すると、自由の身になった。
しかしながら、メンデス・デ・ビゴが誇張したのは理解できる。大使自身、悪いときをすごしており、そのため通常より否定的に状況を判断せざるをえなかったこと、そして外交袋に入れず、電信でのみ送ろうとするとき、自分のものと矛盾するニュースを含むマニラにおける総領事デル・カスターニョの情報がスペインに着くのを妨げようとしたのだった。メンデス・デ・ビゴのメッセージは、とにかく、影響があった。なぜなら反スペイン批判を前に何もしなかったもの、カトリック教会に何の好意的行動もしなかったものとして非難されたセラノ・スニェルの孤立を導いた。結果として、5月初めに、セラノ・スニェルは正式にスペイン人の利益を擁護する役割に燃えて初めて行動し、日本との緊張関係があることを示した。二度ほど、それは行われた。一度目は東京の『報知新聞』のスペインがカトリック教を通じてその政治権力を拡大するために努力をしたとする記事に対する正式な非難であった。また後には、ルソン島パンパンガ地方で何人かの修道士が受けた扱いについて日本に公式に尋ねた。このような宗教に関する燃えるような宣伝効果を生き生きと維持することは、軽くはあったが、初めて双方の緊張関係を引き起こすことになった。
6. セラノ・スニェル失脚
そういった公式メモは関係の衰退をとめるのに充分ではなかったし、そしてそれはセラノ・スニェル自身の落日と重なっていた。スペイン人と日本人との連絡は1942年の夏以降、許しがたいまでに不愉快なものになった。戦前には主に将来への幻想と期待とに基づいて関係を維持することができていた一方、その期待が一度予想されていたのとは非常に異なる形で結実し始めると、火花が飛び始めた。双方の目的がどんどん離れていくにつれて、もう目標達成は不可能だと思う者が出ると、問題を減少させていた政治的庇護は弱まるばかりだった。また、連絡が増えるにしたがって、緊張もとめどなく増えた。その罪は特殊な事件にあるのではなく、むしろ関係それ自体の発展によるものだと考えられる。というのも両政府とも関係進展に満足していたからである。参考資料からは明らかに、1942年夏に友好国の間の緊張関係が口を開き、関係修復が不可能となる限界にまで達していった、と示している。その理由は明確であった、内政が連絡に干渉したからである。日本の場合、初めての日本人の帰還が交換船によってなされたことである;スペインでは、連合国へ方向を変えていく必要性がでたことによる。そうして自身の問題を相手側のせいにしなければならなかったのだった。
アメリカ大陸での日本の権益の擁護は直ぐに国内的な反響を持ち始めた。最初の交換船が日本に着くと、スペインの態度に対する反応は、スペインがアメリカ大陸における日本人居留者をいかに擁護したかをよりももっと進んだものとなった。なぜならば新聞の第一面に利害関係の描写を載せることで、スペインを内政の餌食にしたからである。「アングロ・アメリカンの悪魔」に対する日本の宣伝における主要な非難は、その人道性の欠如と限界のないその残酷性に基づいていた。それは日本の兵士の指揮を高揚させるばかりでなく、彼らの抵抗を盛り上げるのにも役立つ基本的な理由のひとつだった。なぜならば多くの兵士は、これから起こることとして頭に叩き込まれたように、残虐に死ぬまで拷問される以前に死を迎えることを望んだ。日本は無知な臣民がアメリカで受けると予想される虐待を強調するような情報であればどのようなものでも欲しかったのだ。だからスペインには、何らかの形で真珠湾攻撃の後に日本臣民が最悪のとらわれの状態に苦しんでいるということを確信させるようなニュースを認めるよう、期待されていた。しかしスペインはずっと、そういった種類のニュースを補うとアジアでとらわれている西洋人に影響が及ぶことや、また日本の権益を擁護する役割を担って以降ラテンアメリカで行われた新聞の強いキャンペーンにも反響が出るだろうと考え、そのような宣伝熱を促進することは気が進まないという態度をとった。代表権を果たし政治面での将来的な見返りを得ようとするスペイン側の動機は、たった数ヶ月で最小レベルに減少した。それにより、その仕事をきちんともしくはいい加減にやるかどうかというのは、それぞれの国在住のスペイン人外交官の職業性の恩恵に任された。結果として、節度によるにせよ合衆国を不満に思わせないためにせよ純粋な不注意であったにせよ、アメリカにおける虐待に関してスペイン人の下へ届くニュースはできる限りやわらかい形で保存され、もしくは伝えられることになった。日本がスペインという盟友からアメリカ合衆国や他の国々にいる日本人の苦しむ姿を確信させる情報を受け取ることを熱心に望んでいたとしても、マドリードは沈黙することを選択したのだった。
そうして、最初の交換船が着くと、新聞は、「非人道的扱い」「恐怖」盗み、拷問、暴力、強制収容所での生活環境の悪さ、殴打、ゆすり、日本の商店からの強奪などについてはなす、強制送還者の声明でいっぱいだった。これにより、彼らの利益の擁護のためにスペインがおこなったことに対する非難、十分な注意を払わなかったことに対する不満が噴出した。また、日本が選んだ送還者の何人かが帰ってきていないこともスペインのせいにされた。日本に戻るかどうかの決定は個人が行ったのだが、スペインが圧力をかけたので、彼らはアメリカに残り自分の国を捨てたのだとされた。民間の交換による日本人の到着は、まさに、公的な領域でのスペインに対する批判を噴出させた。
その上、日本国外務大臣東郷は、その雰囲気が影響を及ぼすままにした。スペインが調査やアメリカ合衆国政府との交渉に関してあまり注意を払わなかったと、直接スペインを非難した。彼の批判はどんどん急進化した。初めのうちは、強制送還者の身元の変更の目的で、在ワシントンスペイン大使、フランシスコ・ホセ・デ・カルデナスがアメリカ合衆国政府に騙されたからだとして非難した:「カルデナスはアメリカの騙しの意図にあふれた故意のある説明を文字通りにとったようだ。まったく信じがたいことである。彼には自分から態度をしめして、なんらかのよい説明をする能力がなかったのだ。」船が到着した後、東郷はスペイン人に対する非難のためにペンのインクを注入しなおし、強制送還者の宣言は「我々に全てうまくやっていると保証しているスペイン大使の情報の誤り」を示していると認めた。スケープゴートが必要だったのだ。関係を回復する可能性はどんどん少なくなっていった。
しかしこのような緊張関係を政府が宣伝を必要としていた点からのみ、説明することはできない、なぜならば新聞見出しよりもっと進んでいたからである。アメリカにいる帝国臣民に対する日本の懸念は、代表団への電報のなかにもあらわれていたし、臨時の仕事をする人間を雇ったり、代表を依頼する国を変えることになっても保護をよくしようという試みのなかにも認められる。スペイン人が行わなかった宣伝の肉づけ不足への失望とは別に、実際に日本臣民の状況を改善したいという望みも存在した。そのため、東京はマドリードにかわる選択肢を探した。それはバチカンであった。この目的で、「特にアメリカ合衆国での日本臣民の状況を全般的に」調べるようにと、1942年7月に東郷大臣は教皇庁日本大使に原田けんを任命した。交換に、日本人は占領地域における捕虜、特にカトリック教徒に関する情報を流すであろう。それは法的分野においても政治的分野においても困難な解決策ではあったが、ピウス12世は最終的に「戦争捕虜、交戦国にいる民間人に関連する情報交換」に「個人的に参加すること」を受け入れた。
このことは明らかに、日本が人道的作業の行方に満足していなかったことを示している:「我々の権益を代表する国(スペイン)を通じてアメリカ国内にいる日本人居留者についての確かな報告書を得ることは難しいようだから、バチカンを通じて正確で詳細な情報を手に入れられればと考える。」外務省は直ぐに事柄に長けているスイスのような国を代表国として選ばなかったことを後悔した、と同時に移民たちの状況を改善するために多くの外交官の力がいることを過小評価した。このような宣伝を非常に必要とした戦時の文脈においては、政治目的が人道目的を凌駕したのだった。
スペインの場合では、過程は別方向へいった。具体的な事実のせいで変化がおきたのではなく、むしろ、耐えられない状況を招き、双方の関係をもう引き返せないところへまでもっていったのは、様々な逸話であった。そうして、1942年夏にはフランコは日本と距離を置く国際的な傾向に追従することを決定した。ポルトガルや教皇庁のように、スペインが友好関係を保っていた体制は、時間の経過とともにますます日本と、またどんどん影響力が少なくなる枢軸国との緊張を深めていった。ポルトガルでは、チモールの「予防的占領」は日本軍による島の占領を呼び起こす目標を果たし、ポルトガルと日本の関係に、強い緊張が生まれていた。教皇庁の場合は、日本との関係は、日本が宣伝するカトリック教会への支援に対する教皇座の不信が増えるとともに緊張が生まれた。矛盾したニュースを受け取って、日本は教会が連合国へ情報を流しているのではという懐疑心を抱くようになり、またその中立性を疑っていた。最後に友人たちのそういった緊張関係の例として、イタリアのカトリック新聞連合が日本の大使に出した、在東京ドイツ人特派員の、日本のカトリシズムに対する不信感・「神道を通じて大東亜における宗教を統一する」計画に関するニュースを否定するようにという要望書が指摘できる。日本はだんだんとヨーロッパとのつながりを失っていった。
こういった一般的な傾向のほかに、スペインにとっては、日本との緊張関係は友好国というより敵対国の機能に近かった。日本がイタリア、ドイツ、ポルトガル、バチカンなどと対立しているのは、日本がアメリカ合衆国と敵対していることと同様に、スペインには影響しなかった。ファランヘ党員の幻滅や日本のフィリピンにおける活動に対する失望は極度に影響することはなかった、というのもそれは新しい要素ではなかったからである。
たとえそうなるとは思っていなかったとしても、フィリピンにおけるスペイン的なものへの考慮を日本が示すようにとした、フランコから須磨大使への申し出に見られるように、皆がその可能性を勘定にいれていた。むしろ、太平洋戦争勃発後、スペインが日本との関係をどのように見ていたかに関する新しい点は、その友好関係によって泥がかかってくるようになる、ということであった。アメリカ大陸におけるスペインに対する攻撃はスペインを困惑させた。リオデジャネイロ会議の失敗、日本の利益を代表することに対する新聞のキャンペーン、反アメリカ合衆国の傾向をもったニュースを流す宣伝の中心として機能した在ワシントンの大使に対する直接的非難などは、その例である。アメリカはスペイン政府を日本の仲介者として強く攻撃した。アメリカは内戦後のスペインで必要とされた生産品の供給のための鍵を握るのみならず、日本との関係を責めればこれ以上スペインが枢軸国寄りに肩入れして反応することはないだろうとわかっていたのであった。
アメリカ政府は壁際にマドリードを追いやるすべを知っていた、そしてスペイン政府は唯一可能な方法で反応したのであった:日本との友好関係を弱め、太平洋戦争という背後の扉を通じて連合国側へ近づく、ということである。それで1942年夏に、アメリカ大使を前に、フランコが枢軸国中で初めて離反することを選択したのが日本だった訳を説明できる。内戦の間はナショナリスト側の厳格な支持者でありスペイン研究者としても有名なアメリカ新大使、チャールトン・J・ヘイズが、が身元を自己紹介する間、総統は彼に、アメリカにはヨーロッパの平和こそが望ましい、というのもそれによって全戦力を太平洋に集中することができるようになるからであると言った。続けて、世界における戦争についての彼自身の理論からはじめのうちの方向性について述べ、まったく別々の戦争が二つあり、ひとつはヨーロッパにおける反ソ連の戦争、もうひとつは太平洋における反日本の戦いだと評した。ヘイズは驚いたに違いない、なぜならば到着した当時から、フランコ総統は明らかに日本の将来に限界を見ていたからである。日本はアメリカの敵であった、しかしフランコの友人たちの友人でもあったのに、である。スペインは、決定的に、これらの国々がスペインに対するのと並行して、日本に対峙することになっていった。ただし動機の違いやある意味もっと大きな内部的な意見の相違はあった:スペインは日本を援助しすぎている、しかしそのわりに見返りがないと感じていた。
その直後、日本はマドリードにおける日本の偉大なる擁護者ラモン・セラノ・スニェルを失った。軍とファランヘ党の困難な関係は1942年8月半ばにべゴーニャのマリアというバスク地方の聖地で起きたファランヘ党員の攻撃で終わりを告げた。事件後、陸軍大臣と内務大臣を務めていたホセ・エンリケ・バレラ将軍とバレンティン・ガラルサ将軍とが、セラノ自身と共に内閣を後にした。セラノはその上、ファランヘ党政治評議会長も辞任している。「娘婿」ではあったが、権力は失われた。彼の奉仕を無視するというフランコの決定を覆す可能性はまったくなく、それは非常に小さな権力のみでやってきたセラノが恒常的過程で消耗したすえ起こった当然の結果であった。
セラノ自身、日本への決定された支援を通じて自分の権力喪失を避けようとしていたが、しかし何の役にも立たなかった。その上、日本はオープンな形では一度たりとも対峙できなかったフィリピンとの関係をめぐる問題で、セラノを泥沼におとしいれた。日本を盾として恩恵をこうむろうというセラノの期待は全て無駄に終わった。真珠湾でのアメリカの敗北は決定的なものではなく、フィリピンの占領は言われていたように恩恵に満ちたものではなかった、またカトリック教会は宣伝にあったように尊重されてはいなかったし、またソ連との戦争は勃発しないままであった。決定的な形で日本を支持しながら、セラノはスペインにおける日本の利益の独占的な代弁者に、どんどん人の心が離れたものとなっていく日本という大義名分の擁護者となっていった。
日本はセラノのことをもっとありがたがってもよかったのだ。しかし日本はまったく彼を助けようとはしなかった。彼の権力がどんどん失われていること、ドイツやイタリアの盟友からの信頼も少ないこと、また彼の政治的手腕をもよくわかっていたので、日本はセラノを丸ごと信じていたわけではなかった。東郷茂徳外務大臣はセラノ・スニェルが1942年6月にムッソリーニとチアーノの支持と友愛を得ようとして、彼らはもうそのようなことはできなかったわけであるが、(また彼らはそれを望まなかったのでもある)、イタリアへ旅立ったときに、そう示している。ローマでなんらかの和平に関する転換を画策していると考えて、東郷はセラノ・スニェルに対して大きな不審の念をあらわにした:「彼の性格から考えて、セラノがこの情報について知っているに違いないのは確かである。にもかかわらず、なぜあなたに言い逃れを探しているのかを知りたい。特別な理由があるのか?私の情報のためにお答え願いたい」スペインの大臣は彼の友達であった、しかしあまりに緊張をはらんだ状況のせいで、日本人は何者をも信じることができなかったのだ。
しかし、最後の瞬間まで彼を支持したのは、日本人にとっては有効であったであろう。「娘婿」が天使だったからではなく、他に選択肢がなかったからである。セラノ失脚で、スペイン国内でも国外でも、日本とスペインの相互協力はほとんど決定的な終結を迎えた。なぜならばスペインと日本との相互の不信の間には、重要な相違があったのだ:片方が作業の能力を維持しようとしている間、もう片方はそれを大きな歩調で失ったのだ。セラノの後任、ホルダナ伯が中立へと方向転換したときには、日本政府には戦争を遂行する以外に方策は残っていなかった。人々は諦めなくてはならなかった。日本がますます遠のく最終勝利を手にしないうちは、スペインと協力する選択肢はないのだろう。戦争を遂行しながら、日本人は外交的解決策を捨ててしまっていた。日本にはトランプカードのエースだけが残り、掛け金を上乗せするたびごとに、そのカードの価値は薄れていくのだった。
第5章 厄介な友好関係
1942年9月1日、日本でもスペインでも外務大臣が失脚した。東郷茂徳とラモン・セラーノ・スニェルである。それは権力基盤の崩壊と軍との対立という二つの平行したプロセスが最高潮に達した時であった。日本では新組織、大東亜省の創設により、すでに失速していた外交力はさらに弱まることになった。スペインでは、ますます援助基盤の弱体化が明らかになる危機的状況の結末だった。ファランへ内部でもさえそうだった。
両国の進展の均衡はここで終わる。日本の外相の役割はスペインの外相と比較すると、たいしたことがなかったし、新大臣の谷正之の行動力は弱かった。翌春、重光葵に大臣が交代しても、日本の外交政策の基本路線に何ら変更はなかった。武力による問題解決という考え方が支配的で、政府はさらなる武力増強が必要だと考えていた。他の選択肢はあまり考えられなかった。どんどん狂信的になっていく国にとって、外交の役割はたいしたものではあり得なかったからだ。それとは反対に、スペインのホルダーナ伯爵の役割は重要で、さらにその重要性は増していき、スペイン外務省はますます強力になっていった。一つの理由は、フランコ政府の中で常にフランコと接触し、重要な役割を担っていたし、さらには、日本の場合とは正反対に、外交がますます決定的な役割を持つようになってきたからだった。スペインが、戦争による解決を拒絶し、枢軸国との友好関係から、中立に向けての方向転換をするよう指揮したのがホルダーナだった。彼は、谷よりも、後の重光よりも重要な役割を担っていく。
もっと難しい決定をも下す必要に迫られた。戦争が連合国優勢で進展していくなか、枢軸国寄りに深く傾いていたフランコ体制の外交代表として調整役を務めなければならなかったからだ。ホルダーナは、連合国の圧力、枢軸国の圧力、フランコ政権の野望との板挟みで、様々な意見が飛び交うなか、外交においてボビンレースの役割を果たさなければならなかった。ひょっとすると他の人物の方が上手くできたかもしれない。しかし、彼の前任者セラーノ・スニェルも、後任者のレケリカも、ホルダーナほど、沈黙のうちにすべてを遂行することは出来なかっただろうというのが大方の見方である。きわめて慎重な政策遂行が求められた。彼は経験が豊富であったわけではないが、大方の人に上手くやったと評価された。スペイン外交の方向転換は比較的スムースに進んだ。
対日関係は、中立へ方向転換をしていく一部分だった。日本に対する逡巡や緊張感が、サンタ・クルス宮でホルダーナが率いる外務省を特徴づける二面性を示していた。表向きは日本や枢軸国と友好関係を保ちながら、他方では、それまでの関係を精算する方策を模索していた。しかし、この時期の日本の重要性は、単に、将来の敗戦国に向けの政策の一例というだけではすまなかった。連合国側への接近のベンチマークの役割を果たしていた。スペインとのつながりがそれまであまりなかったのが、日本である。対日政策は、友好関係から中立に、さらに中立から次第に対立へと進んでいくという政策転換の試みの最初のケースだった。日本の軍事力は枢軸国3国の中で、一番弱かったというわけではないが、スペインの対日外交の変化は、もっとも迅速で完璧なものだった。スペインにとって、日本は、たった2年間で「よい」国から「悪い」国へと変わった。まず個人的な会話の場面から始まり、その後、公の場面に出て、最後には、内戦でフランコ側勝利を援助した国に対してと考えるとひどいと思われるような悪い国として非難された。ホルダーナの時代には、前任者や後任者の時代のように極端な状況にはならなかった。しかし、スペインの日本との関係の激変は、イタリアともドイツとも起こらなかったことだ。
きわめて急激な外交関係の変化を可能にするために、スペインは日本のイメージを完全に刷新しなければならなかった。太平洋戦争当初からあった日本に対する全く異なった2つの見解の一方である伝統的な見解が勝利したからである。この見解が支配的になった結果、スペイン政府の日本に対する公式な立場が、称賛よりもむしろ猜疑心になり、日本の軍事的勝利を切望するよりも、むしろ日本の拡張を脅威に感じるようになっていった。この変化を認めるのに必要とされたのは、日本への認識を様々な段階で複雑に変えていくことだった。まず、以前に認識された枠を壊し、次に友好関係時代に作り上げられた枠とは合致しない情報を再び作り上げ、そして最後には、新しい情報によって、日本についての情報と合致するような新たなる枠組みを作り上げた。短期間に心理的なアウトラインが再構成され、人々は日本について肯定的なニュースを待ち望むのではなく、それが否定的なものだと考えるようになっていった。日本の勢力伸張に対して、文化的にも人種的にも脅威を感じていた伝統的な見方は、日本びいきであったファランヘの意見に勝ることになった。枢軸国側の国々の軍事的に敗北し、国内でも権力が弱まっていったことから、ファランヘはみずからの敗北を認めざるを得なかった。ここでは1943年の春までを取り上げる。この時代、スペイン首脳部の一部の枢軸国側の軍事的評価はまだ高かったが、スペイン政府は太平洋において連合国の勝利の可能性が高いと考えはじめていた。
1 新大臣・新路線
1942年の秋以降、スペインと日本は外交面で、かなり異なった対応を迫られることになる。日本の場合には、この時期はすでに作戦の変更が決定的となり、防衛に向かっていった時代だ。夏の直後、日本軍はミッドウェイ海戦で失敗し、ソロモン諸島のメラネシア群島のガダルカナル島での重要な作戦変更を迫られる。この2つの戦いもいずれもが、敗北ではなかったものの、これらは日本の拡張政策の終焉を意味した。
日本がオーストラリア攻撃のために空港(滑走路)の建設を準備していると判明し、ソロモンでのアメリカ軍の攻撃が開始された。アメリカ軍は8月にその空港を奪取し(それをヘンダーソン・フィールドと名付けた)、しかし、日本軍は空港の奪還を試み、その結果、より血なまぐさい争いが起こる。日本は12月末には秘密裡に兵士を撤退させ、その試みを完全に放棄した。これは戦争における「ミカド」初の撤退だった。「ミカド」はガダルカナルを支配下に収めようとして、25000名の兵士、6000機の飛行機を失った。主導権の喪失だけでは終わらなかった。この後も、日本の軍事的敗北は続き、それはますます大きなものとなり、1945年まで続いていく。
日本軍が制圧した地域についての最大の関心事は、占領した領土をいかにして構造づけていくかだった。それは1940年の8月に初めて示された構想、大東亜共栄圏と呼ばれる大「東アジア」の共栄する地域を指す構想だった。当時の外相の松岡は、この構想をアジアの新秩序圏内に統合された国々を規定するのに用いた。満州国・朝鮮といったすでに制圧した領土から、将来的に制圧を目指していた国々を含んでいた。例えば、抵抗を続ける中国やヨーロッパでの戦争の結果、より熟成した果実として日本の手中に落ちることが望まれていた植民地諸国、仏領インドシナやオランダ領東インドが含まれていた。簡単に予測できることであるが、真珠湾攻撃後、この大東亜共栄圏という言葉は、ある地域にどのような一体感を持たせるのかということの意味は深く問われないまま、日本軍が占領したすべての場所を指すと再定義された。日本は、計画性を欠いたため、その支配下に落ちた新たな地域も、日本が直接支配するようになった地域であれ、その資源を十分に活用することはできなかった。日本政府は大東亜という偉大なコンセプトのもとに、集中した指揮権を押しつけようとしたが、その指揮権を用いることが出来たのは唯一プロパガンダにおいてだけだった。多くの領土間の水平的に関連づけていくというようなダイナミックな共同体を作り上げる可能性は拒絶した。なぜなら、そうすれば日本のリーダーシップが危険にさらされるからだ。東アジアの5つの地域の国の代表が集まって1943年11月に行われた盛大な会合(大東亜会議)のみが、多くあったプロパガンダの唯一の成果だった。日本の野望のうぬぼれが、共栄圏という幻想によって示された。まさに大山鳴動してネズミ1匹である。
さらに、内部での議論が噴出する。1942年11月1日、日本とその占領下の国々、地域との関係を調整する新たなる大東亜省が設置された。しかし、その結果は軍部と外務省の間の意見の相違がより鮮明になっただけだった。軍部が占領地域との外交関係を求める一方で、外務省は新組織に反対していたからだ。外務省が大東亜省設置に反対したのは、「日本外交路線の基本方針の統一」が崩れたら、占領国の独立を求めるという何度となくくり返された約束が反故にされたためだった。これは、あきらかに両者の権力争いだった。外務省はわずかに残された権力に固執した。多少の可能性が残っていた南米を別とすれば、政府、そして日本社会のなかで、周縁部に追いやられるなかで、何らかの政策を遂行する能力はなかった。1939年に米庁という新しい商務省の設置の動きがあった時には、根回しをしてその設置阻止出来たが、1942年には外務省は敗北し、大東亜省が動き始めた。外務大臣の東郷は、戦争が激しくなり、部下の外交官たちが戦あまり当てにならないことがあきらかになるや、辞任する以外に残された方策はなかった。外務省の役人がいかに疎外されていたかは、1944年の夏のサイパン陥落が隠蔽されただけでなく、それが日本の偉大な勝利だとして彼らに知らされ、祝勝会に招待されるといった事態が物語っている。外交官の影響力が低下する一方で、戦争という状況下、首相東条英機が内務省大臣・陸軍大臣も兼務するに至り、軍人の支配権がさらに伸張するように思われた。
軍部と外交のおかれた立場の違いを語るのは難しい。日本では、ヨーロッパでのナチやファシストほど、軍部が集中した権力を掌握したことはなかった。伝統的な農業を中心とした社会が産業を中心とする社会へ変換する中で、異なった政治集団同志の政治的緊張感や、こうした過渡期に独特の社会紛争を消し去ることは不可能だった。なぜならば、多くの場合、戦争によって加速化されたそうした争いはより先鋭化したからだ。イタリアやドイツの体制との違いは、日本では戦争の真っ最中の1942年5月に選挙が行われたことだ。しかし、より際だった特徴は、軍人たちが自らの目的をより容易に達成出来るような組織の設立に失敗したことだ。以前に、単一政党による政府樹立の目論見に失敗したように(大政翼賛会はその目的を達成出来なかった)、軍人が実施した議会選挙は、帝国主義勝利の大混乱の中で実施されたにも拘わらず、彼らが望んだような、十分な立法機関の刷新をなしえなかったし、自らが好きなように国を支配するだけの権限も確保出来なかった。つまりは、軍部は権力の掌握に失敗し、1943年以降、議員との和解を求めるというあきらめの姿勢をとった。戦争の間、反体制派はつねに潜伏していた。
戦争はスペインに急迫していたが、今となっては、一撃を回避するための努力をしていた。枢軸国と連合国側の勢力均衡は、それまでの予測とは異なり、スペインは、もはや1年前のように枢軸国側で参戦しようとは望んでいなかった。しかし、自らの意思に反して、近隣での何らかの軍事行為により、戦争に巻き込まれてしまう可能性も否定できなった。ホルダーナは就任以来もっとも難しい時期を送ることになる。2ヶ月後に連合軍が北アフリカに上陸することになるからだ。スペインの北にはピレネーにドイツ軍が駐屯し、南では二重の形で連合軍に囲まれることになる。一方には戦略的な重要地点であったジブラルタル海峡にイギリスがいたし、他方には、モロッコの大西洋岸に上陸後、東のスペイン領モロッコの国境近くに沿って進軍していく連合軍がいた。東での作戦の相対的な行き詰まりのあと、スペインは偶発的に起こるかもしれない軍事行動を考えざるを得なくなった。
しかし、スペインが抱える外交問題は、当時、フランコ体制が直面していたディレンマのほんの一部にしか過ぎなかった。伝統的な保守主義者がファランヘ党員よりも力をもっていた。そのころ、ファランヘは支持基盤のかなりを失っていたが、その一方で、当時、支配的だった保守派の間で激しい議論が起こっていた。その議論とは、スペインが王制に移行すべきか、大統領制になるべきかということだった。これは国内で起こった議論だったが、全体的な文脈では重要な問題だった。スペインが将来どのような体制になるのかという議論は二次的なものとされたが、当然のことながら、それはきわめて現実的な問題でもあった。ドイツはスペインの政策に決定的な影響を与えるだけの影響力を持ち続けていた。南フランスに駐留していただけではなく、スペイン国内に枢軸国寄りの意見を持つ熱狂的な支持者がたくさんいたからだ。しかし、かつてのイタリアのケースとは逆に、ドイツはスペインがどんどん中立に傾いていくの回避する方策はほとんど講じなかった。トゥセルによれば、「要するに、東ヨーロッパでも、ヒットラーはファシズムと同様の体制よりも、軍事体制を信頼していた。」枢軸国の政治的圧力から比較的自由であったために、フランシスコ・フランコはより長く政権の座にいることができた。そればかりか、王政復古を望む高位の軍人たちと、フランコこそが自分たちが生き延びていくための保障だという念をますます高めていったファランヘとの間で、フランコは再び自らを諸政治勢力の中心に置くことに成功した。フランコは長年の間、内戦の経験によってトラウマを背負っている人々に対して、内戦の恐怖(妖怪)を思い起こさせることに成功した。内戦を引き合いに出すことは、権力への要求をなだめることや、より光輝く未来への希望を中和させるのにもっとも効果的な方法だった。フランコはまだましなほうだった。フランコはスペイン国民の疲弊を利用していたのだった。
フランコはやっかいな対応がせまられる外交において、ホルダーナがセラーノ・スニェルとは違って、忠実で、なおかつ野望を抱いていない人物だということを知った。フランコは以前からずっとホルダーナを信頼し、周りからの絶え間ない介入にもかかわらず、就任直後から、外交政策の変更を自由にさせた。ホルダーナは、あまり性急ではない形で政策の変更をはじめた。みずからが全面的にかかわりながら、外務省の行政機構の再編を行った。政策決定権を外交の事務局長のホセ・マリア・ドウシナゲに集中させた。ドウシナゲは外務省の事実上のナンバー2として、すべての地域の調整を行った。その後まもなく、1942年9月17日から21日まで開催された閣議で、ホルダーナの決めたスペインの新方針がお披露目された。それ以降、スペインの方針は、セラーノ・スニェル時代の非交戦から、さらに一歩進んで、中立へと向かっていく。その一方で、反共産主義への戦いが、以前からの友好国であるポルトガルやイスパノアメリカ諸国、それにバチカンといった国々のみならず、大戦での中立国、スイス、スゥエーデン、アイルランドなどに、接近していくという目的で準備された。ホルダーナは内戦から引き継いだ構造に基づいた体制の仕上げに使う新しいソースを味付けする調味料を増やそうとした。ドイツは、数年前の枢軸国寄りの姿勢から離れた新しい「味」がまったく気に入らなかった。その一方で、連合国にとっては、これは、材料の古めかしい味を隠すことも出来ない茶番にしか過ぎなかった。これは誰をも満足させられない料理だった。スペイン政府やフランコ将軍自身でさえも。しかし、世界秩序の新しい料理人たちに出すためには必要な移行だった。なぜならば、ヒトラーのかまどは絶えず燃料不足となり、十分な温度を保つために、「とても遅く、ほとんどわからないくらい緩慢な」形でいくつかの変化を成し遂げた。その結果は時がたってはじめてわかった。そのようにして行われたのが、セラーノ・スニェルの時期の産物である日本との協力であった。これが、この章で取り上げるまず第一のことだ。
2 協力は続く
日本は外務省から「寵臣」のセラーノ・スニェルが去ることに、一抹の不安を抱いていた。その証拠に、日本の外務省はチリ、アルゼンチンの公使館に対して、彼の移動にともなう反応についての情報を求めた。たくさんの問題を抱えた人物の失脚によってもたらされるであろう利益や、セラーノが始めていた援助は継続するつもりだとのスペイン側の意向など、日本側を安心させるようなこともいくつかあった。その上、フランコは秘密裡に、外交政策に変更はないだろうということを伝えた。また、少し後には、おそらくはアメリカ合衆国の雑誌の情報に基づいたものであるが、日本軍に向けての新たな賛辞で以下のように述べた。「日本人は120マイルをたった5分間休むだけで72時間進んでいくことが出来る。」彼は日本についての新たな具体例をあげるなかで、太平洋戦争で日本兵士が決して降伏せず、敵はそれが信じられないと思っているとも述べている。そしてこう付け加えた。「私は日本軍の強さに疑問を抱いたことはないし、とても満足している。もし、日本がこのままであれば、蒋介石打倒はたやすいだろう。」また、フランコはカルカッタへの爆撃に際して喜びを表明した。なぜならば、インドの産業の半分がそこにあったからだ。彼はこう尋ねた。「そこを完全に破壊して、インドへの攻撃拠点としようとしているのか?」
ホルダーナは彼なりのやり方で、日本に対して誠意を示し始めた。かなりの部分は大臣としての最初の任期中にすでに作り上げられていた友好関係からだった。例えば、日本使節団との晩餐会でスタッフと「親密な」会話を交わしていた。それは、極東でのボルシェビキ化を回避するための組織としての新しい大東亜省と見解を共有するものだった。ボルシェビキ化については内閣にも説明していた。また、報道されていた日本の軍事的勝利を称えるメッセージを送った。ニューヨークのスペイン領事のフィリッピン亡命政府の晩餐会参加へを認めなかった。もっと重要なのは、諜報活動と利益代表が活動の継続を認めたことだ。
さらに、1943年1月4日の最初のNO-DO で、ボルネオから帰国した軍の天皇裕仁の前での勝利パレードのニュースを流した。アリューシャン列島への日本の上陸2週間後、報道記者は日本について当を得たイメージを伝えた。「日本は480万キロ平米を征服した。」そして、同年4月には「日本は延安地方から共産党ゲリラを駆逐した」と伝えられた。日本は、スペインは味方だと信じて疑わなかった。
しかし、ホルダーナは就任当初から前任者とはかなり異なった行動をとった。スパイ網に関しては、あたかも何も知らないかのように行動すると知らせ、実際には、そのまま機能させ続けた。論理的に考えると、状況を大きく変える理由はなかった。実際に、スペイン人が入手した秘密情報は、日本に届き続けた。TO 網から届き、アメリカ人によって解読されたのは9月に9、10月には8あった。不安定な時期に、まずまずの数だ。8月の21メッセージでなく、同1942年7月の10に匹敵する数字だ。おそらくは同じくらいの数が利益の代表でも行われていただろう。フィリッピン占領から発生した問題についても、ホルダーナは特別なことは何もしなかった。
変化の表れは、間接的な方法で到来した。最初の不協和音の知らせをもたらしたのは、真珠湾攻撃後、須磨に、両者の関係強化の必要を説いていたスペイン系諸国会議会長のマヌエル・アルコンという人物だった。ホルダーナの着任後まもなく、エフェ社が8月に配信したニュース、フィリピンでスペイン語が公用語から消え、日本語とタガログ語だけが公用語となり、英語は暫定的に公用語になったというニュースに対する懸念をアルコンは須磨に伝えた。須磨はこう言った。「スペインの政府と人々は(フィリピンにおけるスペイン人に対する)日本のやり方について、とてもショックをうけている。」これははっきりとした知らせだった。
須磨はそれぞれの目的が異なり、和解不可能になっている2陣営の板挟みになっていた。スペインと日本は、かつてそうであったように、異なった態度を示し、もはや個人的つながりや政治的同一性によってその相違を覆い隠すのは難しかった。かつてのやり方では通用しなかった。スペインでの猜疑心が増長する一方で、日本ではフィリピンの法廷におけるスペイン語の使用についての苦情に対応していた。他の言語は使えない裁判官や判事がいたので、スペイン語の使用は暗黙の了解だった。しかし、おそらくはスペインからの抗議に嫌気がさしていたからなのか、こう付け加えた。「この道は通らなければならない。私が思うに、スペインは気にいらないのだと思う。しかし、彼らは、今になって、我々が何をやるべきかについて指示すべき立場にない。」この法廷における表立っての許可はあまり大したものではなく、翌月、谷大臣はそれ以上の解決策を提示しなかった。「スペインが抗議出来ることはない。」彼は東京の大臣に対して、緊張感の責任だけを問い、(メンデス・デ・ビゴの非難にも拘わらず)昔と同様に上手い言葉だけを語った。「我々がスペイン文化を根こそぎにしようというつもりは毛頭ないといことを彼らに理解させなさい。」と述べた。確かに、スペインを落ち着かせるには、須磨の巧みな手腕にゆだねる以外の方策はなかった。
東京の援助なしでは、須磨にとって遺された唯一の可能性は、以前の時代と同様に、上層部からの援助を模索し、緊張感を政治的覆いで弱めることだった。須磨はホルダーナが以前のセラーノ・スニェルのような役割を果たすことを望んでいた。彼が自分が外務大臣として前の在任期間に、スペインが、反コミンテルン条約に調印するよう後押ししたことを思い出させた。これは、当時の西日関係の基本となるものだった。しかし、須磨は間違いを犯した。まず、ホルダーナについて誤った情報を得ていた。ホルダーナはフランコが反コミンテルン条約にサインしないようにありとあらゆることをした人物だ。2番目として、外務省とスペイン系諸国会議間の書簡によれば、マヌエル・アルコンと須磨との会談は、ホルダーナの知っているところで彼の指示で行われた。須磨はまた、ホルダーナがセラーノ・スニェルを批判し、「現実主義者、貴族、大企業家と多くの軍人」がものごとをひっくり返していると気づき始めていた。ホルダーナは上層部の緊張をほぐすための助けとはならなかった。
それどころか、日本に対してよりきっぱりとした態度をとる決意をしていた。1942年10月26日に日本公使館に口頭で伝えられた覚え書きがその証拠である。彼の着任からほぼ2ヶ月後のことだった。ホルダーナは「強い不快感」を表明し、フィリピンとの文化的関係の重要性を思い出させ(フィリピンが文明国になったのはスペインのおかげだ)、それとともにスペイン系の他の国々からの不快感を表明したばかりか、友好関係の終焉をほのめかして脅しをかけた。そして、良好な関係を再び作り上げるために、とても困難なことを提案した。それは、スペイン語を、日本語とタガログ語を補完する言語として認定することだった。数日後の11月2日、この新しい姿勢が、利益代表に関して外務省から報道機関むけの文書によって明らかになった。その文書では、「特に日本の参戦以降、中南米のいくつかの国々が数ヶ月前から、日本の行動に対して、スペインの代表部に対して繰り返し行っているキャンペーンがあり」、日本との友好関係から生じる問題点がはっきりと表されている。これは、おそらくはバチカンと協力して行った新しい態度だったのだろう。同じころ、バチカンはフィリピンの大部分を占めるカトリック教徒に対する日本の仕打ちに対して、苦悩を示していたからだ。そして、司教区の学校が以前と同じように機能し続けるようにと求めていた。日本は新大臣とともに再び最初から始めることが必要だと気づくべきだった。関係は再構築されなければならなかった。
須磨は利益代表についての報道機関への文書を見ていなかったので、かなり驚いたようだ。「この国において、このスペインの文書ほど乱暴な言葉を見たことはほとんどない。」スペインの世論の激しさを、マニラのスペイン語日刊紙、ラ・バングアルディア(La Vanguardia)—これはスペイン語で唯一残っていた新聞だがーの廃刊や、会社や教会への資金送付停止などといった具体的な事実によって説明した。その上、彼の上司なら、もっと受け入れやすかっただろうと強調した。「日本人は友人の言語を除外し、アメリカ合衆国のような敵の言語を認めたから、政府の理解の及ばないことになった。」とは言っても、覚え書きでは、ここ40年間の文化的同化への抵抗のみが言及されている。
しかし、実現可能な解決法は見つかっていなかった。須磨は過去に固執し、主として「対面を保つ問題」だと考え続けていたからだ。とは言っても、両国の友好関係が消滅するかもしれないほど問題は深刻だと警告した。「スペインは最後の一歩を踏み出す前に、きちんとした準備をしておくべきだった。」それより重要だったのは、日本がスペインから得るであろう利益がわかっていたことだ。「わかった、私たちにはもうスニェルがいる。新しい大臣(ホルダーナ)ともつきあわなければいけない。彼は白紙委任されている。そして、もし我々が彼に適合しなかったら、彼は我々の日本利益代表への援助をやめるだけでなく、スパイ活動においても我々への協力を認めるのをやめるだろう。」
であるから、須磨は、もし日本の傲慢さが続いて、スペインの要求に何ら応えることができなければ、日本がどうなるのかを明確な形で知らせた。状況をよく理解していた彼は、スペインの不満を和らげる必要性を日本政府に説得することを期待していた。スペインの協力の中断が、日本の戦争努力そのものにとって、否定的な結果を招くだろうことを示しながら、こう言った。(もう一度、この問題について考えて、私が提案するようにやって下さい)。セラーノ・スニェルの外務大臣時代の成果である、スパイ活動も利益代表も危機的状況にあった。この2つの援助は、政治的判断からはじまったものの、外務省における元フランコの弟の存在を越える展開を見せていた。とは言っても、最終的には、両者の関係が悪化し、その影響も受けるようになった。これは次の段落で見ていくことにする。
2.1 ますます難しくなる諜報活動
ホルダーナは日本のスパイ活動へのスペインの援助継続を容認していた。しかし、表だって援助を表明することは決してなかったし、前任者が引き受けていた危険を引き受けるつもりはなかった。外務省から後押しの欠如が、西日協力のきわめて重大な側面を徐々に破壊していき、機密情報によって、その情報を提供すべき組織の中でさえ、彼の名前はますます名誉なものとなっていった。そのようにして、諜報活動は、スペイン政府との距離が広がっていく中で、お金と引き替えに日本に情報を提供した数名の個人の活動となった。ホルダーナの着任以後の3つの事実から、この情報網が担わなければならかった機能の大きな変化を確かめることが出来る。3つの事実とは、公には知られていなかったということ、イギリスでの諜報活動網の終焉、そしてマドリードからの秘密情報部員との連絡が困難になったことである。
セラーノ・スニェルの解任で、情報網が不確実になるのは予見できた。なぜならば、「すべてが」セラーノの個人的な活動によって機能していたからだ。トップのアンヘル・アルカサール・デ・ベラスコが認めているように、セラーノが新たな命令を下すまで、情報を送るのを止めるようにと部員に命令したほどだ。10月4日のホルダーナはベラスコと会見し、着任以来日本のためのスパイ活動についてだいたい情報を得ている、そしてスペインの枢軸国との協力関係の政策に何ら変化をもたらそうとは思っていないと述べたことによって、スパイ網の状況は明らかになった。しかし、セラーノ・スニェルのふるまいはあまりに向こう見ずだったので、時には問題が生じていた。ホルダーナはベラスコに以下のように指示した。「表明上は私は可能なかぎり厳密に中立を保つつもりだ。私が情報網について何ら知らないかのように、遂行して欲しい。」方法については、以前のようにこれまでの暗号と外交荷物を使い続けることに何ら反対するつもりはない、と付け加えた。「しかし、もし何か問題が起こったときには、スペインの中立という立場がいかなる形でも危うくなることが決してないように、細心の注意を払うようはっきりと要望する。」
この情報については確証があるわけではない。アルカサール・デ・ベラスコが日本に流した情報なので、ひょっとするとでっちあげかもしれない。ともかく、スパイは「だます」というのが生き方だ。それが彼らが完璧に身につけていた技である。イギリス人がみずからの身を挺して確かめたことである。その上、彼らの立場を危険にさらした。ホルダーナとアルカサールの会談が実際に行われたのかどうかについては、ここにあげた発言以外の証拠はない。しかし、ホルダーナがそうに言ったと考えることも可能だ。一方で、セラーノ・スニェルが始めたことはとても難しいことだったので、ホルダーナがたとえ望んだにしても、彼の命令ひとつでやめられるほどではなかった。他方で、アルカサールが日本に述べたことは、ホルダーナの名前で、リアルプ伯爵が日本に提供した情報と適合していた。リアルプ伯爵はサンタ・クルス宮の諜報問題を担当していた行政担当官だった。「我々のスパイ網との協力は、以前と同じように行われる。しかし日本が全く何も知らないという姿勢をとってくれるように要望する。」最後に、このホルダーナのスパイ網に対する表面上の決定が、変化がとても緩慢であったためにほとんど気がつかれなかったという外務省のほかの行動と首尾一貫していたからでもある。情報は日本公使館に届き続け、ある時点ではホルダーナがスパイ活動について知っていたかもしれないという事実は相対的重要性を持っている。なぜなら、重要なのは、外務省内部での秘密主義だったからだ。ホルダーナが何も知らないかのようにするのは、あたかも本当に何も知らないかのようであり、他の人も同じように振る舞わせた。つまり、アルカサールに秘密情報を送るのをやめるようにそそのかした。
二番目に、イギリスの外務省から、外国貨物がドイツに機密情報を流す役割をしているのではないかという疑念に対しての新たな苦情が届いた。これは何も目新しいことではなかった。なぜなら、以前にも、ルイス・カルボ事件が起こっていたからだ。セラーノ・スニェル時代には、ロンドン経由でのアルカサールへの情報の流れが止まらなかったものの、ホルダーナの時代にはそうではなかった。もはや「不実なアルビオン」からしか情報は届かなかった。ロンドンのTOメンバーからの情報は、新しい大臣の着任後まもなく届かなくなった。マドリードから東京へ送られたメッセージの数の減少からも証明されている。したがって、8月に須磨からTOメンバーに送られた21のメッセージのうちロンドンからの情報は4だけだった。9月にはマジックMAGIC誌にも反映されたように、ロンドンからのものは2だけだった。その上、双方ともセラーノ・スニェルの解任直後の9月2日に東京に送られている。
三番目に、スペインからアメリカ合衆国の部員への秘密情報は特に大きな影響を受けた。東京からの依頼に対する2つの返信には、明らかにアメリカ合衆国にいる部員へ指示を送るのが困難になったかが示されている。ひとつは、東京から合衆国政府と国民が戦争をどう思っているのか知りたいと尋ねた件。もう一つはラジオ放送についての情報を求めた件である。前者のケースで、アルカサール・デ・ベラスコが渡したのは、スペイン大使カルデナスの書簡とされるものだった。これは、ホルダーナ自身が要求し、「全くの秘密裡に報道局長」から到着の瞬間に受け取ったとされるものだった。この文書に書かれていたのは、いかにその回答を得るためにカルデナスが熱心に動いたかである。彼は役人たちと多くの会談をもったばかりでなく、アメリカ合衆国国務長官のコーデル・ハルを昼食に招き、日本が欲していたテーマについてよりフランクな形で話し合う機会まで設けたという。2番目のケースは、アメリカ合衆国における日本のラジオ放送に向けられた信頼と関心の度合を知りたいというものだった。回答は、「部員の一人」とされる人物からのメッセージで、日本放送の傍受はいっさい禁止されていること、それが見つかればとても厳罰に処せられるだろうと結論づけられていた。後に、アメリカの反スパイ活動によって、これらすべてが嘘だったことが証明された。カルデナス=ハル会談は行われていないし、アメリカ合衆国には日本の放送傍受を回避するような弾圧もなかった。これが示しているのは、明らかに、アルカサール自身によってメッセージがねつ造されていたことだ。彼の情報の多くがあやしい出所からでていること、かなりの程度まで彼の想像力が情報不足を補っていた。組織として動き始めていたとは言え、当時、可能だったのは、定期的に情報を得ることだけで、彼は、その中から出来る範囲内で日本の要望に沿った形のメッセージをでっち上げた。
その間、日本はスペインでの情報収集のための枠組みを広げていた。スペインが好意的な態度であるということ、インフラが次第に整ってきたこと、,他に方法がなかったことという理由から、スペインの首都マドリードが、日本にとって情報収集に好都合なヨーロッパでの中心地となった。情報量は多かったし、さらに集まるかに思えた。1943年1月26日から28日までベルリンで開かれた諜報担当代表者会議には、スゥエーデン、スペイン、ポルトガル、スイス、トルコ、ブルガリア、イタリア、ヴィシー政権、パリ、バチカンで働く17名ほどの役人が集まっていた。この会議で、スペイン、ポルトガル、トルコが情報収集の「最前線」にあると認識され、また、表だって、中立を保っている複数の政府からの秘密情報を得たいという日本の提案にも拘わらず、スペインが日本の活動を援助している唯一の中立国であり続けているということも確認された。その上、自らが主要だと考えている情報機関の中で、ベルリンとソフィア(ドイツとブルガリア)とともに、マドリード(スペイン)が唯一、高速受信器を受け取っている場所だった。その受信器で、敵国にいるスパイからの情報を受け取ったり、英米間の通信を傍受しようとしていた。他方で、世論の支持を保ったり、秘密情報を得るのに、プロパガンダがよい方法だと考え、再び、スペインが中心的な役割を担うようになった。会議の席で提案されたのは、プロパガンダを効率的に行うために、東京とのコンタクトのための中心のオフィスは、中立国、出来うればスペインにおかれることが望ましいということだ。そして通信社や、新聞社の買収が考慮された結果、再び、スイスとスペインが取りざたされた。イベリア半島における戦争当初の安定した諜報活動の表向きの均衡は崩れた。マドリードの代表部がヨーロッパの秘密情報の中心地となった。
さらに、スペイン領モロッコでの活動が盛んになりはじめ、次の4月にタンジールに領事館が設置された。そこはマドリードの代表部の役人がよく知っている場所だった。確かにこの町は、スペインの帝国的野望にとってだけでなく、日本のスパイ活動にとっても重要だった。ここから、双方の陣営にとって重要になった町、すなわちジブラルタルでの出来事、海峡を越えていく船舶や護送船団を観察することが出来た。とりわけ、インドに向かうイギリスが観察出来た。そのため、日本は、フェズに「たかわ(田川?)」領事を送る一方で、「日本にとって、スペイン領モロッコの商業的・経済的重要性可能性が増した」という口実で領事館の開設を要求した。そのように見え透いた言い訳をしても、その要求を受け取るはずであったセラーノ・スニェルは気にしなかっただろう。しかし、実際にその文書を受け取ったホルダーナは、タンジール領事館開設の正式の許可を与えるのを遅らせた。まず、政府代表部のモロッコ・植民地局に答申を求めた。モロッコ・植民地局はテトゥーアンとの代表部の合併のみを提案した。その後、ホルダーナは後に行われる須磨との会見設定の返信をなかなか送らなかった。しかし、日本は自分たちで主導権をとって動き始めた。それは、連合軍の攻撃の結果、カサブランカやフェズに在住していた日本人が退去せざるを得なくなったからという理由も大きい。スペインは日本人のタンジール方面への避難を手助けし、日本からとても感謝された。しかし、それはまた軍事執務室の重要性を高めるものでもあった。1943年の春以降、正式の使命で、2月に事務官の大林書記生が送られ、この執務室はもはや公式に開設されていた。「アメリカ合衆国とスペインとの関係は、ある意味では安定していたからだ。」と須磨自身が述べている。「軍人の会、高等弁務官代理も含めた会合に参加した」タンジールでの日本人と、スペイン政府当局者との関係は、きわめて良好で、日本国旗を掲げて車を使用することすら認められたほどだ。
タンジールからの当初の情報は、ジブラルタルを通る護送船団の増加やチュニスへの攻撃などについてのものだった。時間の流れとともにその重要性は増していく。タンジールはアフリカでの唯一の観察地点だった。主としてアルジェリアでの連合国の統治を観察し、アメリカ合衆国がどの程度までヨーロッパでその戦力を用いているかを知ることが出来た。イタリアの降伏以降、ジブラルタルが再び太平洋へ向けての交通ルートとなり、タンジールの重要性は増した。どの船がインド洋を経由して極東に送られるのかを知ることが出来、紅海におけるドイツのスパイのデータと照合すると確証を得ることが出来た。これは1944年4月まで機能したが、この頃、日本の諜報活動に従事するスペイン人の状況はもっとも困難な時期を迎えていた。
2.1.1 困難なTo情報網拡大
スペインにおける日本への諜報活動の最重要部分を担っていたのは、アンヘル・アルカサール・デ・ベラスコを中心とする組織網である。理由は簡単である。日本は手探り状態だったからだ。徐々に、主たる敵であるアメリカ合衆国についての情報が必要になった。アメリカはかなりの反撃能力を示していた。あるスパイからの情報によれば、そのころ日本が欲していたのは以下のような点についての情報だった。軍事面では、アリューシャン列島の空港と海軍施設、ソ連との通信網、ワシントン州とアラスカを結ぶ道路網の情報を必要としていた。プロパガンダの側面では、アーサー・クロック、ドロシー・トンプソン、レイモンド・クラッパー、アーネスト・リンドリー、ハンソン・ボールドウィン、ジョージ・エリオット、プラット総督など蒼々たるコメンテーターの社説、「フォーリン・ポリシーForeign policy」 「フォーリン・アフェアーズForeign affairs」, 「フォーチュンFortune」誌などの主要記事を求めていた。ここからわかるのは、日本が敵について、あらゆる情報を収集する必要性に気づいていたということである。のは、解答能力が大きければ大きいほどである。そのため、「ルイス・カルボ事件」とニューヨークでのスパイの一人の脱落が原因で情報配信が失敗したにも拘わらず、アメリカ合衆国での部員の数の増加を主張した。ニューヨークの部員はホルダーナの着任以来、反スパイ活動の廉で捕まってしまい、最終的に情報を送るのをやめてしまった。アルカサールはこの機会を利用して、最低でも20名の人材が必要だと主張した。アルカサールは、政府の正式な代表とともに、定期便の飛行機を使って自らの責任と危険を犯しながら入国するジャーナリストもしくは諜報部員を送ることが必要だと考えた。そのために様々な偶然を装うことが必要だった。ありとあらゆる方法で、アメリカ大陸に部員が到達したが、その多くは表向きは失敗した。
もっとも安全な方法は、外交官フェルナンド・デ・コッベ・チンチージャのものだった。表向きの派遣目的はカナダ西海岸での日本の利益代表の保護増強だった。この任務はモントリオール総領事の指揮下でバンクーバーの名誉副領事のフランシス・ベルナール(Francis Bernard)が担当し、ワシントンのスペイン大使館員ペドロ・E.・シュワーツが手伝っていた。この任務を正式の領事に任せることによって、より効率的なものにしようとした。これは、セラーノ・スニェルの時代に考えられたものだった。それは日本の利益代表をするというスペインの役割から考えて当然のことだった。コッベは自分の仕事をする一方で、北太平洋における敵の行動についての情報を送っていた。その際に、出発の日取り、荷物、対日戦のための護送船団の方向などを示すために、援助を必要としていた日本人の名前を暗号として用いていた。
ホルダーナは着任後、カナダ政府に対して、その任務を遂行する外交官の承認状を出さなければならなかった。こうした状況下、他の政策と歩調とあわせるために、ホルダーナは、ポストの候補者を変更し、枢軸国よりも連合国寄りの人物のコッべを任命することにした。コッベはもうすでにカストロ・ヒローナの経済ミッションのお別れ会の際に、日本と多少の関係があった。こうしたホルダーナは、明らかなかたちで、スペインと枢軸国との関係から生じるかもしれないマイナスの結果を押さえようとした。メンデス・デ・ビゴに荷物をニューヨーク経由では送らないようにと命令するメッセージを送ったのと同様の方法で、全く疑惑のない人物を任命することで日本の計画をぶちこわそうとしていた。もし、アメリカがスペイン人の足跡を追い続けるとすれば、詮索されないようにあらゆる手段を講じなければならなかった。
それにもかかわらず、ホルダーナは失敗した。アルカサールがコッベを説得し、彼に秘密情報を送るようにさせたからである。アルカサールはホルダーナとの戦いに勝利した。コッベに何らかの形での諜報活動への参加を説得したからである。アルカサールは彼をバンクーバーにおける将来の諜報網のトップにし、日本にはさらにお金を要求した。須磨は東京にこう知らせた。「現在、協力と信頼を勝ち得る唯一の方法は、お金である。したがって、将来的には彼らに莫大な金額を払わなければならなくなるだろう。」その間、日本政府はその代表部に対して、どのような情報を集めて欲しいのかの明確な指示を送った。日本が求めたのは、北太平洋での通信網、とりわけ、千島列島とソ連に向けての通信網についての情報だった。コッベは1943年1月11日にコッべはマルケス・デ・コミージャス号に乗船してバンクーバーへと向かった。
バンクーバー到着後、コッベが何をしていたかというと、現地の新聞報道によれば、日本人拘留所への訪問と、領事館への短時間の滞在を別にすれば、贅沢なスポーツカーを乗り回し、町の有名人になったことだった。ただし、彼がマドリードに機密情報を送ったという証拠はない。アルカサールによれば、1943年3月以降、「船舶、貨物、武器、潜水工作員がいかにして、ベーリング海峡に沈没した日本の潜水艦の電気系統の部品から情報を引き出そうかとしているか」についてのニュースを送っていた。しかし、この情報は信じがたい。須磨が1943年5月に日本政府に伝えたところによれば、コッベのすべての通信手段は危うくなり、それ以降、須磨からカナダでのコッベの活動について、言及されることはなくなった。
確かにコッベは当初から困難な任務を任されていた。カナダ政府(オタワ)がバンクーバーの副領事からの昇進に対して疑念を抱いていたし、彼の赴任直後の1942年11月以降、カナダはこのスペイン人が要注意人物であるとの情報を得ていた。その結果、コッベの任命を取り消すことは出来ないにせよ、外務省は彼から外交官公文書袋の特権を剥奪し、彼から送る情報は、ヴィシー政府代表部のものと同様に、すべて通常の郵便で送らなければならないと命じた。それだけではすまなかった。なぜなら、コッベの着任が巻き起こした批判的な反応以降、スペイン人外交官を通じてのローマやベルリンへの情報伝達について、新聞の報道が相次いだからだ。彼のスパイ活動との関係は、それが本当であったかどうかは別として、公然の秘密だった。
おそらくこのためにコッベは、出来る限り疑念を抱かれないように細心の注意を払ったのだろう。着任後、スペインはドイツとの協力はしないと断言しただけでなく、常に、悪く解釈されるのではという不安から、物議をかもしそうな発言や状況に陥るのを避けていた。唯一の証拠はワシントンの大使館からモントリオールへと送られた郵便荷物だけだった。そこから、書留としてバンクーバーに送られ、1943年8月末にカナダの検閲によって差し押さえられた。カナダの諜報局は、封蝋で閉じられた封筒のなかに、秘密情報を送るための指示(2つの暗証番号、日本人の名前のリストは軍隊派遣、防御の設置、船舶の派遣についての情報が得られる意味のあるものだった。)、あぶり出しインクの作り方、それに1000ドルの現金を見つけた。その封筒にはあぶり出しインクでグルタボ・ビジャパロスとサインされた手紙が同封されており、その手紙には、マドリードの外務省の外交貨物係職員のアントニオ・ロサス・バルディア(もしくはロサス・バルドン)とマリアノ・イダルゴに情報を送るようにと指示されていた。コッベからの送付は大失敗だった。とは言っても彼のアルカサールとの約束についての疑念は残る。彼がマドリードからあぶり出しインクで送られたと日本人に伝え、またそれが後に差し押さえ品のひとつだということを考慮すると、コッベの情報網での役割は、単に日本からお金を巻きあげるための調整役に過ぎなかったのではないかと考えられる。
次に、アメリカ合衆国行きを命じられたのは、アルカサールの友人で、おそらくはカステホン(Castejón)(彼の名字のカタカナ表記では、カステホン(kasutehon)となっている)という人物である。、彼を大使館で空ポストとなっていた陸軍武官として派遣し、その一方で日本向けの情報を収集するという計画だった。しかし、アルカサールが最後になって日本に伝えた情報によれば、アメリカ大使館が彼を拒否したという。実際にはそのような要請は出されてはいない。公のルートでの日本向けのスパイ活動の失敗から明らかになったのは、TO情報網が権力の中心からどんどん離れていたことだ。ホルダーナはセラーノ・スニェルの時代に考えられた2名の候補者のいずれをも認めなかった。一番目の人物は問題を起こさないだろうと考えられた人物に変えられ、二番目の人物については、1942年8月に肯定的な情報が多くあるのを考えると、ホルダーナが、自分の前任者が「指名」した人物を選ぶより、そのポストをあけておくことを望んだのではないかと考えるのが妥当であろう。ホルダーナは情報網の活動継続は受け入れたものの、それを自分の政治責任として負いたくはなかった。
もう一つのスパイルートは、新聞社の特派員を通じてだった。こうしたケースでは、新聞社に特派員の滞在費用を支払い、特派員が記事と同じ紙にあぶり出しインクで秘密情報を書き、それを彼に送るというものだった。この計画は困難だった。ドイツがあまり乗り気でなかったし、情報は英語で送られなければならなかったからだ。しかし、利点もあった。それは、ビザを得て、なおかつあまり疑念を抱かれないでアメリカ合衆国に正式のルートで入国する数少ない方法の一つだった。
この方法で入国した特派員は2名いた。しかし、これもまた大失敗だった。その一人、ギジェルモ・アラドレンは、マドリードのアメリカ大使館で、ビザ申請時に旅行の真の目的を明かしてしまった。その結果、彼は二重スパイとなり、アメリカが直接準備した間違った情報を送り、それは東京に送られる時には特TO(特別なTO情報網)と銘々された。アラドレンが報復の対象にならないために、1944年夏、アメリカ合衆国の情報機関は、彼が自分を受け入れた国、アメリカに心から尽くしていたことと、アルカサールに送った情報は日本をだますためにアメリカが考えたものだったということだと示した。ただし、彼は情報の信憑性を高めるために、多少の真実を追加していた。もう一人の特派員は、敵側に行くよりは、お金を得て逃げることを望んだらしい。彼はアラドレンと一緒にアメリカ合衆国に入国したが、それ以降のことはあまりわかっていない。しかし、マドリードから東京に送られたメッセージの中に彼のものはないので、おそらくはスパイ網から抜けたのだろう。、ひょっとすると、FBIが諜報問題に積極的に動いていたと考えた人物のトーレス・ペロナとかいう名前の新聞特派員かもしれない。
東京の大使館の直接の詳しい調査対象をならなかった人物のなかには、いろいろな名前がある。ほとんどすべての人に関して、書類は1点しか残っていない。唯一、その存在が確かめられるのが、フランス生まれの、エンリケもしくはアンリ・グラベーである。彼は(コッベとともに)アルカサールが対米諜報網のメンバーとして認めた2名のうちのひとりである。後に、彼はガリシア人というふれこみでロヘリオという名前になった。おそらくは、ベラスコの個人的な友人で、それまではスペインのグアテマラ大使館で働いていた人物だろう。彼は外交官パスポートを持ち、1943年の4月にカボ・デ・オルノス号で、カディスからブエノス・アイレスまで行くことが出来た。そこからグアテマラに向かい、さらにサンフランシスコかロスアンジェルスに向けて出発し、彼の妻の叔父、セバスティアン・ドブと一緒に諜報活動をする予定だった。しかし、原因は不明だが、この新メンバーの派遣は失敗した。すでにその年の6月には彼はスペインへ戻りたがっていたからだ。これは、アルカサールの文書送達人の一人、セレスティーノ・モレーノへの手紙から明らかである。
グラベーの他に、マドリードの代表部と日本の外務省の間のメッセージを作っていた人物は「信じられる紳士」と命名され、1942年11月8日、空路メキシコ、ペルー、コロンビア、エクアドル、グアテマラへと旅立った。この「紳士」は「日本のスパイ網形成の援助」に同意した。そして日本はラテンアメリカで諜報活動をはじめたいと思っていた。しかし、情報収集の主目的は、アメリカ合衆国との関係においてあったため、日本は彼が基本的には国の北部に滞在していることを望んでいた。メッセージから判断すると、彼は日本からとても感謝されていた。しかし、マドリードを出発して以降の彼の行動については、ほとんどわかっていない。
チリの政治家で、造船、労働条件、政治状況について調査するためにアメリカに送られたラファエル・モレーノについては、わかっている。しかし、彼は後をつけられている事がわかると、仕事を辞めてしまった。アルカサールはまた、アメリカへの無料の切符入手のためにマドリードのアメリカの軍事武官と話をしたという偽共産党員を信頼しすぎたとも述べている。アメリカはスペインの共産党員を集めて、勢力とするためだった。このいいわけは成功した様だ。なぜなら、1942年8月の最後の伝達は、リスボンから船を待っている間に届いたものだったが、それ以上のサインはなかった。さらに、書類には、ロジスティック、メッセージ、財政の向上のために情報を送ろうとしていた電信専門家がでてくる。この人物については、もし仮に実在していたとしても、これ以上のことはわからない。アメリカ合衆国の諜報サービスはマガジャネス号船上で彼を探そうとしたが見つからなかった。おそらくは、間違っていたのか、もしくはひょっとすると須磨が望んでいたように、小舟で送られたのかもしれない。コッベ、カステホン、2名の特派員、ロヘリオ、セバスティアン・ドブ、信じられる紳士、偽共産党員、電信専門家は、アメリカ合衆国が日本に対して降伏するつもりはないと示した時に、情報網を拡大するための試みだった。しかし、これですべてではなかった。
マドリードでの日本の情報収集は、TO 諜報網の枠のみに留まっていたわけではない。アルカサール・デ・ベラスコが、日本に情報を売っていた唯一のスペイン人だったわけでもないし、日本はスペイン人以外からも情報を得ていた。様々な人から多くの情報が日本に提供された。たいていの場合、金銭が目的であったが、そうした情報が信じるにたる物だという十分な論拠はあった。戦後、アメリカ合衆国の諜報機関は日本が直接雇っていた人物を何名も特定した。例えば、灯台員のフェルナンド・グティエレスは、彼の兄弟のファン、ルイス、それにマルハととも、軍人「はせべきよし」に、ドイツに送ったのと同様の、船舶の航行に関する情報を送った。日本はさらなる機密情報収集を必要としていた。スペインの公式ルートからの援助が困難になったこともあったが、連合国側の手に落ちた領土を手放し、人手が余っていたこともある。新聞記者たちは、さらに、日本に機密情報を流し、アメリカの反スパイ分子はかれらの家が日本の機密情報の事務所になっていると考えていた。朝日新聞の特派員や、マドリードの同盟通信社の「いとうのぼる」や「こじまりょういち」などが疑われた。いとうのスペイン到着は1942年春、こじまが来たのは、ジュネーブでの労働会議の代表で来て以降の1944年の6月だった。しかし、きわめて明らかだったケースは、後述する「まつおくにのすけ」のケースだった。彼は1943年11月にマドリードに到着した。そして、皆が知っていたのは、「いしかわけんじ」が1942年以降、北アフリカで活動していた日本の秘密情報部員のグループを指揮していたということだっだ。彼はそのために、何度もリスボンを訪れていた。このデータが想起させるのは、この任務を遂行するのに十分な援助を政府から得られるスペイン人がこれ以上いなかったということだ。おそらくは、アルカサール・デ・ベラスコとの関係は、数ヶ月後には上手くいかなくなったのだろう。日本は出来る限り力を尽くしたものの、すべての望みを叶えることは出来なかった。
- スペインでのスパイ活動の評価
スペインでの日本の諜報活動の最終局面や、1944年以降にこの活動が生み出した問題について述べるのはあとに譲ることにするが、スペインと日本のこの時期における接触の真の重要性について、少しだけ考えておくことは意味のあることだろう。たとえ、その装置が、後にリーダーが主張したほど「完璧」でなかったにしても、その重要性を看過することはできない。情報の追跡と、ワシントンにとってメッセージの傍受が意味する利益を知りながら、スペイン人の言うことにあまり耳を貸さなかったの理由は、検閲をうけた「マジック・サマリーズ」の開始直後に、アントニオ・マルキナが書いた記事のタイトルにあらわれている。そのタイトルは「夜祭のスパイ」である。1978年にスパイ網の存在が判明した際、その批判に用いられたのは、彼の外見や風変わりな性格、以前にあったスペイン人スパイが騙した事件(ガルボがヒットラーを騙した有名な事件)、それにアルカサール自身の闘牛士としての過去までもが、情報網がいかにいいかげんであるかいう印象を作り出すのに用いられた。そうした中で、日本は捏造された文書を得るために惜しげもなくお金を使っていた。
この見解を支持する論拠はあるが、あまり強調しすぎるのはよくないだろう。アクセス可能な情報の大部分はアメリカ合衆国からのものであり、情報傍受係のアメリカ人スパイシガーの本国の上司への報告によれば、アメリカの情報網は合衆国における日本むけのスパイ活動について「とても完璧な書類」を持っていたという。シガーは判読不能のインクで書かれた手紙を所持していると述べたが、果たして伝えられた情報が重要なのかどうかについては何らの意見も受け取っていないと不満を述べた。彼はその点について何らかの見解を求めていた。おそらくは、アメリカは情報を握っていたにもかかわらず、第二次大戦後に日本むけ諜報活動への援助の横糸を解くことだけが出来、あまりはっきりとした見解を抱くことは出来なかったのだろう。
アルカサールが厳密であったことは全くないが、1978年にはTO情報網には30名のメンバーがいたと断言した。アメリカ合衆国に住んでいた2名(そのうち一人は1942年秋に逮捕された)、運転手とその妻(妻がメッセージを受け取っていた)、タラベラに1名、彼らのほかに、ルイス・カルボ事件が原因でその派遣が失敗した4名がいたし、その後の9名の派遣で、彼自身を含めるとこの数字20に近づく。これはおおよその数字であるが、、(もし、数名の、おそらくはスパイではないかという人が本当にスパイであったなら)尊重すべき数字かもしれない。しかし、その効率は、連合軍側の反スパイ活動の技術的・組織的成功によって減少してしまった。これは情報「網」というより、釣り針にすぎなかった。
他方で、外国人の作家たちは、アルカサール・デ・ベラスコ同様に、TO情報網を理解するのに、想像力やスペイン人についての常套句を最大限利用しようとした。たとえば、ロバート・ウィルコックスは、アルカサールの家で目にした彼の闘牛士姿の絵を思い出しながら、「アルカサールは祖国の最高の闘牛場で闘牛をし、名声を博した。しかし、より賞賛すべきなのは、彼にとっては、かき回すという名人技よりも闘牛への情熱がより支配的だったことだ。反ユダヤ主義は彼の闘牛界での芸名ヒタニートとあまり合致しない。さらに、外務省文書館に唯一残っている彼の文書(彼が出場するであろう闘牛場への周りの人々を連れていくための列車の要求)から判断するに、闘牛士としての彼の技があまりたくさんの人をひきつけたわけでもなかったし、公金をいかに使うのかについての考え方も常軌を逸していた。アルカサールの人格は、偏狭で、空威張りをし、女好きというスペイン人のプロトタイプと完璧に適合した。機能不全の責任はスペインサイドに押し付けられた。他の日本向けの情報網と比較することも必要性もあるだろうが、TO情報網全体と、マドリッドのトップであったアルカサールのパーソナリティーは多少切り離して考え、アルカサールが決して暴露しようとしなかったメンバーのこと、とりわけ、アメリカ合衆国にいたメンバーについて考察しておく必要があるだろう。諜報活動の動きを知るのは難しいこととは言え、主たる誤りを犯したのは日本側である。アメリカによって判読されたメッセージは日本の外交官が送ったものだった。
情報量に関しては、アルカサールが送ったものと、他の国々で日本人外交官が自分たちなりの方法で入手したものを比較すると、解読されたメッセージの機密文書雑誌マジックにいくつもの情報が載っていたのは、TO情報網からのものだけだったことがわかる。総目次に乗っているレファレンスだけを見ても,TO諜報網に関するものは、BU, D, FU もしくはFuji, I, Kita, MA, NC,PAといった日本人外交官が入手した情報のいずれよりも多いということが確認出来る。
しかし、質ということになるとそうでもない。日本に渡された情報のかなりの部分が全くのでっち上げだったということはもう既に述べた。敵に対して傍受をでっち上げたこともある。例えば、イギリス外相のアンソニー・イーデンからマドリードのホアー大使に向けて戦争についての意見を述べた電報とされるものがあったが、後に海軍が確かめた所、まったくの嘘だったことがわかった。しかし、アメリカ合衆国のG—2によれば、実際に日本に届いた情報の大部分が、雑誌や新聞といった連合国側のジャーナリズムから採られたものであったが、軍隊や物資の移動に関する情報の中には、これらの情報源からではない確かな情報がいくつかあったという。アメリカの諜報機関が確認したあるメッセージは信憑性の高いものである、1942年11月に送られた情報にはいくらかの真実が含まれている。
アルカサールのおかげで、日本は護送船団の出港や最高機密だったTNTの5割増しの威力をもつ爆薬RDXについての情報を入手できた。また、スペインで1942年8月に得たニュース、アメリカ合衆国がソロモン諸島方面への部隊増強を行っているというニュースを入手し、アメリカ合衆国の戦略にとってのソロモン諸島(すなわち、ガダルカナル島)がいかに重要であるかを知ることが出来た。また、他方、アルカサールを通じてではなかったが、須磨大使は連合軍のアフリカ上陸を察知し、アフリカのスペイン人領事が入手したオランでのアメリカ合衆国の船舶の動きについての情報を流していたが、これは「基本的には正しい」ものだった。連合国側の反スパイは、TOの情報を「つじつまのあわないもの」だと定義づけた。本当の情報が足りなければ、自分たちのイマジネーションでメッセージを補完した。しかし、これらのメッセージにはきちんとした根拠があることを否定したことはなかった。
とは言っても、騙していたのはアルカサールだけではなかった。例えば、アンカラから届いたIの情報も、アメリカの反スパイ活動にとって「評価するのが困難な」正確さをもっていた。意図的だったのか、それとも無知ゆえだったのかはわからないが、誤った情報を流していた。いずれにしてもおおむねトルコ政府の見解を反映したものだった。これと類似のことが、リスボンの日本のスパイから「かなりの月数」にわたる観察から確かめられる。アメリカの反スパイは「アメリカの新聞が支払った金額から判断すると」、情報の質の悪さに「幻滅」し、「そうした種類の印刷物の輸出禁止がされたことを、まだ知らないのだろう。」と述べている。日本が、ポルトガルに対して、スパイ活動に関連して与えた利益から判断すると、結果はひどいものになるだろうと予測された。「今日ではポルトガルは新聞の切り抜き事務所に毛の生えた程度のものだ。」これが唯一のケースではなかった。前述のスパイ、ホアン・プジョル・ガルシア(もしくはガルボ)はもっとはっきりしたケースだ。彼はリスボンから、電車の時刻表だけを用いて、イギリスの状況についての報告書を作成していた。これは7名の部員網で作成したものとされていた。ヒトラーでさえガルボの報告書についてそんな疑念を抱かなかった(彼には鉄十字が与えられた)し、トルコやポルトガルからの報告書に疑問がもたれたことはなかった。マドリードの日本代表団(つまりは須磨と三浦)は、以前に組織されたグループの情報を信じていた様々な代表団の一つだった。そうした情報の過ちを認識していたにも拘わらず、本国には情報網がいかに上手く機能し、それを誇りに思っているか伝え、自画自賛した。
その上、敵の反応を観察すると、敵たちはアルカサール・デ・ベラスコに腹を立てていたようだ。1943年春、レティーロ公園での、おそらくはセラーノ・スニェルへの襲撃が示唆しているのは、将来の活動で脅威となる何人かの敵対者に加害を与えようとしたのだろう。同様に、1944年夏、連合軍側からのアルカサールに対して彼ら側に協力するようにとの提案があったことからも、連合国側は少なくともその活動に終止符を打ちたいと考えていたことがわかる。
そのために、こうしたメッセージが日本政府でどのように受け止められていたかを確認しておくことにしよう。
2.1.3 日本政府への信頼
まさに東京で、情報機関に対してお金を払っていた人々が、その情報をどう捉えていたのか、また、その情報が戦争計画の中でいかに用いられていたのかを知るのはもっとも難しいことだ。東京への情報到着は、正しいものであれ、間違っているものであれ、多かれ少なかれは作り上げられたもので、傍受されたものであれそうでないにしても、それは第一ステップにすぎなかった。その後、困難な決定作業があった。世界大戦がどんなかたちで終結するか、ヨーロッパでの戦況、アメリカ合衆国内での状況も不明なまま、政府は、戦地から部下が送ってくるメッセージに応じて資金を割り振らなければならなかった。敵の状況についての情報は、多くの場合、部分的なものにすぎなかった。したがって、高官たちは、具体的なメッセージに含まれているデータの信憑性を判断し、経験に基づいて分析するという必要性に迫られた。一つのメッセージが送ってくるニュースとは別に、予見される文脈が、それがきちんとしたものか、いいかげんなものなのかという評価を得るために、また、具体的な行動を実行に移すのか、それともほかの手段によって裏付けられるのを待つのかを決めるのに、決定的だった。スペインのもっとも重要な諜報機関 toの場合には、3つの要素がそのニュースを評価する際に重要だった。すなわち、第1に以前のメッセージを通じての経験、次に、情報提供している国とのイメージの側面、そして最後には、スポークスマンを通じての報告、つまり、補完する情報がマドリードの代表部から得られるかどうかである。
1 アルカサール・デ・ベラスコの一連のメッセージの信憑性についてが、よかれ悪しかれ彼の情報を判断する最初の要素である。他とそう異なるはずはない。この闘牛士のスパイは、スパイでなくても闘牛士でなくとも、内戦以降の貧しいスペインで生活をしていた他の人と同じ経済的な必然性を抱えていた。あるいは、スペイン以外の国であっても同じだっただろう。セラーノが後に語ったところによれば、アルカサールは「他の世界中のどんな理髪師よりも須磨をからかった」という。しかし、確かに彼は、当初、何らかの理由で日本の信頼を得ていた。理由はたくさんあるだろう。考えられる理由のひとつとして、ドイツのスパイとの関係があげられる。それゆえ、彼はイギリス関連の情報にアクセスできたし、キム・フィルビーが彼のメモ(libreta)の内容が間違いだと確かめた後の戦後に執筆した回想録で述べているように、外務大臣からの確実な援助があり、さらに、彼は完璧なまでの騙しの術をもっていた。ここでアルカサールのいくつかの成功例についても思い出しておこう。例えば、ガダルカナルに対するアメリカの関心、海軍から諜報網存続のために支払われたお金、軍事作戦のための役に立つ情報を提供したことへの賛辞、アメリカ合衆国において情報を蒐集する際に無敵だったことなどが挙げられる。
アルカサールは日本が望んでいたような情報を提供したことを付け足しておくべきだろう。1942年春のアメリカ合衆国の世論についてのカルデナス大使のメッセージとされるものなどは、その好例である。なぜなら、まさに崩壊しようする国のシーンを描いたからである。それは以下のような話である。「太平洋における日本の勝利は大きなショックを与え、アメリカの人口の70%が戦争に反対し、工場では政治状況に抗議するために、不良品の軍需品を作ることを決定した。イギリス帝国主義への反感は、反ナチス感情同様に強かった。中にはローズベルトよりも、みずからの目的を達成したヒットラーを好ましく思う人までいた。」こうした情報はでっち上げだった。しかし、OSS所長のビル・ドノヴァンまでが驚愕した。彼はこれについてこう書いている。「カルデナスと知り合いだったら、もう少し客観性を求めただろうに。」
日本が諜報活動に向けて支払ったお金はどこの国でも歓迎され、「アルカサール牧場」から発せられたメッセージは、日本では十分に考慮された。しかし、これは、彼の言葉が永遠の誠実さを持っていた例だと解釈されたということを意味しない。もちろん、彼の情報についての疑念は報告されているし、また、ミッドウェイ海戦での日本軍の敗北についての報告の際には再確認するようにとの指示が出ている。これは須磨がこれは確認するようにと指示している。しかし、日本は、よい結果が出ると信じて資金を使っていたとも言える。こうした信頼を暗示する別の例として、セラーノとアルカサールが、自分たちの信頼を高めるのに都合がよいと考えた場面で、その信頼感を自分たちのために利用しようとした例がある。これは、西日関係に影響を与えることになる。
1943年の当初、アルカサールとセラーノは、ソ連が対日攻撃を計画していると日本を納得させようとした。ベラスコによって、開催されたと知らされた和平会談以降、日本は警戒態勢になった。彼は、セラーノ・スニェルが秘密裏にローマに赴き、スペインでの王政復古の可能性について話をしたという情報を流し始めた。その後、アルカサールは元大臣(セラーノ・スニェル)の帰国を須磨に伝えただけでなく、日本に直接関係する驚愕すべきニュースを伝えた。それは、セラーノ・スニェルがある会談に出席し(チアーノ、リッベントロップ、それにアメリカからの代表者とともに)、そこでは和平協定の可能性について話し合ったというのだ。その上、アルカサールによれば、その会談は実りのあるもので、ある程度の原則が固まったが、ドイツが日本帝国抜きでアメリカと別に和平協定を結ぶことに反対したため、ぶち壊しになってしまったという。そのメッセージはこう結ばれていた。「(平和に関する)意見の不一致は、日本ぬきでやるかどうかである。」こうした大日本帝国と歩調をあわせていきたいと考えていたドイツへの言及にもかかわらず、この議論は、日本の不安をあおった。他の連合国に対して、孤立していることは出来なかったからだ。日本が一番おそれていたのは、イタリアの弱体化のあと、ドイツが単独で和平協定を結ぶことだったに違いない。
日本はまず、アルカサールの情報の真偽を確かめた。須磨はすぐにセラーノ・スニェルと話をした。セラーノ・スニェルはアルカサールの発言を基本的に裏付けた。そのため、須磨はすぐにこのニュースを東京と他のヨーロッパ諸国の日本代表部に知らせた。その後、日本はニュースの真偽を確かめ、行われたとされる会談についてより多くの情報を得ようと、多くのメッセージを送った。その会談はヴェネッチア宮殿で行われたとされ、特派員はニューヨークのフランシス・J.スペルマン枢機卿で、彼は2月中旬に、バチカンに向かう途中でパルド宮でフランコとも会談をしたとされた。さらに、セラーノ・スニェルは日本に、秘密の旅で毎日どんなことが行われていたかを詳細に知らせた。しかし、ほかに出席していたとされた2名の人物、リッベントロップとチアーノのいずれもが、この会談をしたとは言っていない。そして、ほかの手段でもこれを裏付けることは出来ない。この会談は行われていないのだ。そして日本がアルカサールの話はまったくの作り話だったと納得すると、その問題は忘れ去られた。ただし、スペイン人がデマを流すことが出来た理由、こうした活動が、スパイ活動や西日関係全般に及ぼすであろう結果について、もう少し踏み込んで考えてみる必要がある。
もうすでに述べたレティーロ公園での事件とされるものと時期を同じくして、アルカサールとセラーノが二人そろって嘘をついた理由はわからない。アルカサールが会談を裏付けるためにより多くの話をでっちあげたのに対して、セラーノはそういった「嘘」をつき続ける人を「歴史のゴシップ記者」との厳しい言葉で批判し、きっぱりと拒否した。アメリカ合衆国の反スパイ活動の諜報サービスの憶測が、おそらくもっとも的を射ているであろう。彼らの目的は、日本が対連合軍戦で孤立する可能性もあると脅し、日本がシベリア経由でソ連を攻撃するようそそのかすことだった。この解釈によれば、それ以前のいくつかのメッセージも納得できる。たとえば、1943年2月のTOのニュースは、ワシントンがアラスカ経由でモスクワに送った武器は、「行われるであろう日本攻撃の準備」のためにシベリアに送られたというものだった。その策略の出所はベルリンだと言われた。これは考えられることだ。攻撃があれば最も利するのはドイツであろうし、そればかりか、アルカサールの情報に報いることができるからだ。その上、こう解釈すれば、大島大使がこの件について話したときに、リッベントロップが見せたというなぞめいた微笑みも説明できる。
いずれにしても、スペインは、ドイツのこの考えを喜んで受け入れたに違いない。これはスペインの政治的直接的野望と完璧に合致していたからだ。ソ連攻撃は、戦争の流れを変えたかもしれない数少ない可能性のひとつだ。ソ連の敗北は、ファランヘとその取り巻きだけでなく、スペイン人の多くが望んでいたことだ。したがって、この会談のでっち上げは、スペインの国内状況や、再び政治の場面へ返り咲きたいと思っていたセラーノの野望と無関係ではない。権力闘争のなかで彼に残された少ない手段を用いることは彼の最後のあがきだったかもしれない。日本がソ連を攻撃すれば、かなりの場面で変化が起こり、枢軸国勝利の可能性も出てくる。その場合には、日本への持続的な援助が正しかったことになる。セラーノはすでに半年前に外務省から去っていた。しかし、まだ、外務省で指揮するという野望は十分に持っていた。
スペインのだましの結果は尾を引くことになる。しかし、それはファランヘのメンバーが望んでいたことではなかった。大枠のなかでは、ソ連攻撃の可能性についてはブーメラン効果があった。たとえば、須磨は日本とソ連の関係強化を提案した。その一方で、ウラジオストックに貯蔵されているという武器についての以前の情報に関しては、2月初旬にアメリカとソ連が軍事的に結託するのを回避するために「どんなことがあっても」アリューシャン列島の西で抵抗するという日本の決定がその原因かもしれない。もっと具体的な面では、だましの試みは、広義にはスペインのイメージに影響を与えた。とは言っても、ほかの誰にも知られることはなかった。少し後で須磨はスペインが和平の仲介者になろうとする試みについて、次のように書いている。「それはあまり支持されない単なる野望に過ぎない。あんなに威信のない国が、この戦争を終結させることができるなんて期待するなんておかしい。」個人的な場面では、特に、その主人公、とりわけセラーノへの影響が大きかった。なぜなら彼のイメージはもっと汚点のないものだったからだ。しかし、職業面では、アルカサールにダメージを与えた。彼の情報網の信頼性はきわめてゆらいだからだ。影響力のあるベルリン大使大島浩は、同僚たちに、情報問題に関してアルカサールとあらゆる関係を終わらせることの有益性について語った。「私の考えでは、将来も情報を収集し続ける目的をはっきりしないままにこの問題をそのままにしておくのは、本末転倒だ。
したがって、スペインは、きわめて危険な賭けをして、日本の信頼を無駄に使い果たしたことになる。日本が自分たちの目的に同調するようにと、必死な試みを行ったが失敗した。しかし、この事件から明らかになったのは、戦争の遂行の困難さで、自らの友人が失敗の理由であると考えるようになるほど、増大していたストレスでもあった。スペインも日本も、より重要だと考えていた昔からの信頼関係の重要性をより大きなコンテクストの中で、過小評価したいと思っていたので、当然のなりゆきだった。たとえ、1年前にセラーノ・スニェルがそういったぺてんに巻き込まれていなかったとしても、1943年春には、ソ連攻撃の必要性が増大したばかりでなく、日本と決別しても、大したことはなかっただろう。もうトランプのエースは最も簡単な遊びしか出来なかった。
2 日本人のスペインに対するイメージは、アルカサールが伝えた情報の評価を高めたりしなかった。スペイン人の仕事の能力と誠実さは、まず、はじめにありきなわけではなかった。戦時中ゆえに、長期に及ぶ信頼関係を作り出そうとは考えず、すぐに実現可能でより具体的な目的達成が目指された。生き残りをかけての問題だったので、みなが嘘をついていた。さらに、全体的な文脈の中では、文化の違いが、スペイン人が日本人についた一連の嘘の連鎖と歩調を合わせる物だった。もっとも、人々の関心を引き、早い時期のものは、フランコ将軍のものだった。彼は1937年に朝日新聞の記者に、内戦が終結したら、「田舎で家族との生活をのんびり送るために」引退すると述べた。彼がその牧歌的な未来についてこれ以上の発言をしたとは思えないが、この文章が示しているのは、新聞記者、しかも日本人の記者などどうでもいいと思っていたことだ。より重要な国の世論に対してならもっと注意を払ったはずだ。フランコの精神構造には明白な優勢順位があった。そして日本の優先順位が高かったことはなかった。
その上、須磨の着任は、スペイン政府の様々な層からのだましをより容易にした。須磨はマドリードの社交生活が好きで、よく出かけていたが、通訳を伴うことはほとんどなかったので、話の内容が理解できなかった。セラーノ・スニェルが回想録で、須磨との個人的な関係について強調するのは彼の馬鹿正直さだ。彼の親密さ、愛想よさを評価する一方で、セラーノは彼が「純真無垢だった」と述べる。須磨はマリアーノ・フォルトゥニィの偽絵画を騙されて、買わされ続けたが、セラーノによれば、彼が買った12枚うちの1枚だけが「本物だったかもしれない」という。外務省情報局長のリアルペ侯爵や、正直だといわれていたホルダーナも、表立って須磨をだました。アントニオ・マルキーナは次のように書いている。「略 須磨との会話で、大嘘が出てこないことはほとんどなかった。」
この無垢な日本人の話から明らかになるのは、植民地小説を通じて流布していた「黄色いサル」というイメージの存続だ。サルは善者にも悪者にもなれる。しかし、ともかく単純だった。日本人は単純で、白人が持っていた高いレベルの知能を持っていなかった。だから、日本人は親密な相手に対しては反対であっても、西洋ではごく普通のことなのだが、反対意見を表立って言うのが困難であり、結果的に嘘の悪循環を招いてしまう。しかし、これが意味するのは、日本人がそれに気がついていないとか、都合にあわせて知らんぷりをするということではない。たとえば、須磨が買った絵画コレクションは、彼の生まれ故郷の町の美術館で展示され、彼は思ったよりも物をよく知っていたということが明らかになった。たしかに、須磨はマドリード政府によって送られた彼の同僚の誰よりも多くのスペイン美術のコレクションを手に入れた。彼は人々が思っていたほど単純ではなかった。
3 日本でスペイン人の情報がどう評価されたのかを理解するには、マドリードでの日本人のスポークスマンの報告を考慮に入れなければならない。須磨、三浦、そのほかの協力者の信憑性が、アルカサールのデータのよしあしを評価するのに決定的だった。最初は、須磨の政治的重要性がこの信頼感を強めた。彼は東京に対して、スペイン人友人たちの長所を示した。おそらく、もっとも関心を呼んだ文章は1944年2月にセラーノ・スニェルについて語った次の言葉だろう。「彼は日本に対してこれ以上ありえないくらいの親愛の念を抱いている。」ソ連攻撃についてのだましの後、「これ以上ありえないほど」だったのは、須磨が友人を見つける必要があったからだ。彼はだまされたにもかかわらず、リアルプ侯爵からアルカサールまで、多くの人について良いことを言っていた。
政治面では、彼の意見はベルンやストックホルムの日本人外交官と一致し、ベルリンの大島大使とは意見を異にしていた。しかし、上司たちの彼への信頼性は明らかに失われていった。戦争の進展に伴い、彼は日本の外交組織図のなかで重要な人物ではなくなっていた。彼の報告書からわかるのは、彼の精神的なバランス感覚が太平洋戦争中に弱っていたということだ。それは、職務上の大きな変化、すなわち日本代表部が賞賛される対象から、もっとも屈辱的な批判を浴びる対象になったことを考えれば説明がつく。
お世辞から無関心への大きな転換、そしてそこから不合格、さらにはよりはっきりとしたかたちでの非難への転換、これが、彼の人格に深刻な影響を与えた。おそらくはそんなに大きな変化に準備ができていなかったのだろう。インドへの攻撃からロシアとの関係強化と同盟関係の調印、ムッソリーニ失脚の後にシベリアの海軍地域の侵略の必要性を述べるというめまぐるしく変化をする戦略を上司に報告したことは、そういった時期の、常軌を逸した個人的失望感を示している。1944年2月にはドイツ大使に「枢軸国の威信を高める」ためにスペイン人ガソリンを提供するようにとの提案もしている。その他に日本の兵隊の精神的の衝撃的な高揚を示す発言、すなわち、もし日本本土が占領されることがあったら、「1億の愛国人が人間の銃弾になる」という発言をした。彼のコメントはあまりに過激になり、普段なら慎重なマジック・サマリーズ誌の関心を呼ぶまでになっていた。同誌はこう結んでいる。「日本人外交官の中にこんなに洗練された人はいない。」彼の同僚もそれに気付いたらしい。しかし、彼を解任したり、外務省の中で直接彼に反対する人はいなかった。こうして彼の精神状態が不安定だと判明したことは、マドリード代表部の政治的重要性に影響を及ぼしたに違いない。リスボンとベルリンのみにあった軍事基地をイベリア半島に作るために、スペインとポルトガルで同盟して交渉が出来ないかとの問い合わせが東京からあったときに、その事態は起こった。戦争の最終局面で、アメリカ合衆国との和平交渉もしくはその企ての際に、マドリード代表部は疎外された。
ついに、日本はマドリードからの情報を疑うに足りる十分な理由を入手した。スペインへの信頼、文化的同一性はどんどん薄れ、スペインは故意にだましてきたし、日本はその機密情報のなかで、大切な情報とそうでない情報(小麦と藁)を見分けることがあまり出来なかった。しかし、スペインからの情報を受け取り続けることを望んだ。大島自身の言葉を引用するならば、日本は本末転倒だった。牛の前に牛車を置いていた。この決定の理由を知るのは難しい。しかし、超愛国主義的は雰囲気が蔓延していたそのころの日本を分析しなければ、首尾一貫した説明は不可能だ。
2.1.4 日本のナショナリズムの逸脱
太平洋戦争についていまだ残る主たる疑問点の一つは、なぜ日本人外交官が盲目的に自らの通信システムを信用していたかだ。日本人はコワレフスキーの暗号文システムは解読されないと信じて疑わず、戦後になっても、いかにしてその暗号が解読されたのかを理解できない人がいて、おそらくはより高い技術ゆえに解読されたものだったのだが、それを背信行為だと信じて疑わなかった。その一方で、戦争中は、通信システムの失敗についての報告は常にあったし、また、暗号化されたメッセージは多くの国によって解読されていた。
1941年夏の真珠湾攻撃以前からそうだった。そのころ、同盟国ドイツから、日本の参戦を回避すべく、日本とアメリカ合衆国との秘密会談について情報を得ているという知らせがあった。そして、もうすでにみたように、間接的な形ではあるが、新聞にもそれを示す記事が掲載されていた。出来るのは、ワシントンの代表部に尋ねることだった。ワシントンの野村吉三郎大使は、調査の結果、実際にいくつかの暗号は解読されていたと認めたものの何ら手段はとらなかった。
アメリカ合衆国との開戦後、新しいニュースが届いた。たとえば1943年、東京に数年間赴任、かなりの親日家のファン・フランシスコ・デ・カルデナス大使のスペイン帰国中に、彼は友人の須磨との個人的な会話で、いくつかの疑惑について語った。須磨は東京に次のように伝えた。「(カルデナスは)二度まばたきをし、とても用心深く、考えるように、ソフトな声で、半ば自分自身に問いかけるようにこう言った。「アメリカがこんなに早くこの事実(スペインの外交荷物で真珠を送ったことの傍受)を知ったのは奇妙ですな。日本の暗号は安全なのでしょうか。」」数ヵ月後、日本の駐リスボン公使森島守人が報告書で次のように述べた。「アメリカは日本語のわかる約200名の専門家を使って、捕虜に尋ねながら暗号を解読している。」しかし、いずれの場合もなんら手段は講じられなかった。スペイン人カルデナスのコメントを知った重光外相はこの件について「様々な角度から検討したが、敵がわれわれの暗号を解読した結果であるとは信じがたい」と述べた。アメリカの傍受が明らかになってから、リスボン代表部では一度だけ暗号が変えられた。新しい暗号は解読までにかなり時間がかかり、アメリカ指導部の気をもませることになった。
この行動を理解するためには、当時の日本の熱狂的な愛国主義を考察しなければならない。この熱狂的な愛国主義が、日本をどこにいくともわからない、必要性も目的もはっきりとしないままに開戦へと向かわせた。後に本間雅春将軍が述べたところによれば、東条は「国民の精神を高め、モラルを向上させさえすれば」すぐに戦争に勝利すると信じていた。この直感的な感情はヒットラーのドイツに比類できるものである。ヒトラーはすぐに戦争に勝利するのであれば、あまり長いスパンで戦争について心配する必要はないと考えた。最初の勝利の後、第三帝国が犯した深刻な過ちは、日本が主たる目標を実現した後に犯した過ちと同じだった。軍事省が征服した地域の兵隊の数を減らそうとしていた一方で、南方の軍隊の宿営地では、情報局を廃止し、それを作戦局に統合した。これは「連合軍軍隊への軽視から生まれた」と解釈された結果だった。勝利に酔いしれる日本は、軍隊を削減した。同じことが暗号コードの完全な見直しのために必要な費用に関しても起こってもおかしくない。解読されるおそれのある200万の暗号、その送付によっておこるであろう問題、新しいシステムが短期間しか機能しないという問題の解決費用が削減された。
しかし、ドイツの場合とは反対に、日本の決定システムはひとりの人間によるわけではなく、むしろ、西欧民主主義国家と類似したものだった。そのために、アメリカとの開戦を察知した後に、日本がさらに過ちを犯した理由を追及するためには、具体的な一人の人間について解き明かすよりも、より深い理由を考察することが得策であろう。とりわけ、その時期の激化したナショナリズムについてである。日本人はみずからの生き残りをかけて戦っていると考えた。したがって、外国人の言葉すべてに対して、極端なまでの猜疑心を抱き、日本人の行為のみが完璧に信頼するという傾向にあった。ほかの多くの場合のように、もう少し含みを持たせなければならなかった。
日本文化の独特の特徴に基づいた明らかな4つの誤りを指摘することができる。1)外国人が日本語を完璧にマスターすることはきわめて難しいと考えたこと。現在でも同じであるが、西洋人が日本語を完璧に話すと「へんな外人」と思われる。日本文化と、言語のもっとも奥深い言い回しへをマスターするのが困難だと考えたため、外国人と伝達システムを再構築する努力をするのがほとんど不可能だと考えたことに大きく影響している。デビッド・カーンが名著「暗号破り」で述べているように、日本人は自分たちの暗号が危険な状態になるなんてありえないという幻想に「陶酔」していた。2)他方で、自国人が自発的に日本人と戦うのを何とか理解しようとした。それは、移民の場合に多くあったケースだ。とりわけ移民の息子の2世たちだ。日本では、いかなる日本人でもそのためなら命を差し出すべきとされた祖国を守るための戦いと思われたものが、日本を出ると様々な異なった形で受け止められた。アメリカ合衆国在住の日本人の何人かは、交換船での帰国を断念しただけでなく、アメリカ人の暗号解読に協力した。とは言っても、こうした日本人はあまり複雑ではない仕事を引き受けていた。それも、もちろん2世のケースである。3)ドイツとの協力はあまり進まず、それゆえ日本もドイツも敗北することになった。ドイツが技術先進国であったにも拘わらず、お互いのある程度の不信感が払拭されたことはなく、日本は緊急事態にだけドイツに援助を求めた。ガダルカナル島の戦いが始まってまもなくがそうだった。オーストラリアのシドニー近郊のベルコネン基地から情報を傍受する必要性が生じた。ドイツへの疑惑は、リヒャルト・ゾルゲ(Richard Sorge)事件が原因である。ドイツ大使館に勤務していたゾルゲは、モスクワに、ドイツのソ連への攻撃にもかかわらず、南進するという日本の決定を伝えた。その発言は、日本でもドイツでも多くの人々を巻き込み、国内でも海外でも陰謀への恐怖をかきたてた。しかし、それはもう既にしめった土地に降った雨に過ぎなかった。4)最後に、諜報活動自体が日本ではあまりよく思われなかった。そしてそれはもっと困難な事態に陥った結果、際立つことになる背信行為と同一視された。部局の見解と矛盾するような報告書を書けば、危険な事態にもなりえた。そんなことになる位なら、部局によって支持された見解を持ち続けるほうが望ましかった。戦後、日本の役人自身が、かれらのスパイ活動は「いい情報はごく僅かしかなかった」ことを認めた。結局は、日本人は外国人嫌いなのだ。だから、日本人は自分たちのスパイコードが解読された際に起こりうる問題を回避するために何もしなかったし、雇っていたスペイン人の仕事を厳しくチェックすることもしなかった。
これとは逆に、スペインの伝統に固執する外交官は、彼らの報告書の何部かが、ワシントン、ベルリン、ロンドン、もしくは東京の執務室に届く可能性もあることをよく知っていたのだろう。その上、真珠湾攻撃の後、ワシントンは彼らに対して、彼らの進路を見張っているし、もうすでに言及したことだが、多かれ少なかれ根拠のある非難の記事が新聞には掲載されたし、外交貨物も開けられたりした。それに加えて、国務次官のサムナー・ウェルズは、1942年10月に、枢軸国のスパイがチリとアルゼンチンから、キューバとバルセローナ経由で情報を送っていると言って、スペインを非難した。外務省文書館に残されている文書から、彼らの情報伝達の能力の謙遜を知ることが出来る。例えば、太平洋戦争以前の1934年には、メンデス・デ・ビゴがスペインの「事実そうであったし、おそらく今後もそうであろうが、目的地に到着する以前に解読されている」暗号電報について指摘した。彼の文書で日本に対するもっとも厳しい批判は、鉛筆で書かれている。太平洋戦争中、陸軍武官のフェルナンド・ナバーロは任務地に到着するや、同じ様な発言をした。「(東京のスペイン代表部の)暗号を変えなければならない。なぜなら、絶対に(それは)知られていて、(であるから)保障がない。」その間に、あまり改良はされてはいなかった。新しい暗号とともに新しい助手を送ることは不可能だったので、「もし、文書が解読されているのであれば、慎重に、都合のよいと思うことだけ、そしてそこでの任務遂行に支障のないことだけを」伝えるようにと指示した。これはあたかも文書を送ることが意味のないことだと表明するようなものだった。
結局、諜報活動におけるスペインと日本の協力は、欠陥だらけだった。もっと重要なものになる可能性もあった。しかし、それは、敵自身や、超国家主義といった戦争から生じた要素から実現不可能となった。原因を作ったのは、つまるところ、協力を始めた人々だっし、それを支えたきた人々だった。平和が訪れるまで、その世界をこわすことはできなかった。その間、外交官及び日本とアジアにいたスペイン人は困難な時を過ごした。スペインの保護下にあった日本人も同様である。
- 日本の利益代表
在米日本人は反感が強まる中、苦難の時を送っていた。少なくとも、当初の蛮行は、やや穏やかな憎悪へと変化し、緊迫したなかでの状況の持続となった。すべてが、実際そうであったように、大戦の結果待ちだった。彼らは、「アメリカでの冒険」をまた始めるために大戦の終結を待ち望んでいた。多くの場合、数年の時間を強制収容所で失ったあと、ゼロから再び始めることになるのだった。
外国からの援助はほとんどなかった。バチカンでさえ、日本政府が望んでいたような、彼らの利益代表の情報提供者としての役割を担うことは出来なかった。スペインも、日本人に対する人道的関心を増やすことはなかった。それどころか、ホルダーナの時期には、難しい問題が起こった。それはセラーノ・スニェルの時期の場合のように、ついには非難になり、2番目の交換船の到着後、日本は他の選択肢を探さざるを得なくなった。スペイン・日本両国のこの面での進展を知るために、スペイン人が行なった最も意味ある仕事に言及することから始めよう。その後で、その仕事の主たる困難な点に触れ、最後に、他国が行った利益代表のための行為と比較することにする。
スペインが行った仕事のなかでもっとも称賛すべきは、戦中の2番目の市民交換である。最初の経験から考えて可能だとは思われなかった。第三国が自国民も含めるようにと繰り返し要求してきたし、アメリカと日本からの冷酷な回答があった。彼らは2番目の交換を認めない点で意見の一致を見、それが妥当と考えた。アメリカは投獄されている自国民がいかに大変な目にあっているかとの情報を得て、意見を変えた。そして、4月末に市民交換実現のための尽力を約束したカルデナス大使、それに東京にいたメンデス・ビゴというスペイン側からの圧力が上手く機能した結果、日本人の説得に成功した。ある部分では、日本政府は1943年5月に、当初の見解の変更を示した後で、2番目の交換を受け入れた。それは43年の9月上旬に実施され、それぞれの側のグループが自国へと到着した。この仕事のほかにも、戦争遂行に伴ってどんどん難しくなる問題の解決をスペイン人に求めるようになっていった。その中には、法的に考えてスペイン人にまかせるのにふさわしい問題ではないものもあった。例えば、インドでの日本人の扱いについてのイギリス政府への抗議から、満州国がイタリアへの代表部設置まであった。スペインは戦争の具体的な問題を前にして、想像上の解決策を探った。例えば、日本からソ連に「青の師団」のメンバーの消息について照会してもらうなどである。
しかし、日本が、セラーノ・スニェルに日本の代理人役を依頼した際に、スペインから期待していた「慈悲深い中立」は、与えられなかった。書類によれば、スペイン人外交官たちはホルダーナの就任以来の方針にしたがって、どんどんアメリカ寄りになっていった。多くの場合、日本人の前で、アメリカ当局の批判をしないようになっていった。おそらくは、自国の領土での日本からの報復を回避するためであった。とはいっても太平洋の向こう側での補償を回避するというこの目的は行き過ぎのように思える。アメリカでの日本人の権利擁護がスペイン人にとって、深刻な問題になったケースは一度も明らかになっていないし、アメリカの「再居住者」の担当特別部局は、スペイン政府を「確実で、忠実な友人」と考えていた。アメリカ合衆国に対して抗議する理由は確かにあった。アメリカは、日本人に対して、外国人官僚の前で文句を言う権利があるということを隠していた。そして、苦情が目的地に届くのを可能な限り困難にし、第一世代の日本人(一世)に限って利益代表の役割をしようとした。とは言えっても、かなりの部分が第二世代、もしくは第三世代以降の世代だった。必要以上の熱心さを見せるように駆り立てられる人はいなかったようだ。
その上、スペイン人役人の何名かはで自分たちの義務を果たすのを完全に放棄してしまった。例えば、ジュネーブ協定の条項のひとつ、収容者の戦争関連業務従事を禁止した条項を破ることを認めた。アリゾナ州ポストンの強制収容所の近くにカモフラージュのための工場を作り、そこで日系アメリカ人と、日本人をともに働かせた。これは、責任者が摘発しようとしなかった協定違反である。その上、その仕事を受け入れるべきかどうかをめぐって内部で対立があり、争いにまで発展した。スペイン人はほかの収容所への移送があったときに責任のがれをしようとしたし、暴力事件の際にも当局側の責任を減らそうとした。そして、ツールレイクやマンザナーの強制収容所での問題への干渉を避けようとした。これらの収容所では収容者の何名かは命を落としたし、ローズバーグ収容所で脱走騒ぎがあった際に、守衛が発砲し死者が出たが、それを「人種的反感」のせいだとはしなかった。役人たちはあまり細かい点に注意を払ってはいなかった。既に述べたように、日本の利益の保護はますます彼らの個人的誠実さにのみかかっていた。
たとえ彼らが民間人だったとしても、明らかに政治的文脈が、援助を必要としていた人への援助に影響を及ぼした。外務省の文書では、日本の利益代表がスペインとラテンアメリカの関係悪化に結びついたと認められているが、これがもっとも意味のある例だろう。しかし、もっとも明確に日本に対してスペインの問題を表明したのは、駐アメリカ大使のカルデナスだった。彼は同僚須磨とのスペインでの会見で、須磨に対して、報道機関で日本政府かの何らかのニュースがある時にはいつでも、「略 スペインは日本の利益を代表している」と付け加えた。また、彼は、その事実により、スペインの評判が犠牲になっているし、もしこれまで日本の利益代表をしてきたとすれば、それは「単にセラーノ・スニェルの日本への個人的な友情による」とも指摘した。
アメリカ合衆国での損害は、利益代表における政治面での障害のひとつにしか過ぎなかった。日本の報道機関でも、スペインの仲介を批判する記事が出ていた。状況を察した須磨はそれを検閲するようにと勧めた。なぜならスペインが代理を立てないままに利益代表を放棄するかもしれなかったし、批判が増えれば、それ以降の交換交渉を複雑にするかもしれないからだった。いずれにしても、利益代表とその役割を果たすもとになったスパイ活動は、スペインの仕事の最大の障害となった。ホルダーナは中立にむけての道のりで威信を高めることに関心を抱いていた。人道的な方策がその役に立つはずだったが、ホルダーナの関心にもかかわらず、スペイン領事館での決定や人員増加はつねに猜疑心をもって受け止められた。確かな理由があった。もっともわかりやすいケースは、カナダ、バンクーバー領事館のケースだった。そこでは、日本人の保護という名目で機密情報が収集されていた。これは以前にサンフランシスコ領事館やニューヨークのスペイン情報図書館( Biblioteca de Iinformacion Espanola)でも行われていたことだった。一方で、送金はいつでも疑われていた。ワシントンがアメリカ合衆国への送金を阻止するために見張っていたからだ。というのも、お金は利益代表のためだけでなく、スパイ活動の費用となることもあったからだ。同じことが、例えば、日本人が日本に行くために集められたお金でもおこった。それは、利益保護を援助するために渡されたお金であったにもかかわらず、アメリカ政府の疑いを招いた。ワシントンの大使館の金庫に置かれた5万ドル(おそらくは50万ドル)でも同じことがおこった。そのお金が当時保管されていた極めて安全な場所から出てしまうことを、皆が恐れていた。アメリカはそれがスパイ活動に使われるのではないかと恐れ、スペイン人は彼らに与えられる仕事に恐れ、日本人はそのお金のかなりの部分がスペイン人の手に渡ってしまうのではないかと恐れたからだ。結果的には、金庫は閉じられたままで、敗者は本当に必要としていたお金を受け取れなかった収容されていた日本人だった。
その一方で、スペイン外務省のスタッフの行動は、日本の利益代表を任されていた他国の役人と比較しても痛手をこうむることになった。具体的なケースの擁護のためにアメリカ人役人に借金をしなかったために、在ハワイ日本人の擁護を任されていたスゥエーデン人と比較しても、スイス人と比較してもそうだった。なぜならスペインの中立の伝統は認知されていなかったからだ。重要な任務を信用していない相手に任せるには、意見が一致するかどうかを見極めるために、尊敬と道徳心が必要だ。スペインの外交官が何を見、何を聞いていたのかを確かめるのは不可能だし、入手した情報のどれくらいを東京への報告書に記したのかを正確に知るのは難しい。しかし、外務省文書によれば、日本側の不満もあながち理由がないわけではないということがわかる。保護の仕事はほとんどいつでも疑念をもって遂行された。
日本政府は、ワシントンのスペイン大使館が「特段疑念も興味も示さず、われわれの質問に対する返答はしばしば遅れた」ことに不満を述べる一方で、アメリカの利益代表をしていたスイス人外交官に、強い尊敬の念、時には満足心を示していた。とは言っても、時には不満を述べていたし、彼らはあたかもアメリカの機関のように行動していると述べたこともある。新しい交換船の到着がスペイン批判のトーンを高める要因となった。須磨は問題を理解し、それを東京に伝えた。きっぱりと、きわめて教養のある言い方で次のように言った。「外国にいるスペイン人役人の何人かは、彼らの祖国の感情を反映して、我々の利益を守るときに我々が望むような熱心さを示してくれない。」一方、カナダの騎馬警察隊の一人は、バンクーバー領事のフランシスコ・デ・コッベが日本人をほとんど尊敬していないし、日本人を「物乞いの有色人種」だと形容したと証言した。
この事件後、最初の交換船の到着時と同様に、利益代表をしてくれる他国をさがす必要性が生じた。スイスにするべきだと皆が同意していたが、変更自体に不都合があった。一部には、相互関係への直接の影響、しかし、それだけではなく、ラテンアメリカでのスペインの代表部の政治的影響力が使えなくなるだろうということもあった。とりわけ連合軍に関してのイベリア半島からの情報のかなりの減少が予測されたからだ。人道的利益よりも、短期間の軍事的利益が優先された。よって、最初の船の到着後と同様に、妥協策はひとつしか考えられなかった。それはスペイン人に贈り物をして、彼らの仕事がより効率的になるように彼らのやる気をおこさせることだった。そのためにスパイ活動の資金を使うことが必要になった。日本政府は同意した。しかし、アジアに住んでいたスペイン人は以前抱いていた日本びいきの気持ちを完全に失ってしまっていたことも確かである。
3 戦時下日本のスペイン人
スペイン・日本の公式の協力関係によって守られていたのは、日本軍占領下のアジア地域のスペイン人外交官だけだった。毎月給料を受け取れると保障されていたわけではないが、彼らの状況は特権的だった。そのため、ありとあらゆる人、スペイン人だけでなく、戦時下の国の人々の、そしてそれが日本と関係があろうが、なかろうが、あらゆる種類の問題の対処をする必要に迫られた。その上、彼らは孤立していたため、彼らの間でのコンタクトは増加した。外国と連絡をとるのが困難だったのみならず、同じような問題を抱えていて、その上、そのような例外的な状況だったために、サンタ・クルス宮が一般的な指示以上を出来ず、外交官にそれをきちんと遂行するようにということを強要するだけの能力もなかったのである。
その地域からの出国は出来なかったので、地域内での移動があった。例えば、上海領事のアルバロ・デ・メンデスは中国でファランヘが起こした問題が原因で東京への移動命令を受けたが、妻の病気を理由に移動しなかった。また、エドゥアルド・バスケス・フェレルは、1939年1月に外務省とほとんど連絡をとっておらず、外交官としての仕事をほとんどしていないことが発覚し、スペインへの帰国を要求した。しかし、メンデス・デ・ビゴの彼の名前を乗船者名簿に載せるためへに尽力や経済的困窮にもかかわらず、最終的には交換船に乗船しなかった。前北京大使のフスト・ガリド・シスネロスは、内戦中にその職務から離れ、その時から、再び職務に就くことを訴えていたが、かれは、交換船に乗ってスペインへ向かった。しかし、外交荷物を持っていくことは拒否した。ホセ・ゴンサレス・デ・ゴレゴリオは、数年前には、帰国を拒否したが、1943年8月には、喜んで上海への移動を受け入れ、2ヶ月後には、上海で、中国の国民政府とのスペイン側の代表と総領事の仕事を引き受けることになった。領事のリカルド・ムニィスはそのポストに留まることになった。彼の仕事は、(1941年11月26日に火災があった)北京代表部の建物の管理だけだった。彼の仕事の大部分は、多くのスペイン人が居住していた天津のイタリア領事がやっていたからだ。それぞれの外交官が、他のアジアにいたスペイン人と同様にそれぞれの話があった。外務省は地域内での移動を命令するだけだった。
もっとも移動の少ない場所は、入国者も出国者もいないフィリピンだった。デル・カスターニョの唯一の変化は、「フィリピンのスペイン社会の代表」となったことだ。実際には彼の立場は変わらなかったし、可能性のあったフィリピン半島から他へ移動することもなかった。しかし、スペイン代表部がきちんと機能するようにと領事館の職員数は増加した。この増加は彼の愛するファランヘ運動を利することになった。ネグロス島の南のバイスで、領事と代表者、それに、警備員が任命されが、彼らすべてがファランヘのメンバーだった。お金を定期的に受け取る仕組みをきちんと作り上げたので、彼は、経済的にはもっとも優位な地位にある外交官だった。東京の同僚にお金を貸すすらもあった。そのほかにも、食料などと交換するために、フィリピンから煙草を送った。これが、メンデス・デ・ビゴとビダル・トロサナが、爆撃と食料不足の困難な状況下で受け取った唯一の援助である。なぜなら、スペインから日本へ生活必需品が送られることはなかったからである。スイスの外交官たちにはそうではなかった。
その代わりにマドリードから送られたのは、空軍武官だった。フェルナンド・ナバーロ・イバニェスがこの職務に任命され、東京に送られた。この任命はなぞめいていて、その事情は書類上は残っていない。理由のひとつとして、スペイン政府が、太平洋戦争について、より詳しい情報を得たいという願望があったに違いない。東京には外交官2名と、しばしば不在にする1名の長官がいただけなので、戦争の進展をきちんと伝達出来る専門家がいたほうが便利だった。日本政府は受け入れざるを得なかった。なぜなら、こうすることによって、マドリードでの武官の数をもっと増やすことが可能になったからだ。日本政府がヨーロッパの首都に再配置できる武官は少なくなっていた。それにも拘わらず、これは、人々を驚愕させるような任命だった。フォーリン・オフィスの役人は、彼らが乗る2隻の交換船の4席(本人、妻、義母、娘分)を予約するようにとのスペイン側からの要請があったときに、「このような種類の要請は先例がない」と書いている。
ナバーロ・イバニェスは連合国側の諜報活動のために送られたとも考えられる。スペインは、日本との敵対に協力しようとしていたし、日本について何らかの情報を集めようと申し出たのかもしれない。これは、彼のたどった奇妙なルート、日本に向かうのに、「この旅行についての指令を受ける目的で」アメリカ大使と会見したリオ・デ・ジャネイロを経由し、その後、ブエノス・アイレスとモンテビデオを回って、そこから、グリップスホルム(Gripsholm)号でモルムガオ(ゴア)とオールド・ゴアを経由し、その後、約1500名の日本人とともに交換船「帝亜丸」に乗って日本にきたというルートを説明する仮説でもある。イギリスが、当初の驚きにも拘わらず、秘密機関を調査した後で許可を与えたことへの説明ともなる。また、後に、イギリスが(日本生まれのスペイン人で、かつてのイギリス商務官の官長で、中国・満州国・日本の補給部隊の長に任命され、彼らの移動に同行できるように任命した)諜報機関の事務局長、ギジェルモ・デ・レメディオス・キムラのスパイ容疑での告発を許可したこともここから説明できる。これらのデータのいずれもが、ナバーロ・イバニェスの任命の決定的理由とはならない。しかし、理由としては挙げられるだろう。なぜなら、テレサ・プラナスの男のきょうだいも同じ理由で逮捕されたからだ。より確かなのは、彼(とその家族)の引っ越しが、彼の任務の遂行へと結びつかなかったことだ。イバニェスは戦時中にスペインから東アジアに運ばれた唯一の荷物を持っていたにもかかわらず、秘密情報送付のための新しいコードを忘れてしまったからだ。1943年11月14日に東京に着すると、ナバーロ・イバニェス自身がメッセージの暗号の変更が不可欠だということを強調した。しかし、その問題解決にあまり興味を抱くべきではない。なぜなら、すぐに、知っていることを新聞で知らせるとだけにとどめると提案したからだ。新しい暗号とともに、補佐官のエステバン・ジョルディー中尉をおくるという計画は頓挫した。。
日本は熱狂的な愛国主義の雰囲気に満ちていたため、日本在住の50名ほどのスペイン人にとってあまりよい環境ではなかった。皆が次から次へと起こる政治的変化に適応しなければならなかったし、彼らの個人的状況は商業分野に課せられた制限や布教活動への増加する猜疑心故に、急激に変化していた。商売人たちは小さな仕事をたたんで、大会社への就職を探す必要に迫られ、宗教関係者は心配し続けていた。とはいっても、遠く離れた場所に住み、日本人に責任ある仕事を任せたため、当局からは、あまり気にされない存在となった。公式にはスペイン・日本両政府は良好な関係にあったが、実際には、白人に対して戦争を宣言した国での日常生活を送ることは、かなりの困難な状況を生み出すことになった。メンデス・デ・ビゴのコメントは多くの西洋人が意見を同じくするものだろう。たとえ、闘牛に興味のない人であっても。「白い顔や金髪がいるということは、現地人にとっては、闘牛がケープを前にしたような反応を起こす。」それは日本だけでのことではなかった。
スペイン人居住者の間でもっともやっかいだった問題は、日本国内での移動の自由が制限されていたことだった。それは、他国人に対してよりも明らかに厳しかった。いくつかのケースでは、真珠湾攻撃以前からそうだった。また、別のケースでは公使館へ行くことさえ禁止された。その上、アメリカ合衆国が、米国内の日本の口座を凍結したことで、何人かは破産した。例えば、かつての陸軍武官でファランヘ代表者のエドゥアルド・エレーラ・デ・ラ・ロサの場合がそうだった。彼はさらに、短波ラジオがあるのではないかとの疑いで家宅捜索をうけた。エレーラのケースは、ナショナリズムの高揚を表す象徴的な事件だ。なぜなら、彼の日本の高官との関係も、近衛との友情も、ファランヘの代表としての地位も、警察の捜索を回避するために何ら役に立たなかったからだ。エレーラはファランヘが大使館と比べて明らかに低い「地位」の扱いしか受けなかったことを認めざるをえなかった。彼はメンデス・デ・ビゴに、彼らの間の冷え切った人間関係にも拘わらず、その件について知らせなければならなかったばかりでなく、外交官の家は特別扱いだったことを認識させられた。この違いは大使が享受したものだった。
メンデス・デ・ビゴの個人的状況もまた興味深いものだ。準備の出来ていない人物が被る苦悩を体現しただけでなく、彼がマドリードへ送った情報の影響も興味深い。想像できるように「ドン・サンティアゴ」は戦争中、当初の連合国よりの姿勢を変えなかった。これは、明らかに非合法行為への参加だった。週に4回、警察の執拗な攻撃から離れたところで持っていた傍受装置を使って入手した連合国のニュースを載せた小冊子を発行した。それを一緒にやったのは、アルゼンチン人の業務担当者だった。そして、テキストを元フランス大使夫人の沢田がタイプを打った。そのあとで、約20部を刷り、傑出した外国人や何人かの日本人に配布していた。これは彼の戦争終結への強い願望のもっとも顕著な形での表明だった。東京の北西120キロにある軽井沢の寒い居宅で、辛い時を過ごさなければならなかった。彼は軽井沢に送られたが、この町が東京の裕福な人の避暑地だと事実や、マリアノ・ビダルが東京で彼に対してその仕事をしていたことも、ほとんど彼を癒すことはなかった。戦前の参加していたカクテルパーティを懐かしく思ったにちがいない。そして、戦時中に要求した物資のなかには、ビタミンや薬だけでなく、「冷凍肉、かなりの量のワインとコニャック」が含まれていた。生き延びるという考えは、もうわかっていることだが、それぞれの感じ方によって異なっていた。
その上、彼の個人的状況が、マドリードヘ送る情報を変えていた。当初は、日本のプロパガンダと現実との違いに懸念を抱いていた。数ヶ月後には、スペイン向けの外交荷物の中に興味深い文書を入れていた。その中で、戦争の厳しさについてのみならず、日本での西洋への嫌悪感だけでなく、既出のことだが、米国大使グリューと彼の緊密な関係を語ることまでしている。しかし、1943年以降、スペインと日本の緊張関係が増加するや、関係をそれ以上悪化させない情報を送るようになった。そして時には、関係に水をさすようなデータは隠蔽することもした。たとえば、それは終戦の年、彼のまわりでの逮捕についてだ。両国の関係の文脈でのいかなる変化も、さらなる苦悩を生んだ。もうすでにかなりを失っていた。
3,1 大東亜共栄圏でのファランヘ党員とペロタリ
日本軍支配下でのスペイン人コミュニティーの大半は宗教関係者だった。バチカンによれば、人数は269名だったが、他のすべての計算を含めると少なくとも400名が、多くの国のミッションのメンバーとしてあちこちにいた。ある一定の場所にまとまっていたスペイン人もいる。湖南にいたアウグスティヌス会隠遁修道士(商丘市), 湖南のアウグスティヌス派修道士(長沙、吉首, 沣县)、湖南北部ののアウグスティヌス会の女性平信徒、福建(廈門、福州、福鼎)と香港のドミニコ会、福建のドミニコ会(女性)、安徽のマリアの御心会(黄山市),カプチンは江蘇と新彊、マリアのフランシスコ会は上海と山東に、フランシスコ会は陜西北部、延安に、イエズス会は安徽(安庆, 蕪湖)、清貧女性聖職者会(Hermanitas de los pobres)は上海と香港に、ベリス・メルセス会修道女は武漢に、パウロ会は香港にいた。ホルダーナ外務大臣の時期には、こうした宗教関係者の他に、2つのグループが大きな状況の変化にさらされていた。
それはフィリピンにいたファランヘと、中国にいたバスク出身のぺロタリ(彼らのうちのかなりがファランヘでもあったが)である。彼らはきわめて困難な状況に直面していた。フィリピンでのデル・カスターニョの協力は、1942年の10月で終わった。それは、日本軍の占領が永遠に続くものではないだろうという増えつつあった予感とともに、デル・カスターニョ領事がセラーノ・スニェルが去ったあとでマドリード政府の態度の変化を感じとったからだ。ある意味ではアメリカのせいでもあった。ヘイズはサンタ・クルス宮での交代劇を、デル・カスターニョが「スペイン領事として不適切な行動に巻き込まれて」いると口頭で抗議した。彼によると、デル・カスターニョのせいで、マニラでアメリカ人が1名、フィリピン人3名、スペイン人4名が投獄され、その中で、まだ、ベニート・パボンが投獄されていると述べた。デル・カスターニョに「中立国の代表として、特に、自分の立場をマニラにいるアメリカ人とほかの収容されている人々の苦しみを増大させるためでなく、むしろ和らげるために使うこと」を求めた。この知らせは表面上は何ら実効はなかった。もうすでにパボンが自由の身にあったからである。しかし、外務省の新役人はそのことを知らず、内政干渉だとして激しく抗議した。しかし、ワシントンからの警告は忘れられなかった。なぜなら、1943年4月末にスペインが日本とのあらゆる協力関係を終焉させたとき、デル・カスターニョに知らせただけではなく、彼に命令してただちにパボンの保釈を依頼するようにしたからだ。スペイン人が日本占領下にいたにもかかわらず、フィリピンではアメリカの息遣いが聞こえ始めていた。
さらに、太平洋での戦争は、アジアにおいて、真の意味で、スペインと深い関わりがある活動を復活させた。それはバスクの球技である。中国とフィリッピンにおいて、スペイン人、エジプト人、ブラジル人、キューバ人が参加する試合が連日行われていた。その球技には、「かけ」があった。かけによって、試合への熱狂は増し、企業の利益も出た。(券の15から20%)それは、闘鶏と同じような形で行われていた。球技は成功し、大都市ではいくつもの競技場がつくられるた。天津のイタリア租借地はフロントン(frontón) フォーラムが作られた。ハイアライの競技場は2箇所、一カ所は上海のフランス租借地に、もう一カ所はマニラに出来た。そのため、フィリピンには若いバスク人が大挙した。戦前にも戦後にも。そして彼らはその後の人生をフィリピンで過ごした。賭の仕事をにぎっていたのは、仕事を手中におさめていたのは、いくつかの会社だった。上海では北米資本の会社が最初に失敗した。(ブッカーという人物が1930年に始めたスポツ会社とともに)しかし、フランス租借地で1934年に銀行家ブーヴィエF.Bouvierが資金援助してこの国の企業と、再び始めた時には成功した。3000名収容のセンターオーディトリウムが連日平均2000名の観客を集めるまでになった。天津のイタリア租借地では、レバノンの資本が入っていた。ただ、フォーラムという会社はイタリアのものだった。マニラのハイアライ競技場は1940年に開場し(2000年に取り壊された)たが、アールデコ様式の優雅な建物だった。そこでは、総支配人(cogerente general)はエジプト人のアサドゥライン(Assadurain)だったが、すべてにおいて、かつてのペロタリであるテオドロ・ハウレギが重要な役割をはたしていた。1935年以降、スペイン選手及び競技場での選手の契約権を独占していたのはハウレギだった。
開戦と1942年のフォーラムの再開とともに、その競技は以前を上回る成功を収めるようになった。理由のひとつは、「かけ」がブラックマネーの逃げ場所の一つとなったからであり、それは、手っ取り早い儲け話や投機が時流れとともに重要になっていった日本軍下での戦時経済の反映だった。ハウレギと日本軍当局との関係は、もっと友好的ものでなければならなかった。仕事の継続を認めなければならなかったし、彼が、日本軍の占領下で、マニラから上海まで向かうことが出来た唯一のスペイン人であったからだ。その仕事の旅には、領事のデル・カスターニョの後押しがあった。デル・カスターニョはハウレギに感謝しなければならなかった。というのも25名のペロタリの多くがファランヘのメンバーとなったのはハウレギが熱心なファランヘ党員だったからだ。ただ気がかりは、中国で彼らによい給料の仕事を探せるかどうかだった。選手の契約交渉は、確かに、きわめて複雑で、デル・カスターニョとハウレギの間の関係が冷却化していった。その後、デル・カスターニョはよくある方法を使った。つまり、マドリードに電報を送って、グループのトップに彼の盟友ダニエル・グリディをおくようにし、それ以降、スペインからのペロタリの契約が領事館を経由するようにした。
フィリピンのペロタリがそこでのスペイン人社会のごく一部に過ぎなかったのに対し、中国のペロタリはそのすべてを占めていた。他のスペイン人居住者は、フランコ体制への援助を示していたにしても、その表明方法は、ミサへの参加や献金程度だった。それは司祭たちがやっていたことだった。しかし、それ以上のことはほとんどやってはいなかった。
例外がアウグスティヌス会司祭オクタビオ・クブリーアで、彼はファランヘの地方代表にまでなっていた。また、イエズス会司のアノトニオ・エグレンはファランヘの主任司祭だった。中国でのファランヘの創設者は天津にいたペロタリのアラメンディーだった。中国にはファランヘの拠点が二カ所あった。一つは上海で、そこには、中国の地方代表がいた。彼がより多くのメンバーを抱え、より高いランクにいた。もう一ヶ所が、天津で、そこではハレアギが指揮していた。それぞれの街で代表が任命されていた。1943年以前の中国でのファランヘの活動についての資料はあまりないが、フィリピンと同様だったのではないかと思われる。内戦中も内戦後もスペインに送金をし、慈善組織として「社会扶助」を創設した彼らと外交官の間には意見の相違があったのだろう。天津と北京が地理的に近距離であったにも拘わらず、7月18日を記念する行事が別々に開催されたことはその証左であろう。
アルバロ・デ・マルドナドが上海に新領事兼大臣として着任した1941年春以降、内部対立は深刻化した。フィリピンの場合とは反対に、スペインの役割についても、日本や他の列強についての批判に関しても、政治的内容はなかったし、むしろそれは組織的文脈においてだった。それは短期間の間に、直接的な形での賃金増額から、年金の増額までを実現し、ペロタリをマルドナドが懸命に守ろうとしたからだ。その結果、上海のペロタリはマルドナドの側についた。しかし、天津では同じようなことはおこらなかった。天津のペロタリたちはハウレギや北京公使館を任されていた外交官のムニィスの影響下にあった。
そのため、問題は主として個人的な展開を見せていった。マルドナドへの援助回避のために、ハウレギは天津のファランヘのリーダーであるフリオ・イバロラサを中国の地方代表にし、このような形で、天津において、どんどん問題を抱えてくる上海のペロタリに対して、より大きい影響力を持つようになった。マルドナドはハウレギの画策に対して黙ってはいなかった。マドリードのファランヘの外交部代表部に圧力をかけ、イバロラサの任命を回避すべく動いた。イバロラサが「文化のない人間で、ペロタリでcasas de juegoと結びついた人間」だと、明らかにハウレギの仲間に対して明確は形で非難したのだ。そのかわりに、マルドナドは書記官(canciller)だった彼の親類、アルマンド・サルディバルに中国でのファランヘのトップになってくれないかと提案した。マドリードのファランヘ外交部は、中国からの別途の情報がないまま、マルドナドの提案を受け入れ、中国のファランヘの代表としてサルディバルを送った。その後、マルドナドはイバロラサを解任し、天津の代表部を彼に忠実な昔のリーダーに指揮下の、アンドリニアを着任させた。
在留スペイン人同士の亀裂は決定的になった。外務省には全く異なる2つバージョンの電報が次々と送られた。そのため、上海にこの問題とはまったく関わりのない外交官ホセ・ゴンサレス・デ・グレゴリオが送られることになった。彼は、問題を解決する能力に長けていた。赴任地の満州国からより暑い土地に南下してきたデ・グレゴリオは、ほどなくサルディバルに反対するようになり、マルドナドと関係の深い天津の代表部同様に彼を解任した。彼がペロタリのパトロンに対して好意を抱いていたということは、対立をより深刻化した。なぜなら、1944年の1月19日にペロタリ連合の約35名のメンバーが、サルディバルに率いられて領事館を占拠し、デ・グレゴリオを人質とし、賃上げとペロタリの相互扶助に関連するかつての借金の返済を迫ったからだ。
やっかいな事態となり、問題解決には当地の警察が介入する寸前だった。しかし、この時点から、いらだちは終息へと向かっていった。領事館占拠はたいした暴力沙汰がないままに終焉をむかえ、企業家ハウレギはデ・グレゴリオを解放し、労働争議を解決するために15万ドルを保釈金として提供した。同様に天津でも問題があった。ペロタリが賭博場(casa de juego)の開設準備に反対していた。領事館の法廷はアウグスティヌス会士の検事(procurador)セレサルとイエズス会士教授のエグレン、それに領事によって構成されていたため、本当の権力と同調した宗教関係者の仲介と、マドリードからの圧力(ホルダーナ大臣からの電報)によって、活力を沈静化することができた。ペロタリたちは、戦争が終結したら彼らの労働問題を解決するという約束を取り付けただけで、保釈金を返還した。その間、警察は盗難書類を発見し、サルディバルを逮捕した。彼はもとファランヘ党員のマルドナドとともにこの小競り合いの主たる敗者となった。緊張感は彼に個人的、心理的に大きな影響を与えた。本省は問題から遠ざけるために彼を東京に移動させようとしたものの、それは実現しなかった。ペロタリは政治上の目標を持つことが出来たが、解決を目指したのは、金銭面においてだった。
この紛争の一件は、マルドナドが、彼と同じ政党に属するパトロンの搾取に対抗し、中国での外交官仲間二人のムニェスとゴンサレス・デ・グレゴリオの共謀を非難して、ペロタリの労働条件を守ろうとしたことが如実に現れている。これは、ファランヘが内戦以来、どのようにして変化してきたかを示す多くの事例の一つである。マルドナドが国家サンディカリズムのイデオロギーのレトリックに吹聴され、社会正義という理想を実現しようとしていた一方で、ハウレギは腐敗や、密輸などに対して、嫌悪感を示すことはなかった。それはファランヘにおいて別段不思議なことではなかった。マルドナドの解任はペロタリにとって敗北だった。なぜなら、第二次大戦の終結後、約束されたお金の一部が払われなかったからだ。その一方で、紛争はファランヘの限界を示してもいた。なぜなら、ファランヘが中国で創設されたのと同じ様に、つまりそれはハウレギの利便のためにということだが、まったく中国から消えてしまった。独自の通信手段を持たなかったために、ファランヘはすべての決定において、外務省に頼りきることになってしまった。
他方で、紛争は公共治安の問題にまでなり、スペインの外交関係のために政治上の暗示的意味が重要になってきた。フランコ体制は失望しながらも、その時期に日本とのかつての友好関係をする一掃する道を探った。望みうる最後のことは、ある部分では、領事マルドナドのせいで、その手から逃げてしまった日本の占領者の介入だった。そのため、ゴンサレス・デ・グレゴリオが任命後に与えられた命令の一つである「植民地の警察の介入を回避せよ」ということばに集約されるようなことが他の役人にも押しつけられることになった。ペロタリたちの給与よりも、サンタ・クルス宮での活力に、どんどん微妙になってくるスペインの国際的状況はかかっていた。。その状況は外交関係の刷新、とりわけ、以前の日本との協力関係を見直すように求めていた。次にこの問題について取り上げよう。
4 伝統的なイメージへの回帰
これまで見てきたように、日西政府の目的の相違はどんどん大きくなっていった。日本が容赦のないヘゲモニーを求めたのに対して、スペインは、配慮の欠如と他の西欧諸国同様に占領の結果の犠牲となり、ますます傷ついていた。当初はこうした両者の相違は枢軸によって、期待と、スペイン・日本両国が利益を得るであろう共通の目的を探すという隠れ蓑で隠れていて、違いのすべてを水に流していた。その後、民主主義勢力(連合国側)の勝利の可能性が高まったこともあり、フィリピンの一件以降、その違いが、国内においても、海外においてもますます際だっていった。そのため、もうすでに見たように、フランコはますます離れて行き、1942年6月、スペインの将来を日本の将来から切り離した。セラーノが外務省を去ってからは、フランコ体制の外交姿勢の枢軸国離れは決定的になった。
政治的相違を覆っていた隠れ蓑がなくなっても、日本のスペインに対する意識は変わらなかった。なぜなら、かなりの部分で、たとえ良好な関係になっても、この関係悪化とバランスがとれるとは思われなかったからだ。逆に、スペインにとって、ホルダーナ時代の始まりは、日本に対する意見が大きく転換をとげた時期だった。それは、1943年を通じて、実現していったが、これには分析が必要だ。なぜなら、新たなるイメージが、1944年と45年の政治変化を先取りし、それを正当化したからだ。
ホルダーナはフランコと同じ道をたどった。その道すじは、戦争中の1942年11月9日に日本から届いた唯一の荷物によって決定的となった。彼の最後の通信は、5月であり、最重要なものはすでに電報で届いていた。しかし、メンデス・デ・ビゴとその他のスペイン人の個人的体験の詳細、カトリック教会に対する誠意を欠いた攻撃、もしくは、フィリッピンにおけるスペインの行動を攻撃やフィリピン共和国の名称を「タガラ」に変更すべきだと提案した新聞の切り抜きなどは、ドーシナゲのために書かれた文書による要約から判断すると、重要な影響をもたらした。日本はその荷物の到着日までには、ホルダーナについては、セラーノの場合のように問題を大目にみることは出来ないとはっきりわかっていた。フィリピンでのスペイン人の扱いについての苦情、また、ラテンアメリカにおいて日本の利益を代表することを了承したと勘違いしていたという誤りを認めることは、たとえ、反スペインキャンペーンをやっていた「あか」に責任があるとは言っても、動かしがたい論拠となった。新しい大臣とともに、日本との政治的覆いは数日で消え去り、スペインは大日本帝国に対する批判を強めていった。
しかし、サンタ・クルス宮での変化のすすめからについては、ホルダーナの考えで、ゆっくりとした形で、新聞の第一面からは関係のないところで進んでいくことになった。彼自身がアルバ公に対して「いずれの交戦国にも知らせずに、しかし、結果的に中立に進んでいくような、変化を導入していくような慎重な政策」の必要性を語った。しかし、日本との場合には、変化はより早いものだった。そのため、1943年の2月末、ガダルカナルからの日本の全面撤退の後、連合国軍がメラネシアの他の地域への攻撃を始めようとしていたとき、ホルダーナはイギリス大使のサミュエル・ホアHoareに、彼とスペインが東アジアでの連合国の勝利を望んでいると打ち明けた。「我々は(ロシアに対抗するのと同様に)ヨーロッパの連帯という同じ条件で、アジアにおけるヨーロッパ権益の再構成を求める。そヨーロッパ連帯について語るとき、我々は経済的利便のみならず、我々の文化、白人種が実現した文明化という事業、我々の国があれらの東の国々(アジア)において実現した事、例えば、キリスト教の布教などを考えに入れている。これは、日本ばかりでなく、中国やロシアの勝利によっても消え去ってしまうことである。」ホルダーナはフランコの後追いをしていたのだ。事態を観察すると、彼の対日政策は、ドイツやイタリアに対するものほど慎重ではなかった。おそらくは、最後の結果として求めていたのは、中立ではなかったのだろう。しかし、また対日政策は試験台(試金石)としての役割も果たした。
対日政策の変更は、他国向けのものよりもより急激だった。おそらく、戦闘の具体的結果との関係はほとんどなく、それに対して許容されていたイメージの変化があったからだろう。その変化の2つは、主として外交面でのものだった。連合軍のプロパガンダの影響と、ロシアへの攻撃がなかったことだ。他の2つは、スペイン人自身の必要性と、内戦以前の「伝統的な」平時に戻りたいという要求から発生し、それは、プロパガンダにおいてもそうだったし、イメージにおいてもそうだった。つまり、太平洋戦争の位置づけの変化と白人種連帯という考えの再生だった。これらについて、詳細に分析していこう。
1 連合軍のプロパガンダ 反日本プロパガンダがどの程度効果があったかを確かめるのは難しい。多くの場合、文書館にその証拠があまり残っていないパンフレットや噂だからだ。しかし、わかっているのは、スペインが重要な対象者だったということだ。こうしたキャンペーンで批判された当事者がそれに気がついていた。セラーノ・スニェルと須磨はそれについて何ら下す術がないとわかっていた。その上、須磨は「あらゆるところでばらまかれていた反日本のパンフレット」に対して、何も出来ないことを嘆いていた。なぜなら、日本は純粋に軍事的な問題にお金を使い果たしてしまったからだ。連合軍のプロパガンダは、東アジアの占領地域における日本軍の蛮行を非難するのにとても効果的だった。次から次へと明らかな例が出てきたばかりでなく、それが日本人に関してあらかじめ抱かれていたイメージにぴったりと合致したからだ。これらの非難は、両国間の政治的友好関係の一掃、それにこの大きさの亀裂をふたをするのはあまり意味がないということを示すのに役に立った。エル・アルカサルのような日本よりのメディアにおいてでさえ、大使と編集者の何名かと夕食の席での会話で、フィリッピンにおけるスペイン人の苦悩が語られた。
2 軍事的興味の終焉 日本の軍事的価値は、外務省に最高司令部から送られた2つの報告書が示すように、決定的に崩れていた。この報告書では日本に対する決定的な失望感が表されている。1943年3月31日の最初の報告書を書いた軍人は、「枢軸国と関係の深い人物たち」が信じていたように、日本の攻撃の可能性の有無について、判断を下せずにいた。攻撃がない場合には、「アメリカ合衆国の副大統領のデーウィット・ウォレス(dewitt wallace)はドイツとロシア間の情報作戦が可能だと信じていて、また、日本が仲介者以上にはならないだろう信じてが、彼の予言は正しいだろうとしか考えられなかった。」5月にはすべてが明らかになっていると思われた。5月7日、新しい情報からの変化に応じて、日本軍のオプションを試すときが再び到来した。日本の軍事行動はオーストラリアでも、インドでも予想されないと言われはじめた。なぜなら、距離があるし、モンスーンの到来が近づいていたからだ。そのため、より近い目標、つまり中国やシベリアへの攻撃だけが行われるのではないかと思われた。シベリア前線での平穏状態を考慮して、報告書の執筆者は、それがスペインにおける日本のイメージにどのような影響を与えたかをきわめて明確にした。「これまでに判明した事実から、我々は以下のような確信を抱くに至った。天候のよいを5月が過ぎて、シベリアへの攻撃が具体化しなければ、日本とロシアの間に情報網があると考えられる。その危険性は十分にあるので、我々はこの文書を書くに至った。」
1943年春以降、スペインは満州国からのソ連への攻撃の可能性は全くなくなったと考えるようになった。シベリア前線での和平はゆるぎないものだと(inamovible)と判明し、日本の援助で、スターリンに対して勝利を収めるという希望は徐々に消えていき、この感覚は変化した。以前からの猜疑心から、日本が友人たちを放棄したということを確信するようになった。その結果として、日本へのイメージうちの主たる2つが消えた。その2つとは軍事的利益と信用である。三番目の反共産主義は弱くなった。とは言っても報告書によれば対ソ戦は日本軍にとって、もっとも大きな野望だった。これは、それまででもっとも熱心な「日本びいき」だったファランヘ党員の野望に特に大きな影響を与えるニュースだった。
3 忘却された太平洋戦争
1942年秋以降、雑誌ムンドMundoに掲載された太平洋でのスペインの歴史についての週間の連載記事がなくなったばかりでなく、マスコミにおいて戦争の情報がかなり減少したのは驚くべき事だ。NO-DOがそのもっとも顕著な例である。なぜなら、開戦から第二次世界大戦の終結までの間に、戦争関連のニュースは合計1100本だったのに対し、、そのうち、アジアでの戦争についてはわずか60本であった。(もちろん、それ以前に放映されたドキュメンタリーの数を加えれば、割合は異なってくるのだろうが。)
1943年9月のムンドの記事ではその理由が説明されている。「日本が戦っている大戦は、スペイン人にとって大いに興味をそそられることであるとは言え、より心を動かされるのは共産主義と反共産主義のとんでもない出会いであることは明らかである。(中略)アジアと太平洋地域において、世界のある部分の運命が決められていることは、疑いがない。その世界とはヨーロッパに隣接した、そして人種的にはヨーロッパに入っている地域、そして、その一方ではアメリカ、それに植民地としてとても貴重な意味を持つ島嶼部に目を向けていた。しかし、これらすべてがどんなに大きな意味を持っていたとは言え、—東京からの公式報告書によれば、「現在、深刻な症候群を示していた」状況下にあるーソ連に向けて(中略)の関心だったことは明白である。ムンドの記事によれば、スペインに影響を与えていたことは、より近隣でのことであり、アジアでのことは遠く彼方のことだった。太平洋での戦争について深く分析することはやめて、理解してもらうのには複雑過ぎると考える始めた。中国の有名な作家、林語堂(Lin Yu-tang)の作品がアメリカ合衆国でベストセラーになっていることへのコメントで、アジアでの戦いについてこう語られている。「誰も、なぜ戦っているのかわかっていないし、平和という明白で共通の目的すらない」戦争はエキゾチックなものへと変わっていた。
4 「白色人種連帯」の再生 アジアでの白人の連帯を助けようと言う考え、つまりは世界の他の地域でのヨーロッパの優位性を思い出させるのは、多くの記録から見いだすことができる。しかし、とりわけ注意を引くのは、この見解をイデオロギー化しないようにしようとする努力だった。これが論理的なものであると説得させようとした。太平洋戦争下で「西洋の価値観の優位性」が危うい状態にあったので、スペインがアメリカ合衆国の側についても当然だった。ホルダーナ自身が、この見解が合理であるというのは、たった一つの論拠からでなく、様々な理由、経済的、文化的、文明の普及に至るまで様々な論拠に基づいているのだと示した。
イデオロギーの違いは別にして、アジアに対抗して、ヨーロッパが共闘していく以外に解決法はなかった。ホルダーナがイギリス人のホアー(Hoare)に対して行った、白人連帯を求めての太平洋での連合軍の戦いへの援助の宣言が続いたことは、そのように理解させた。「これらの理論が(中略)我々の国が感じている不安と、共通の利益を守るためにヨーロッパの緊密な協力への願望を正当化するだろう。ヨーロッパの緊密な協力によって一度に共産主義という大問題を一気に解決し、アジアにおける我々の立場、我々の権威が再生されるだろう。そして、日本の拡張を阻止し、アフリカ大陸を正常な状態に再びもどすことが出来るであろう。」そのような脱イデオロギー化はなかったし、そうしたロジックは普遍的に圧倒的であったわけではない。それどころか、そうした白人の間の連帯は保守的な考えによってあきらかに変化していた。戦争以前の植民地での平和に戻ることを切望していた。もはや平和の時代は完璧に過ぎ去っていた。しかし、ホルダーナの伝統的な切望を反映していたものでもあった。共産主義に対して、政治的領域をほとんど認めていなかったばかりでなく、カトリックと「偉大な時代」の遺産に基づいたスペイン文化とのつながりによって、キリスト教を守るスペインにとって、とても大きい空白を感じていたからだ。大臣のメッセージが示していた主義主張は表には現れなかった。
日本のイメージの認識された概要の変化は、以前の考えを再解釈する場合のみならず、新しい情報の到着を吸収する際にも結果を及ぼした。コルデーロ・トレスの本での提案は、以前に述べた例を示せば、とても短期間のうちにすたれてしまった。東アジアで起こっていたことについて、新しい結論をし、それを分析することが必要だった。なぜなら、政府が外国に向けて新しい立場を示す際に、意志決定の過程で影響を及ぼしたからだ。
1 日本はスペインの連合国接近に役だった。それを示すには2つの例をあげるだけで、十分であろう。NO-DOが1943年8月に連合国軍からの資料に基づいた最初のニュースを放映している。それは、ビルマでのイギリス軍の存在と、太平洋でのアメリカ船の存在を報道していた。ファランヘの日刊紙「アリーバ」は、1943年10月に、枢軸国の拠点から、連合国軍の下にある都市、たとえばアルジェ、メルボルン、ワシントン、チュニスなどにいたるまでの、さまざまな戦線に出向いていた特派員(と推定される人)からのニュースコラムを掲載するようになっていた。実際には、このニュースはラジオから取られたものだった。なぜなら、アリーバ紙はそんなにたくさんの場所に多くの特派員を送り維持するだけの経済力を持っていなかったし、想像に難くないように、連合軍戦線での取材許可を得ることはとても困難だったからだ。
この2つの例が示しているのは、連合軍からの情報の中で、アジアからのものは、民主主義勢力の勝利の見通しを示した最初のものだった。よって、ドイツの陸軍武官が、かつてはとても忠実だったファランヘの新聞が、連合軍側のニュースを掲載したことへ抗議をした時、その件に触れたのは、太平洋戦争についてのアメリカのニュースを載せたメルボルンからのコラムだけだった。それが、太平洋戦争についての情報でもっとも枢軸国寄りではないものだったことは偶然ではない。スペインにとって、アジアにおいて連合国寄りである方が、ヨーロッパでそうであるよりは容易だった。スペインにおける戦争関連のニュースにおいて、連合国側への不満がなくなり、枢軸国側の不満が噴出しはじめたのは、極東戦線の戦況と関係していた。これはとても興味深い進展である。スペインの日本批判は連合国側へ突進していくための踏切板の役割を果たしたと言うことすら出来るだろう。
2 スペインにとって、アメリカ時代は日本時代より良かった。ホルダーナ時代の政治認識は、かつての植民地との関係において急激な変化をした。日本との友好関係時代以前に回帰したばかりでなく、アメリカ時代をスペイン文化の永続にとって好ましい時代であったと評価し、称賛するにまでになった。それは、急進的な野望と理解できる変化だった。しかし、それを連合国への接近に上手く使うことは出来なかった。なぜなら、フィリピン独立に賛成するという伝統的な考えが残っていたからだ。そのころ、フィリピン独立の認識が支配的であり、フランコ自身が何度か、日本に対して、(フィリッピンの独立)という約束を果たしていないと批判したすらあった。当時の状況を拒否する考えがあったものの、フィリピンの将来については意見が対立していた。
3 蒋介石は共産主義者だという評価ではなくなった。日本の反共産主義のイメージが弱まり、以前には「自明の理」とされたことが、再び問われることになった。例えば、中国での日本の戦いを共産主義に対する戦いとする考え方である。そのイメージを変えようと努力したアメリカ合衆国のプロパガンダ装置の足跡を追っていくと、新聞Ya紙にたどりつく。1943年末に、それまで疑いの余地もないように思われていた中国国民党リーダーの共産党的傾向を否定した。その後、他の新聞においてもイメージは決定的に変化した。アリーバ紙においてもそうだった。そこではプロパガンディストのマヌエル・アスナール、—彼はフランコ体制後の中道右派の首相の祖父に当たる人物であるがー、が蒋介石について、意味深いタイトルでの記事を書いている。「中国の不思議な戦争」「重慶の総統は公然とした明白な反共産主義者だ」。この記事は何らオリジナルなことは言っていない。しかし、内戦後のスペインにとっては新しいことだった。
4 スペインは中国での治外法権を要求しはじめた。セラーノ・スニェル時代には、19世紀以来享受してきた権利を、不平等条約によって失うことを認めていたものの、ホルダーナになって態度は変化した。ホルダーナの前任者とは反対のことをやろうという願望の産物のようにも見えた。なぜなら、1943年には枢軸国だけでなく、アメリカ合衆国やイギリスも治外法権を放棄したからである。しかし、放棄した場所は南京ではなく重慶だった。日本の新しいイメージと、ホルダーナのこの件で植民地での和平を復活するという希望により、スペインは孤立させた。
5 「アジアの野蛮な遊牧民集団」についてたびたび語られるようになった。東からの共産主義への恐怖は、世界大戦以前のものだ。しかし、その時代のソ連軍の勝利により、その感情がより先鋭化した。フランコが表明した立場、「文明化された」国々(つまりは、連合国とドイツ)間の和平を求め、ヨーロッパを侵略しようとしている「飽くことのない輩)」を止めようとしたのはその一例だ。1944年4月11日付けのアリーバ紙の社説も、ヨーロッパでの敵対関係の出来る限り早い終焉を擁護するという同じ様な見解を示した。「ヨーロッパでの戦争が長引けば長引くほど、太平洋での状況が固定化する。この戦争の本来の目的はアジアにあるのだ。」新聞ではこうした「遊牧民集団」が示す様々な側面や、単なるうわべだけにしか過ぎなかった文明の外見で、もともとの心をいかに隠していたかが報道された。しかし、こうした厳しい評価はまだ日本人には適用されてはいなかった。
6 アジアの連帯 この頃、ソ連にとっても日本にとってもお互いに対決しないことによる利点について、語られ始めた。以前に、背後から攻撃をするという日本の決断力のなさを批判したのと同じように、なぜソ連が日本を攻撃しないのかについての疑問が浮上してきた。1944年春、日ソ両国が漁業領海を更新し、石油に関する合意に達したいわゆる「漁業条約」を締結した。この条約は批判が噴出するきっかけとなった。アリーバ紙の第一面には、スイスのような政治的に正しい国からの情報を引用するという不思議な方法によって、いかに状況がパラドックスにとんでいるかが語られた。
「本日のジャーナル・ドゥ・ジュネーブによれば、ソ連と日本との間で、アジアの連帯が強化されたことが判明した。両国は条約を結んだ。(中略)この「アジアの連帯」の強化によって、ソ連の政治的現実主義が明らかになった。つまり、主義主張よりも現実の便宜を優先するということだ。しかし、アジアの2大国の間で保たれているこの「パラドックスにとんだ中立」という事実は、政治面で関心を抱かれずにはいられない。日ソ両国にとって、この中立は大きな利益をもたらすことになった。このとき、それぞれが、他方の同盟国との戦いにおいて死闘を戦っていたからだ。」
これら2国の行動がいかに不可解なのかかが注目された。ともにアジア人であるからだろうと結論づけられた。後に、ヨーロッパ人はあんなふうな小手先の工夫をしたり、堕落したりは到底出来ないと考えられるようになった。こうした再解釈とともに、全面的に批判されることになった。日本との友好関係継続の理由は次から次へと取り崩されていった。
日本のスペインとの関係の過程は異なっていた。他の方法がなかったせいでもあるが、あまり希望もてなかったというのも理由である。それにもかかわらず、スペインの姿勢から生み出された緊張と失望から、日本は両国の関係を過小評価するようになった。戦争目的にとって役に立たなかったからだ。したがって、1943年のはじめの数ヶ月から、スペインに対する不信感が高まった結果、それが軍事面でも形成されたと考えることが出来る。日本はドイツに対してイベリア半島占領を提案したほどである。ヒトラーがソ連攻撃の必要性を日本に主張したとき、その論理は一貫性を持っていた。日本は答えて言った。第三帝国がなすべき事は、東の前線を主張するかわりに、地中海の鍵となるようにジブラルタルを征服することだ。資料によれば、日本人がおおっぴらに、イベリア半島を征服することが必要不可欠だと言ったわけではない。しかし、もし仮に第三帝国が、ジブラルタルを奪取したいとすれば、上手くいくには陸からの攻撃以外に方法なかった。したがって、連合国軍がイベリア半島かマジョルカに上陸したらスペインの北の港や航空場を奪取することしか考えていなかったドイツの立場(giselaプランと呼ばれた)に対して、日本は彼らに南に向けて侵攻していくようにと、しむけた。ジブラルタルの奪取が実行可能だったために、ジブラルタルがドイツと日本との間の戦略上の議論の中心となった。
これまでみてきたように、日本のスペインに対する不信感がどんどん増し、日本はスペインの命運について全く心にとめないようになっていった。須磨がソ連との連携を強化しようとしていた一方で、他の人々はドイツの軍事攻撃を考えていた。スペインに対する不信感が増してきた証拠は、他のより重要な人物、外務省の重光などにも見受けられる。彼は連合軍がスペイン領土内に「国際空路の」途中の寄港地として使うために商業航空基地を獲得したか調査するように命令した人物である。すなわち、連合軍のドイツ攻撃のために、スペインがカナリア諸島の利用を認めたかどうかを調べさせた。後に、重光はイベリア半島に軍事基地を設置するためにスペイン・ポルトガルと連合軍との交渉があったかどうか再調査した。ホルダーナは最初の質問にきっぱりと答えたものの、日本はそれを信じなかった。もしスペインが背後から日本を攻撃することあれば、日本も攻撃をしただろう。
ホルダーナの第2期目は、両国関係の二面性を示した顕著な例だ。なぜなら、対外的には友好関係のイメージがあったのに、それぞれが、もし自分の利益になるのであれば、他方をだまそうとしていたからだ。基本的に両国関係は不安定で、相手国が自分たちの目的の達成のために役に立たないばかりか、それを妨害しているとまで考えるようになっていた。
ともかく、より複雑だったのがスペインの場合だ。日本の利益代表と太平洋戦争における利益代表の結果、ホルダーナ期のスペイン外交は、きわめて複雑で急激な変化の道をたどることになった。それ以前に確実だと思われていたことが信じられなくなったばかりか、まったく正反対の何かを受け取ると考えるようになった。以前のイメージを覆し、以前には興味すら示さなかったニュースに耳を傾け、以前には意見の一致をみず過小評価されていた声にまで耳を傾けるようになった。もし、その解釈が、以前にはまったく異なったものであっても、もはやどうでもよかった。
この変化を理解する鍵は日本の軍事的敗北の連続である。しかし、それだけでは十分ではなかった。そうしたイメージの変化は、ナチ政権とともに起こったのではない。ムッソリーニが倒されたあと、イメージの再生が可能になっていたファシストとでもなかった。それどころか、日本のイメージの変化は、両国の友好関係以前の考えが存在し続けていたゆえにおこった。それは根底で静止していただけだったので、以前のことを思いおこしさえすればよかった。新たな認識を作り出したのではなく、単に、数年間の間、重要視されていなかったいくつかの伝統的な側面が回復されただけだった。伝統的なイメージによって、以前にはなかった日本の敗北を望むようになった。これは保守主義者によって支持された変化で、彼らはファランヘ党員の説得に成功した。
終わり
- 日本と戦後のスペイン
外相にホセ・フェリクス・デ・レケリーカが任命されたことは日西の相互関係が新段階を迎える上でよい契機となった。というのは、新外相は二国間の接触において鍵となる人物だったからであり、またその就任が第二次世界大戦の最終局面という時期においてだったからである。ホルダーナが更迭されてから数日して、枢軸国の軍事的劣勢はドイツ軍が西・仏国境から最終的に撤退したことに表れた。このことは、この戦争で連合国が勝利するだろうとの信を高めさせただけでなく、イベリア半島が世界戦争の戦闘の舞台となる可能性を消失させたのである。スペインの外交当局はドイツ軍の撤退を喜ばしいものと見ていたが、いよいよ近づくことになった将来に何が起こるだろうかということを考えざるをえなくなった。戦争の終結が近くなったことはマドリードの政府にとってはカフェでの常連の会話以上の意義を持っていた。というのは、戦後の世界がどうなるかということを考えることは、この新世界秩序におけるドイツやフランスの役割について思惑をめぐらせることだけでなく、スペインの将来そのものに関わることだったからである。以前の明らかな後見人がいなくなってもマドリードの体制が存続できるかどうかという問題の期限が迫ったのである。戦争の終わりが見えてきたことで、ドイツの最終的敗北の後にすぐに侵入や攻撃がまちがいなく生ずるようなことはありえないことになったので、それから免れようとすることは主要なことではなくなった。たいへんに錯綜した段階で、世界の秩序におけるスペインの将来の役割を準備しなければならなくなったのである。いまやあらためて細かいところまで計算しなければならなくなったが、今度は戦争の一方の側を満足させればよかった。ヴィシーのスペイン大使がその役割を委ねられたが、それはさらにこの仕事を難しくさせた。というのは、レケリーカはそれまで枢軸国のことだけ考えていたからである。
太平洋での戦争も、一九四四年夏にグアム島とサイパン島が陥落したことで軍事面で新たな段階を迎えていた。これによって、アメリカ合州国は初めて日本本土を大規模に爆撃できるようになった。日本の戦争装置は他ならぬその展開の拠点つまり日本列島そのものにおいてますます疲労していった。日本の崩壊は確実に近づいていた。
それでも、スペインにとって日本は新たな意義を持つことになった。この意義は、太平洋での戦闘がイベリア半島に直接に跳ね返ることはけっしてなかったし、また政治的変化の故にスペイン政府が他の戦闘地域により関心を持ったことによって、太平洋での初期の成功の後には消えてしまっていた。かくして最終局面において、フランコ政権のあらたな対外的要請によって、東京[日本]にはほとんどありがたくない役割、つまりスペインにとって最も攻撃しやすい目標という役割が与えられたのである。ソ連はドイツ国防軍に対する打ち続く勝利によって国際的部面においてさらに大きな重みを獲得しており、マドリードもそれを無視することはできなかった。フランコ政権はその批難の的を他の国に向けなければならなかったが、それはできるなら敗者の側にいる国でなければならなかった。
日本がその対象として選ばれた。他にもっと適当な敵がなかったので、この帝国との関係悪化がスペインの体制にとって必要とされたのである。それに、以前の日本との関係はドイツ・イタリアとのように深くはなかったし、また日本と敵対したとしてもスペインの国内政治に影響することはほとんどなかったので、この政策はとくにやりやすかったのである。かくしてヨーロッパでの戦闘終了後における体制の生き残りを目論んで、日本との関係は、反対の意味ではあったが以前に持っていた意義をいくつかの点で再び有することになった。以前には日本はスペインの帝国の夢をかき立てたアジアの闘士だったが、レケリーカの時になると日本は文明諸国そして連合国とともにあるスペインのまがうことなき位置を示す敵となったのである。この国との対立は戦後に向けたマドリードの新たな政策の鍵の一つとなった。それ故に、後に、フランコ政権の対外政策の研究史において古典的著作であるアグスティン・デル・リオ・シスネーロスの本がこの局面を「大西洋重視と日本との決裂」と称するまでになったのである。体制の生き残りが何にもまして優先され、英米との友好と日本との敵対がそのための手段とされたのである。
ホセ・フェリクス・デ・レケリーカが異なる様相を持つこれらの切なる意向をうまく繋ぐ役を任されることになった。ホルダーナがすでにその道を準備済みだった。すでに見たように、この2年間に日本との関係は大きな変化を見ていた。日本は、友好国からファランヘ党の新聞でさえ批難する対象へと変わっていた。以前の協力状態から日本が提起するあらゆることをスペインが拒否する状態となったのであり、最終目標は同じでもなく共同で追求できるものではないとのスペイン側の決定により、共通の目的を追求した協力は後景に退いてしまっていたのであった。スペインが太平洋で共同を目指したのは何よりも英米となった。
これは日西関係におけるかなりの程度の変化だったので、それは両国の関係そのものだけでなく日本のイメージにも及ぶものとなった。ホルダーナの時代から日本の見方を規定していた認識の枠組は180度の転換を見ていたので、スペイン人たちは日本から肯定的な情報を期待するよりも否定的な情報に反応するようになっていった。日本の敗北やその野蛮さについて語る敵意を込めた情報がそれまでの言辞にうまく組み合わされようになった。かくして、レケリーカの時代には以前のステレオタイプの日本イメージが再び表れたというより、その否定的イメージがさらに進んだのであり、あいまいで矛盾さえする情報がこの敵意を込めたイメージにますます重ね合わされることになる。日本についての厳しい見方が多くなった。日本についての情報は日本人がいかに野蛮で反西洋的であるかを示すような論調を備えることになった。状況の変化はすでに数か月前から決定的に始まっていたので、レケリーカの時代に実際におきたことは日本についての見方が形状化されたことであった。
このことには外相の個人的野心が与っていた。外相レケリーカはスペインの対外関係において必要とされた転換を遂行するのに、ましてや確実に日本との敵対を導くのに最も適合した人物というわけではなかった。しかし理由は何であれ、レケリーカはおそらくホルダーナではそうはいかなかった程度まで日西両国の関係を緊張させただけでなく、もっと重要なことには、それを違った形で見せるようにまでした。つまり、関係の悪化に当惑していると思わせたのではなく、むしろ対立関係を誇示し始めたのである。レケリーカは、日本との関係を改善しようとするのではなく、その関係の悪化が他の諸国との関係を有利にするようにと日本との対立関係が高ずるままにしたのである。かくしてレケリーカは可能なことをとことんまでやったのである。
- 日本への新たな姿勢
一九四四年の夏に日本は表面的にはほどほどの状態で戦争に向かい合っていた。海軍の敗北は続いていたが、陸軍は攻撃を継続してアジア大陸での征服地の大部分を維持しており、いくつかの攻勢によってインドと中国で新たな地域をも獲得していた。日本は、ある地点で敗北しても他のところで勝利しているからそれは大したことはないと見せかけようとした。しかし実際にはそうではなかった。海軍が敗北したことは陸軍が前進したことよりももっと大きな意味を持っていた。アメリカ合州国の攻勢によってミクロネシアのいくつかの島々が奪取されただけでなく、多くの日本の海軍ルートが寸断されてしまった。かくして大東亜共栄圏なるものは砂上の楼閣となってしまっていた。
夏を過ぎると状況は急速に悪化した。一九四四年一〇月に連合国軍はフィリピンに向かって進撃し、レイテ湾で日本の海軍をほぼ完全に壊滅させた。これは太平洋の戦争での最後の重要な海戦となった。戦争のために肝要だったこの戦力を失ったので、一九四五年初頭に帝国の最高司令部は日本列島の防衛を全ての戦略的考慮に優先するものとした。それ故に、アジア太平洋地域の軍は成り行きにまかせるままにされ、援軍を得る希望も持てずに、占領した地域の資源よって自らを維持するしかなくなった。兵の集結が少なすぎたり、あるいはあまりに多くの兵が終結したりした(たとえばメラネシアのニューブリテン島のラバウルには七万の兵が集結していた)ので、多くの部隊は餓えに苦しみ、かといって移動することも出来ずに、司令部からも忘れられてしまった。いくつかの部隊の場合には敵軍からさえも忘れられた。このような軍事的破局は中央政府に及ぶことになり、一九四四年六月に東條英機が更迭されて小磯国昭が首相となった。以上の変化は少なくとも、日本をこのような道に導いた人々が予期したような結果を得られなかったことをはっきりと認めたことを示すものであった。同じことは、一九四五年一月二〇日にもなってまとめられた最初の帝国陸海軍作戦計画の策定についても言えることである。しかし、事態の打開はもはや不可能だった。
小磯は事態を立て直すことも、以前に東條がなしえたような結束を自身の周囲に得ることもできなかった。それまでの多くのやり方を変えることは不可能であり、沖縄にアメリカ合州国軍が上陸した後の一九四五年三月に小磯内閣は崩壊した。沖縄の戦闘は帝国を非常に困難な状況に陥れた。日本列島への敵軍の侵入が切迫しまた現実のものとなったことが初めて明らかとなったからである。小磯は鈴木貫太郎に内閣を譲った。鈴木は一九三六年二月に急進派軍人から襲撃されたことがある退役海軍大将で、この間は枢密院顧問を務めていた。 鈴木内閣は切迫した状況の産物であり、半年ももたないという日本の歴史上で最短の内閣だったが、重要な意義を有していた。一〇年間以上も軍人が権力を持っていたことに反発する潮流に促されて、鈴木は日本の寡頭制が再び国家の機能を動かすようにしたのである。その目的は戦争を続けることではもはやなく、一億の日本人が全滅しないように講和を実現することだった。戦争継続を叫んでいた人々の大部分もこのような講和を受け入れる用意があった。かくして、最後まで戦って国体を保持するとの宣言が引き続きなされてはいたものの、この政府の仕事の中心をなしたのは受け入れ可能な講和を追求することだった。物質的にも精神的にも消耗していた困難な時期であり、帝国の様相は帝国がまだ安定しているというイメージをますます与えなければならないような状況になっていった。
他方、スペインの公的世界でも動揺が見え始めていた。スペインへの攻撃の時期はドイツや日本においてのように切迫したものではなく、またそれは軍事的形態をとるものではなかったが、将来の戦争の成り行きはスペインにとって有利となるようにはとても見えなかった。国際舞台の新たな主人となった連合国はフランコ政権をそれほどよく思っていなかった。イギリス、ソ連、アメリカ合州国はいずれも、当面のもっと重要な仕事が終わったならフランコ政権を崩壊させようと思っていた。そのうえ、スペインの防衛力は限られたものだったので、政権はきわめて弱い基礎の上に立っていた。将来のこれらの困難に対するスペイン政府の最初の反応は、伝えられてくることをまともに受けとめようとしないことだった。フランコ将軍や参謀本部のメンバーなど何人かの人々は、ノルマンディーからの連合軍のヨーロッパへの侵入はどのような結果を生むのか少なくともまだわからないと主張していたし、ベルリンが流し続けていた反撃や強力な秘密兵器についての情報にしがみついていた。戦争終結の様相についての彼らの考え方は、おそらく認識の枠組みをいかようにもあらためようとしないこのような姿勢によって非常に歪められていた。たとえばフランコ将軍はかなり遅い時期まで、ドイツの降伏はドイツが戦後のヨーロッパにおいても重要な位置を占め続けることができるような寛大なものとなるだろうとの予測をほのめかしていた。つまりフランコ体制は、次第に対応を変えながらも明確な方向も持たずに「事態のなすにまかせる」ほかなかったのである。しかし、これ以上に待ってもいられなかった。
レケリーカの外相任命は、戦争終了を前にしてのこのあいまいな姿勢を最もよく示すことの一つだった。彼が選ばれたのは、ある当面の問題を解決することが緊急に要請されていたからだった。ドイツに占領されていたフランスの首都ヴィシーの解放が間近に迫ったので、そこでのスペイン政府の代表者であるレケリーカを急いで引き揚げねばならなかったのである。しかし、このようにして引き揚げても連合軍が抱くかもしれぬとまどいを避けることができるようには見えなかった。かくして、ヴィシーの町が総崩れになったときにこの町からけがれなく撤退できるということで、ビルバオ市長だったことがあるこの外交官レケリーカが外相に任命されたのである。この地位には他のもっと適当な人が就いてもよかったのである。ツッセイが名づけたようにレケリーカは「ファシズム化した」政治家であり、親枢軸の姿勢を度々示していた。よく知られており、スペインと第2次世界大戦についてのアメリカ合州国の政治家たちの回想記で引き合いに出されるレケリーカについての逸話は日本に関することだった。レケリーカは枢軸の最終的勝利を祝するためにヴィシーの大使館の中庭で七面鳥を育てており、真珠湾への攻撃の後でこのことを明らかにしたというのである。フランコは、自分の頭には当面の諸問題のことしか入っていないことを示していたが、レケリーカの外相任命によって日本との関係にさらにもう一つの難題を付け加えたのだった。
それでも、新外相の就任は日本との懸案事項を遅らせたのではなかった。レケリーカは就任の翌日に日本大使の須磨弥吉郎と会見して、ただちに「駒を動かした」のである。スペイン側の資料が無いのでどのような話しがなされたのかを正確に知るのは難しいが、日本側の電報からするとホルダーナの時とはかなり異なった接触だったようである。つまり、何かを議論したということではないのである。レケリーカは、彼自身も国家元首も「日本との友好関係を進めたいと思っている」、「ホルダーナの時期にあった緊密な関係を減じようとの意図」を持っていないと述べた。須磨の側は、日本の利益をスペインが代表していることに対する日本政府の「心からの謝意」を表明し、「両国間の末長い友好関係を維持するためのレケリーカの協力」を要請した。双方とも相手側の反応を探ろうとしたようだ。須磨が中国における日本軍の前進については述べて、グアムとサイパンの最近の敗退が日本にとって持つ意味については述べなかったのに対して、スペイン側が自分たちはそのようには受けとめてはいないと言ったことは無いようだ。両者の会見からは、儀礼の範囲を越えた率直な話し合いがなされたようには見えない。日本の軍事問題の検討というよりも接触を開始することに意義があったのだが、須磨はただちにホルナーダの時期のようにもっと率直な会話をした方がよかったことに気がついた。
そのことはすぐにはっきりと確認できた。レケリーカが日本に対して批判めいたことを言わなかったのは日本を好意の目で見ていたからではなくむしろもっと冷ややかに見ていたからであることがわかったのである。スペイン外相は、もう壊れてしまっていた友好関係を進める気がないことを明らかにし、双方の相違に関して日本大使と率直に話し合うよりもむしろ自らに有利なようにそれを際立たせようとした。ホルダーナも可能な限り須磨を欺こうとしたのだが、レケリーカとホルダーナの違いは明白となった。この違いは、とくに日西両国の関係の将来についての異なった見方に示されていた。ホルダーナは両国間の緊張を減じようとの期待を持っていたが、レケリーカはそんな期待は持っていなかった。さらにこのバスク出身の外相は、この緊張がもたらしうる積極的な要素を見つけようとし、日本との諸問題を違った形で受けとめ始めた。諸問題を解決するよりも、むしろそれらを戦後のために使える踏み台と見たのである。それ故に日西両国の関係は、どう見ても容易ではないフランコ体制が生き延びるための闘いの一部を成すことになった。要するに、日本に対する批判はスペインに敵対的な世界においてスペインがかちえる一つの保証とみなされたといえる。反日本のカードを使うことが必要とされたのである。
フィリピンにおけるスペインとスペイン人コミュニティーの利害は、戦後においてフランコ体制を救うための以上のような意向のために、その第一義的な重要性を失っていった。日本との接触開始直後に起きた3つのことが新たな状況をよりよく説明する。一方で、亡命フィリピン政府大統領マヌエル・ケソンの死によって前の副大統領セルヒオ・オスメーニャが新政府の舵取りをすることになったが、新政府には元蔵相のアンドレス・ソリアーノとワシントン駐在政府代表のホアキン・エリサルデという二人の重要なスペイン派が入っていなかった。他方で、ポルトガル政府と日本との関係はますます緊張したものとなった。連合国の働きかけを受けてサラザール政府は8月7日に公式に東ティモール植民地からの日本軍の撤退を要求し、それが拒否された場合には国交を断絶すると迫った。ポルトガルは日本に対してすぐにも宣戦布告をするだろうと見てよい十分な理由があった。というのはポルトガルは、連合国軍がティモール島に攻撃をしかけたらポルトガルもティモール島奪取作戦に加わるために兵を派遣できるかとの誘いを連合国から受けていたからである。サラザール政府が目論んでいたことは後にフランコの政府がやろうとしたことと同じものだったであろう。つまり、アジアに派兵するというちょっとした投資をすることで、リスボンの政府は勝者の側に立てるという大きな政治的利益を得られるのである。このような緊張した関係は、マドリードの政府においてと同様に二国間の関係を越えたものであった。最後に、レケリーカはドイツ大使ディークホーフとの最初の会合で、通常の問題では日本の須磨大使を援助することをやめるよう要請した。新外相は、日本がマドリードにおいてその寵臣のような存在を失うことになるように、独・西の関係と日・西の関係を切り離したいとの意向を示したのである。合州国における新亡命フィリピン政府、リスボン政府の対応、日本との対立関係を恐れないようにドイツに通告したこと、以上のことはホルダーナが決してやろうとしなかったことをレケリーカに可能とさせた。つまり、はっきりと公けに日本を非難することである。
須磨とレケリーカの最初の会見から二日後の一九四四年八月一六日、国家新聞管轄局はマスコミ関係者にいくつかの通達を発したが、そこには新聞というこの公けの場を使って日本を徹底して非難しようとの明確な意図が表れていた。これらの通達の以下のような題名がスペインがいずこに寄り添おうとしているかを疑いもなく示していた。「日本に対する戦争において合州国の側を好意的に報ずることについての指示。とくにフィリピンにおいて起こるだろう戦闘についてこのように報ずること」、「とくに太平洋における戦況とスペインの対応についての指示。反キリスト教的で反西洋的な日本の行動に対する非難」。三日後に発せられた第三の通達は、ヨーロッパにおける戦争について以下のような新たな指針を示していた。「ヨーロッパにおける戦争の現況についての指示、西部戦線および東部戦線についての報道のスタイルについて、いずれにおいてもスペインの中立が適当であることを示す内容にすること。共産主義の広がりについて。ドイツから解放された地域の内政についての報道の基準、とくにフランスについて。国際平和に向けてのスペインの行動」。レケリーカは、日本に対するまた同時にその他の国に対するその実際の意図がどこにあるかを明確に示したのである。
最初の二つの通達の文面を立入って検討するのがよいだろう。というのは、これらの通達は当時スペインのマスコミが従わなければならなかった中立という考え方がいかに難しかったかを明白に示しているからである。「中立というスペインの姿勢を失わずに[としながら以下のように命令調である]合州国の側に好意的であること」。最初の通達は「太平洋においては大きな戦闘が間近に迫っているが、スペインは日本の勝利よりアメリカの勝利を望む」と述べ、次ぎのことを一般的な規範とするように警告した――「文明諸国間の戦争については新聞の論調はまったく中立的で客観的であること。東洋の国々についてはそうではない」。第二の通達はソ連と日本の間の非交戦状態を「アジアの狡知」と呼び、それを宣伝のために使おうとしていろんなことを述べまくっている。さらに、それについて次ぎの五点を提示した。
- [スペイン人の]生活の政治的意義は「キリスト教的で西洋的な思考」に基づいている…。
- 我々は深くヒスパノ・アメリカ諸国と結びついており、…またこれらのヒスパノ・アメリカ諸国はスペイン政府と友好関係にあるだけでなく合州国とも同盟している。かくして、我々の新聞が太平洋の戦争において西欧的国家の利益を削いでアジアの国を支持することはけっしてないであろう。
- 我々の国際的行動はポルトガルとの協調に強く規定されている。とくに外交の分野にはそのいくつかの理由が存する…。この第一級の理由が東洋で起きていることを見るについても我々に同様な態度を採るようにさせている。そこではポルトガルが日本と衝突しているのである(チモール)。我々の支持と利益はもちろんポルトガルの側にある。
- 日本はロシアと友好関係を維持しており、それは通商関係の深さと外交協定に見られる。このことによって、ロシアは太平洋の戦争において中立の態度を採っており、また日本はこのヨーロッパの反共産主義戦争において実際には(現実主義的にも)中立の態度を採っている。日本は反共産主義的な政策をやっておらず、帝国主義的な野心を持った政策をおこなっている。この点では政治における一種のアジアの狡知が働いているのであって、これはヨーロッパの精神とは全く異なるものである。このことは、ヨーロッパのあらゆる人々やヨーロッパに起源を持つあらゆる人々にとっては巧妙な策略とはいわないまでも世界戦争のとてつもない逆説を成しているのである。両国は現在闘われている戦争に加わっているのだが、事実上ロシアと日本の間には友好状態が存在しているのである。
- スペイン文化の小島であるフィリピンが太平洋の戦争において争いの場となっているが、フィリピンの人々はその歴史においてもその文化においても日本の東洋的世界との近似性を持たないことを想起すべきであろう。スペインはこの場合にこれをアジアにおけるキリスト教文化の前進と見て、フィリピンの人々の利益のみを徹底して政治的に擁護する必要がある。具体的には以下のことである。共産主義の拡大とアジアの国々の伸長に反対するという我々の姿勢に照らして、太平洋の争いにおいて我々の新聞は合州国の側に賢明な礼儀と敬意を示すべきである。ヨーロッパにおいて共産主義の前進が歓迎されないのと同様に、太平洋においてもどのような日本の行動も歓迎されるべきではない。
スペイン政府は、いまや困難となった解決を見出そうとして絶望するのではなく、国家間の懸案事項をも利用しようとしていた。日本とのこの対立関係を明らかにしながら、さらにスペイン政府はワシントンの方に友好関係を求めようとしたのである。その証拠に、スペイン側はカールトン・J.H.・ヘイエス大使に対して「適当な時機に」日本との関係を断絶するかもしれないことを何回もほのめかした。年末にワシントンに戻る前にヘイエスはフランコから、フランコが日本を好んでも信用もしていず、それまでにもいくつかの日本との問題をうまく処置してきたことを長々と聞かされた。フランコは、公使の地位を格上げしたいとの日本側の提起を「三回も四回も」拒否したことを想起させただけでなく、外交関係を断絶するとか利益代表を放棄するとか言って須磨を脅したこと、さらには「グアムとフィリピンにおける何人かのカトリック神父の遇しかた」やフィリピンにおけるスぺイン人とその財産への攻撃をめぐる日本との対立について述べ立てたのである。おそらくレケリーカの伝記がレケリーカはこれ以前のことよりこの後のことについて多く語ったと書いていることもあってレケリーカはフランコほど大げさではなかったようだが、それでもレケリーカも決定的な解決策もありうると言って日本との対立についてきちんとヘイエスに伝えている。フィリピンとグアムにおけるスペインの権益を日本が尊重していないこと、日西両国の間の「ぞっこんな愛」がもう消えてしまったことについてスペインの世論が受け入れるだろうこと、最後に、ポルトガル政府との共同の行動が可能である(かつ望ましい)ことが以上に述べた方向転換を正当化する理由とされた。
ヘイエスがマドリードでのその最後の日々にフランコおよびレケリーカと会談した際には他にも多くのことが話された。言うまでもなくその他の世界の情勢についても多くのことが話されたが、スペインの対外関係のこの新段階にあってはアジアの戦線のことが一番重要な意味を持っていた。というのは、ホルダーナのときと同様に、このことが後にヨーロッパについても起こりうる転換への探りの意味を持っていたからである。アジアについての新聞への通達がヨーロッパの戦争についての通達より先に出されたこと、またレケリーカがドイツのディークホーフと会う前に須磨と会談したことは、太平洋の戦闘についての姿勢の転換こそヨーロッパの戦争において新政策を求めることの始まりだったことを示している。八月一九日のヨーロッパについての通達の文面がそれまでの姿勢に少し色を付けたのに過ぎなかったのにたいして、アジアの戦場についての指示はそれよりも前の一六日に出されただけでなく、新たな政策を示していたのである。
スペイン政府は新たな敵に対峙することになった。ソ連についての情報に対しては、中立の原則を適用するために、「国家」としてのロシアと「輸出される共産主義」とがはじめて区別されようとした。以前からの悪の帝国について初めて分析がなされ、その結果それを少しく「東洋から外す」ということがなされた。日本がこの空隙を埋めるべき主要な資源となり、そのために日本は逆に異国であることが強調される処理をされることになった。結局、日本はスペイン政府にとって意義を持つものとなった。というのは、日本は、世界戦争の最終期のスペインにとって最も都合のよい敵という烙印を押されることになったからである。
- ステレオタイプ化の再進行
一九四四年八月の新聞への通達は
Reseñas
フランコと大日本帝国 フロレンティーノ・ロダオ著 大戦下の両国関係を実証的に
2012/3/7付
保存
共有
印刷
その他
第2次世界大戦勃発(1939年9月1日)の3日後、スペインの独裁者フランコ将軍は、スペイン内戦で疲弊した国内再建のために「中立」を宣言する。これは、盟友ヒトラーやムッソリーニのスペイン参戦の強硬な要望を蔑(ないがしろ)にしたものだったが、すでに独・伊と結んだ「反コミンテルン協定」の関係上、枢軸国に傾く「中立」であった。一方、内戦で敗北した亡命共和国政府陣営からの執拗な反フランコキャンペーンと対峙しなくてはならなかった。つまり、内憂外患のフランコ体制であった。
画像の拡大
(深澤安博ほか訳、晶文社・5500円 ※書籍の価格は税抜きで表記しています)
したがってフランコは、ヨーロッパ戦線の戦況に応じて「中立」、「非交戦国」、「武装中立」と立場を変える。例えば、41年6月、ヒトラーのソ連への武力攻撃に鼓舞されて、「非交戦国」を名目に、1万8千人の反共産主義の義勇軍「青い師団」を東部戦線に投入する。はたせるかな、連合国側から「青い師団」の撤退を強要され、フランコは「中立」を宣言し、「青い師団」を解散させた。
ところで、この時期、フランコ政権下のスペインと日本はどのような関係だったのだろうか。このテーマを実証的に論じた本書によると、太平洋戦争勃発時においては、反米感情も手伝ってか、スペインは、日本軍のフィリピンの占領を歓迎し、南北アメリカ大陸における日本の利益代表国になり、20人余りの対米スパイ組織「東」の諜報(ちょうほう)活動を容認するなど、実に好意的であった。
しかし、時の経過とともに、枢軸国側が劣勢となり、イタリアが降伏し、ドイツも完敗する兆しを見せ始めるや否や、フランコは掌(てのひら)を返すがごとく、連合国支持を鮮明にする。これとほぼ同時に、フィリピン在住のスペイン人に対する日本軍の残虐行為を告発し、さらに日本との国交断絶を含む、敵対関係を公にしつつアメリカにすり寄っていく。それも「黄色い野蛮」とか「文明的世界とは正反対の人種」といった人種差別的な罵詈雑言(ばりぞうごん)を浴びせ、日本に最悪の敵という烙印(らくいん)を押したのだった。
だが、こうした外交の妙手であるフランコが目論(もくろ)んだ戦後の国際関係のシステムへの参入は、連合国の反対のために、見果てぬ夢となったのである。
(法政大学教授 川成洋)